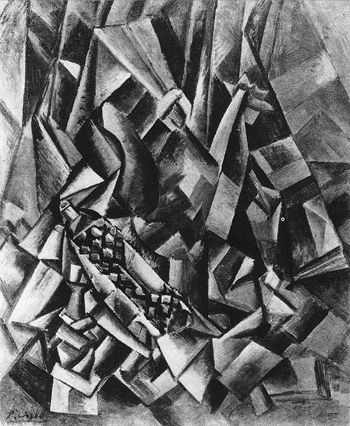第104号 |
|||
| 2009年04月20日 | |||
「問われている絵画(96)-絵画への接近15-」 薗部 雄作 |
|||
| 岸田劉生は晩年に洋行を計画した。結局果たされずに倒れたが、その目的を人から聞かれて、「自分は学びにゆくのではなく、教えにゆくのだ」と答えた。人はそれを負け惜しみの豪語とみて笑った。負けん気のつよい劉生にその気がないとはいえないかもしれないが、本音でもあっただろう。すでに肉筆浮世絵に心酔し油絵具を嫌悪していた劉生に、もはや西洋から新たに学んで身につけようとするものはなかったであろう。ただ当時の日本の美術状況のなかでは、西洋…本場へ行って学んでくるのが当然で、教えにゆくのだといった画家は一人もいない。本場は絶対に近かったのである。洋行した画家と、していない画家では社会的にも信用度がまるで違う。とにかく一度見ておこうという気持ちもあったかもしれない。けれども美術ジャーナリズムや画壇のなかでこのような発言はきわめて異例で、画家たちにもまともには聞こえなかったのだ。 ここで桜沢如一(一八九三〜一九六六)に登場してもらおう。といっても、画家ではないので美術家のなかには知らない人もいるのではないかと思う。食養家であるのだから。もっとも近ごろでは自然食やマクロビオティックなどという言葉もよく耳にするので、あるいは知っている人も多いかもしれない。いずれにしても、このような食に対しての考え方は、ほとんど桜沢如一に由来しているようである。 桜沢如一は、マクロビォティックな食の在り方をすでに一九一〇年代に身をもって体験し、一九二〇代からはその普及に全身的に邁進してきたのであった。一九三七年に実業之日本社から出版された『新食養読本』は大ベストセラーで七百版も重ねたという。だから当時は食養家として大変よく知られていた人であるのだ。もちろん今でも多くの人たちによって、それは引き継がれかつ広められている。その重要性はますます高まっている。けれども彼は、たんに食養家として有名な存在だけではない。食を通したきわめてオリジナルな思想家でもあったのだ。食養家の面にくらべると、こちら…思想家としての面を深く見つめる人は少ない。もちろん双方は一体となっていて本来は切り離すことはできないものである。けれども多くの人はさしあたり体の健康の方に関心があるのである。したがって、それがある程度達成されれば、それ以上深く突っ込んで、その思想のよって由来する根源にまで身をもって深くたち入らなくても、それですむからである。それはともかくとして、桜沢如一はこの東洋的な食養思想を国内だけではなく外国…西洋にまで教えに行ったのだ。そして西洋に広めたのである。西洋だけではない。世界中に広めたといってもよい人であった。 ちなみに海外で出版された桜沢如一の本を国別に上げてみる。 フランス語 15冊 英・米語 9冊 ベトナム語 8冊 スエーデン語 3冊 ブラジル語 2冊 ベルギー(仏文) 2冊 この他、主要図書は、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、トルコ 語、ヘブライ語などで多数出版されている。(桜沢如一資料集より)
この度、この特異な食養人…桜沢如一の著作をあらためて読みなおしていて、意外にも岸田劉生との共通点が多々あるのに気がついた。まず第一に同世代だ。劉生は一八九一年生まれで桜沢如一は一八九三生まれであるから二つ違いである。劉生は日本の美術界における西洋の圧倒的な影響下にありながら、ひとり東洋的…宋元の絵画や日本の肉筆浮世絵におのれの「内なる美」と同質の美を見て、以後その美感を作品の上で実行しかつ文章によっても主張しつづけた。桜沢如一は、やはり圧倒的な西洋医学や栄養学の影響下にあるわが国において、東洋的な食の思想によって心身の健康の回復を目指し、実際指導と文章によって終始奮闘した。もちろん両者ともたんなる排他的な国粋主義者ではない。西洋美学や西洋科学・医学をもふまえた上での行為であり発言である。西洋や東洋といっても、つまりは人間存在の基底まで降りてゆけば、人種や思考形態は異なるとはいえ結局は同じ地盤に突き当たる。桜沢如一はいう「私は従来の[日本人]というような狭い観念の殻を脱け出したいのである。私は全世界を私の故郷とし、全ての民族を真実の同胞と感じるのである。」そして「東洋の古代思想の自由な広々しさに呼吸することを覚えたばかりに、全く日本という島に容れられるには余りにも放埒な思想をもつに至ったからなのであろうと思う」と。 中国の古代思想とは『易』のことである。この『易』の思想を、占いとしての側面ではなく、実証的な科学書としての側面を、西洋の科学とも照合しながら、事物…現象物一切をふくめた宇宙的存在論として読みとり、それを人間の食の構造に翻訳したのであった。つまり、雑然と混在する食物の海のなかに確とした陰陽の法則を見出し、それを人体のもつ陰陽の法則に結びつけたのであった──ここでわたしは思う、これは芸術作品内の構造や法則とも共通するということを──それは画期的なことであった。なにしろ、今までもっぱら易断としてのみ名高いこの古色蒼然とした奇書を、わたしたちのリアルな食養原理として蘇らせたのであるから。桜沢如一はいう「近来、易の陰陽道は、新しき西洋科学学徒によって手ひどく痛められ、蒙昧なる蛮人迷信の代表者の如く言われるか、原始的素朴人によって神秘化され、神聖化され、ますます嘲笑軽侮の焦点におかれている。」「五千年来、あるいは数万年来、聖賢といわれるほどの全ての熟烈真剣な苦道者、真理探求者を導く唯一無二の指導原理たりし易が、左様に軽々しく葬り去られるであろうか。私はそれを信ずることができない」そして「古来東洋の多くの聖人叡智によって長い間研究され、完成された全科学の栄光であり、全科学を統合する唯一無双の原理であり、最高の哲学であったものであると思う。と同時に、それは最近西洋に生まれた科学に一条の光を投ぐるものである」と。 そしてたしかに、食に関する実用面は広く普及した。しかし、それにくらべると思想家─見者─としての側面はあまり注目されていない。とくにわが国の学者や文化ジャーナリズムには受け入れられていない。当時の進歩的文化人のほとんどは今よりもさらに西洋医学・栄養学崇拝の姿勢が徹底していたので、東洋の、それも占いという、多少いかがわしい側面によって大衆化している『易』などに傾倒した食養人の思想には、復古的・反時代的マユツバ的なにおいを嗅ぎとって、思想家としてはまともに見ていなかったのであろう。それに彼の語り口にも原因がありそうだ。ざっくばらんであけすけだ。終始多くの読者…大衆を相手にしたための結果でもあるのだろうか。読者の鼻づらを…知っている人が知らない人を、一方的に引き回しているようなところがある。とくに日本の読者向けに書いたものにその傾向がつよい。フランス語で書かれたもでは、翻訳されたものからでももっと論理と格調を感じる。けっきょく彼自身も、一番根底的なところへの、とくに日本の一般読者や知識階級の人たちの無理解と無関心への不満といらだちが終生消えなかったようだ。晩年はアメリカヘ去ったが、しかしてアメリカでもやはり、その側面に関しては満たされないままであったようだ。「私はオセンチで余り長い間大衆のお相手をし過ぎた。」「なるほど何十万人かの人はそれをカンゲイした。しかしわたしのカンジンのネライは果たされていない。」「それは私の健康の七大条件の最後の項[無畏、無争、無疑、無為]つまりウソを絶対につかないことを守れる人がタクサンでなかったのである。」と…老子の言葉を思わせるようなことを述懐している。アメリカで大勢の人達にとりかこまれた、外から見れば幸福な晩年ではあるが、やはり思想面での孤独感は最後まで消えなかったようである。いや晩年に至ってさらに強まったように見える。「私は七十二歳をもって、私の東洋医学宣伝世界行脚は一応とじたのである。キリストは三年で成功した。私は五十二年やって成功しなかった」。 ここで夏目漱石の言葉が浮かんできた。漱石は(一八六七〜一九一六)であるから二人よりさらに先輩である。時は日本国の西洋化まっしぐらのなかである。そんななかで漱石は、そのちぐはぐな、しゃにむに西洋化してゆく流れのなかで一人深く悩んでいたようである。「現代日本の開化」(一九一一年和歌山における講演)で、漱石自身のなかでわだかまっているこの問題──現在進行中の性急な日本の西洋化という現象──について、実に明噺なそして忌悼のない見解を語っている。当時としてはこのように現状の深部を直視して、それに対して自分なりに何らかの回答を見出そうと真剣に取り組んで悩んでいた人は稀であったのだろう。その孤立感をひしひしと感じる。ここで漱石は、開化ということを「内発的開化」と「外発的開化」とに分けて語っている。そして「西洋の開化は内発的であるが、現代日本の開化は外発的である」と。そして「内発的というのは内から自然に出て発展するという意味で、ちょうど花が開くように自ずから蕾が破れて花弁が外に向かうのをいい、外発的とは外からおっかぶさった他の力でやむ得ず一種の形式を取るのを指したつもりなのです」という。「おっかぶさった他の力」とはもちろん西洋文明のことである。そして西洋の場合は自らの内発によって現在の開化に至っているが、日本の場合は外発…西洋の開化を大急ぎで形式だけを模倣することによって開化しようとしている状態であると言う。 「たとえばこれは学問を例にお話するのが一番早分かりである。」といい「西洋の新しい説などを生かじりにして法螺を吹くのは論外」としても、「本当に自分が研究を積んで甲の説から乙の説に移りまた乙から丙に進んで、毫(ごう)も流行を追うの陋態なく、またことさらに新奇を衒うの虚栄心なく、全く自然の順序階級を内発的に経て、しかも彼ら西洋人が百年もかかってようやく到着した文化の極端に、我々が維新後四十五年の教育の力で達したと仮定する」と、そこでは、「体力脳力共に吾らよりも旺盛な西洋人が百年の歳月を費やしたものを、いかに先輩の困難を勘定に入れないにした所でその半ばに足らぬ歳月で明々地に通過し了るとしたならば吾人はこの驚くべき知識の収穫を誇りえると同時に、一敗また起つ能わざるの神経衰弱に罹って、気息奄々として今や路傍に坤吟しつつあるは必然の結果として起こるべき現象でありましょう。」といい、そして「現に少し落ちつい考えて見ると、大学の教授を十年間一生懸命やったら、大抵の者は神経衰弱に罹りがちじゃないでしょうか。ピンピンしているのは、皆嘘の学者だと申しては語弊があるが、まあどちらかといえば神経衰弱に罹る方が当たり前のように思います」と。 これは美術などを例にすれば具体的に眼に見える形になっているので、もっと分かりやすい。すでに度々言っているように、ここ百年ぐらいのあいだに西洋で次々に起きた新しい流派を、わが国の美術家も、我々自身の内発ではなく、西洋からの外発によって、描き方…形式だけを「おっかぶされたかのように」して次々に模倣してきたのであった。そしてそれが歓迎され喝采されたのであった。近・現代美術史とは、極端に言ってしまうと、その・おっかぶさってきた無数の形式や美的思考によって展開・開化してきたといっても過言ではないように見える。やはり「ピンピンしているのは皆嘘の美術家といっては語弊があるが、まあどちらかといえば神経衰弱…欝病…に罹る方が当たり前のように」思えるのは今でも同じである。漱石はつけくわえて「この理屈の開化はどの方面へも応用ができるつもりです。」そして、この「現代日本が置かれたる特殊の状況によって吾々の開化が機械的に変化を余儀なくされるためにただ上皮を滑って行き、また滑るまいと思って踏ん張るために神経衰弱になるとすれぱ、どうも日本人は気の毒と言わんか、誠に言語道断の窮状に陥った者であります」といっている。事実、漱石しばしば神経衰弱やまた胃病を患い、そして四十九才という若さで生涯を終えている。 けれども、それは当時だからこれほど深刻であったのだ、という感想をもつ人もいるかもしれない。しかし現代日本でもこの窮状がとくに変わったわけではない。ただ表面の状況が──欧米化が格段に進み、都市の観景や生活環境や欧米の知識が当時よりいよいよ普及し──その文化も文明もわれわれの共同財産のように観を呈してきたからである。たしかにそれは人類の共同財産ではある。しかし走っている車になりふりかまわずいきなり飛び乗ったという感は否定しがたい。しかし乗車時間の経過とともに、やがて初めからのっていたような気分になり、自分の車のようにも思えてくる。たしかに、その文明形態は今まで未開発国といわれた国々を巻き込んで広がりつつあり、世界はますます一様化の方向へ加速しているようにもの見えるのだ。しかし、だからといって、こと創造に関しては、その彼らの「開化」してきた流れに簡単に便乗して、それを土壊とするのでは──そしてその文明がもしかしたら開花や発展ではなく崩壊過程であるとするならば──それはきわめて危険な流れにこぞって合流してしまったことになる。いずれにしても、おのれ自身の根っこからの自然な「開化」ではなく、上辺だけの合流で、そしてその先端に立ったつもりになって、現代芸術を切り開いていると思い込んでいるのだとすれぱ、やはり「百年のところをその半分にも満たない年月で見習う」という、大急ぎの不自然な「開化」には、どこかに大きな無理があり、それが自身の内部に空洞を、無意識のうちにもますます大きく育てているのだ。 かって池田満寿夫はアメリカでの個展の際、タイム社のインタビューに答えて「モダンな工業国ゆえにモダンアートの存在する理由を述べても少しも理解されなかった」といい、「わたしは外国の記者に向かって、私たちは小学生のときから西洋方式で学習することを課されて来て、それに何の疑いももたない生活環境にいたことを説明した。西洋の遠近法や明暗法や色彩処理も学校教育の中で課せられてきて、フォービスムやダダやシュール・レアリスムにいたるまで、それらの芸術は同時代という、疑いもない思想によって私たちのものだったのだ」といった。しかしこれは客観的に聞いたならば不思議な意見であろう。教えられたからその通りにやった、というのと変わりなく、創造とは程遠い考え方といわざるをえないであろう。しかし、今現在でもこういう状況は特に変わってはいない。場面と配役が変わっただけで、ことはますます過激な空回りなっているかもしれない。 桜沢如一は、第二次世界大戦直後に、フランスで出した『道の原理』(一九五二)のなかで言っている。「ある国民が平和と自由に生きる文明の基礎とは何なのか、また固有の文明を根絶やしにされた国民の運命がどれほどみじめなものであるか」といい「文明の母体を根こそぎ取り払われた国民が、遅かれ早かれ根なし草のように絶滅するのは火を見るより明らかである。」そして「日本は余りにも軽率に自国文明を捨て去り、他国文明を採用した。おそらく他国文明の方がより美しく、より力強い、と思ってのことであろう。だが、しかしだ、それは全く違った、まるっきり反対の文明だった。」と。 (以上)
|
|||
「負けること勝つこと(60)」 浅田 和幸 |
|||
「人類社会の急変貌〜科学と神の座標軸からの吟味」 深瀬 久敬 |
|||
【編集あとがき】 |
|||
| - もどる - | |||


編集発行:人間地球社会倶楽部