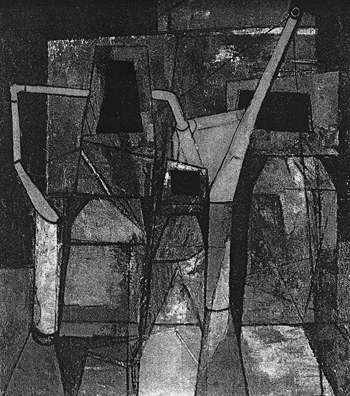第106号 |
|||
| 2009年11月01日 | |||
「問われている絵画(97)-絵画への接近17-」 薗部 雄作 |
|||
わが国の戦後美術の経過を見ていると、多くの画家が一九五〇年代によい仕事をしているという傾向に気がつく。数年前になるが東京ステーション・ギャラリーで小山田二郎展を見たときもそのことを感じた。全体を通してとくに目だったスタイルの変化や乱れは見えないが、やはり五十年代の作品とそれ以後の作品をくらべると、やはり前者の方が作品に純度や張りがあるのだ。それ以後がよくないというのではない。しかし、五十年代の作品の方が、絵画へのひたむきさや造形的な集中度が感じられるのだ。以後はそれがやや鈍り、かわって生(なま)な情念のようなものが座を占め、そして饒舌にもなり、やはり、なにかが変わってきているように見えるのである。これは画面だけの問題ではなく、画家自身の内なるものが大きく関わっているのだと思う。が、さらに時代状況の変化が大きく関わっているのだとも思う。なぜなら冒頭でふれたように、これは小山田二郎だけではなく、一九五十年代に登場して脚光をあびた画家たち──作風やその後の変化の様相はそれぞれ微妙に異なるとはいえ──にもやはりいえることであるからだ。すぐに思い浮かんでくる画家だけでも玉置正敏、森芳男、鶴岡政男、麻生三郎、池田龍雄などがいる。これは目だった画家だけではなく、とくに目を引くことのない多くの画についてもいえることである。
一九五十年代! …わたしは一九五一年に高校一年生であった。油えの具で描きはじめ、それまでの水彩画とはちがう濃厚な、なにか体感的な手応えのある素材に魅せられて、描くことへののめり込みが一段とエスカレートしていた頃である。それまで、とくべつ焦点のなかったわたしのなかで、はじめて美術が焦点のようになってきたのであった。とにかく描くことが面白く…対象…画面…自分…とが一体となる恍惚感が、わたしをますます引き懸け、引き込んでいくのであった。こんなに全身的に夢中になって、なにかをやるということは今までになかったことである。わたしは外界……学校への行き帰りの自転車から見る風景や、また身の回りの目に入るもの何でも〈描く〉ということを念頭にして見るようになっていた。 そんなあるときである。学校の帰りに町の小さな書店でなにげなく雑誌のコーナーを見ていると、ふと「美術手帖」(一九五一 四月号) という雑誌が目にとまった。はじめて見る雑誌の名前である。どんな内容なのだろう。とくに期待もせずに、手に取って開いて見ると、今まで見たこともない海外や日本の画家たちの作品や情報が眼に飛び込んできた。未知の世界……魅惑がまるで感電したかのようにわたしをとらえた。わたしは即座に買ってしまった。自分で雑誌を買うなどということは初めてであった。今から見れば、たいへんうすっぺらい粗末な雑誌であったが、美術の世界のことをほとんど知らなかったわたしに、それは、まるで乾いた砂に水がしみこむように浸透していったのであった。わたしは雑誌のすみずみまでくり返し読んだり図版を眺めたりした。その「美術手帖」は今でも手元にある。 目次を見ると次のようになっている。 美術手帖 No 41 1951 口絵 原色版 デビュッフェ 二重自画像 オズヴァ 赤鉛 クラーベェ 白い椅子 スーラ クールブヴォワの橋 アングル トルコ風呂(部分) 写真版 海老原喜之助 殉教者(サン・セバスチャン) 伊藤憲治 リンゴと椅子 ヴドウ 麦刈 ロルジュ 静物 駒井哲郎氏 アトリエ アングル 奴隷の居るオダリスク グラビヤ版 ミノオ 椅子の静物 オージャム アリエ河の小鳥 フランセス 扇風機 ヴェナール フランスの村 アングル スブィンクスの謎を解くオイディプス アングル モアッシェ婦人像 アングル グランド・オダリスク アングル 奴隷のいるオダリスク 本文 アンリ・マチス展実現す 猪熊弦一郎 一つの問題 土方定一 『二重自画像』解説 滝口修造 ドンゲンの警句 大久保泰 ブラックの映画 硲伊之助 バレエのデコオル 芦原英了 私の希望する美術館 猪熊弦一郎・三好十郎・長谷川三郎・今泉篤男 「赤鉛」解説 滝口修造 伊藤憲治写真展評 木村伊兵衛 雑誌の表紙 茂原茂 シュールレアリスムと アブストラクトアート 植村鷹千代 東京美術地図 茂原茂 佐藤敬論 竹林賢 自画像 桜井浜江・桂ユキ子 双曲線 駒井哲郎アトリエ訪問 佐藤朔 「クールブヴォワの橋」解説 岡鹿之助 技法ノート 筆のはなし 展覧会評 憶い出のアングル 伊原宇三郎 「トルコ風呂」解説 嘉門安雄 海外ニュース これで全内容であるが八十一ぺージという薄い雑誌である。しかし、これは今でも見応えがある。体験と結びついた懐かしさがあるのでよけいにそう思えるのかもしれない。スーラやアングルが脳裏にやきついたのもこのときであった。とくにグラビアページのアングル作品は、顔や手の部分が一ぺージ大に拡大されていたので、はじめて見る『スフィンクスの謎を解くオイディプス」の異様な横顔や「グランドオダリスク」の流麗な上半身に、わたしはつよい印象を受けた。スーラのスタティックな「クールブボワァの橋」も岡鹿之助の解説とともに記憶に刻まれた。また、駒井哲郎という新進版画家も、この雑誌の訪問記ではじめて知った。しかし、そのときには、彼の一連の作品は、とくに抵抗はないもののよく理解できないのであった。文学者・佐藤朔のアットホームな叙情的文章につられて、わたしもそのような気分になって、なんとなくロマンチックに眺めていたようだ。たしかに、今から見るとクレーの影響を感じさせる一種叙情的な作品のように見える。しかし、わたしはここでも思うのだ。冒頭でふれたように、彼の作品も一九五〇年代のものに、もっとも迷いのない素直な感性の肌を感じるのである。 それはそうと、当時のわたしには、この雑誌に掲載されている図版のなかで、まったくわからない絵がいくつかあった。とくにジャン・デビュッフェという初めて聞く画家のよ「二重自画像」という作品が皆目わからない。赤や黄や緑の原色がぎらぎらして生々し、そしてなによりも顔の表情も異常だ。今までこのような絵は見たことがない。はねつけられるだけで、美感などはひとかけらも感じられなかった。これが絵であろうか!わたしの美的感性に入ってくる余地はまったくなく、何度見ても駄目であった。しかし、その気味悪い強烈な印象だけは記憶にやきついた。そして思ったものだ。わたしにも、このような作品がわかるようになるときが、いつかくるのだろうか、と。というのも、数少ないカラーぺージの一枚として載っているということは、世界的にも評価されているのに違いないからである。 そして、もう一枚はアーサー・オズヴァというアメリカの画家の「赤鉛」という抽象的な作品であった。当時アメリカでは注目されていたようであるが、今ではまったく聞かない名前である。強烈でもないが、そして際だった個性も感じられないが、しかしわたしには、やはり、わからない絵という印象がつよかった。とはいうものの、こちらの方が「二重自画像」ほど衝撃的ではなく、抵抗は少なかった。よくわからないのは同じであったが、まったく不可解というほどでもなかったからである。なにか建物…工場のようなものが抽象的に描かれているようにも見えたのである。いずれにしても、わからない絵を前にして、どこがよいのだろう、何をポイントにして見ればよいのだろう、と不可解な気持ちのまま絵のなかをしきりに探したのであった。どちらの作品も滝口修造という人の解説であった。解説で「二重自画像」のデビュッフェについては、「アメリカヘ行ったことは聞かなかった」が「彼の活動はサロン画壇よりも、ジャン・ポーランとかアンリ・ミショオなどの先鋭な文学畑の人々と親しく交わって、NRF系の雑誌「プレイヤード」などに寄稿している前衛作家の一人である」と書いてある。すべて聞いたこともないことばかりであるが、ここで滝口修造という名前が、こういう難解で前衛的な作品とむすびついて、他の解説者とは違う、美術だけではなく世界の文学や思想にも詳しい、なにか鮮烈で一種特別な印象として、わたしの脳裏に刻み込まれたのであった。
|
|||
「負けること勝つこと(62)」 浅田 和幸 |
|||
「人間の存在についての再考」 深瀬 久敬 |
|||
【編集あとがき】 |
|||
| - もどる - | |||


編集発行:人間地球社会倶楽部