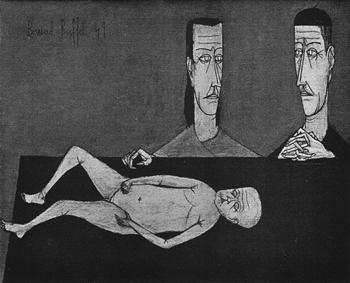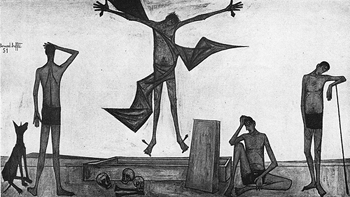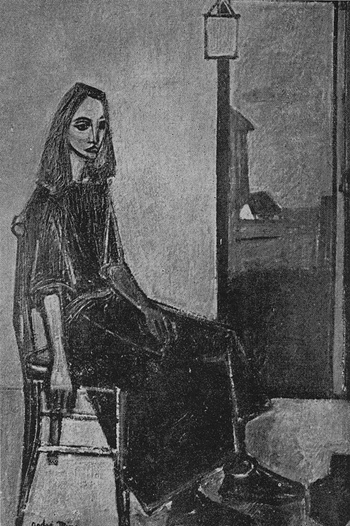第107号 |
||||
| 2010年02月08日 | ||||
「問われている絵画(98)-絵画への接近18-」 薗部 雄作 |
||||
| それにしても一九五〇年代には多くの美術雑誌があった。時代の要求でもあったのだろう。たぶん人々の美術への関心が今よりも高かったのだ。それらの雑誌を支える読者がいたのであるから。もっとも、今のようにメディアが多様でなかったということもあるかもしれない。おもな情報としては新聞と雑誌とラジオだけであったのだから。また、現在のように海外からの頻繁な美術展というものもない時代であった。ということで雑誌は欧米やわが国の美術の情報を知る唯一の媒体といってもよい存在であった。そして、それは単に情報の媒体だけではなく、美術の評論誌の性格も合わせもっていたので、画家たちも美的・精神的な指針や刺激を受けていたのだと思う。店頭には単行本の美術書もまだそれほど多くはなかった。 当時…五十年代に出版されていた美術雑誌を挙げてみると、「みづゑ」「ATELIER」「美術手帖」「美術批評」「三彩」それに総合芸術誌「芸術新潮」と実に多彩であった。「みづゑ」が最も高度な美術雑誌という感じで、そして「ATELIER」も当時は「みづゑ」とほとんど同レベルの質の高さがあった。今でも当時の「ATELIER」 (一九五一年八月号)が一冊手元にある。内容にひかれて自分で買ったものだ。 目次を見ると次のようになっている。 3 和田定夫 オム・テモアン 14 富永惣一 野口弥太郎君の絵 21 難波田龍起 秘められた画家の魂(高村千恵子の切り紙絵の遺作展について) 22 宮崎揚子 伯母高村千恵子のおもいで 27 中川暢子 ゴヤ 45 岡鹿之助 アンリ・ルッソウは日曜画家ではない 48 宮田重雄 ルッソウの牧歌 66 勝見 勝 白い眼・黒い眼 13 コンメト 41 展覧会 68 寒暖計 70 記録 表紙・植木茂(案) 冒頭の「オム・テモワン」とは美術グループの名称で、当時フランスで抽象絵画の隆盛に対して登場した社会性をおびた新具象ともいえる青年画家たちである。ここで取り上げられているのはベルナール・ロルジュ、アンドレ・ミノー、ベルナール・ビュッフェなどであるが、これらの画家は一種鮮烈な印象としてわが国の美術界にも入ってきた。ロルジユは大胆で重厚な静物や人物などを描き、ミノーもまた人物画や静物画が多かったが、ほとんど灰色にちかい黄土色で、強靭ではあるがどこかさびしげな魅力があった。しかし、もっとも衝撃的だったのはビュッフェである。なにか有無をいわせず引きつけるものがあった。魅力的というのではない。引き伸ばされて、硬直したような人体フォルムの望感感が衝撃的だったのだ。しかし、絵に夢中になったばかりの高校一年生の、さしたる苦労も厳しい孤独の体験もないわたしには、むしろ気持ち悪いものであった。けれども、その時はまだ意識の奥底に隠れていた孤独の地層がつよく衝撃されたのだと思う。また、当時…大戦後まもない荒廃した時代的雰囲気も大きく手伝っていたのであろう。紹介者の和田定夫は「ビュッフェは二十三歳でミノーは二十八歳という若さである。しかもビュッフェの作品はピカソやマチス等と同じく国立近代美術館に収められている」と書いている。ここでも、無名の若者を、作品さえすぐれていれぱ即座に評価するという美術館の姿勢に感心する。しかし貧しく孤独な若者が、このあとにわかに世界的なスターになるのであるが、その後の経過は知っている人も多いと思う。時代の寵児となったビュッフェは個展のたびに大変な話題となってわが国の雑誌や新聞にまで報道された。そして「サーカスシリーズ」や「風景シリーズ」などビュッフェ独特の作品が次々に描かれていった。衆目注視のなかで持てる才能は全開されていった、と見えた。画家自身もおのれの天才を自在に発揮しているとの意識があったかもしれない。たしかにずば抜けた何かがあった。ビュッフェ展はまるで事件のようなおもむきで報道された。当時はわが国でもビュッフェ・スタイルの模倣者が目についた。 けれどもやはり、少しずつ、あるいは急速に、以前とは何かが違ってきている。そして生涯の画業を見渡すと、芸術家としてかならずしも素直な成長をとげたとは思えない。若き日、ひととき厳しい孤独と向き合って真摯に創造した芸術家も、絶賛の嵐と商システムのなかで、いつしか芝居がかった制作行為に転化されていったようにも見えるのだ。もはやかつての絶望的ではあるが清新な精神世界は消えていて、今はあがきにも似た濁った絶望感に変わったようにも見える。おなじく同時代の生き、やはり細長い人体の絵画や彫刻の仕事で注目されたジャコメッティなどとは対照的な芸術家の生き方だ。ジャコメッテイは世界的な名声をえてからも、依然として生活も制作姿勢も変わっていない。薄暗い陋屋のようなアトリエで黙々と、とり憑かれたような悪戦苦闘の制作をつづけている。しかし、ビュッフェ作品の経過を見わたすと、やはり一九五〇年前後…貧しく孤独の時期…の作品がもっともよいものに見える。芸術家にとってはもっとも苦しい時期だ。しかし作品は正直だ。そこでは心的な切実さと彼の資質とが一体となって、絶望的ではあっても純潔で豊かなものになっている。たしかに、孤独で貧しい芸術家が、にわかにスターになってゆくのは、画家としても生活者としても幸福なことにはちがいない。が、しかしやはり、芸術家の素直な成長ということになると、必ずしもそれは適した環境でも境遇でもないようだ。そこではやはり、肝心の何かが失われてゆく。芸術はむごいものだ。けれども、あれだけ商資本の荒波にもまれながらも、ビュッフェ自身の質を貫きとおしたのはまだしもである、といえるのかもしれない。しかし天才の無惨を感じる。ロルジュもミノーもその後ほとんど名前を聞かない。ミノーにっいては、後年何かの本で、きわめてなまぬるい抽象画を描いている写真を見たことがあるが、かつての心が何もないのにわたしは大変失望した。
詩人リルケは芸術家のこのような成り行きを極度に警戒していた。そして『マルテの手記』のなかでいっている。「名声とは、成長する人間を途中でみんなが寄ってたかって打ち壊すことであり、その者の工事場に群衆がどやどや侵入して、せっかく積んだ石を押し崩してしまうことだ、」と。しかし、貧しく孤独な青年芸術家にとって名声ほど切望するものもまたないであろう。それは現状を一挙に打開するように思えるからである。そしてたしかにそれは打開ではあるだろう──極端に感受性の敏感なリルケも半世紀前のパリを、異国の貧しく孤独な詩人として、まるで妄想患者のように孤独地獄のなかを生きていたのだ。しかしリルケは、それを自覚しておのれの詩人の運命を耐えて生きた。わたしはビュッフェの初期作品「自画像」や「女」を見ると、そこにリルケが重なる。けれども二十世紀後半の商世界のジャングルを、芸術家の素裸の心で生きるのは並大抵のことではない。まして世間的な経験のとぼしい青年芸術家に、突然当てられた強いスポットライトである。物見高い一般観衆も目を向け、どっとおし寄せる。そこでは、芸術家へ襲いかかる有形無形の外的圧力もまたはかりしれないであろう。微妙繊細な芸術の魂─翼─は名声の嵐によってぐしゃぐしゃに折れて墜落する。しかし外見は社会的にも輝かしい成功者だ……。 リルケの警戒心はさらにいう、「どこかにいる無名の青年よ、君の心に戦慄させるようなものが起こってきたら、君を知る人間がいないことこそ大切なのだ」。「孤独な、疎外のなかにある作家よ、世人はおまえの名声に乗っておまえに追いついてしまったではないか」。「彼らがおまえに心底から逆らったのは、どれほど前のことだっただろう。その彼らがいまは、みずからの同類のようにおまえをもてあつかっている」。だから「世間の人の口にのぼる根も葉もない風評にもましてそれを真剣にとってはいけない。自分の名前は駄目になったと考えて、脱ぎ去るがよい」。そして「どれでもいい、別の名前をつけて、深夜神がその名を呼ぶことができるようにせよ」と。(生野幸吉訳) すでにふれたが、リルケもまた二十世紀初頭のパリで貧しく孤独な日々を耐えていた。当時のリルケの面影をジャン・コクトオが語っている。「毎晩おそくまで、いつも隅の窓の一つに明かりがとぼっていた。ぼくはずっと後になって初めてそれが誰の部屋であったかを知ることができた。あの夜ふけのランプはロダンの秘書をしているリルケだったのだ」。「僕はすでに世のなかを知りつくしたつもりでいた。そして、無智な、僣越な、くだらぬ青春の日をすごしていた。名声が僕をそこないはじめていたのだ。僕は無名や失意よりもなお始末にわるい名声がある一方に、すべての名声より一層偉大な失意の時代があることを知らなかった。リルケのとほい友情が、この夜ふけのわびしいランプの光をとおして、他日どのようななぐさめを与えてくれるか、まだ僕は少しも気づかずにいた」と。(大山定一訳) 「美術手帖」はやや入門者向けという側面もあったが、内容自体がとくに軽いわけではなかった。「三彩」は日本画を主にした専門誌であった。そして「芸術新潮」は現在でも続いているが、つくりも内容もその頃とはまったく変わってしまった。当時は文芸雑誌などと同じようなサイズの分厚い雑誌で、音楽、演劇、工芸をも含む芸術全般を網羅したたいへん読み応えのある雑誌であった。しかし、ユニークであったのは「美術批評」である。この雑誌は比較的短期間で廃刊になったが、いわば美術評論の専門誌で、紙も粗末でほとんど文字ばかりで厚さも数ミリであった。あのような雑誌は戦後美術史のなかでも異例であろう。それだけではなく、それ以前にもそれ以後にも見たことがない。一時期とはいえ、それほど美術への気運も高かったのであろう。 けれども、思いかえせば不思議である。わたしは一九五一年の四月に「美術手帖」を読みはじめたばかりである。「オム・テモアン」の記事も同年の「ATELIER」八月号である。たった数ヶ月で、こんな時代の先端美術まで関心をもち、感受できるようになっていたのであろうか。たしかに、若者の美的・知的好奇心はするどく敏感ではある。しかし、それほど作品も衝撃的であったのだろう。また第二次大戦後まもない、同時代のもつ共通の雰囲気も手伝っていたのかもしれない。加藤周一は『現代美術2』(昭和三五年 みすず書房)の巻頭の論文で、「ベルナール・ビュッフェの時代は、われわれの時代である。これが彼の芸術のわれわれにとっての意味だ」といって、ビュッフェ芸術の最大の特質を〈時代性〉ということに結びつけ語っている。しかしまた、同書の別の解説でピエール・ド・ボアデフルはいっている。「偉大な芸術というものは、時代のポスターであることに甘んじない」。時代の証人であると同時に、「その時代だけにしか属していず時代とともに姿を消してしまうような恐れのあるものを、はねつけねばならない」。そして「ビュッフェのあの苦いマスクが、より深く恒久的なヴィジョンをかくしているかどうか。そして、彼の画布が、フランソワーズ・サガンの苦い小説と同じように、今の時代の反映であると思われている時代から、自由の身となることができるであろうか? それは未来が教えてくれるであろう。」(青山典子訳) その後、時代は変転をかさねて六十年が経過した。そして「その時代にしか属していない」ものはほとんど消えていった。それはまた、そっくりわたしの生きてきた時代でもあった。そしてそこで見てきたものの多くは、やはり、時代に密着しすぎていたがために、時代が変わるとともに、舞台からも消えていったということであった。
|
||||
「負けること勝つこと(63)」 浅田 和幸 |
||||
「機能主義への潮流について」 深瀬 久敬 |
||||
【編集あとがき】 |
||||
| - もどる - | ||||


編集発行:人間地球社会倶楽部