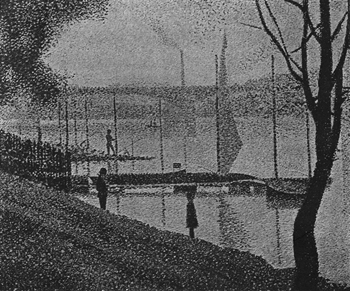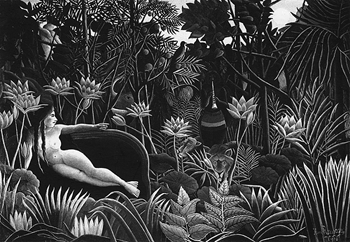第108号 |
|||
| 2010年05月23日 | |||
「問われている絵画(99)-絵画への接近19-」 薗部 雄作 |
|||
| けれども、わたしがこの雑誌…「ATELIER」を買ったのは、むしろ岡鹿之助の「アンリ・ルソーは日曜日の画家ではない」や中川陽子の「ゴヤ」の記事とともに作品写真が多数載っていたのに引かれたからだった。いや、ルソーもゴヤもビュッフェも一緒になってこの雑誌に強く引かれたのだと思う。 ルソーという名前は、幼稚な感じの絵を描く画家として知ってはいたが、それまでとくに親しみを感じていたわけではなかった。ましてそれを自分との関わりで見たことはなかった。一見稚拙な印象なので、面白くはあるが、とくに学ぶべきものはないように思い込んでいたのであった。その頃のわたしは、セザンヌやゴッホなど印象派近辺の画家たちが模範のように見えていたので、幼稚っぼいルソーの絵は、やはり、日曜日だけ描いていた素人画家だから、目鼻のつり合いなどはあまり考慮しないので……というよりうまく描けないので、このようになってしまったのであろう、というくらいに漠然と思っていたのであった。 ところが岡鹿之助は、この文章の冒頭からいうのだ、「ルソーの絵が幼稚だからということで〈日曜日〉の画家というのなら、こんなばかげたことはない」。また「税関に勤めているかたわら描いていたからというのであれば、それは間違いだ」と。そして、当時アカデミックな絵をみなれている人たちには一見不思議に見えたルソーの作品も、それは「希代な独創の天分に恵まれた無垢な手で描きだされた〈現実〉であった」ので、一般に見慣れているプロポーションとは違う、「現実でないルソーの世界が、人々の眼に子供らしくも奇妙にも見えたのは、仕方がなかっただろう」と。けれどもルソー自身は少しもおかしな絵を描いているという意識はなく「自分は当時の生きている人々の間では、もっとも重要な地位を占めている一人であると確信していた」というのだ。つまり、できなくてこうなっしまったのではなく、おそらく彼のなかではごく自然で、色彩や造形のリズムやハーモニーなどからみても──ルソーは音楽家でもあって作曲作品もある。数年後になるが『みづゑ』のルソー特集に、ルソーの作曲した「クレマンス」という楽譜が載っていたので、わたしは知人にピアノで弾いてもらったことがある──自分はまったく正しい作品を作っているのだという確信があったのであろう。そのために、世間の人々の眼には幼稚と見える絵を描いているにもかかわらず、「その強靭な信念が作品に底流して」いるので、「人々に抵抗をあたえていたことも察せられる」と。当時のほとんどの人々の眼には、まだアングルやドラクロアなどの堂々とした写実作品や、また時のサロンを占めていたアカデミックな均整のとれた作品のイメージが美意識を支配していたのであろう。そのような眼でルソーの作品を見るならば、それは当然異様に見える。そして目鼻のつりあいさえ不自然な幼稚っぼい絵を描いているにもかかわらず、それを堂々と押し切っているのが、多くの人に抵抗感や嘲笑をまねいたのであろう。
けれども不思議なことに、今、あらためてルソーの作品をよくよく見ると、この下手そうに見える顔かたちが、画面全体のなかではとてもしっくりしていて、ここへいわゆる正確なデッサンの人物を入れかえたばあいを想像すると、全体の造形的リズムやハーモニーが壊れてしまうのを感じる。つまり一見不自然に見える顔かたちも、画面のなかでは部分と全体との関係が見事に調和し交響しあっているからである。したがって、たとえば、いわゆる素朴派展──ナイーブな画家たちをあつめた展覧会──などで、多くの本物のナイーブ画家たちの作品のなかでルソー作品を見ると、彼の作品だけが全然ちがう雰囲気なのだ。一見ナイーブそうに見えるのであるが、画面全体の格調がまるで違うのである。ヴァルールが正確で空間が透明である。一種古典的で静謐なのだ。やはり彼は根っからの素朴派ではないのである。つづけて岡鹿之助はいう、「秩序ある構図。ノーブルな色の階調。色彩の光輝性。音楽のようにリズミカルなヴァルール。こんな表現の技術は、一朝一夕で獲得できるものではない。」といって、日曜日だけの画家などではなく本格的なそれもきわめて傑出した画家であることを強調する──岡鹿之助のアトリエにはルソーの「蛇使い」の複製がかけられていた──たしかに初期の作品にもすでに「独自の様式は窺われるが、ヴァルールの破綻など眼につきやすい。」まだ「無数のニュアンスに富んだルソーの緑」は現れていない。しかし一九〇〇年代に入ると、熱帯の異国風景が発表されるようになり、独創にみちた不思議な詩の世界が展開する。様式は密度をまし、表現技術は驚くほどの重厚さに輝きだす」のである、と。 ルソーの友人ウーデの語るところによれば、「税関史の職を辞してから亡くなるまでの二十余年の間に、普通の人間が五十年間に費やすほどのエネルギーを傾けつくし、ルソーは勉強をつづけたのである。眠る時間や休息の時間さえ縮めて」。そして「ルソーの描いた肖像画ほど本人に似ていないものもめずらしいといわれるが、」これもまた、別の友人ジャリによれぱ「ルソーが肖像画を描く場合に、眼、鼻、口、耳などの寸法を絵筆の柄で計って、パースペクティヴから生じる釣り合いの誤差には一向頓着せず、その寸法で描いていたからである」という。なんという不思議なモデルヘの忠実であろう…これもなぜか強く印象づけられた…しかしそれがまた、ルソーの絵を見た瞬間わたしたちを釘づけにする不思議さの要素にもなっているのだ。目や鼻や口は、それぞれしっかり描いてあるにもかかわらず何か変な感じなのである。「人体の肉色をそのまま現すために、自分の手に絵の具を塗って、皮膚の色と同じ色をだすことに苦心した」という。また「幾十枚の木の葉を蒐めてきては、緑の変化の勉強をしたり……というふうに、ルソーは彼らしい独特のやり方で自分の色を豊富にしていった」のであった。いわれてみれば、ルソー作品のなかでも、とくに植物の葉っぱの表現に特徴がある。一枚一枚がきわめてしっかり描かれているのだ。何の木かは分からないが、とにかく葉っぱが並列的にきちんと描かれ、画面全体をおおっている。その大小の形と色の階調がきわめてリズミカルで心地好いのだ。そして全体はきわめて整然としたものとなり、部分と全体は有機的に連動して、いやがうえにも主題を盛り上げて色と形を交響させているのだ。 それは一つの示唆であった。そのときはまだ漠然としていて、明確な意識までにはならなかったが、わたしは何かを感じとっていたのだと思う。一年後に『美術手帖』で滝口修造の「ポール・クレー」を読んだとき、そこに載っていたクレーの「植物園」に惹かれたのも、だぶん共通した何かを、わたしの深部では感じ取っていたのだろう。しかしこの時も、そんなことは少しも意識には上らなかった。それもすべて今思えばである。さらに、はじめて『美術手帖』で見たスーラーの「プールヴボォワの橋」も何回も熟視していたので、この絵の世界もそれに重なっていたかもしれない。岡鹿之助はこの絵の解説で、「このように、垂直線と水平線が秩序だって組み合わされると、人の心に、しずかな美しさを伝えるのである」といい、「自然のありのままの姿は、けっして、このように秩序だっていない。」それを「スーラーは、このように秩序立て、線のコントラスト(すなわち水平線と垂直線が直角に交わること)によって、しずかなる美しさを整えようとする」のであると。これもわたしの心にうち込まれた言葉であった。 これらの作品を並べて眺めると、その画面は一見それぞれまったく違うように見えるのであるが、しかし、その表面をこえて、画家の表現意思の根底にまで眼をむけてゆくと、そこにはまた、共通する何かが見えてくるような気がするのだ。それをあえて言葉にしようとすれば、それは、ある要素や行為の〈くり返し〉ということになると思う。ルソーの樹の枝や葉っぱの連なりも、クレーの平行する線の集合も、スーラーの気の遠くなるような点描の垂直線と水平線の交差も、すべて単純なそれぞれの要素の繰り返しや組み合わせである。しかしそれが、思いもよらない深い世界をつくりだしているのだ。たとえば熱帯の「異国風景」シリーズを描いていた晩年のルソーは、樹木の葉についてソフィチ(イタリー人、ルソー賛美者で画家・著作家、一九一〇年にイタリアの雑誌「ボォーチェ」に本格的なルソー論を発表)に、次のように語っている。「二十二種類の緑ですよ。と彼は微笑しながら、満足げに言った。私が少し驚いて見つめたので、彼は実際、二十二の色調の緑を一つ一つ葉の上に塗ったのだのと、葉の残りの部分も同じことをするのだ、と説明した」。ここでふと思い出したが、子供の頃、冬の陽ざしの縁側などで、わたしたちが何かで遊んでいるときでも、女の子たちは、よく編み物の手を終始動かしていることがあったが、それも一向にはかどらない何か袖口のようなものを編んでいるようなのだが、あんなことのいつたいどこが面白いのだろう…それに形あるものが出来たのを見たことがない!…と、わたしはいつも不思議に思っていた。しかし、今思えぱ、あの単純な行為には熱中させる何かがあったのだ。中近東の豪華な絨毯なども、若い女たちが、手で糸を通しながら、一枚の絨毯を何年もかかって織っているのを、いつかテレビで見たことがある。 このたび、わたしは念のためというくらいの気持ちで『アンリ・ルソー楽園の謎』(岡谷公二著)という本を読んだ。そして驚いた。今まで知らなかったルソーという人間が現れ出てきたからである。すると絵もまた少し違って見えてくるのであった。岡鹿之助の文章のときも一種の驚きではあったが、そのときはまだ部分的な紹介だったので、ルソーの生涯について、くわしいことは何も知らないままだった。しかしこの本は評伝である。それも従来の文献をほとんど踏まえた上での著作だ。するとルソーのあの作品が、意外な生活状況のなから生み出されていたことがわかってきたのである。それはわたしの思っていたルソーとは少し違っていた。わたしの思っていたソーは、税関を退職したあとは「二十年の間に、普通の人が五十年間に費やすほどのエネルギーを傾けつくし」たとしても、あるていどゆうゆうと趣味の音楽などに親しみながら制作に没頭していたのであろう、というものであった。でなければどうして、あのように一貫した密度ある作品を生み出すことができるであろう、と。 ところが事実は違っていた。ほとんど終始、生活費や画材費に追われる逼迫したなかで制作されたのであった。そして、「寝る時間や休息の時間さえ縮めて」描かれたルソーのほとんどの作品も、人々からは嘲笑や椰楡で迎えられていたのであった。批評家からも、「ルソー氏は目を閉じて足で描く」といった酷評や、ルソーの作品の前は、いつでも笑うために集まった大勢の人々のため、或る批評家は「わたしはルソー氏の絵に近づくのに苦労した」と書き、別の批評家も、「ルソーの絵のあるところ、人だかりがあり、彼の肖像画や風景画の前で、人々は笑いころげている」と書くのであった。一八九二年のアンデパンダン展では、一部の組織委員の主張により、ルソーの「子供っぼいなぐり描きや滑稽な絵」は、組織の威厳をいちぢるしく損なうとして、「会場のつめたい片隅にかくされ、追放され」たのであった。しかし人々は、「ルソーはどこだ、どこだ?と叫びながら会場中を探しまわり、やがて発見した。」そして「爆笑の渦がバラックを揺するのであった」(コキオ「アンデパンダン展」)。とはいえ、それにしても〈注文〉よって、作品がずいぶん描かれているようなのも不思議である。 しかしながら、多くの作品は失われてしまったという。人々は、まったくルソー作品の価値を認めていなかったからである。しかしルソー自身はそんなことに落ち込む様子はない。ますます制作にのめり込んでゆく彼は、画材店への借金がどんどん増えてゆく。けれども支払いは滞ったままだ。一九〇一年には、その額六百一四フランで「彼の年金の半ばを超える額」に達していたとう。「事は裁判沙汰になって月賦を命じら」れるが、それもなかなか支払えない。そして「金のかわりに、しぱしば自作の絵を商会に持ちこんだ。商会では、それを化学液につけて絵の具を洗い落とし、キャンバスとして再生させた。こうして数々の、ルソーの美しい小品が失われた」という。しかも「これは例外ではない。この時期の彼の多くは、似たような運命を辿ったのである」。そのことは「三十年近く描き続けてきた彼の作品中、現存するものが二百点に満たないとい事実がそれを証する」と。 さらに、彼は絵画や音楽教師としても多忙な毎日を過ごしていたのだ。自宅で私塾を開いていただけではなく、デッサンやヴァイオリンの出張教授もしていたのだ。たとえば一九〇八年の八月十日のスケジュールを見ると、「レオミュール街に二つのレッスンがあり、一つは午前十一時から、二つ目は午後五時半から始まる。」そして「そのあいだにも、いくつかの訪問をしなければならない」用件があるという。さらに、その弟子たちを集めてオーケストラを組織して練習もかさねている。それだけではなく「この時期、ルソーは教会の入口でボンボを売っているころを見られている」ともいう。 これらはすべて死の二年前のことで、ルソーが「異国風景」の傑作群を描いていた頃だ。そしてさらに驚くのは、この熱帯の密林シリーズは、ほとんどが大作(二〇四・五×二九九・〇㎝から一一四×一六二㎝)であるのだが、それがきわめて狭い部屋で描かれていたということだ。ピカソやアポリネールなども参加した有名なルソー家の夜会の日には、一間きりの狭いアトリエの「折畳み式の鉄のベットは隅に片付けられ、椅子が順序よく並べられ、ルソーが三枚の絵と交換した安物の絨毯が床に敷かれ」(ウーデ)て開かれたという。ルソーの熟心なコレクターであり伝記も書いているウーデが、初めてルソーのアトリエを訪問したとき、ルソーは「蛇使い」の制作中であった。そのときの印象をウーデは、「この絵は、ルソーが住んでいた狭い部屋を占めていた。部屋全体に、この絵から発する神秘的な気配が漂っていた」といっている。この絵の大きさは一六七×一八九・五㎝であるが、それが部屋いつぱいに見えるということは、いずれにしても、かなり狭い部屋である。そしてこのアトリエが、居間でもあり寝室でもあったという。その部屋で、「蛇使い」よりもさらに大きい「飢えたライオン」(ニ〇〇x三〇〇㎝)や最晩年の「夢」(二〇四・五×二九九㎝)も描かれた。しかもこれらの絵が「キャンバスや絵の具にも事欠く極貧の中で、」である。「彫刻家のロッソ・ロッシに、画家がこんな場所で暮らし、制作できたなんて信じられない、と言わしめた」という「タゲール街四十四番地の陋屋で描かれたのは特記しなけれぱならない。」と岡谷公二もいっている。
|
|||
「負けること勝つこと(64)」 浅田 和幸 |
|||
「これからの学問の在り方」 深瀬 久敬 |
|||
【編集あとがき】 |
|||
| - もどる - | |||


編集発行:人間地球社会倶楽部