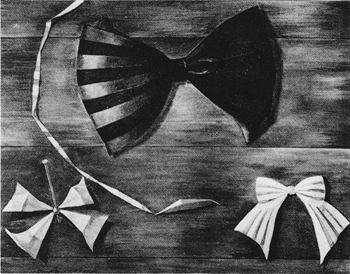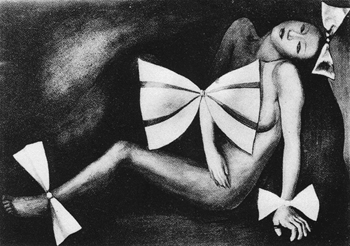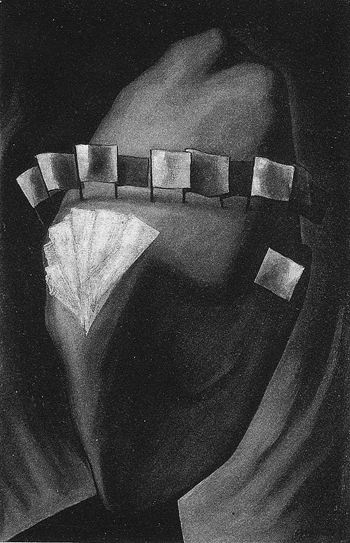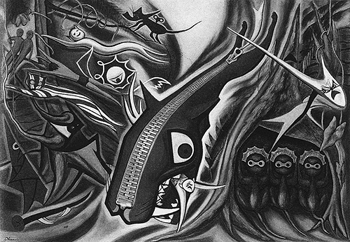第109号 |
|||||
| 2010年08月15日 | |||||
「問われている絵画(100)-絵画への接近20-」 薗部 雄作 |
|||||
| 通っていた館林高校の敷地内に、同窓会館という淡いグリーンの瀟洒な三階建ての津館があった。松林を背にして、いかにも絵になりそうな風情があった。事実、すでに美術の時間に写生もしていた。当時、高校の周辺には松林が多く、わたしの記憶のなかでは校舎全体も松林に囲まれている。その同窓会館の三階が図書館になっていた。「美術手帖」に刺激されて、ますます絵に熱がはいっていたわたしは、美術の世界をもっと知りたいという好奇心から、ときどきその図書館へも行くようになっていた。 そんなある日、たぶん初夏の放課後だったと思う。ほとんど人のいない、がらんとした物憂いような薄暗い本棚の間で、立ったままあれこれ本を開いて見ていると、奥の方から誰かがわたしの方へ近づいてくるのであった。同級生のK君である。入学まもないクラスのなかでも、比較的目立っていたので顔はよく知っていたが、話をしたことはなかった。そのとき、何故か彼が図書館部員であったというのが少し意外であった。K君は数冊の美術雑誌をわたしに差し出して、「これ返さなくてもいいよ。」といった。わたしは反射的に受け取ったが、そしてそんな彼の行為がうれしかったが、なにか釈然としない気持ちもあった。けっきょく得をしたような、少し後ろめたいような気持ちのまま家に持ち帰った。その何冊かの雑誌は、たしか月遅れの「みずゑ」や「ATELIER」だったと思う。図書館では月遅れの雑誌類は処分してしまうのかな、とも思った。しかし、偶然の出来事とはいえ、今から思うと、その雑誌を持って帰ったことは、その後のわたしにとって大変重要な出来事となっている。 そのなかの一冊に…たぶん「みづゑ」だったと思う。「制服の芸術家」という花田清輝の岡本太郎論があった(単行本では『アヴァンギャルド芸術』のなかに入っている)。当時のわたしは、わが国の前衛的な芸術には、まだ関心はなく、というよりその存在すら知らない。だから花田清輝も岡本太郎も、そのとき初めて見る名前であった。といっても、岡本太郎については「美術手帖」四月号に、土方定一の「ひとつの問題 絵画とレアリテ…第三回日本アンデパンダン展の各国の傾向と性格について…」という文章のなかに掲載されていた「室内」という作品を見てはいた。しかしそのときは小さなモノクロ写真だったので、とくに強い印象はなかった。ただ変わった絵だと思った。「室内」とはいうものの、それとわかるのはテーブルくらいで、あとは不可解な物体が空中を舞っているように見え、わたしは、これがなぜ室内なのか? と不思議に思いながら見ていた。しかし、今度の雑誌では一ぺージ大のカラー版であるから強烈である──当時はカラー印刷は一冊に数ぺージしかなかった──しかし、けれども、ここでも依然として岡本太郎の絵はよくわからなかった。「森の掟」という作品であったが、画面中央の巨大なナマズ? のような魚の腹がファスナーなのである。なぜ、魚の腹がファスナーなのか! ゴッホやセザンヌに魅せられている、その頃のわたしにはまったく理解できないのであった。しかし、その不思議さ、そして今風にいえばマンガ的で、原色の生々しさが、やはり強く印象的であった。しかしやはり、わたしの感性はかみ合わず、親しめないのであった。けれども、読み始めた花田清輝の文章はぐんぐんわたしを引き込んでいった。 「あまりにもおのれを主張しすぎる態度には下品なところがあり、ポーの詩が英語のわかる人間にはいささか下品な感じがするのは、すべてが抜け目なく計算されており、強調されなければならない点が、容赦なく強調されているからであり、それはあたかも十本の指に十個のダイヤの指輪のきらめいている光景を連想させる。と主張したのは〔黄金の中庸〕をおのれの唯一無二の信条とするオルダス・ハックスリー──だったような気がするが。」そして「もし、この渋好みの先生が、わが岡本太郎の猛烈な作品──十本の指に十個の指輪はおろかなこと、腕には腕輸を、耳には耳輪を、首には首輪を、さらにまた、しばしば、奇想天外にも、アフリカの土人みたいに、鼻には鼻輪までぶら下げ、全身ダイヤにおおわれて燦然とかがやいているようなかれの作品を見るならば、おそらく全身眼でおおわれた死の天使に出会ったときのように、不意に総毛立ち、口のなかがからからに乾いてしまい、もはやとりすました顔つきをして、対象を批評する余裕など、完全に喪失してしまうに決まっているのだ。」
ほとんど何も知らないわたしは、いきなり知的パンチをくらったかのように、一瞬ふらつく。ポーは聞いたことがあるが、オルダス・ハックスリーなど聞いたこともない。しかし、ともかく、またシャキッとする。「ポーの詩に比べると岡本の絵が、はるかにぎらぎらと不思議な光芒を放ち、」その「下品さにおいてすこぶるたちまさって見えるのは、われわれの環境が、一世紀前のアメリカ…ボードレールの、いわゆる、ガス燈のついている巨大な蛮地よりも、いまなお、依然として、いっそう遅れた段階にあり、ヨリ強くおのれを主張しないかぎり、たちまちわれわれ自身が、粉々に打ち砕かれ、雲散霧消してしまわなければならないからであろうか。」 今では、世界有数の大都市…東京を蛮地! などと想像するのは困難かもしれないが、これが書かれた一九五〇年前後の東京は、敗戦後まもない、まさに混沌とした、しかし熱気にみちた蛮地さながらのおもむきがあった。ここでふと思い出したが、わたしは、中学生のとき一度だけ戦後まもない東京を見たことがある。たしか知人に連れられてやってきたのだ。今では、そこが、東京のどのあたりであったのか見当もつかないが、まだ、あたり一面に瓦礫のちらばる赤茶けた焼け跡のままで、ところどころに突き出た水道管から水がちょろちょろ流れているのが、妙に記憶に残っている。もちろん、これ…「制服の芸術家」を読んでいたわたしも、西洋とはおよそかけ離れた、石やコンクリートの建物などどこにも見当たらない、田舎の草木に覆われた、ふるびた〈離れ〉の、障子に囲まれた薄暗い畳の上で、である。たしかに、わたしたちの多くは、西洋のにおいなど皆無のそんな生活スタイルのなかで、西洋にあこがれて西洋風な絵を描いていた。ここで記憶に刻まれたオルダス・ハックスリーは、その後、十年ほどたってから上下二冊の文庫本『文学と芸術』『社会と文化』を見つけて読んだ。やはり気になっていたのである。 花田はつづける、「あるいはまた、それは、われわれの錯覚にすぎず、岡本にしろ、ポーにしろ、理知と本能とのあいだの釣合いをとることばかり考えている、ハックスリーのような〔紳士〕を腹の底から軽蔑し、理知か本能か──はっきり、いずれか一方の肩をもちそれぞれの立場から、思いきって過度の強調を試みている点において、彼らの下品の程度には、ほとんど優劣はないのだが」──岡本が本能の側にポーが理知に側に──しかし「本能のなかに理知の収斂してゆくばあいの方が、その反対のばあいよりも、常識的なわれわれの眼に、なんとなくどぎつくうつるからであろうか。」「それとも、それは気のせいばかりではなく」、ポーよりも岡本の方が「みずからのなかの理知と本能との対立を、対立のまま、ぎりぎりのところまで激化させていき──ようするに、理知的にも、本能的にも、あまりにもおのれを主張ししすぎているからであろうか。」と、一気に岡本太郎の唱える「対極主義」に入っていくのであった。 対極主義とは、簡単にいってしまうと、人間や現象界におけるもろもろの対極するもの、たとえぱ西や東、昼や夜、理知や本能、硬や軟、その他あらゆる相反するものを対立させて、それをぎりぎりまで強調し、そしてぶつけ合い、火花を散らす──爆発させる──というものだ。ついでにいうと、岡本太郎は晩年になっても「芸術は爆発だ!」と、これを主張していた。 こんな調子でぐんぐん進んでゆく岡本太郎論は、今までに読んだ画家論や名画の解説とはまるで違う。文学、哲学、心理学、民族学、そして数学用語などを縦横に駆使した、一見難解なような文章であるが、わたしは、わかったような、わからないような、にもかかわらず不思議な快感と説得力に引き込まれて読んでいく。 「なるほど環境の影響もあるかもしれない。岡本の滞仏作品には、彼の最近の作品のように、並はずれた騒々しさはみとめられず、うはべは悠々と落ち着きはらっている。」しかしそれは、「うちに沈んでしまっている闘志には気ちがいじみたはげしさがあるが、クレッチュマー風にいうならば、まるで、焼けつく太陽をさえぎる鎧戸でとざされ、森閑としずまり返っているが、内部では、盛んな祭と酒宴のおこなわれているローマの別荘に似て」いる──またも知らない名前や出来事が次々に出てくる──「単純で、堅固で、叙情的で──古典的な理知の機構の鋭さと、浪漫的な心情のながれのあざやかさとが、対立のまま統一されているかのようである」──ここでは対立するものをぶつけ合って爆発するのではなく、統一が支配している……そして初期作品によく描かれているリボンに注目する。「それかあらぬか、これらの作品にしばしば登場するリボンはつねに整然と結ばれており、一度も、風のまにま、ひらひらと翻っていることはない」。そして「なによりも上品な〔芸術〕が好きで、最近の岡本の傾向に、たじたじとなっている、われわれの周囲の作家や批評家たちも、この種の作品にたいしては、よろこんで同調するにちがいない」と。 たしかに、爆発的表現は見られないが、わたしも初期の作品には親しみを感じる。第二次大戦後まもない頃の作品にも、まだその作風はうけ継がれている。例えば「憂愁」(一九四七)という作品がある。後の、勇ましい岡本太郎の言動には似つかわしくないタイトルであり絵の表情だ。ほのぐらい空間に浮く頭部のようなオブジェに立てられた一列の白い旗が、吹き寄せる憂愁の風にはためいている。「うつろなる心に、風がたちそめると/あゝこの旗は/それぞれの傷ましい思い出に戦き/高く、或いは低く/声をあわせ/ハタハタと鳴る」(一九四八年の詩「憂愁」より)。ここではまだ、対極主義は内に秘められたまま意識化されてはいない。憂愁のなかで何かが育まれているようである。そして花田清輝もふれているように、初期作品には実にしばしばリボンが登場している。たしかにリボンは対極主義の象徴的形態だ。両端は激しく対立して外へ伸びひらいているが、しかし中心に結びつけられて、整然と統一されている。岡本太郎の内部では、言葉より先にまず、形による対極主義が無意識のうちにも育まれていたのであろう。「露店」(一九三七)では台の片隅にリボンが並べて売られているし、「机のある静物」(一九三六)では花瓶に大きなリボンが活けられている。「リボンを結んだ女」には、腕や足に大小のリボンが結びつけられ、まるで花のように咲いている。よく知られた「痛ましき腕」では、こちらを向いて伏せている人間の頭部が巨大なリボンだ。すでにリボンは力にみなぎり闘争的ですらある。対極主義の萌芽であり表明であろう。この作品は、第二次大戦の空襲で焼け、戦後になってから再制作されたという。同じ図柄ではあっても、作品のもてる動勢には、かつての原画とは大きな違いがあるのに違いない。 花田はつづける。「しかし誤解を避けるために一言しておくが、これらの作品を貫いているものは、芸術にとって不可欠とされている〈黄金の中庸〉──理知にせよ、本能にせよ、とにかく、極端に走らず、いい加減のところで、対立するものの闘争を終焉させ、妥協や折衷以外のなにものでもない、小綺麗にまとまった、見掛け倒しの統一や調和をもたらす、あの分別臭い〈黄金の中庸〉ではなく、」「相反するもの同志が、いずれも同等の力をもって対立するため、対立したまま、戦線の膠着してしまうばあいにうまれる力学的均衡の原理」からきているのであって、それは、「それを表現する側の懐疑の深さを──おそろしい緊迫感をたたえた、判断中止の状態を思わせる。つまるところ、これらの〈芸術的な〉作品が生まれたのは、当時の岡本が、収拾のみこみさえつかない、引き裂かれた心の持主であっためであり、」「必ずしもその頃のかれが、今のかれと異なり、かくべつ心の釣り合いばかりとろうとしていた紳士だったためでもなければ、あるいはまた、フランスの環境がわが国のそれよりも、はるかにかれの芸術を生むのに適していたためでもないのだ。」 そして、「岡本の最近のきらびやかな作品──なによりもそのはげしい色彩の不協和音のゆえに、つねにこれらの芸術愛好者たちを、茫然自失の状態におとしいれる作品は、〈芸術的〉雰囲気の欠乏している、われわれの環境に負け、心の均衡をとれなくなった岡本が、まるで孔雀が羽でも広げるように、おのれを誇示しようとする衝動に駆り立てられ、あまりにも過度に、みずからを主張はじめた結果でないことは、いま、ここで、あらためて、断るまでもなかろう。」といって、ここでは、はじめに断定したかのようであった「野蛮な環境に対する強烈な自己主張」は否定されて、そして「ポーが当時のアメリカを眼中においていなかったように、岡本もまた、今日の日本をいささかも気にしていない。かれらの視線は、たえずヨーロッパにそそがれており、そうして、かれらの念頭を、終始、往来して離れないものは、いかにして芸術を破壊するか、という一事につきているのだ。」そして今、岡本は「颯爽としておのれの年来の宿望を実現しながら、一歩、一歩、前進をつづけているようである。」と、今度は、対極主義者そして〈爆発〉──従来のすべての〈芸術〉の破壊者としての岡本をクロースアップしてスポットを当る。そして「近ごろ、しきりにかれは制服の芸術家たちを非難する。しかし、われわれの第一に脱ぎ捨てなければならないのは、むしろ、〈芸術家〉の制服ではなかろうか。」と結ぶのであった。 突然、マジカルな論理の綾に巻き込まれたかのように、岡本芸術の世界へ、そして花田清輝の文学空問へぐいぐいと引き込まれていった。未知の名前や文献の頻出する、起伏ある地形をくらくらしながらも、まるで迷路をくぐり抜けたかのように出ロヘたどり着き、外に出た。わたしは、読むまえと読んだ後で自分が変わったよう気がした。不思議なことではあるが、わたしはなんだか少し頭がよくなったような気がした。
|
|||||
「負けること勝つこと(65)」 浅田 和幸 |
|||||
「近代社会化の理念の再考」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部