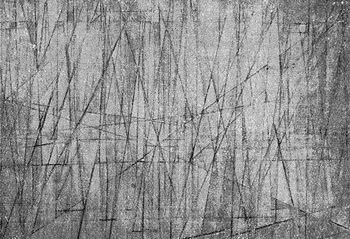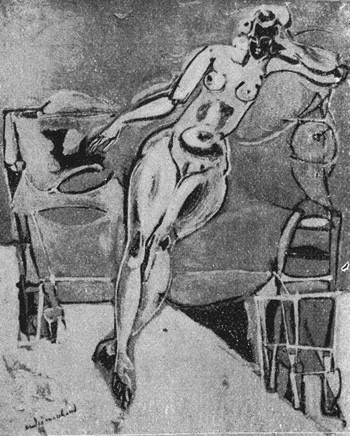第110号 |
|||||
| 2010年11月08日 | |||||
「問われている絵画(101)-絵画への接近21-」 薗部 雄作 |
|||||
| すでにふれたが、岡本太郎の作品は「森の掟」が初めてではなかった。初めて見た「美術手帖」四月号に、土方定一の「一つの問題 絵画のレアリテ」という、第三回日本アンデパンダン(展読売新聞社主催)に関する文章があり、そこにも「室内」という作品が掲載されていた。しかしそれよりも、今その雑誌を見ていて気になるのは、ここに紹介されている内外の多くの画家たちである。その後どうなったのだろう。フランスのマルシャン、ピニョン、ローネル、キャイヤール、オージャム、ベナール。アメリカのコッグシャル、ポロック、ロスコー、フランセスなどの作品が紹介されている。今ではまったく聞かない名前も多いからである。しかし、当時は何らかの点で目立っていた画家たちだったのだと思う。多くの出品画家たちのなかから選ばれてここに掲載されているのだ。日本の画家では野口弥太郎、鈴木信太郎、福沢一郎、岡本太郎の作品が掲載されている。わたしにとってはすべてが初めて見る画家たちである。今、美術の世界の入り口に立ったばかりの初心者には、作品の善し悪しを判断する能力はない。そして、それぞれの画家がどのような評価のされ方をしているのかも知らない。すべておよびもつかない高度な作品に見えるのだ。それに憧れの感情もくわわってひたすら熟視し、何かを感じ取ろうとしていた。 土方定一はこの文章で、「いま開催されている読売新聞社主催の日本アンデパンダン展のアメリカ出品の部屋に入ると、そこには抽象絵画の作品が圧倒的に多いのに驚かれるのに違いない。」──この頃からわが国でもアメリカの抽象絵画が注目されるようになった。画家たちの留学もパリ一辺倒ではなく、ニューヨークヘも眼を向けはじめた──そして、この「前の日米交換展でも、スチュアート・デヴィスのようなアメリカの代表的な抽象絵画の作品が並んでいたが、ここでは現在、最も活躍しているアメリカの抽象絵画の作品が圧倒的に多く並んでいる」といい、「この場合ジェームス・ソラル・ソビーの解説が、現代アメリカ美術の鳥瞰をよくせつめいしているように思う」として紹介する。「それによると、現代アメリカの美術は四大潮流というべきフォーヴィスム、抽象絵画、シュールレアリスム、レアリスム」である──この時代には、ポップアートやインスタレーションなど美術の多様化はまだなく分類は単純である。シユールレアリスムと抽象絵画が変容しながらも大きな流れとして続いており、それをどう超えるか、ということが画家たちの課題のようでもあった──そして土方は、フォーヴィスムやシュールレアリスムに簡単にふれたあと、「キュービスムの後継者である抽象絵画はアメリカでは他の国に比較して最も盛んでここでソビーは、今度のアメリカ出品のなかに見られるマーク・ロスコー、スタモスの作品を挙げているが、今度のアメリカ出品の作家は現在アメリカでもそれぞれ高く評価され、また活躍している作家である。」また、技術的にフランスの抽象画家たちと比較すると「自動的で衝動的である。という意味で技術的でない、といえるであろうが、この明るい自由さ、はまたヨーロッパ的、ないしはフランス的なもののうちないものにちがいない。」といっている。
当時はアメリカで注目されていたという、これらの画家たちではあるが、彼らのなかで今でもわたしたちがよく聞く名前はポロックとロスコーくらいである。しかしロスコーとはいえ、この頃の作品には──制作年代が明記されていない──後年の彼独特のフォルムはまだ現れていない。どこへゆくかわからない模索の過程にあったのであろう。モノクロなので色の感じはわからないが、後年のフォルムヘの兆しは見てとることができる──もちろん今だからいえることであるが──だから晩年のロスコースタイルヘの過程としてたいへん興味深い。この作品も、掲載されている他の作品と一緒に何度も眺めているので、わたしの記憶にもはっきり刻みつけられている。だから後年になってロスコーの作品を見る度に、いつもこの作品が浮かんでくるのであった。 それにしても、ここに登場している他の画家たちは、その後どうなったのだろう。時代の変化と共に作風も変わり、やがて時代の舞台から消えていったのであろうか。あるいはまた、いつか浮上してくることもあるのだろうか……。時代のなかで脚光をあびながらも、その時代が過ぎ去ると、舞台から消えてしまうということは、いっの時代にもよくあることではある。ゲーテは「文化は、いわば若い人が呼吸する空気にまで浸透しているといえよう。詩とか哲学とかの思想が、若い人たちの心中に生起しているとはいうものの、それは周囲の空気と一緒に吸い込んでしまったものだ。ところが、彼らは、それを自分独自のものと考えこんでいるので、自分の名を冠して発表するわけだよ。しかし、時代から受け取ったものをふたたび時代に返してしまうと、ほとんどすっからかんになる。彼らはちょうど噴水みたいなものさ。引いてきた水をしばらく噴き出しているが、その人工的に貯めた水が洞れてしまうと、一滴も出なくなってしまうわけだね。」といっている。 たとえば、印象派の全盛時代には多くの画家が印象派的な作品を描いていた。印象派的な時代の空気を吸っていたからである。しかし現在、そのなかで残っているのはごくわずかな人たちだけである。以前ビュッフェについて書いたときふれたボワデフルは、ビュッフェ論のなかで「偉大な芸術というものは、時代のポスターであることに甘んじない」「その時代にしか属していず時代とともに姿を消してしまうような恐れのあるものをはね付けねばならない」といっていた。ゲーテもボワデフルも、それが何であるかということは特にいっていないが、それはまた、もっとも言葉にしにくいものでもあるのだろう。しかしこういうことは言えると思う。モネやルノアールや、あるいはセザンヌやゴッホやゴーギャンなどの作品を見ると、いかにも印象派の時代の空気を吸って描かれた作品だというふうに見える。しかしまた、その印象派の空気を吸って描いたとはいえ、その空気を吐きだしてしまったあと、何も残らないというわけではない。彼らの作品のなかには、彼らそれぞれの個として刻印がはっきり刻み込まれている。では、消えてしまった画家たちの作品はどうかといえば、彼らの作品のなかには、彼ら独自の刻印がないのだ。あってもきわめて希薄であるのだ。すなわち「時代の空気」──印象派的なスタイルはまとっているが、それを取り去ってしまうと、あとは空っぼ……素材やモチーフのみが残るだけの場合が多いのである。これは、わたしたち現代の美術家たちにもそっくり当てはまる。しかしながらこのことは、同じ時代のなかにいて、同じ空気を吸っているときには、もっとも見えにくいものではある。 とはいっても、わたしには、ここに挙げられているコッグシャルやエステバン・フランセスなどの作品は──とくにフランセスの「扇風機」などは、当時見たときも、そして今見ても不思議な作品に見える。 フランスの出品作にっいては、「サロン・ド・メェの作家よりも、一ジェネレーション前のローラン・ウドー、モーリス・ブリアンションなとが加わっていて、現代フランス美術の多様さを知らせてくれている。」「これらの作家は一九三〇年代に写実的作品を発表した作家であって、この時代の作品の方がいいといえるであろうが、ウドーの「麦刈り」などにしても、視覚の正しさと豊かさ、また技術の洗練された魅力は、一般にフランス絵画の伝統といわれているものを思い出させるに充分のようである。」と、先ず〈本場〉に対する敬意の言葉をのべる。ここに出てくる「サロン・ド・メイ」とは、当時の、フランスの若い画家たちのグループで、わが国でもさかんに紹介され影響も大きかった。特にマルシャンやピニオンなどがしばしば紹介された。その一種抽象化された大胆なフォルムや画面構成が眼をひいたのであった。しかし土方定一はベナールという画家に注目していう、「クロード・ベナールの作品を見る場合にどうであろうか。私は興味深く見るのは、ここでベナールは三つの作品ともに光の明るい部分を紫色に、影を中間色に、中間色を緑色にまたは紫色の入った褐色にして、この四つの色彩を、対象をキュービックに構造的に見て、──例えば、静物のポッと一つを見ていただきたい──その四つの色彩を適用していることである。」と大変好意的に書いている。掲載されていた作品は「フランスの村」という風景画であったが、色刷りではなかったせいもあるが、当時わたしには、この作品のよさがさっぱりわからないのであった。大胆ではあるが、スピード感のある単なる写生的な絵にしか見えないのであった。しかし、観念的な現在の美術批評一般とは異なり、画家の技術面にもふれた誠実な批評であるように思う。 マルシャンやピニオンなども当時は時代を切り開くかのような勢いがあって颯爽と見えたのであった。しかしその後、彼らはどうなったのだろう。着実な成長はできなかったのであろうか。すでにふれたが、その後まったく聞かないからである。ひとときはスターのように輝いて見えた彼らではあったが……。ここでも「時代のポスター」にとどまらず、その「空気のなか」にありながらも、自己に根差した着実な成長をとげることが、いかに困難で希なことであるかということを思い知らされる。たしかに、当時は輝いて見えたマルシャンやピニョンの作品であるが、今見るとマチスやピカソの亜流であるのがありありと見える。マチスやピカソのスタイルを取り入れ、それを抽象絵画風にたくみに構成した、いかにも時代の空気を感じさせる作品であるのだが、その根底に彼ら自身に根差したもの──オリジナリティーが希薄なのだ。軽快な画面作りには「技術の洗練されたフランス絵画の伝統」のようなものを感じさせるが、肝心の彼ら自身の鮮明な刻印がないのである。しかしそれがまた「時代のポスター」としての役割にはピッタりであったが、肝心の彼ら自身の内から生まれて成長する…〈核〉がないので、たんなる「時代のポスターに甘んじない」で、時代を貫いて持続することができなかったのかもしれない…。 彼らだけではなく、時代をつらぬいて──さらに幾時代をもつらぬいて、人々の関心のなかに浮上しているということは、さらに難しいことであろう。ローマの哲学者セネカもそのことに関していっている。「底無しの時の深みが、われわれを没し去るでしょう。僅かな天才のみが頭を表面にだすでしょう。そして同じ沈黙の中にいつかは立ち去るでしょうが、それまでは忘却と戦って、長く自己を護るでしょう」と。 土方定一は最後に、「現代日本美術は、いわゆる技術の上では、両者に劣っているとはいえない。だが、現代日本美術がわれわれに同時代人としての烈しい共感を興えるためには──同国人としての親しみではなく──何が欠けているかは、以上によっても想像していただけるであろう。われわれはわれわれの長所をいうより、欠点を多くいう時代であろうし、その方が健康な精神状況の証拠である。」と結んでいる。 「技術的の上では、両者に劣っているとはいえない。」といっているが、ここでは何を基準にして技術といっているのだろう。それより、そもそも技術とはどのようなことであろう。辞書には「科学知識を生産・加工に応用する方法・手段」「〔一定の方法によって〕ある(特殊な)物事をうまく行うわざ」「物事を巧みにおこなうわざ」などと書いてある。とするならば、「技術的には劣っていない」ということは、現代日本美術は、欧米の現代美術を科学知識?的に生産・加工応用する方法や手段にかけては、決して劣っていない、ということになる。しかしそれだけでは、われわれに「烈しい共感を与えない」のだという。欧米の作品にはあるが、わが国の画家にはないという同時代の共感とはどのようなものなのだろう。世界美術としての同時代性であろうか。あるいはまた欧米作品の同時代性とわれわれの同時代性とは違うのであろうか。「それは以上によって想像していただけるであろう。」といって明言はしていないが、いずれにしても欧米の作品には同時代人としての烈しい共感があるが、わが国の作品にはそれがないという。厳しい批評ではある。
|
|||||
「負けること勝つこと(66)」 浅田 和幸 |
|||||
「変化について」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部