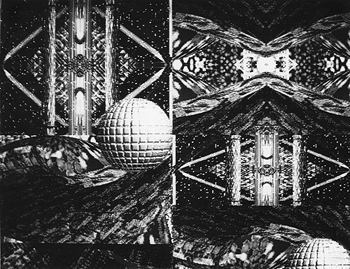第112号 |
|||
| 2011年06月06日 | |||
「問われている絵画(103)-絵画への接近23-」 薗部 雄作 |
|||
| 「公衆によく伝わらない芸術とは何だろうか?「先日書かれ、昨日、世界のどこかの、大きな現代音楽祭のようなもので、大勢の聴衆をまえにして、はなぱなしく演奏されたばかりの作品は、今日からはどこにゆくことになるのか? 」「その何パーセントが、明日、明後日、来年になっても生きているのだろうか? 」。そして「自分達は、〔芸術〕という名にだまされて、そこに何か大切なもの」があると信じているから、こうやって平気で、むしろ積極的に向き合っているが、実際には「〔芸術〕なんてとっくに死んでしまったか、いるとすれば、「まるでちがうところにいるような気がする。」と吉田秀和はいった。 ここでいう「公衆」とは、どのような人たちを指しているのだろう。いわゆる一般大衆を指しているのではないようだ。吉田秀和をふくめた、高度の感性や聴覚をそなえた人たちをふくめた聴衆であるように思える。なぜなら「大きな現代音楽祭のようなもの」に関心をもって集まるのは、すでにかなり選ばれた人たちであるからだ。そのような人たちの心に刻まれ、また聞きたいという思いを持たせるということも大変なことではあると思う。しかしまた、そのような高度な感性をもった人たちによく伝わらない「現代音楽」とは、いったい何だろう。あるいは、ほとんどの人たちにはよく伝わっているのだが、なかには吉田秀和のように、よく伝わらない人もいるということであろうか。
一九六〇〜七〇年代は音楽に限らず「前衛」のさかんな時代であった。わが国の美術界でも「反芸術」といわれた表現? 活動が吹き荒れた。今まで芸術とされていたものに対する否定や破壌的な活動である。社会のなかにもそのような「時代の空気」があったのであろう。それが芸術にも噴出したのだ。岡本太郎なども、それに大きく拍車をかけたように思う。当時出版された『今日の芸術』(1954)のなかで、「芸術はうまくあってはならない。きれいであってはならない。心地よくあってはならない。」と既成の芸術観に対して破壊的な宣言をした。そしてこの本はベストセラーになった。芸術を論じた本がベストセラーになるのは異例である。美術に関わる人たちだけではベストセラーにならない。当時、わたしも早速買って読んだ。そして刺激を受けた。それは若者に起爆剤のような効果があった。たしかに旧世界的なものに対する破壊は、それも、そのような「的時代の空気」のなかでは、カッコいいし喝采もされる。けれども今から思うと、そこでは破壊の側面だけが過大に受けとられて暴走してしまった感が強い。そして創造の方はないがしろにされてしまったのだ。「破壊と創造」という言葉もあるように、破壊は創造があってこそ、はじめて生きてくる。しかし、創造には努力や忍耐が必要だ。人目をひく破壊的行為に比べれば特にカッコよくもない。以後、しばらくは破壊的な側面のみが独走した。 それはわが国だけではなく、世界的な風潮でもあった。今では、その名も聞くことが少ないが、ドイツの前衛作曲家シュトックハウゼン(一九五・六〇年代に電子音による作曲活動で時代をリードした)やアメリカのジョン・ケージ(音楽に雑音や沈黙を取り入れたり楽譜に図形を導入した)なども前衛音楽の世界的スターであった。たとえば当時は、ピアニストが演奏会場で、ピアノを破壊したり、演奏中に突然、音を中断して沈黙の音楽? になったり、トップレスのチェリストが前衛として話題になったりした。わたしも、新宿の風月堂コンサートで、新進のピアニストで作曲家が、演奏ではなく、パントマイムのようなしぐさだけするのを見たことがある。そのようなものが、新しいものとして見られたりしていたのだ。けれどもそれは、すでに亜流じみていて、わたしは何の刺激も感じなかった。とにかく何でも、かつてのものにたいする「反」や「破壊」が、あたかも現代芸術…前衛の正道であるかのように見えた時代であった。 アドルノは、すでに前衛音楽はなやかなりし時代に「新音楽の老化」というエッセイで、「前衛的な音楽が、第二ウイーン楽派の諸発見を受け継ぎ、そして集団で共有され、是認的となり、安全になることによって「偽りの満足に安住している兆候を示し」ているといっている。そして、それらの新音楽は、かっての音楽への否定的なだけであるものの帰結であり、「気を滅入らせ混乱させる」だけである、と。真の新音楽には力がある。そして「ベルクの『アルテンベルク歌曲集』やストラビンスキーの『春の祭典』の初演のとき」それがいかにトラウマ的であったかを思い起こすといっている。それは、「べートーベンの晩年のスタイルの作品から恐れることなく緒帰結を引き出したものだ。」しかし「かつては、目もくらむ深淵があんぐりと口を開けていたところに、今では鉄橋が架けられ、乗客たちは安心して谷底を眺めることができる」と、キェルケゴールの言葉をあげる。つまり、前衛という意識のなかには、すでに危険をはらむ実験も冒険もなく、安全な橋の上で、むしろその方が注目されやすい行為となり、時代のモードとして演じられる破壊的活動のなかには、もはや創造はないのであると。 吉田秀和も、前衛の吹き荒れた二十世紀後半の、この芸術の流れのなかには芸術は「いない」と見えたのであろうか。そして、もし「いる」とすれば別の流れのなかにいるのであろう、と。 わたしは今、映画『ブレードランナー』の薄暗い映像を思い出している。しかし、薄暗いのはわたしの記憶のなかだけかもしれない。なにしろ二十数年も前に見た映画だ。わたしは最初の本『牢獄と宇宙』の「内空間」の章で、この映画…映像が「内空間」的であるということにふれたのであった。ここでいう「内空間」とは、簡単にいうと、この映画に写し出された都市の景観や、室内の窓から見えるビル群の間からも、〈空〉…無限や永遠を暗示する…を排除して、映像全体に閉ざされた密室的な空間をつくりだしているということであった。そのことによって、その空間内に登場する人間や物体を、より有限的で孤独な存在物として描き出しているように思えたのだ。そして、それをキュビズム絵画との対比の上で論じたのであった。キュビズム作品の多くもまた、画面から空を排除しているからである。室内や楽器や人間などが解体され、再構成された断片たちにも、自然の外観は部分的には見出だせるが、そこに空はない。やはり無限や永遠のイメージが入ることが、たとえ部分的であっても、画面の緊密なリアリティーを減退させるからである。そしてさらに、当時生まれつつあったコンピューター・グラフィックスの場合にも、創造的作品には、やはり空を暗示させるようなイメージが排除されているということであった。それをアメリカの作家ディビット・エムの作品を例にして述べたのであった。 しかし、その時はふれなかったが、この映画には別の面があった。原作はアメリカのSF作家フィリップ・K・ディックの『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』(一九六八)である。「世界大戦争」による大量の核爆発で、廃墟と化した地球……場面はアメリカの西海岸の大都市……で、高濃度の放射能ただよう廃墟のようなビル街に、一握りの残留者が、やはり、危うく絶滅をまぬがれた数少ない動物を飼育することに、わずかな慰めを見出しつつ、過酷な生活をしいられている、というものであった。これを読んだときは、異色のSFを読んだという意識しかなかった。しかし今は、違う。わたしたちの日々眼にするこの現実世界……そこにくり広げられている光景……があまりにもSF的であるからだ。 無人と化した街や村。そのなかを頼りなさそうに歩いている犬。あるいは海岸を走っている牛。気象予報のように連日放送されるトップニュースは、原子炉から漏れ出る放射性物質の汚染数値だ。大気、土壌、水、人、動物、植物へ蓄積されてゆく高濃度の放射能。タービン、炉心溶融…メルトダウン、ロボット、セシウム134、セシウム137、ヨウ素131、ストロンチウム90。気がつくと、つねに背後から襲いかかっている〈見えない物質〉との格闘や攻防に、追いつめられているかに見える人間…わたしたちだ。 わたしたちは、持てる最先端の知と技術を結集して、自然─物質─を手玉にとるかのようにして進撃をつづけているが、やがてそれ…自然は、思わぬところから圧倒的な力で、わたしたちを一挙に、あるいは徐々に壊滅させてゆくのだろうか。『創世記』の「バベルの塔」が、映像ではブリューゲルの「バベルの塔」が脳裏をかすめる。
|
|||
「負けること勝つこと(68)」 浅田 和幸 |
|||
「人間と状況認識について」 深瀬 久敬 |
|||
【編集あとがき】 |
|||
| - もどる - | |||


編集発行:人間地球社会倶楽部