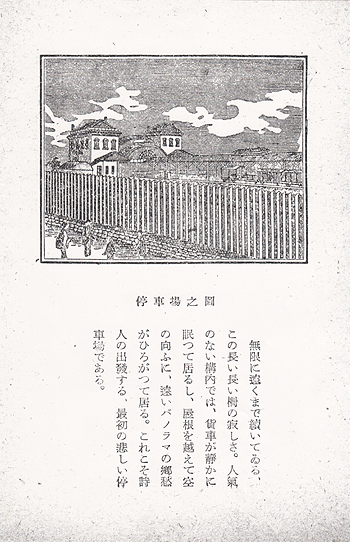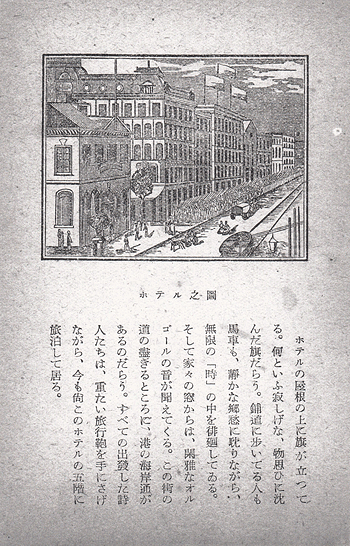第114号 |
|||
| 2011年12月7日 | |||
「問われている絵画(105)-絵画への接近25-」 薗部 雄作 |
|||
わたしは森芳雄に一度会ったことがある…というより近くで見たことがある。たしか女子美術大学の大学祭のときだったと思う。「美術手帖」の訪問記を読んでから数年後であった。森芳雄の講演があるというので出かけていったのであった。間近で見る森芳雄は、雑誌で見ていた写真によく似ていた。やはり真面目で誠実な感じであった。講演は苦手なので、皆さんとここ…部屋の片隅で、何か質問していただき、それについてお話をするというかたちにしたい、ということであった。何人かが−そんなに多くはない−まわりに集まって、何やら質問したり、それに森芳雄が答えたり、というようなことがしばらくつづいた。しかし質問もまばらで−何故かわたしも質問しなかった−間もなく終わってしまった。今では、そこで話された内容は何も覚えていない。たぶん、するどい質問もなく、印象に残るような話はなかったのだと思う。
森芳雄は「アトリエ訪問」のなかで、自作「人々」について−そのときはまだ描きかけであった−記者の「これだけの大きな(一五〇号)ものをまとめるには、イメージがはっきりしていて、かなり計画性がないと描けないのではないか」という質問に、「それがないのです。漠然とこうなったらいいなということはあるけれど、よくわからない。」そして「何故こういう風になったかというと、右上のところに早く形を作ったらいいのじゃないかと思った。この線をひかないといらいらする。そして時々これをすっかりやり直したいと思ったりしてね。」といっている──そういえば、現在のわたしも、作品を始めるときには、漠然とこんな感じにしたい、という思いはあるが、とくにはっきりしてはいない。始めたときとは、まったく違う方向へ進んでいったり、予想とは違った色調になっていったりすることもある──そして絵のなかの人間のポーズについては、「それはきめない。だって今の絵はきまったポーズが多すぎるもの。よくある写実風な絵ね。あんなマンネリズムはない。ほとんどいつもきまっていて退屈なんだ。顔を見ても手を見ても、生活がなんら反映していない」。またモチーフの選択について、「生活からくるもの、それだけしかない。」「早い話が、街を歩いていて道路修繕の人たちを見ていると画興が湧く。おかみさんが赤ん坊を背負ったりして街の人と一緒になってやっている自由労務者、そんなとき、いわゆるモデルより僕は美しいものを感じる」。しかし「表現」となるとまた別で、個性ある造形性がほしい。「働いている人の姿が網膜を通して僕にひびいてくる一つの要素は、「自然」であり、「気取りがない」ことであり、「力」を表現していることであり、又「地」と「人」との昔から変わらない関係も、僕の見逃せないものです。」そして「こうした僕の本質に響いてくる感動の色々な種類を、心の目を曇らさないで生々と受け入れたい、常に、又それがながく失われないならば幸福に思います。僕が受け入れたそれを、より強く、大きく表すためには、どんな形と色が必要なのか、こんな所から僕の終わりのない画面追究が始まります」。実に真摯な画家の姿勢だと思う。「モチーフは、造形的欲望を具体化する、一つのきっかけではないかしらん。僕は既存の常識化された制作の順序を一度疑って観たかった。そして、それを試みている、従っていろいろな迷路に入っているんです。」創造する者の突き当たる、真っ当な言葉である。
先ほど、「心の目を曇らさないで、常に、又それが失われないならば幸福に思います。」と森芳雄はいった。けれどもまた、生涯その姿勢で貫くのも、なみ大抵のことではない。情熱的に画家を目指した者ならば、誰でも、かつて一度はそのような精神の姿勢を生きたであろうと思う。しかし生涯それを持続したという画家もまた、きわめて少ない。画家にとってもまた、人生のいたるところで、その姿勢を打ち崩そうとする様々な芸術と対立する無数の「現実」に向き合うことになるからである。そして「現実」に対してほとんど無力にちかい、芸術の虚妄的な側面のみが目の前にたちはだかり、内部にも広がっていく。画家もまた人間であり「生活」が常にまとわりついている。若き日の決意も、起伏ある長い実生活のなかでは、画家としての幸福よりも、生活者としての幸福が方が、心のなかで次第に比重を増してくる。それは当然であり、それがいけないのではない。無理に純粋に芸術を押し通そうとすれば諸共に沈没しかねない。 しかしなかには、たとえば岡本太郎のように「私には、生活の信条というものはない。芸術の信条があるのみだ。芸術が一切であると考える私は、それに徹することによってのみ、生活を捉えることができると信じている。」といって、全面的に芸術主導で押し切る。大胆な開き直った姿勢である。誰でも簡単にできることではないが、しかし、〈芸術〉の事実は確かにそうなのだ──この言葉は当時のわたしにストレートに飛び込んできた── 〈芸術〉創造は人生全部を要求する。つまり芸術を「生きなければ芸術は生まれない。」しかしまた、それが社会的にスムースに通るということも希だ。そこで、この地帯をめぐって芸術家の悲劇がいたるところに起きることになる。もちろんわたしも例外ではない。芸術には魔力がある。ボードレールは、「僕の頭上の神秘な王冠を編むためには/一切の時間、一切の宇宙の、巧みの限りを要することを」と、みずからの詩に刻み込んでいる。つまり生の一切合切すべてを投げ込んでこそ芸術は生誕する、と。しかしゲーテなどは、むしろ社会的にも健全な生活のなかで芸術を完成させたように見える。
しかし「美しく感じたもの、つまり僕のエモーションを表現しようと目的ある積極的な一筋な動作をはじめる。ところが一歩踏み出すとそこから先ず現在の絵画の表現とかエコールというものが頭にくる。それから過去の原始からの造型が頭に浮かぶ。それとオレしかないという自己本能的な意欲がくるでしょう。──この三つの要素の混乱なんですよ。意欲というものだけで描ければ幸せなんだけど……。」と森芳雄はいう。たしかに、時代を問わず創造する者にはみなこの問題に突き当たり、そして苦闘しているのだと思う。 「真っ白な画面を前にして、僕はいつもあらゆるイマージュを夢みるのです……。」しかしマチスのいう「画面に不必要なものは一つもあってはならない。一つでもあることはそれだけ弱くしたり、不純にする。」この言葉のなかで、不必要なものと、彼がいうことが出来るのは、マチスには明確なモチーフなり技術なり、一切が決定的に存在するから、不必要、必要と分けられるのであって、マチスにとっては、よし、不必要といえる場合でも、僕にとっては必要なものがあるかもしれない。いや、あるだろうと思う。だから僕は僕にとって必要なものを、僕にとってなくてはならないものが何かということを──これは画面の上で──探求していく。僕の乏しい、経験にもとづいた技術をたよりにして……。まあ、ここから実に多くの問題、制作ということの基本が出て来て止めどなく頭がいたくなるから御免にしてください。」「とにかく筆を持って掘り出して行くより他に道はないのですよ……」。
森芳雄の大作「二人」や「人々」はきわめてうす塗りだ。そして褐色の単色だ。その色について「僕は絵具屋にあるあのチューヴに入ったたくさんの色は使いきれないんだ。一つの絵で使える色なんて僕にはせいぜい二つか三つしかないと思う。」そして「だって生活感情からいったって派手になれないじゃあないですか」という。そして「僕の茶色は、向こうの(たぶん西洋の)古い絵を見ると茶色でデッサンをとっているということが一つ。それからもう一つ、この茶色の上にはどんな色でものるということ」。記者の「森さんのパレットの色は少ないですね」という言葉に、「少ない。たしかに少ないですね。だって生活感情からいったって派手になれないじゃないですか」。また筆については、「硬筆とか軟筆とかお使い分けになりますか。」に対しては、「いやヽ僕は終戦後一本も筆をかったことなし、だって買えませんよ。」一九五一年というと戦後六年目である。近くに新宿のガスタンクが見えるとあるが(笹塚)周辺はまだバラックの建つ草っ原とまばらな雑木が見える。まだ当時の貧しい生活風景をうかがわせる。対話のなかにも随所に「生活」という言葉が出てくる。そしてそれは常に貧しいということと重なっている。一九五〇年代はほぼそのような時代であった。そして、そのような生活のなから生み出された作品の方が、後の、豊かではないにしても、やや落ち着いてきた時代のなかで制作された作品よりも、すぐれているように見えるのはなぜか。
それは森芳雄だけではない。この時期…一九五〇年代…の画家、麻生三郎や鶴岡政男や山田二郎など、あるいはその他の画家のについてもいえるように思える。生活は貧しくとも、あるいは貧しいがゆえに、また、情報はかぎられている、しかし限られているがゆえに、制約された生活のなかで、かえって想像力は敏感になり、活性化されて制作への集中度も増したのかもしれない。作品は正直だ。画家の思念や情念のどんな微細のものをも、何らかのかたちで見せてしまう。その後、時代の状況も次第に変化し、海外の新しい美術情報も入ってくる。画家たちも、次々にやってくる最新の美術傾向を目の前にして惑わされる。森芳雄もいっているように、画家は制作に一歩踏み出すにも「先ず、現在の絵画表現とか形式のエコールというものが頭にくる。」つまり、海外美術の新しい流れが画家たちの美意識を直撃する。そもそも、それ以前の画家たちにとっても、その時点での海外美術の新しい情報が画家たちの絵画思考や制作の土台になっているのだ。新しい仕事をしようとしている画家たちにとって、それを無視することは容易なことではない。
いずれにしても時代のなかで制作せざるをえない芸術家の仕事に、時代の変化は大きな影響をおよぼす。一九五〇年代の社会や生活状況も時代の推移とともに変化した。一群の若い美術批評家たちも現れた。彼らはすでにかつての美術とは違う方向を目指している。美術ジャーナリズムの傾向も雰囲気も、画家個人の生活状況も変化する。かつて貧しいといっていた森芳雄の生活が、その後どのように変化したかわたしは知らない。しかし、作品は変わった。表面的にスタイルが変わったということではなく、かつて貧しい生活のなかで制作を主導していた絵画への情熱の火は見えない。 ゲーテは、「時代からもらったもの」は、時代が変わって「ふたたび時代に返してしまうと、ほとんどすっからかんになる」といった。一九五〇年代に活躍し脚光を浴びていた画家たちが、時代から受けていたものを、時代に返してしまった後に、すべてすっからかんになったわけではないが、時代が変わって美術の流れも変わると、やはり、そのころの生気は、多くの画家からも失われたようにも見えるのだ。ゲーテの生活は別に貧しくはなかったが、いや豊かにさえ見えるが、そして変化する時代も生きたが、時代が変わっても、すっからかんにはならなかった。変化する時代のなかに生きながらも、芸術…人間の本質を見つめる眼は変わらなかったようである。芸術の普遍を見通した思想の強さであろうか。
萩原朔太郎は「詩」と「現実」を分けてそれぞれ相反するものとしてとらえ、その葛藤に苦悩しつつも詩の純粋性を生きた。現実…生活に対する、そんな姿勢の朔太郎の〈生〉の感覚から生まれでできた言葉には、陰りある独特な情調がある。たとえば憂鬱、憂愁、陰鬱、暗闇、幻像、夢魔、病気、病霊、遺伝、すえた、くさった、絶望、宿命などという言葉が実にしばしは登場して、それを読むわたしたちの心に、深い陰影ある旋律を刻み込む。
遺伝 萩原朔太郎
人家は地面にへたばって おほきな蜘蛛のように眠っている。 さびしいまっ暗な自然の中で 動物は恐れにふるえ なにかの夢魔におびやかされ かなしく青ざめて吠えてゐます。 のおあある とおあある やわあ
もろこしの葉は風に吹かれて さわさわと闇になっている お聴き! しずかにして 道路の向ふで吠えている あれは犬の遠吠えだよ。 のをあある とおあある やわあ
「犬は病んでゐるの? お母さん。」 「いいえ子供 犬は飢ゑてゐるのです。」
遠くの空の微光の方から ふるえる物象のかげの方から犬はかれらの敵を眺めた 遺伝の 本能の ふるいふるい記憶のはてに あわれな先祖のすがたをかんじた。
犬のこころは恐れに青ざめ 夜陰の道路にながく吠える。 のをあある とおあある のおあある やわああ
「犬は病んでいるの? お母さん。」 「いいえこども 犬は飢えてゐるのですよ。」
*掲載図は萩原朔太郎著・定本『青猫』より。 朔太郎は図について「本書の挿絵は、すべて明治十七年に出版した世界名所圖繪から採 録した。画家が芸術意図で描いたものではなく、無知の織工が写眞をみて、機械的に木 口木版に刻ったものだが、不思議に一種の新鮮な詩的情趣が漂渺している。」といっている。 |
|||
「負けること勝つこと(70)」 浅田 和幸 |
|||
「今、私たち人間はどのような状況に |
|||
【編集あとがき】 |
|||
| - もどる - | |||


編集発行:人間地球社会倶楽部