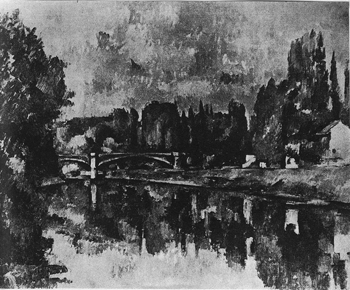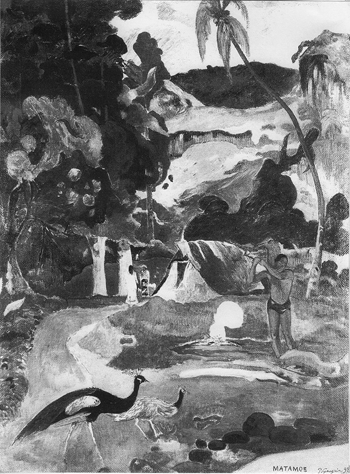第115号 |
||||
| 2012年3月11日 | ||||
「問われている絵画(106)-絵画への接近26-」 薗部 雄作 |
||||
迷宮の文学者ともいわれるアルゼンチンの作家のボルヘスは晩年の対話のなかで、「哲学のない世界は思い浮かべられますか。」という質問に、「哲学をもたない人たちは、貧しい人生を送るのではありませんか? 現実や自分自身について確信しすぎている人たちは。」といっている。そして「哲学は生きていく助けになると思うのです。」「たとえば人生を夢とみなすなら──ボルヘスは実にしばしば人生を夢として語っている──それには何か戦慄的な、あるいは不気味なものがあるでしょうし、ときに自分が悪夢のなかに生きていると感じるかもしれない」が、しかし「現実を堅く揺るぎないものだと思うとしたら、いっそう悪いことになりますからね。」という。 哲学が生きていく助けになるというのは、それ…哲学が「世界に一種の靄(もや)の状態を与えるからである」という。そして「その靄がかえっていいのです」と。つまり「物質主義者なら──堅く揺るぎない事柄だけを信じるなら──現実に、というか現実的なものにがんじからめにされる」からである、と。しかし「哲学はこの現実」を靄のようなものによって「溶解するのです。」つまり「現実はかならずしも快いものではないので、哲学で溶解することによって、わたしたちは救われることになるのです。まあ、こういったことは実にわかりきった考えですが、といってわかりきっているにもかかわらず真実なのです」と。哲学だけではなく、芸術もまた、この堅い「現実」を靄…夢によって溶解しようとしているのだろう。もちろんボルヘスも芸術家…文学者だ。しかしまた彼は特異な文学者だろう。その読書量が膨大である。あたかも図書館のような作家だ。
まさに芸術……芸術家も、たとえ最終的には敗北するとしても、この堅い現実を夢によって溶解しようとしているのであろう。すでにふれた萩原朔太郎なども、現実を夢によって溶解しようとしていたように見える。しかし現実は堅い。簡単には溶けない。不意に、あるいはしばしば目の前にたちはだかり詩人を追いつめる。やはり芸術は、現実に対しては一種の幻想のようなものであろうか。埴谷雄高は自分の文学を〈妄想〉であるといっていた。しかし夢や幻想を見ているのは芸術家だけではない。一般の多くの人たちもおそらく夢や幻想のなかに生きているのだ。わたしたちの、この現実社会……人間風景を見わたすと、そこにはなんとおびただしく夢という言葉が氾濫していることだろう。生活に夢を持て、未来に夢をもって生きよ、人生に夢が持てない。夢のない人生は暗い。商売の夢、事業の夢、スポーツの夢、一見夢とは正反対のように見える物理的な科学の夢。宇宙への夢。そして夢を実現するための苦しく厳しい努力や訓練。夢の挫折。歌謡曲の世界はほとんど夢と愛だ。現実は虚しく厳しくつらい。夢によって光…希望を、色彩を、ということであろうか。しかしそれは人間存在にとって自然なことだ。どうして拒否することが必要であろう。にもかかわらず、ふいに現実が目の前にたちはだかることもある。それは肉体だ。肉体こそはまぎれもない現実であろう。飢えや病気や死が、突然おのれの現実存在に向き合わせる。しかしそこにも夢は不可欠だ。まるで悪夢のようである、と感じることもある。そもそも人間そのものが夢の化身のような存在なのであろうか。 『荘子』も夢と現実について書いている。「荘周は自分が蝶になった夢を見た。楽しく飛び回る蝶になりきって、のびのびと快適であったからであろう。自分が荘周であることを自覚しなかった。ところが、ふと目が覚めてみると、まぎれもない荘周である。いったい荘周が蝶になった夢をみたのだろうか。それとも蝶が荘周になった夢をみているのだろうか。」と。
先の対談でボルヘスは書物……本もまた夢のようなものだ……について「一冊の本を読むということを、私は旅行をするとか、恋愛をするとかといったこととに劣らない経験だと考えている」といっている。そして「バークレーやバーナード・ショオやエマソンを読む、そういうことが、私にはたとえばロンドンを見物するのと同じように現実的体験なのです」と。そして「もちろん私は、ディケンズやチェスタトンやスティーヴンソンを通してロンドンを見たのです。」と。一般に「多くの人たちが考えやすいのは、一方の側に現実の人生がある。つまり歯の痛みとか頭痛とか旅行なんかがある。そして別の側に架空の人生や想像があって、それが芸術だということです。」しかし「私はそんな区別が辻棲の合うものだとは思っていないのです。」そして「すべてが人生の一部です。」というのだ。ボルヘスには『夢の本』という古今東西の夢アンソロジーがあり、そのなかにも『荘子』の夢の話はある。
それはそうと、高校も三年の終わりの頃には、モチーフや絵の具にもなれ、かなり自由に描き、また描く充実感もあった。しかし、かといって、自分の独自な作品を描いているという手応えや確信があったわけではない。そもそも自分とは何か、あるいは自分の本当の絵はどのようなものなのか、などということはまるでわからないままであった。ただ漠然とした期待感や希望のようなものが靄(もや)のように内面をみたしているのだった。けれども今から思うと、描く面白さや充実感にあれほど没入できたのは、あの頃だけだったような気もする。そのような夢のような〈時〉のなかではあったが、それでもときとしてふと思うことはあった。今はまだ、印象派周辺の画家たち……とくにセザンヌやゴッホなどの影響のもとに写生的な絵を描いている。けれどもいつか将来、わたしにも誰の影響でもない、これがわたしの絵だ、といえるような作品を描けるときがくるのだろうか、と。 そしてわたしは単純に考えたのであった。たとえばセザンヌやゴッホやゴーギャンなど思い浮かべる。すると彼らはそれぞれみな違う絵を描いている。しかし違うにもかかわらず、それぞれの作品からわたしは感銘を受ける。ということは、絵の表面…表現はそれぞれ違っているけれど、そして感銘の種類もそれぞれ異なるが、感銘するというそのことにおいては同じである。そしてその感銘は異なる個性…セザンヌもゴッホもゴーギャンも作品のなかで自分自身になりきっている、というところからくるのだ。だから作品のなかで、自分自身になりきることができれば……極端にいえば人間誰でも可能性としては、彼独自の作品をつくることができるのではないか。もちろん、そのときできる作品は、彼らの作品とはまったく違うものになるかもしれない。しかし、わたしも、わたし自身になりきることができるならば、これがわたしの絵だ、という作品を描くことができるようになるのではないか、と。
その時の考えはそれほどきちんとしていたわけではないが、ある直感を交えてそのようなことを思ったのであった。そしてその思いは、わたしの心底に刻まれ、その後、見え隠れしながらもわたしを方向づけてきた。そして、この実生活──芸術に対しては敵対関係にちかい、しかしまたそれが不可欠でもある──に翻弄されながらも、途絶えがちではあったが、耳をかたむけて、いつもその声を聞き取ろうとしてきたのであった。そしてそれは、わたしの基本的な姿勢として現在にまで至ったのであった。 |
||||
「負けること勝つこと(71)」 浅田 和幸 |
||||
「社会的権威のパラダイムシフトにどう向き合うか」 深瀬 久敬 |
||||
【編集あとがき】 |
||||
| - もどる - | ||||


編集発行:人間地球社会倶楽部