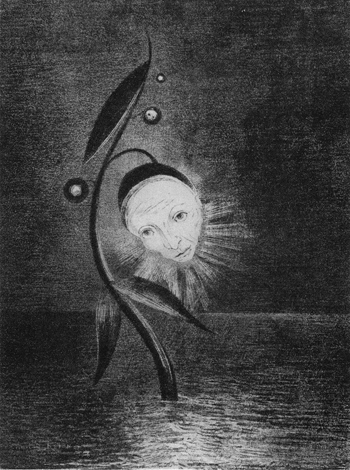第117号 |
|||
| 2012年9月25日 | |||
「問われている絵画(108)-絵画への接近28-」 薗部 雄作 |
|||
いつの頃からか、わたしは絵画作品と植物とをしばしばかさねあわせて見るようになっていた。たぶん『美術手帖』で滝口修造のクレーについの文章を読んでからだと思う。そこで滝口は「樹木が樹液で葉をしげらせ花を咲かせ、実を結ばせる自然な時をかならず必要とし、またその時をかけるのを惜しまなかったからです。」とクレーについて書いていた。そして、そこに掲載されていたクレーの「植物園」という作品の影響もあったかもしれない。その絵は具体的に植物が描かれていたわけではないが、中心にカザグルマのような形があり、それが植物…花を連想させるようなところがあった。だからこれは具体的な花ではないが、たぶん抽象化された花なのだ。そして、たんに植物を横からや上から見るだけではなく、全体を分解して再構成したものにちがいない、と。そんな思い込みのような見方ではあったが、しかしそれ以後は、それまでのように植物をただ漫然と見るだけではなく、花や茎や葉などのむすびつきや全体を一つの構造体としても見るようになり、それが作品をつくるうえでも何か参考になるように思えたのであった。
さらに植物との対比は、たんに絵画作品だけではなく、それをつくる画家の生涯…成長過程ともかさねあわせて見るようになったのであった──もっともこのことは少し後になってからになるが──だから画家のばあいにも、植物のように発芽…成長…開花という経過をたどることが、一人の画家の成長としては理想のように思えたのであった。 そして当時、わたしのごく限られた視野のなかではあったが、そのように見えたのがルドンとボナールであった。というのは二人とも晩年になってから一段と色彩が輝いているからである。それはあたかも植物がながい苦闘?…成長の後に鮮やかな花を咲かせているのとどこか共通しているように思えたからである。しかし考えてみると、たしかに晩年にになって色彩が輝くということも目をひくが、しかし重要なのは、むしろそれまでの過程…準備期間であるのだろう。晩年に輝いた色彩も、植物とおなじくそこには長い準備期間が、探求の過程があったからだと思う。植物の準備期間がおもに葉や茎の緑という単色…もちろんそこにも微妙な階調や、そしてなによりも光を求めて空間に枝葉をひろげる姿は感動的であるが、しかしそこにはまだ花のもつ光彩はない。
ルドンの成長期…初期や中期の作品は、あたかも植物の成長期のように、緑でこそないが単色…白と黒だけの、そして暗く不気味な作品ばかりだ。それはまるで植物の意志が、枝や葉のなかの暗やみで、まださだかならぬ目的…漠とした開花を夢見て懸命に生きているかのように、ルドン自身もおのれの内なる暗やみで、さだかならぬ目的にむかいながら漠とした開花を夢みていたのだろうか。いずれにしてもながい暗雲も消え去り、はなやかな色彩の世界が現れでてきたのであった。 けれども、わたしがはじめて見たのは不気味なルドンであった。偶然にも、当時出版されていた美術全集で、印象派の作品にまじって掲載されていた「沼の花」という作品を見たのだ。夜の湖面の葦のような植物に、白い人頭が花のように咲いて?いる気味悪い作品だった。印象派などの作品にまじってその「沼の花」が載っていたのだ。外光派全盛の時期に、こんな異質で暗い絵を描いていた画家がいたのも意外であったが、それよりこの絵の気味悪さが、わたしを引きつけたのだ。といっても、わたしはその気味悪さに本のページを閉じてしまったくらいだ。見たくないものを見てしまった、という後味の悪いものであった。しかしそのイメージは、妙に記憶に焼きついて消えないのであった。 そうこうしているうちに、まもなく「美術手帳」(一九五二年十二月号)に岡鹿之助がルドンについての文章を書いていた。それを読んでわたしは初めてルドンという画家…人間や、また「沼の花」以外のいろいろな作品を知った。そして気味悪さも次第にうすらいでゆくのであった。 わたしは最初に気味悪いルドンを見てしまったが、岡鹿之助は最初にはなやかな色彩のルドンを見たようだ。「ルドンの絵に、私がはじめて接する機を得たのは、パリに到着して間もない頃であった。プチ・パレの会場にならべられた数十点作品は、その大部分がパステルの花であった。いずれも小品であったが、ドビュッシイのように精緻で、画面の階調、律動に絶妙な感性をただよわせるものであった。」その「ふかぶかとした幻想と繊細な感情」はまるで「音楽の世界だ。詩というよりも音楽のもつあらゆる富を絵画のうちにはらんでいるように感じたのである」と。さらに「ルドンの数少ない友達のなかに「ポーエム」の作曲者ショオソを見出す」し、また「ピアニストのヴィネスやヴァイオリニストのヴランなども見える」。そしてまたルドンの生涯に大きな影響を与えた人に植物学者アルマン・クラヴオノ名を加えなければならい。」「スピノザの哲学に深く傾倒していたこの学者からは、スピノザについて、シェクスピアについて、また自然や植物の生態の不思議について教えられた」という。やはり植物の生態にも関心があったのだ。しかし何よりもわたしの目を開かせたのは、画家でありながらも、常に絵画以外の様々な世界に深い関心をもち続けて絵画を深めていったルドンの画家としての姿勢であった。 そして「生まれながらにひ弱かったこの画家は、それでも七十六歳まで描きつづけた。その七十六年の生涯のうちで、色彩の時代は、わずかに一九〇〇年頃からの十六年にすぎない。言い換えれば、ルドン芸術の最盛期は六十歳から亡くなるまでの十六年間である。」と。
それにくらべるとボナールの作品には不気味さや異常さはない。初期においてはむしろきわだった個性さえ感じない。どちらかといえばおとなしく平凡である。もし、ボナールが夭折していたとしたら、とくに目だった画家にはならなかったであろう。もちろん、その平凡さのなかにも、よく見れば、ささやかではあるがすでに後年のボナールの資質は見ることができる。しかしそれはまだ弱い。けれどもボナールは、漠然としてではあっても、それを自覚して、あるいはしっかり掴まえようとして、また見失うことのないように極力警戒して、自分の感性を頼りにして地道に探求の道を進んだのだ、と思う。あるいはそれは画家の直感や描く快感が、その漠とした内なる資質にひき寄せられ、自然におのれのコースをたどることになったのかもしれない。あるいはまた、試行錯誤のくりかえしのはてにたどり着いたのかもしれない。いずれにしても晩年には、初期を見るわたしたちの予想をはるかに超えて、まったく独自な色彩の世界をつくりあげていったのであった。 他にもルオーの仕事にこの傾向を感じたが、しかしその頃のわたしにはルオーはよく理解できないのであった。太く黒い線で区分けしたような顔の絵が当時の雑誌に大きな図版で掲載されていたが、いくら見つめても、ただ分割された拡散的な顔の印象しか持てないのであった。切り取って壁にはってしばらく眺めていたが、やはりわからないままであった。けれども色彩に関しては、やはり老齢になるにしたがって次第に輝きを増しているように見えたのであった。当時ルオーはすでに高齢であり評価も一段と高まっていた。わたしは自分の理解力の未熟さを克服しようとしたのであったが、そうこうするうちに、まもなく東京に出てしまった。そしてルオーのこともとくに意識はしなくなった。しかし、数年後に上野で大きなルオー展があり、わたしもそれを見に行った。すると不思議なことに、そのときには、とくにわからないということはなかった。感銘さえ受けてかえってきた。いったい、わかるわからないとはどういうことなのだろう。どこかにその境い目のようなものがあるのだろうか?…。
数学とか科学などには、解らないものが解る、という順序のようなものがあるように思う。だからそれにそって適切に進んでゆけば段階的な進歩がはっきりあるように思えるのだ。しかし芸術…美の場合には、そもそもそのようなはっきりした順序や道筋があるのだろうか。あるようにも思えるが、またないようにも思える。たしかに美術史とか解説や絵画論のようなものは無数にあり、そしてそれらを読めば、読む前よりは理解できたようにも思う。また技術的な訓練をかさねれば表現上の進歩もはっきり見られる。しかし技術は進歩しても感性的な裏打ちがないならば、作品は底のあさいものになってしまう。絵画は技術がないと成立もしないが、またともすると技術だけが独走してしまうということもある。技術そのものにすでに魔術的なものがあり、それだけでも人は驚異の目をもって見ることがある。また技術はきわめて幼稚であっても、表現の意志がつよく、知や技術をとびこえて、それが直接衝撃的であるばあいもある。
しかし、一般に知識的に理解はできても、感性的に理解できないということもある。知るということと感じるということは微妙に違うからである。たしかに知識は美へ導いてくれるし、また両者は交じりあっているようでもある。けれども究極的には、美は感じるものだ。だから自然でも人間でも、ふいに美しい光景や場面が現われると、その不思議な力?…が意識をとびこえて思わず…いきなり感動するのだ。また、ふだん絵画などになじんでいないような人でも、何かの機会にある作品が不意に電光のように心身を貫くということさえある。さらに同じ作品を見ても、見る人の知識や感性の度合いによって、それぞれ微妙に違ったものを見ているかもしれないのだ。そして男性はたぶんどちらかといえば識る方にまさり、女性は感じる方にまさっているようにも思う。そういえば大数学者や大建築家や大作曲家に女性は少ないようにも見える。もちろん双方には無数の強弱の差があり、逆の場合さえあるかもしれない。そしてまた芸術作品については、しばしば〈好き〉だとか〈嫌い〉だとかいうことは男女にかぎらずよく聞く言葉である。観賞はやはり感性的要素が強いのであろうか。とくに音楽などはほとんど感性で聞いているような気もする。そしてものをつくる人間は男女両性を要請される。つくるという作業には同時に批評的な目…知や客観性をも要求されるからである。もっともそうでないすぐれた作品も無数にあるようでもあるが……。そして不思議なことに、その批評には感性的なものも要請されるのだ。
|
|||
「負けること勝つこと(73)」 浅田 和幸 |
|||
「第三の意識覚醒?をめぐって」 深瀬 久敬 |
|||
【編集あとがき】 |
|||
| - もどる - | |||


編集発行:人間地球社会倶楽部