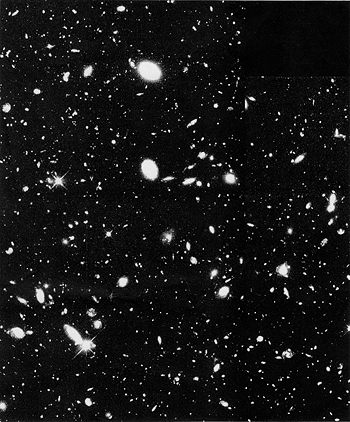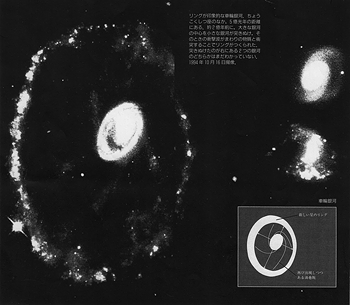第118号 |
|||
| 2012年12月21日 | |||
「問われている絵画(109)-絵画への接近29-」 薗部 雄作 |
|||
わたしは、実にたびたび執拗にこだわって、さらに植物まで引きあいにだして、資質とか成長とかオリジナリティーとかについて述べてきた。それはほかでもない、わたし自身がそのことにもっともこだわり、そしてエネルギーをついやしてきたからである。というのも一九五〇年代の現代美術界は、まだ欧米一辺倒という現象が支配的であり、つまり欧米最前線の美術のスタイルを取り入れ──それを着ることによっておのれを表現するという傾向が主流であったからだ。そしてまた、わたしたちにとってその方法は大変魅力的な表現行為でもあった。海外旅行などもほとんどなく、留学する者もかぎられていた。まだ本物は西洋にあるという風潮であったのだ。とはいうものの、そんな現象に反発する画家ももちろんいた。なかでも岡本太郎の発言や行動が目についた。彼の『今日の芸術』(昭和29年・1954)が出版されたのもその頃であった。そのなかで岡本太郎は「今日の芸術は、うまくあっては、いけない。きれいであってはいけない。心地よくあってはならない」と爆弾的に宣言する。というのも、すでにふれたように当時の多くは西洋の最新絵画をスマートに模したような、いわゆるうまい作品が多かったからである。そして素直に自分自身に目を向けよ、と。「だれでも、その本性は芸術家であり、天才なのです。ただ、こびりついた垢におおわれて本来のおのれ自身の姿を見失っているだけなのです」。しかし、このことは「だれにでもわかっていただける理屈」であるのだが、では「具体的に、どうすれば、その不純物をとりのぞくことができるか、──これが問題です」。これらの言葉は、あれこれ模索していたわたしのなかへストレートに飛び込んできた。そして、とにかく、少なくとも自分でつくる作品は、すでに自分のなかへ入りこんでいる無数の既成絵画の残像…こびりついた垢をとりのぞいて自分の根っこに由来したものに目を向けてつくらなければならない、という思いがつよく心に刻まれたのであった。
しかし自分の根っこといっても、人間は植物ではないので、人間のなかのどこに、そしてどのようなものとして、その根っこはあるのだろう。それは眼によって見ることができないので、直感や感覚あるいは意識や言葉によって探すしかない。そういえば哲学なども古代以来、人間であるにもかかわらず、人間とは何か、とか、存在しているにもかかわらず、存在とは何か、と人間の根っこを問い、探しつづけている。近代や現代の科学でも同じく依然として物質とは何か、人間や生命とは何か、またどこからやってきたのか、と科学的側面からの精密な探求をつづけている。かなり解明されてきたとはいえ、やはり依然として、その究極はわからないところが多いようだ。
そして芸術の世界でも、芸術とは何か、との問いや模索は依然としてつづいているし、なかには芸術を否定する芸術や人目を引きつけるための意外さや奇抜さを狙うものを芸術として追求している者もある。たしかに創造は、創造された一つ一つのものが、それぞれ、それに対する回答ではあるのだろう。時間や距離をおいて眺めれば、それらは当たっているばあいもあるが外れているぱあいもあるだろう。しかし、にもかかわらず相変わらず創作活動はつづいている。ということは、それは人間にとって何か必要なものであるのだろう。わたし自身まで「問われている絵画」などといって、すでに百回以上も本誌で問いつづけている。 けれども幸いにというか、あるいは不幸? にというか、絵画には、すくなくとも画面という限定された探求の場所がある。とはいっても、限定された四角いその場所のなかには、あらかじめ実験の対象物…何かの物質や細胞などがあるわけではない。さしあたり何もない。白い空白があるのみである。そんな状態であるので、すでにふれたこともあるが、かつて二十世紀の抽象画家スーラージュはその四角い場所…画面をにらんでいった。「私が一つのカンバスを前にした時に、私が探しているもの、私が求めているものを教えるのは、むしろ私がカンバスの上にかいたそのものなのです。」と。やはり何もないところには何の手がかりもないのだ。だから、彼はとりあえずそのなかに自分の意図とは無関係に何かを…線や色を無意識的にぬりたくる。とにかく、とくに意図されたものではない色やかたちを、たぶん衝動的に描き込むのだ。そして「私自身は絵の中に、描いているより以前の時の自分の内的なものとか、あるいは外のものとか、そういうものを自分の絵の中に描いてゆくのではないのです」といっている。 これは抽象絵画全盛時(一九五〇年代)のフランスの画家スーラージュの言葉である。しかしまた、こいう思考や方法自体が、こんどは自分の仕事に限界を定めてしまったのではないかとも思う。というのは、にもかかわらずそういう彼の制作した作品には、あまりにも意図的な一貫性がありすぎるからである。つまりスーラージュ的な型ができてしまい、その型からぬけだせなくなってしまったからである。それをぬけだすと、それによって承認されている彼の作品とは違うものになってしまうのだ。さらに成長をつづけるためには、もっと深い内的必然によって彼自身の根源的フォルムを意図的に探求しなければならないからである。けっきょく自分でつくったスタイルに自縛されてしまったように見えるのである。というのもそれ以後、さらなる展開が開かれないようであったからである。その後の彼の作品を、わたしは比較的最近に見たことがあるが、往時の勢いは感じられず、かつての手法やフォルムのパターンだけが目にいたのであった。
とにかく自分の根っこから始めることだというこを、わたしは肝に命じたのであった。しかし、では、わたしの根っことはわたしのなかのどこに、どのようなものとしてあるのか。わたしのなかにあることだけは確かのようなのだが、しかし、それをどうして掴むのかの手がかりがわからない。まずその手がかりを探すのが緊急の仕事であった。けれども、探すといってもどう探せばよいのか。ともかくわたしもスーラージュのように、色や線やかたちを無意識的衝動的にそして偶然性を頼りにして、さまざまな試みを始めたのであった。だからもちろんそこに何かの目的やイメージがあったわけではない。試みの結果には出来不出来があったが、しかし、その偶然性をたよりに同じ行為を続けていても、方向性がないのでいっこうに進展がない。それは糸口のないどうどうめくりである。 そんな行為をくり返してるうちに、ある日ふと色相環のイメージが浮かんできた。色相環とは、虹の七色をふくめた十二の色が円環のなかに分割して並べてある色見本の図である。そのことは最初の本、『牢獄と宇宙』のなかの「色環の思想」で述べた。たとえば「色環が成立しているのは、それぞれの色彩が、お互いに自分の色の純粋性をまもり、自分に徹することによって保たれている。たとえば赤なら赤が、他の色に影響されることにより、混ざって濁り、赤としての存在が希薄になって、赤としての場所が保てなくなってしまえば、もはや赤としての存在の失格につながり、同時に色環自体の危機である」と。そしてこの「色環の成立条件こそ、そのままわたしたち各自の作品の成立条件でもあるだろう」と。この「原理を各自にあてはめて応用するならば、わたしたちもかならず自分の作品を探しだすことができるのではないか」と。 「そうすれば、わたしたちもいたずらに模倣に終始することもなく、お互いの特性を鮮明にして、絵画という世界の、多様性のなかの一員として加わることかできるのではないか」。だから、この原理にしたがって自分を探そうとするならば、一般にいわれたり思われているように、自分の絵画世界をつくりあげようとするとき、まず、多くのものを学んでそれを自分のものにする」ことではなく、むしろ「すでに入り込んでいる多くものを排除することによってではないか。」なぜなら「先ほども色環によって確かめたように、たとえば赤が赤となるためには、他の多くの色をとり込むことによってではなく、逆に自分をにごらせている別の色素をとり除くことによってであるように、絵画のばあいも、すでに自分のなかに入っているものを排除してゆくことによって、自分の質を見つけだし、それをほり起こし、確かなものにしてゆくことである」と。
とにかくわたしは、なによりもまずオリジナルなものでなければならない、ということを肝に銘じた。それはうまいとか、へたとか、わるいとか、よいよりも先行した。そのようなことはみな二次的な問題に思えたのだ。どんなささやかなものでもよい、何よりもまずオリジナリティーを! ということがわたしの制作のモットーとなった。当時は街のなかを歩きながらも、ときおり呪文のように口のなかでとなえていた、「オリジナリティーは西洋にあるのではない! 日本のなかにあるのだ。」そして「日本のなかにあるのではない、わたしのなかにあるのだ!」と。その理論?…観点は他の作品を見るばあいにも同じであった。それは彼ら自身の根っこから生まれたものであるのか、と。たとえどれほどよくできていようが、また大作力作であろうが、評判がよかろうがわるかろうが、その作品の根っこがオリジナルであるかないかが、まず直観的に目について評価の基準になってしまうのであった。そして価値判断はそれによってなされるのであった。そして事実、わが国や西洋の美術史としてわたしたちの目にふれる作品はすべて、やはり、そのようなもの…オリジナルなものであるように見えたのであった。たしかに、はじめは何かの影響が、痕跡が見えるばあいもよくある。しかし、やがてそれは次第に消えてゆき、民族にしろ個人にしろ、彼ら自身の根っこが現れて、それが主流になってゆくようであるのだ。
そしてわたしも、わたしのなかの根っこを探した。しかし、おぼろにかろうじて感知できるかできないかのようなその根っこの先端…その方向や由来をたどってゆくと、それはわたしという人間をこえて植物や動物や鉱物とも混じあっていくようであるのだ。そして、なおもその先をたどってゆくと、それは地球全体にひろがってゆき、やがて地球をもこえて宇宙へと向かってのびひろがってゆくようでもある。太陽系や天の川銀河をこえて、さらにその奥の奥、何千何百億光年という彼方にちらばる銀河団や星雲のなかをよぎり……それはさながらわたしたちの眼の機能のように──もはやわたしたちには縁もゆかりもないような宇宙の果て──果てとはいっても光が届かないので見えないだけともいわれる……わたしたちには縁もゆかりもないような天体ではあるが…にもかかわらず、それらの銀河や星雲の密集した、そしてそこで生まれたり死んだりしている星々の光景を眺めていると、わたしたちは心の奥底に得体のしれない動揺や驚異、そしてまた不可思議な美しさを感じるのであるが、それはいったいなぜか。わたしたちは縁もゆかりもないものに何の驚きも美しさも感じない。
*参考文献『ハッブル望遠鏡が見た宇宙』 (岩波新書)
|
|||
「負けること勝つこと(74)」 浅田 和幸 |
|||
「米中対決の時代に向けた一考察」 深瀬 久敬 |
|||
【編集あとがき】 |
|||
| - もどる - | |||


編集発行:人間地球社会倶楽部