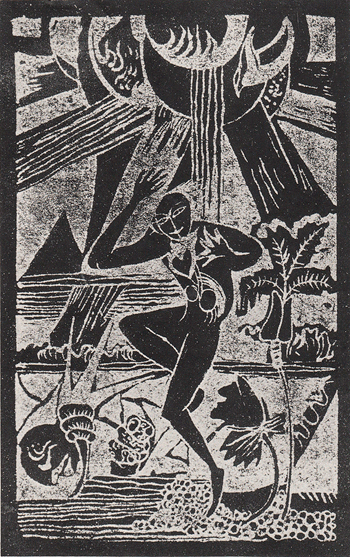第119号 |
|||||
| 2013年4月15日 | |||||
「問われている絵画(110)-絵画への接近30-」 薗部 雄作 |
|||||
梅原猛の『世界と人間』という本を読んでいたら、そのなかの「縄文と岡本太郎」とい文章に次のようなくだりがあった。
「いつかテレビで、岡本氏は司会者とつぎのような問答をしていた。 岡本「俺が縄文土器を発見したのだ」 司会者「どこで発見されましたか」 岡本「上野博物館で発見したのだ」 司会者「まさか」
司会者はでたらめをいっていると思ったのであろう。司会者の嘲笑に応じて、それを見ていた視聴者も、でたらめをいう岡本氏をピエロとして嘲笑する。」
たしかにこの問答だけ聞いていると奇妙に聞こえる。博物館というところはすでに発見されたものが展示されているところである。その博物館で縄文土器を「発見」したというのは。しかし梅原氏もいうように「岡本氏の上野博物館で縄文土器を発見したという発言は間違っていない」のだ。たしかに、考古学的資料としてはすでに多くの縄文土器が発見されている。そして上野博物館にも展示されているであろう。しかしそれはあくまでも縄文時代の遺物としてであった。「しかしそれが芸術作品であることを発見したのはまさに岡本太郎氏その人なのであるのだから。」そして梅原猛はつづけて「ピカソを中心とするパリの前衛芸術運動にいちはやく参加し、戦時中に帰国した岡本太郎氏は日本の伝統に退屈以外のものを見出すことができなかった。唯一彼の心をとらえたのは縄文の土器であった」と。「今では、日本の美術史は必ず縄文の土器や土偶から始まる」が、それは岡本太郎氏の目によるものである。日本では、彼のように今まで美として認められていなかったものをあえて美であると言う画家や美術評論家は、柳宗悦などを除けば甚だ少ない。」といっている。
たしかに、今まで美として見られてなかったものに美を「発見する目」というのはきわめて少ない。そして難しいことでもあるのだ。というのも、それは日常的な社会通念のなかにどっぷり浸っていては絶対に発見できないからである。その目を獲得するには、それなりの努力や訓練が必要であるからだ。つまり、まず日常の常識的な考えや目を捨てなければならない。物に通念のベールがかかっていてはその物の本体が見えないからである。先の問答が奇妙に見えるのも、通念の人と通念を払いのけている人との会話から生まれるちぐはぐさからくるおかしさなのだろう。しかし数の上からいっても通念の人の方が圧倒的に多いのであるから、おかしく見えるのは、通念でない人になるのは当然のことである。もっとも多少は岡本太郎その人の人がらによるところもあるかもしれない。あるは対話者が芸術家のばあいはまたちがうかもしれない。しかし岡本太郎は誰の前でも芸術家岡本太郎のままだ。そんな区別はしていないのである。これは一般に芸術家であっても、誰でも彼のようにストレートに押し通しているわけではない。またできるわけでもない。やはり日常生活と芸術は分けざるをえないというばあいも多い。やはり、できる人とできない人があるのだと思う。わたしがそう思うのは、あるいはそれは気の弱さや実力不足のせいだろうか。
トーマス・マンなどは芸術と一般生活をはっきり分けていたようである。たとえば『トニオ・クレーゲル』──これは芸術家の成長小説なので──のなかで「彼は労作以外の何物も欲しなかった。」それというのも「社会人としての自分には一顧の価値」をも見ず、「ひたすら創造者としてのみ」生きた。「ちょうど一歩舞台を降りると何者でもなくなる素顔の俳優のように」して「沈黙のうちに閉じこもって、隠れて仕事をした。」そして「才能を社交上の装飾とこころえ」て「変わったネクタイに贅をこらしたり、何はともあれ幸福に愛想よく芸術的に生きようと心がけたりばかり」していて「すぐれた作品」というものは「ただ苦しい生活の圧迫のなかにおいてのみ生まれるということや、生きる人間は創作する人間ではないということや、創造する者になりきるためには死んでいなければならないということなどを一向にご存じない小人どもを軽蔑した。」と書いている。つまり、創作からいったん離れれば、そのときは「素顔の俳優」のように過ごした、と。 しかし『ヴェニスに死す』では、このようにして功なり名をとげた初老の作家が、厳しく過酷な創作の日々の息抜きに、ある日郊外への散歩をこころみる。しかしその途中で見た光景に、ふと「旅への誘い」に心をとらえられる。そしてヴェニスへの旅に発つ。やがてヴェニスへ到着してホテルでの日々を過ごすが、そのホテルで遭遇する美少年に心を奪われ、破滅してゆく軌跡をえがいた秀作であるが、あるいはそれは、作家の長期にわたる極度の緊張、禁欲的作業の連続からくる、反動的衝働の現れであろうか。もっともすでに『トニオ・クレーゲル』のなかでも書いている。「芸術には破滅への衝動があるのです」と……。しかしそこで惹きつけるのは、その圧縮された密度と強度、そして広がりのある文章の魅力だ。それは翻訳でも伝わってくる。
いずれにしても岡本太郎はすでに昭和二十七年(1952)『夢と誓い』のなかでも書いている。「わたしには生活の信条というものはない。芸術の信条があるのみだ」。実にハッキリ鮮明である。芸術に徹底する、それが生活であるという信条だ。「芸術が一切であると考える私は、それに徹することによってのみ、生活の信条を捉えることができると信じている」。「だから、ここでわたしは芸術の信条について書くのだが、それがつまり生活の信条にもなるわけだ。」それは「生活を軽視するような旧式な芸術至上主義も、生活が芸術であると考える職人的な捉え方も、ともに正しくない。それでは芸術も生活も把握できないのである。」といっている。通常の日常を、芸術の日常に転化するのだ。それによって通常の日常も異常な日常となって目に見えてくるのだ。
ショーペンハウアーもいっている。見慣れた事物をまるで始めて眺めるように見るためには、日常の世界からいったん自分を切りはなし、別な世界におくことが必要である、と。ショーペンハウアーの影響を受けていた若きキリコも、自作の「形而上学的絵画」の制作動機を、そのような状況のなかで描いたといっている。「ある澄み切った秋の午後、私はフイレンツェのサンタクローチェ広場の真ん中の広場に座っていたのであった。もちろん初めてその広場を見たのではなかった。私は長い腸の病いが治ったばかりで、ある柔軟な感情の状態であった。私を取りまくすべての外界、建造物や噴水の大理石すらも私には病み上がりのようにうつった。その広場の中央には、長い上着を着て、自分の作品を体に寄せてしっかり抱き、物思いにふけって頭に月桂樹の冠をいただいたダンテの彫像が立っている。その像は白大理石で出来ておりながら、天候によってそれは、見た目に非常にここちよいグレーの錆色を呈していた。そのとき私はこれらのものをはじめて眺めるといった不思議な印象をもち、その絵の構図が私の心の目に明らかにうつったのである。」と。
梅原猛は岡本太郎について「日本では彼のように今まで美として認められていなかったものをあえて美であると宣言する画家や評論家は甚だ少ない。」といったが、この少ないなかに詩人の萩原朔太郎なども入るのではないかと思う。岡本太郎とはきわめて異なるタイプの芸術家ではあるが、彼もまたその独特な詩的感性によって、やはり従来いわゆる美として見られていなかったもののなかに独特の美を見出だしている。たとえば詩集『青猫』の播画なども、画家や批評家からとくに注目されていたものではなかったと思う。『世界名所絵図』(絵画への接近25・掲載)という大衆向けの本からであるから。朔太郎は詩集のなかでその絵の解説を書いている。「画家が芸術意識で描いたものではなく、無知の織工が写真を見て、機械的に小口木版(西洋木版)に彫ったものだが、不思議に一種の新鮮な詩的情趣が縹渺(ひょうびょう)している。」そして「つまり当時の人々の、西洋文明に対する驚き──汽車やホテルや蒸気船や街路樹のある文明市街やに対する、子供のような悦びと不思議な驚き──が、エキゾチックな詩情を刺激したことから、無意識で描いた織工版画の中にさえも、その時代精神の浪漫感が表象されたものであろう」といっている。今ではこの種のものに一種の不思議な美しさを感じるのは珍しいことではないが、当時はまだそういう観点から見る人はいなかったのではないかと思う。 また、また最初の詩集『月に吠える』には田中恭吉という画家の多くの作品が入っているが、当時彼はまったく無名の画家だったと思う。なにしろまだ若い上にすでに重い結核を患っていた。手紙に「私はとうてい筆をとれない私の熱四十度を今二・三度でれば私の詠百四十を、いま二三十出れば私は亡くなる」と書いている。朔太郎も、「当時、重患の病床中にあった」恭吉氏は「わたしの詩集の計画を聞いて自分のことのように喜んでくれた。そしてその装丁と描画のために彼のすべての「生命の残部」を傾注することを約束された。」と。しかし病状は深まるばかりで、やがて消息も絶えてしまったという。そして「それから暫くしてある日突然「一封の書留小包が届いた」。「それは恭吉氏の私のために傾注しつくされた〈生命の残部〉であった。それは病床で握り占めながら死んだという痛ましい形見である。」そしてこの「金泥の口絵と、赤地に赤インキで薄く畫い」た絵は「劇薬を包む」紙であった、という。おそらく田中恭吉が広く知られるきっかけとなったのは詩集「月に吠える」からであると思う。ここで感じるのも、世間の目にとらわれることなく、自分の詩的感性によって決然とものを見ていた詩人の目と心である。
わたしは、見慣れたもののなかに美を発見するのではないが、見慣れた雑草などのなかに、芸術家のあるべき姿のようなものを発見することがしばしばある。かれらは、とくに自分のなかの垢を意識的に払いのけているわけではないと思うが、実にストレートにおのれを貫徹し表現をまっとうしている。つい先頃も、散歩の途中コンクリートの石段を登っていたら、段と段との間のごくわずかなひび割れた隙間…もちろん土など全くない…ところから芽を出して立派な花を咲かせているのを見かけてた。
*『トニオ・クレーゲル ヴェニスに死す』高橋義孝訳 新潮文庫
|
|||||
「負けること勝つこと(75)」 浅田 和幸 |
|||||
「近代社会における世界の客観ということの吟味」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部