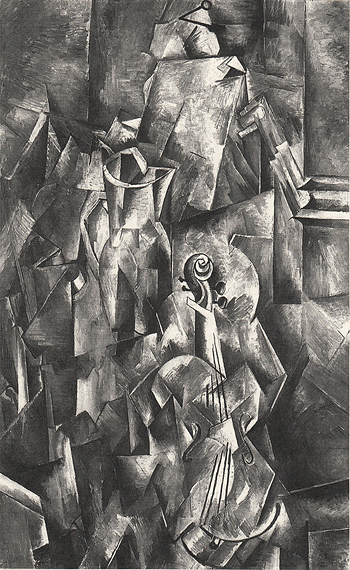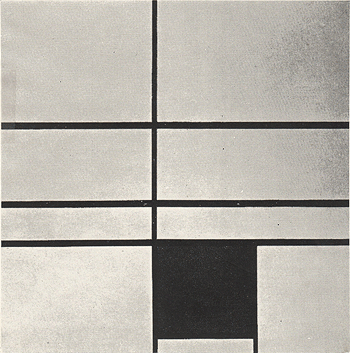第120号 |
|||||
| 2013年7月25日 | |||||
「問われている絵画(111)-絵画への接近31-」 薗部 雄作 |
|||||
何よりも先ずオリジナリティーを、というのがわたしのモットーであったということはすでに書いたが、それというのも、ある芸術家の仕事に深く感銘してその世界に没入し…あるいは飲み込まれ、自他の区別も消えて、あたかもその世界は自分の世界でもあるかのように思え、ようするに影響を受けて、それを基盤として自己形成を始めてしまうならば、それは真の自己に根差していないところに楼閣のようなものを築いてしまうかもしれない。実際そのようなことは、自分ではとくべつ意識はしなくてもありそうなことである。つまり根底的に西洋のある画家の、あるいはある時代のスタイルのなかに没入したまま、それを無意識のうちに自分のものとして、そして当然のこととして描いているというばあいである。とはいっても、影響を受けているということ自体ならばべつに問題はない。そういうことは…誰でも初期の段階ではあることで、むしろ普通で正常ともいえるパターンである。問題はそれ以後である。いくら強い衝撃でも外から受けた影響というのは次第に薄らいでゆく。だからその影響が消えたあとに出てくるものが問題なのである。それが真の自己であるばあいはよいのだが、また別の何かの影響圏内に入ってしまうということもある。というのは美術界にも流行があるので、しかもそれは変わりやすく、そして大きく見ればわたしたちはほとんどその流行のなかにあるので、そしてさらに大きく見れば西洋の流行の影響下にあるので、その変転のなかで右往左往しているわけである。
いずれにしてもわたしは西洋の近代・現代の美術から出発した。しかしそうした世界の誰かや何かの影響下で仕事をするということは、彼らのスタイルや手法のなかで自分を表現するということである。もちろんそれはそれでよいのだが、しかし、それではすでに他人の衣装を着て自己表現することで真のオリジナルということにはならない。そのようなやり方では、それをいつまでやっていても、またいくらよくできていても、やはり本質的にはどこか弱いように思えたのである。たとえばそれは音楽ほどではないが、というのは音楽は音による構成体なので、もともと描写には不向きでるが、そしてまたあえて描写や説明をしようとすると、かえって音楽性が減退してしまうところもあるが、絵画もまた色と形による形態…構成が主要な要素であるからだ。もちろん絵画は音楽と違って描写にはきわめて適した媒体ではある。だからむしろ描写が主要な要素にさえ見える。しかし二十世紀になってからそれも変化してきた。たとえばピカソやブラックのキュビスム作品のようになると違ってくる。そこではよく楽器などが描かれてはいるか、それらは分解されたり断片となってちぐはぐに組み合わされている。たとえばブラックの「水差しとヴァイオリン」を見ると、たしかに水差しやヴァイオリンはあるのだが、それは明らかに水差しやヴァイオリンをそれらしく描こうとしたものではない。ようは描き方…形式が問題なのだ。だからキュビスムをさらにおし進めて独自な絵画的展開を遂げたモンドリアンの作品「コンポジション」になると、もはや具体物らしきものは何もない。ただ縦と横の線の組み合わせと、いくつかの色面があるだけだ。そしてこのような作品のコンポジション…構成の影響をまともに受けて描くならば、ほとんど模倣にちかくなる。線の面の構成そのものが表現の主体であるのだから。そうでなくとも、誰かの作品のつよい影響のもとに制作するならば、いくらがんばっても、その形式や手法のなかでの自己表現という消極的な作品になってしまう。
もちろん、それほど影響ということに神経をとがらしてオリジナリティーにこだわらなくてもよいのかもしれない。実際すぐれた画家や文学者であっても、はじめはほとんど誰かの影響のもとに出発しているし、すでにふれたようにむしろそれが常道で正道といってもよい。だからポール・ヴァレリイなども『文学論』でいっている。影響を恐れることはない。誰からの影響もないオリジナリティーなどというものは、いってみればお手製のものばかりである、と。そして要は影響されたものをしっかり消化すればよいのだ。「他人を自己の栄養物にすることほどオリジナルなことはない。獅子は同化された多くの羊から成る。」と。ヴァレリイの『文学論』は二十代にくり返し読んだ本の一冊だ。そこには次のような文もある。「模倣が正当であり、価値があり、見るに堪え、かつ模倣されたがために損なわれたり、価値を失ったりすることも、また原作のゆえに模倣の価値も失われることのないものこそ大芸術品だ。」また「ある作品についてなされる模倣は、その作品から模倣され得るものを剥ぎとる」。そして「最高の作品はその秘密を最も長く保ち続ける作品。長い間、誰もその作品に秘密があろうとさえ気づかない作品」であるのだ、と。
にもかかわらず、わたしはオリジナリティーにこだわった。徹底的に自己に根差したところから仕事を始めることはできないものか、と。しかし自己にこだわるということは別の難題に遭遇する。というのも自己は決して心地よくも美しくもないからだ。あえていえばそれは一種の怪物である。この自己…怪物に対面する感覚を埴谷雄高は「自動律の不快」といった。そしてまた、それを生きることの不合理を積極的におし進めて「不合理ゆえにわれ信ず」ともいっている。さらにサルトルは、自己存在という物質とそれを取り巻く外界の物質的存在に同質を感じて「吐き気」をもよおしたという。これに比べれば、誰かの影響のもとに仕事をするということは、むしろ一種の快感である。模写の楽しさ、あるいは風景写生の楽しさなどもそこに由来するのかもしれない。しかし、そのような影響的方法のもとに、いわゆる正道? を歩いたわが国の画家たち……それもまた苦闘ではあったが……また素直な根っこからの成長をとげたという画家がきわめて少なかったのも事実である。それが苦闘? というのには理由がないわけではない。わたしたち日本に生まれた画家は、東洋人であるにもかかわらず、西洋の絵画を勉強し、ほとんど全面的に影響を受けて出発する、という状況にあったからである。それは画家だけではなく日本の教育の全般的な方針でもあった。それは現在でも大きく変わってはいないと思うが、かつてはそれがもっとつよかった。そして真剣にやろうとすれはするほど、わたしたちの伝統や何よりも自分と彼らとの資質の違いも分かってくるのであった。
しかしくり返すが、そんなことにこだわる必要はないのかもしれない。資質など違っていても共通しているものの方が、そして感動の方が重要なのだ。たとえば晩年の吉田秀和もドイツの歌曲にふれながらいっていた。「シューベルトの『菩提樹』は、もはやドイツの歌なんかじゃない。誰の歌でもない。僕たちみんなの歌なんだ」。それはまた「幼いころに母親と歌ったフォスターの「金髪のジェニー」と深いところでつながっている。」わたしもまったくそう思う。子供の頃から歌っているし、わたしたちの気持ちにもすっかり馴染んでいる。そして内心からわきでてくるような感情だ。それはおそらく全人間の共通感情で、音楽とはそのようなものであるのだろう。だから個々の作曲者によってつくられた楽曲は、いわば原音楽の現象として音楽なのだろう。シューベルトの音楽も例外ではない。とくに世界の多様な民族音楽などを聞くとそれをつよく感じる。音楽だけではない。世界の文学も絵画もまた原文学や原絵画の変奏であるだろう。ゲーテも個々の文学はバラバラで複雑なように見えるが、しかし「われわれはその中に無数の繰り返しを見出だす。それによって、人間の精神と運命がどんなに限られているかがわかる。」といっている。
|
|||||
「負けること勝つこと(76)」 浅田 和幸 |
|||||
「伝統的自然発生的権威と存在感を増す科学の権威の両立」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部