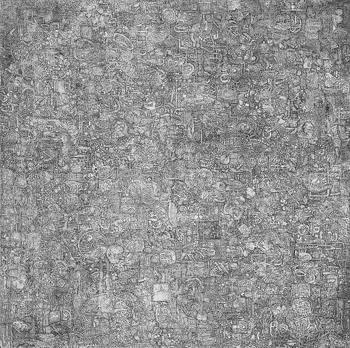第121号 |
|||||
| 2013年11月12日 | |||||
「問われている絵画(112)-絵画への接近32-」 薗部 雄作 |
|||||
わたしは執拗にオリジナリティーや資質などということをいってきたが、それでは実際にそのようなことを実践している画家がこの現代日本に存在するのか、という意見もあることと思う。ところが幸運にも、わたしは身近なところにそのような作家を見てきている。そのことはすでに『鎖国の方法論』(一九九五)のなかでも書いている。鎖国の方法論とは、実際に鎖国の敷かれていた江戸時代にきわめて創造性が発揮されたというところに注目し、現代のような情報過多な時代にはとかく情報に翻弄されやすく、さらに社会的にも情報の必要性が要請されるので、創造のようにおのれの根幹に関わる仕事においては、とかく真のおのれを見失いがちであり、あえてみずから鎖国的状況をつくりだし、その情報をシャットアウトすることによって、かえって創造を活性化することができるのではないのか、と伊藤若冲や浮世絵などを例にあげて論じたのであった。そして現代においても、精神にそのような一種の鎖国的な状況をつくりだし、過剰な絵画的雑念を払いのけて、おのれ自身の質に対面し、意識的にそれを貫いてきわめてオリジナルな仕事をなしている画家として嘉手川繁夫や齋鹿逸郎をあげたのであった。
嘉手川繁夫についてはすでに何度か書いている。もう十数年前になると思うが、彼の個展に際して、たとえば「嘉手川繁夫の作品を最初に見たのは一九五四か五五年であった。まだ二十代初めの頃である。何かの集まりのときだった。その時たずさえていた作品を見たのだと思う。その場の状況よりも、とにかく、そのずばぬけてオリジナルな作品にきわめて強い印象を受けたことをよく覚えている。」そして「その作品が、とりわけわたしの心に突き刺さってきたのは、写生とは無縁とおもえる、何か植物的なものを感じさせるそのフォルムが、内心わたしの模索していた形にもちかく、しかも現実のものとなってわたしの眼の前にある、という驚きと焦燥がないまぜにいたためでもあろう。」と。しかしそれ以後四十数年が過ぎた。「けれども、ここでわたしはとくに驚くのであるが、にもかかわらず、彼の作品は現在でも、最初に見たときの印象とほとんど変わらない。もちろん表面的な多少の変化や起伏はあるが根幹は少しも変わらず、その一貫性に目を見張ったのであった。さらに沖縄県立美術館の「哀愁と血の造形・嘉手川繁夫の世界」展のときには、彼の作品の特異な印象について「一度見たら忘れない、という作品がある。わたしの経験では若いとき見たムンクの『叫び』やアンソールの『仮面に囲まれた自画像』がそうである。またアンリ・ルソーやゾンネンシュターの一連の作品も忘れない。そして日本の画家では若冲のニワトリの絵や劉生の『麗子像』などが一度見たら忘れない。」そして「嘉手川繁夫の作品も一度見たら忘れない。印象が強烈である。それだけではない。その作品に他の類例がないのだ。すくなくともわたしの見てきた東西の絵画作品のなかには見当たらない。」とそのオリジナリティーについて書いたのであった。
けれども齋鹿逸郎についてわたしは今まで書いたことがない。彼が亡くなってからもう六年もたっているという。最近、ギャラリー・ジ・アースで彼の七回忌展という個展があり、あらためてそう思ったのであった。きわめて丈夫そうに見えていたので、すくなくともわたしよりははるかに健康であると信じていたので、わたしには意外なことであった。亡くなる一週間前にもわたしの個展に元気な姿を見せている。しかしわたしより一週間後に個展のあった木下晋氏は「オレは亡くなる前の日に会ったのでなおショックだ」といっていた。 亡くなる一年ほど前だったと思うが、鎌倉のギャラリー・ジーアースの帰りに三・四人で駅ビルの居酒屋へ寄ったことがあった。そのとき帰りぎわに「薗部君にたのむよ」といっていた。そのときは冗談のような雰囲気もあったので、すぐに忘れてしまっていたが、しかし今から思うと案外素直な気持ちでいったのかもしれない。というのも彼とは二十代からのつき合いだし、作品の経過もずっと見てきている。彼の作品とわたしの作品は、表面的にはまったく異なるよう見えるかもしれない、いやまったく正反対のようにさえ見えるかもしれないが、しかし制作者としての姿勢…自分の質に徹底的にこだわろうとするその制作姿勢には、どこか共通するものがあるように思える。また、わたしが画家であるにもかかわらず本なども何冊か書いているので、おなじ画家としての立場からの何か作家論のようなものを期待していたのだろうか。しかしわたしには、とてもそのようなものはできそうもない。それに彼の作品は言葉になりにくい。あまりに作品がそれ自体で存在しすぎている。言葉はつけたしのようになってしまいそうである。やはり作品自体を見て感じとるしかない。だから思い出を交えた感想のようなものになってしまう。
齋鹿逸郎という名前をはじめて知ったのは二十代の後半だったと思う。たぶん一九六十年前後である。しかし最初に会ったのは人間ではなく一枚の案内状であった。それもわたしにきたものではなく、当時近所に住んでいた女流画家のK氏に来たものであった。あるときK女史が「オソノさん、あなたの親戚のような絵があるよ!」といって齋鹿逸郎の案内状を見せたのであった。彼女はすでに活発な発表活動をしている活躍中の先輩画家であった。だから見知らぬ新人からの案内状もよく届くのであろう。「親戚」という言葉に好奇心を感じなからその案内状を見ると。なるほどそれは親戚?…同類のような傾向の絵であった。その作品は何かのイメージを描いたというものではなく、ごく単純な幾何学形のようなものが鉛筆で点状に描かれていた。描き方はともかく、たしかにどこか同類のように思えた。というのも、その写真を見て、作者が今、どういう模索の状態にあるのか、またその手探りで何を探そうとしているのかなどが、わたし自身の手探状況と照らし合わせて、よくわかるように思えたからである。たぶんK女史も作品にそのような共通するものを感じて「親戚」といったのであろう。そこには既成絵画いっさいを払い落として…時の流行には距離をおいて、たとえたどたどしくとも、自分の意志や心情にそって、一から何かを形成してゆこうという作者の意気込みが感じられたからである。
最初に齋鹿逸郎に会ったのは、それから数年後のことであった。その頃わたしは藤沢に住んでいた。そしてやはり藤沢に住んでいた田口雅巳氏に誘われて、調布に住む齋鹿氏を一緒に訪ねたのであった。南武線の登戸駅から立川寄りに二つか三つ先の駅で降りて、多摩川を渡し船で渡り(当時はまだ渡し船があった)向こう岸の調布へ行ったのであった。彼は住まいとは別に近くの木造アパートの一室を仕事場にしてた。こまかいことは忘れたが、ある一場面だけが今でもはっきり記憶に残っている。わたしたちは薄暗い四畳半ぐらいの部屋で立つたまま話をしていた。たぶん作品を見たり説明を聞いたりしていたのだと思う。しかし不思議なことにそこでの会話や作品などの記憶はほとんどない。ただある一場面だけが鮮明に記憶に残っている。それは「これで描いている」といって鉛筆を出して見せたときの場面だ。押し入れから底の浅いボール箱を取り出してわたしたちに見せたのであった。開くとなかには奇妙?な鉛筆…大工さんの使うという…やや太めでひらべったい芯の削った鉛筆がきちんと並んで入っているのであった。そんな箱がいくつも重ねてあった。その鉛筆がとても印象的で、その場面だけ今でも鮮やかに記憶に焼きついている。
しかしあれから四十数年にわたって鉛筆は使われ続けたのであった。あのときでもすでに鉛筆に対する決意のようなものは感じたが、その鉛筆が彼の将来にどんな軌跡をえがかせるのかは、おそらく当時の彼自身にも、まだ漠としたものであったことと思う。「鉛筆は偶然天の与えたものだと思ったこともあるけれど、こうして四十年持ちつづけてみると、もうすっかり自分の代弁者の位置を占めるまでに」なった、と晩年になっていっているが、たとえ最初は偶然手にしたとはいえ、鉛筆はその後四十数年のあいだ持ちつづけられたのである。「日常生活の四十年と制作持続の四十年があって、その違いは鉛筆を持つと持たないことの違いにしか過ぎない」が、「この両方がぎりぎりのところで相拮抗しているところに何時も自分を置きたかった。」そして「それが制作というものだと信じていた」といい、またその制作は「少しでも他所見をしたら見失うような淡々としたドラマ」である、と。ここで唐突のように「他所見をしていたら見失う」ということがいわれているが、「余所見とは」何か、また「見失われる」とは「何を」か。それは四十年数の間、ただ鉛筆を握って作業をしていたといことではない。鉛筆と内心の意志はたえず密着していなければならない。さらに密着したまま方向感覚を維持して何かを探しながら進行しなければならない。それが「少しでも余所見」をすると…雑念に気をとられたりすると…たちまち鉛筆と内心との密着度はズレてにぶいものになってしまう。そして熟練した単なる手作業に落ち込んでしまう。終始、内なる深層への密着の意志とその向かう方向感覚の維持が要請されるのだ。制作とはまことに心身を磨り減らすような作業ではある。しかしそれは、ある種の作家には避けることのできない宿命のようなものであるのだろう。「最初カーペンターペンシルに出会ったとしても、使ってみたいという欲求がなかったら馬に念仏みたいなもので」あっただろう。この「鉛筆の単純さが、私の生来の単純さとマッチしたということであって、それが偶然に見えただけである。」ともいっている。
生涯にわたって鉛筆は使いつづけれられたが、それがすべてカーペンターペンシルであったかは知らない。しかし初期のある時期以後はもっとやわらかい普通の鉛筆や胡粉などが使われていたようである。やがてカーペンターペンシル独特のはばひろい点状の描き方は消えて、こまかい点や線の絡まりや重なりあった緻密で密度ある画面になっていったからである。作品のサイズも次第に大くなっていった。しかし画面のなかの幾何学的な形は消えてゆき、有機的な曲線状の形態が現れはじめた。やがてそれらが密集して重なりあい微細な「ものたち」が広がりだした。あの「ものたち」? あれはいったい何だろう。記憶のなかを探せばどこかで遭遇しそうな「ものたち」のようにも思えるが、しかしあれは「物」であろうか。「物」のようでもあるが、しかしそれは現実の「物」や「物体」ではない。それを見極めようとして画面のなかにわけ入り熟視しても、それは何か物のようでありながらも、しかしそれは何物にも重ならないし行き着かない。一見、地層の断面や壁のしみなどを連想させるが、それは自然現象の再現ではない。イメージでも観念でもない。偶然性に導かれて画面に氾濫していったようにも見えるが、しかしそこには、はっきり意志的なものも感じられる。さらに全作品を眺めると、そこにはきわめて強固な一貫性が見られる。にもかかわらず、それは地層のなかにうごめく菌類や忠類のようでもある。あるいはまた電子顕微鏡の拡大写真を連想させるようなところがある。それだけではなく、この得体のしれない「ものたち」は、暗やみのなかで何かはっきりした形あるものに成ろうとしているようにも見えるのだ。
「画における空間にしても、何もないと思わせる空間と何かで充満している空間とあるなら、何かで充満している方が当然ということになる」という。そして「微細な物質だって拡大してみればみんな形もあるわけであって、もし、画面の空間を作るとすれば、それは私の我流空間になるはずである」ともいっている。「我流空間」といって齋鹿逸郎は画面を鉛筆で埋め尽くした。そこには余白もない。サインもない。ひたすら空間を埋め尽くした。そしてそれはまた内的拡張でもあり内的探索行為でもあった。さらに未生のものを蘇らせる行為でもある。そうして齋鹿逸郎は齋鹿逸郎を掘りおこし、探し出して齋鹿逸郎にゆき着いた。それは外見的にはきわめて単調な持続のドラマであった。齋鹿自身も晩年に自分の全作品のタイトルを「無題、持続、集積」としている。
|
|||||
「負けること勝つこと(77)」 浅田 和幸 |
|||||
「知性と知識のバランス」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部