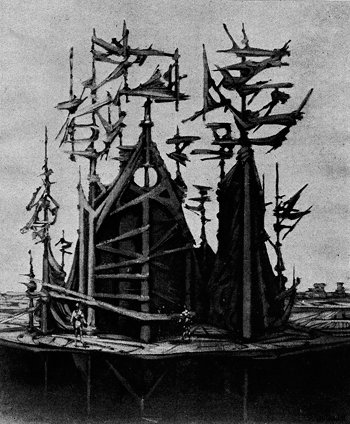第122号 |
|||||||
| 2014年3月12日 | |||||||
「問われている絵画(113)-絵画への接近33-」 薗部 雄作 |
|||||||
今では知る人も少ないのではないかと思うが、一九五〇年代に目についたリシュアン・クトーという画家がいた。一九五二年の日本国際美術展(毎日新聞社主催)にフランスから出品されていた「デ・ロワラブル」という作品が『美術手帖』の七月号に掲載されていたのだ。わたしはそれを見て、どこか心ひかれるものがあった。沈んだグリーンの色調で何かの建造物のようなものが静まりかえった水に浮いている。建造物とはいっても、それは抽象的な構成物で、船のようなあるいは王冠のようなものを想像させるところがあった。末松正樹の解説を読むと「デ・ロアラブル」とは、おそらくクトーの造語でLoir(冬眠する山鼠)とArbres(木々)を組み合わせたものだと思うが、Loirはまたロワール河を連想させる」といい「地上のどこかの片隅の、河岸にすてられた廃船の宮殿」のようであると書いてある。初めて見るこの作品に、なぜかわたしは心惹かれのであった。たぶんこの作品のもつ、抽象的ではあるが何か具象性を暗示する形と構造が、わたしをとらえたのだと思う。それは当時、抽象絵画のマンネリ化に新たな方向性を感じさせ、何か新しい表現の可能性を感じさせたのだと思う。そして、そんな作品の世界がわたしの心にもスムースに入ってきたのであった。
リシュアンークトーはこの作品によって当時のわが国の美術界にも関心を持たれたようであった。というのは、翌年には鎌倉の近代美術館で彼の作品を集めたリシュアン・クトー展が開かれているからである。地方に住んでいたわたしはどちらの作品も直接には見てはいないが、そのクトー展が『美術手帖』(一九五三年二月号)に滝口修造の作品解説と末松正樹の「地平線の神秘─リシュアン・クトー展の印象─」という文章と何点かの作品が紹介されていた。当時の美術界では二人とも、とりわけ輝いて見えた存在であった。滝口修造については、すでに何度かふれたこともあるが、美術を志す青年にとっては、ひときわ大きな存在であった。滝口修造に注目されるということは、美術界への登竜門でもあった。たとえば、かつて池田満寿夫は「わたしが滝口修造の名前を知ったのは、たぶん十五歳位の時だったが、どの名前よりも、その名前はまぶしかった。シュルレアリスムという名前がまぶしかったように、滝口修造はもっとまぶしかった。この不思議な名前はどういう訳か、私に年齢を感じさせなかった。それは少年のようにも見えたし、青年のようにも感じられたし、老人のようでもあった。すでに夢の方向がその名前の中にあった。青年の心をあやしくかき乱す銀色の星くずが、秘められていた。」(『本の手帖』─特集・滝口修造─ 1969)といっているが、わたしも、おなじく美術にとりつかれた地方に住む同世代なので、その気持ちがよくわかる。当時、新聞や雑誌に書く文章や紹介する作品には、いつも特別に注目させられていた。 末松正樹も、当時はよく美術雑誌に登場して新しい美術を紹介していたので注目させられていた。そして、そこで紹介される海外…とくにランスの画家や作品もまた新鮮で刺激的であった。さらに末松正樹の描いている抽象的作品も清新な印象があった。たとえば当時、美術批評家の寺田透は「井上長三郎論」(『美術批評』一九五三年十二月号)のなかで「今年の初夏の第三回日本国際美術展の折、僕は坂本繁次郎、林武、鳥海青児、末松正樹、それと井上長三郎の作品は、海外の作品に幻惑された眼で見過ごされていいものではないという考えを簡単にしめした」(「群像」八月号)。そして、今あげた画家たちをどういう根拠にもとづいて選択したかの理由を、それぞれの画家について述べているが、そのなかで「末松正樹の作品が繊細でヨーロッパ的抽象作業には必至の理知の強靭さを欠いており、マネシエやヴィヨンのように色に遊ぶべきかアルトゥングやスラージュのように線を固守すべきかの態度決定の必要すらここでは自覚されないということは明白であるが、しかしその叙情的心情による色彩や形の選び方には不純なものがなく、またさらに、長く同じ画風をつづけて来た作者の内的変化……抽象という作業が本来もっているリアリズムへの覚醒があるように思えたのである」と、当時画壇のなかで特に評価の高かった具象画家たちのなかへ、ただ一人の抽象画家として名前があげられている。また「美術手帖」1954年2月号では「アトリエ訪問」(瀬木慎一による)にも登場している。わたしはどちらも熱心に読んだ。とくに「アトリエ訪問」に掲載されていた何枚かの写真は、いろいろ想像しながら何度も眺めたものだ。
鎌倉近代美術館のクトー展からしばらくたってからだったと思う。すでにわたしは東京に出て来ていた。そしてクトーのこともほとんど忘れていた。そんなあるとき、たまたまブリヂストン美術館の前を通りかかるとクトー展をやっている。わたしは迷わず券を買ってなかに入った。そこには以前に雑誌で見た作品が一堂に並んでいる。かつては写真版であったが、今目の前しているのは本物のクトー作品である。会場は薄暗かったが、やはり原画の生々しさが全身につたわってきた。それは写真ではわからなかった作品の肌から感じる現実感…作品の生理のようなものが伝わってくる。ここで〈生理〉という言葉が浮かんできたのも、たぶんクトー作品のもつ一つの特徴をあらわしているのだと思う。たしかに、そこに描かれているのは、一見風景や静物らしきものではあるが、それらは見えるままの自然の姿ではない。人や風景は切断されたり、再構成されたりしていて、さらに、それらには、どこかバラバラに切断された生き物の内臓を思わせるような生々しさがあった。そして、何よりもわたしの関心を惹いたのは、すでにふれたように画面構成の点で、何か示唆されるものがあるように感じたからであった。つまりそこでは、たしかに人や風景を思わせる形が描かれているのではあるが、それは単なる写生ではく、いったん解体され、あらためて抽象的に再構成されているのだ。そのことが、とくにわたしの関心をひいたのであった。当時そんなふうに言葉で考えたわけではないが、今から思えば、そんな好奇の眼で会場を見てまわっていたのであったが、ある壁面にあった「パン運搬人の戸棚」という作品にわたしはとらえられた。薄暗い戸棚…密室のなかで、得体のしれないガラクタたち…物体が、なにか惨劇をくりひろげた後のような、奇怪な作品であった(写真が不鮮明で掲載不可能)。
すでにふれたように、その頃のわたしは抽象的な形成物というものに関心があった。そしてたとえば次のようなことを考えていた。建築物などはもともと自然のなかにはなかったものである。しかし建築という名前がつけられて、すでにわたしたちは風景の一部としてごく自然に眺めている。しかしこれは人間によってつくられたもので、もともと自然のなかにはなかったものだ。さらに、これをバラバラ解体してみれば、ほとんどの部分は幾何学的な断片になる。つまり幾何学的な断片を組み合わせて一塊に物体に作り上げたものが建築と呼ばれているのである。たとえばこれを初めて見たとする。そしてこれが何のための物であるかも知らないとすれば、それはまったくの抽象的形成物として見えるにちがいない。それは建築物だけではない。自然物の生成物…たとえば植物などでも、わたしたちは、すでに植物という名称がついているので安心して見ているが、しかしこれも、まだ 植物という名称もなく、そして、これを初めて見たとすれば、やはり、それは不可思議で抽象的な形成物として見えるのではないだろうか。 つまりそのように、絵画も造形的要素…色や形や面などによって、それを自分の意にそって何かの形…自然とはまた別の…につくりあげることはできないものだろうか、と思ったのであった。そしてそんな実例としては、すでにたびたびふれているクレーの線だけで構成された「植物園」などを思い浮かべるのであった。
滝口修造は「果物娘」という作品の解説で、クトーの作品の特徴について舞台的であるといっている。それはどんなところかというと、「ほとんどすべての主要なモチーフが登場人物のように、ある背景のなかに立ってだんまり芝居をしているように見えるからである」。そして「その背景は野原であれ、水辺であれ、街であれ、廃墟であれ、空間を粧ったとざされた空間であり、形而上的な書割り的な風景である」と。そういわれて、あらためて眺めてみると、たしかにそのように見えるのであった……そして、この究極的には閉ざされている舞台的な空間というのが、なぜかわたしをひきつけた。さらにその登場人物あるいは物たちは「ボードレール(イロニー)ランボオ(彼岸)ロートレアモン(巨大な非常)などの落し子であり」そしてまた「フロイド的な人間像が寓意画のように」描かれている」と書いている。かつてデビュッフエの解説のときもそうであったが、ここでも文学や心理学を引き合いに出して語っている。それがまたとても魅惑的に聞こえるのであった。
けれどもわたしには、解説の「果物娘」や、ほかにも人物を思わせたり、人物そのものを描いた作品もいろいろあったが、それらの作品にはあまり関心が持てなかった。たしかに、大きく見れば「閉ざされた舞台」のようなところに登場しているように見える人や物ではあるが、とくに人物になるとその舞台は次第にひろがってゆき、やがて取り払われて、ほとんど自然の観景のようになり、閉ざされた空間感は消えてしまっているようにも見えるのだ。それと同時に緊迫感も失われて、どこか自由を楽しんでいるかのように見えるのである。それがいけないというのではないが、なぜか他のクトー作品にあった、閉ざされたような舞台的空間感がなく、作品の吸引力も弱まってしまったように見えるのであった。そんなことが原因かどうかわからないが、だんだんクトーの名前も聞くことがなくなってしまった。その後どうなったのだろう。画家クトーのなかで芸術という病が癒えてしまったのであろうか。そういえば滝口修造も、さきの解説でクトー作品の特徴の一つとしてふれていたボードレールのように、病…詩をまっとうするのも容易なことではない。
|
|||||||
「負けること勝つこと(78)」 浅田 和幸 |
|||||||
「『個人と人間の時代』における人類の責務」 深瀬 久敬 |
|||||||
【編集あとがき】 |
|||||||
| - もどる - | |||||||


編集発行:人間地球社会倶楽部