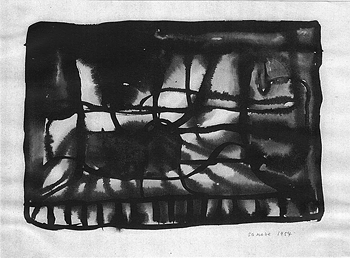第123号 |
|||||
| 2014年6月24日 | |||||
「問われている絵画(114)-絵画への接近34-」 薗部 雄作 |
|||||
書き割り的な…閉ざされた空間感がなくなるにしたがって、クトー作品の特徴であった舞台と登場人物という関係も消えて、ごく普通の風景のようになり……すべての作品がそうなっていったのかどうか、わたしはよく知らないが……ただ数年後に、浜辺に立っている人物を描いた作品を見たときには、すでに舞台的な感じはなく、ありふれた浜辺の風景のようにしか見えなかったので、その後わたしの関心も次第に消えてしまった。
わたしは〈限られている〉とか〈閉ざさている〉という物や場所にひかれる傾向があるようだ。なぜそうなのかはわからない。たとえばY線のある場所…わたしは毎週一度そこを通る。いつものように電車の窓から外を見ている。ほとんどは住宅…屋根ばかり見えるのであるが、あるところにくると山林になり鬱蒼とした木々が現れる、と、まもなく木々に囲まれた草地の空間が一瞬現れる。そしてそこだけ何故か別の世界のように見える。あれは何だろう? と思うのだが、またたくまに過ぎ去ってしまい残像だけがあとに残る。その人の気配をまったく感じさせないわずかに草地が妙に気になるのだ。一瞬の光景で、実際にそこへ行って見ることができない、ということがよけいに気になるのかもしれない。わたしはそこを通るたびに、そろそろあそこにくる、と思いながら車窓から外を見ている。するとまさしくそれは現れて、過ぎ去る。そんなことを何十年もくり返している。しかし、ごく最近、その閉ざされた草地に杭が打ち込まれたり、まわりの木が一部切られたりして、森の向こう側か垣間見えるようになった。すると向こう側は普通の人家であった。何十年も好奇の眼で見ていた謎のような風景は、急にありふれた風景になり、わたしの関心も急にさめてしまった。
素粒子ニュートリノをとらえるためにつくられたスーパーカミオカンデの内部空間を写真で見たときも、わたしは異様な感銘を受けた。やはり、そこに巨大な閉ざされた空間を感じたからだ。そして、その巨大空間には天井の一角からわずかな光が降りそそいでいるのが印象的であった。わたしはそのとき思った。「この空洞……装置の真下の中心に立って上を見上げたと想像する。すると一万二千二百個の光電子増倍管に埋め尽くされた全壁面にすっぼり取り囲まれた自分を感じる。それは立体的なマンダラにつつまれたかのようである。」と。(『抽象絵画の世界』)。今思うと、これも、あの森のなかの木々に囲まれた草地の空間から受ける感じと、どこか共通したところがあるような気がする。さらに、すでにたびたびふれているが、映画「ブレードランナー」の映像…室内や都市の観景にも閉ざされた空間を感じ、全体として切迫したようなリアリティーを感じたのも、何か共通したところがあるような気がする。
そんな閉ざされた空間にひかれるのは、わたしの特殊な性格によるものだろうか。それとも人間一般の感じる傾向なのだろうか、わたしにはわからない。しかし人間の一生…時間にも、長短のちがいはあっても区切られているということに変わりはない。あるいは絵画制作という行為を長年やってきたことも影響しているのだろうか。絵画は多くのばあい、四角く区切られた小さな面積のなかで悪戦苦闘する。そんな行為を数十年やってきたためであろうか。それに、その四角いスペース…画面もだんだん小さくなってきた。それだけではなく描く部屋…空間もますます狭くなってきた。狭く閉ざされた空間の方が、身体と空間の一体感が持ちやすく精神の集中やエネルギーも発揮しやすいように感じる。しかしそんな感じ方をするのは、あるいはわたしが、そもそもの出発当初にきわめて狭い空間…部屋で制作していた、ということに由来しているのだろうか。つまり狭い空間が心身にしみついてしまい、いつしか感性や想像力にまで影響してしまったという……。
たしかに、わたしは当初狭い…三畳の部屋で制作していた。三畳というのはまことに狭い。床…畳三枚の面積より周囲の壁…といっても当時はベニヤ板…の面積の方が圧倒的に広い。あお向けに寝ていると、部屋を横にした方が広くなる! と思ったものだ。ところが、あるとき友人のI君に誘われて彼の住まいを訪ねた。するとそこは、わたしの部屋よりも狭かった。二畳である。といっても、わたしのところより畳一枚狭いだけだ。大差ないといえばいえる。しかし極小空間における畳一枚の面積の差は大きいといえばいえる。しかしその部屋には壁がない! 四方が障子なのである。これは部屋? だろうか、と思ったものだ。障子を開ければそこは部屋でなくなる!。第二次大戦の空襲で焼け残った家屋のようであったが、その頃の家には、そんな部屋?のある間取りの家がよくあったような気もする。つまり、玄関を入るとすぐ突き当たりに二畳くらいの四方が障子になっている部屋…空間があった。その空間が何のためのものであるのか、わたしはよく知らないが…あるいは、まずお客さんに上がってもらって、そこから次の部屋へ行けるようになっている、ひかえの間のようなものだろうか?………。 彼はその部屋?を借りて住んでいた。貸す方も借りる方もそんなことは、部屋の大小にかかわらずよくある時代であった。けれども彼は、そこにただ住んでいるだけではなかった。その小空間で猛烈に制作していたのだ。四方の障子全面には、彼の最近作…紙に墨で描いたおびただしい習作がびっしり貼りつけられていた。それらの作品からくる熱気と気迫! その猛烈さにわたしはショックを受けた。
わたしは思った。作品はどんなところでも描けるのだ。制作に部屋の大小はかかわらない、と。自分の狭い部屋へ帰ると、わたしもさっそく制作にとりかかった。もちろんわたしの部屋も似たようなものだ。もちろん椅子やテーブルのようなものはない。それより何もない。何かあればそれだけ部屋が狭くなる。床の上で描くのだ。さしあたり、わたしも彼の影響で、とりあえず墨で小さな紙に、とくにイメージもないままつづけざまに…衝動的に得体のしれない何かを描いた。今、あえてそのときの制作状況を思い出すと、筆の勢いにまかせて線を走らせ、墨の濃淡やばかしやにじみを生かしながら…偶然の効果をたよりとした、とくに目的もない場あたり的な行為であったようだ。掲載作品は一連の試作のなかでは比較的サマになっている方だが、ほとんどは単なる試みの域をでていない。意図も目的もないくり返しなので発展的な持続は困難だ。どうどうめぐりである。やがてわたしは、そこに何か目的…何かを形成することが必要であると感じはじめた。とにかく何でもよい、なにかの形を…もっとも単純な線や面の組み合わせ…それを自分の心情にそって意志的に形成してゆかなければ、と模索し始めた。今から思うと、このあたりが現在のわたしへの始まりであったように思う。しかしここでも頭のなかにはクレーの絵や言葉がちらついていたようだ。
そしてわたしは、いつしか、そしてなぜか「限られている」ものや「閉ざされている」ものに関心を持つようになっていた。しかし、あらためて外界や内界を見つめると、そこもまた、ほとんどのものが「限られて」いたり「閉ざされ」ていたりしているように見えるのであった。「閉ざされている」というのは、あるいは少しオーバーかもしれない。囲われている、といった方が適切かもしれない。いや、どちらにしても似たようなものだ、と思って辞書を引いてみると、「閉ざす」は、門・戸などをしめて錠をおろす。出入口をふさいで外部との関係を絶つ、などとある。「囲う」は、周囲をとりまき中心と外を区別する。塀で屋敷を囲う。女を囲う、などとある。どちらもあまりよい意味には使われていないようだ。しかしこれは一般的な解釈の例でる。これ以外にもひろく解釈すれば、いろいろなばあいに使えると思う。たとえば人間は、それぞれ自分の肉体に閉ざされて存在してる。あるいは皮膚に囲われている。そして、その肉体からわたしたちは外へ出られない。想像や夢のなかでは出ることもあるようにも思うが、実際には出ることができない。わたしはそんな意識をかつて書いたことがある。「私は人間存在の個別性ということについて考える。つまり、私たちはそれぞれ個別のうちに閉ざされて存在している。それは想像力によって、どれほど遠くまで出てゆこうと、本質的には少しも出られない。たとえば私の死は他者の死と交換不可能である」(存在論的絵画・1967)。また別のところでは「わたしは、わたし自身を、一つの実験場として、ここで絵画作品の開発や成育が可能であろうか、ということを四十数年やってきた。なぜそんな限られた場所を耕作地に定めたかといえば、そこ以外には、真にわたしに根差した場所はありえないという直感と確信をいだいたからである」(内なる耕作地・1999)。そして今までに書いた本を見ても 「牢獄」とか「鎖国」という、「閉じる」や「囲われる」に関わる言葉をタイトルにしている。
そんな眼で見たり感じたりして制作してきたわたしの作品には、やはり外部の眼からも、そんなふうに見えるようであった。たとえばわたしの作品を初めて見た人から、ときどき「閉ざされている」とか「作品のなかへ入れない」ということを聞くことがある。なかには「見ることを拒絶しているような作品だ」といった人もいる。たしかにそんな印象があるのだと思う。かつて美術批評家の坂崎乙郎氏は「薗部さんの作品を見ているとリボンが桟に変わり、桟が鉄格子になって、いつしか幾何学的な牢獄に閉じ込められている「私」を発見する」(1971年・あかね画廊企画展のDM)と書いている。わたしはそれまで、とくに牢獄というイメージは意識していなかったがピッタリだと思った。その言葉は心に刻まれ、そして後年わたしは『牢獄と宇宙』や『鎖国の方法論』を書いたのであった。坂崎乙郎氏は先の文章のつづきで「牢獄の住人は脱出を夢みる。できればどこか桟がはずれていればよい。鉄格子にすきまがあればよい。願望は飛翔する。垂直に。しかし、これは制作者にとって、必要不可欠なスペースなのだ。唯一の自由なスペースなのだ。」そして「彼はいくたびか脱出をみて、けっきょく彼の牢獄に帰ってくる。そこで生を終えるために……」と書いている。
たしかに、牢獄(肉体)に閉じ込められているだけではどうにもならない。やはりある種の脱出が必要だ。しかしそれは桟をはずしたり鉄格子をはずしたりしてではない。むしろ牢獄の内部…の中心に深く潜入し意識を集中する。そして「光がレンズに当たって焦点を結びまた広がってゆくように、意識の視線が焦点をむすんで中心を照らしだしたとき、白光は個の壁を焼きつくし、わたしはわたしの壁を突破して、内なる宇宙のなかへ侵入し、広がってゆくであろう。」(『牢獄と宇宙』)。ここでわたしは、内なる宇宙と外なる宇宙を連続したものとしてとらえた。内と外は、一見逆方向にひろがっているように思えるが、にもかかわらず究極では重なる、と。それは作品制作の内的体験であった。しかし、そのような考え方は現代の物理学や天文学でもすでに常識のようだ。たとえば村山斉は、ギリシヤ神話の「ウロボロスの蛇」(自分で自分の尾を飲み込んでいる)にたとえていっている。「わたしはよくこの蛇を思い出します。広大な宇宙の果てを見ようと思って追いかけていくとそこには素粒子があり、いちばん小さなものを見つけようと追いかけていくと、そこには宇宙が口を開いて待っている」と。(『宇宙は何でできているのか』岩波新書)。 しかし、このような考えは、かたちは違っても古代インドにもよく出てくる思想だ。たとえばムケルジーはタントラについて語りながらいっている、「タントラ画家というものは、たえず発見をし続ける世界に入り込んだ人間である。発見といっても、自分自身をではなく、彼が自分のなかに見いだすことのできた宇宙の根源を発見しつづけるのである。いまだ知られざる世界が、われわれの内部にある。それはわれわれ生きとし生けるものの原子のなかにある。われわれはそのなかに入りこんで経験しなければ、それを学ぶことができない」(『タントラ東洋の知恵』新潮選書)。やはり脱出は外へではなく、内へである。そして内へ深く入ってゆくことが究極では外へ出ることでもあるのだ。 「無限の中に歩み入ろうと欲するか。有限なるものの中をあらゆる方面に行け」「制限のなかに初めて名人が現れる。そして法則のみが、我々を自由を与えることができる」 「無制限な活動は、どんな種類のものであろうと、結局破産する」(ゲーテ)
たとえば囲碁や将棋の世界も限られた数十センチの四角い盤面だ。そして無数の制約に満ちている。しかしそこにはまた無限の広がりもあるようだ。かつて羽生善治はいっていた。「盤面をにらみながら、長時間、いくとおりもの手を先の先まで考えていると、ふと、盤面という限られた場所から解き放されて、あたかも海原のまっただなかに立っているような思いになる」と。
|
|||||
「負けること勝つこと(79)」 浅田 和幸 |
|||||
「人間の存在そのものを客観する時代へ」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部