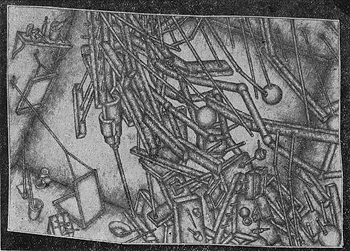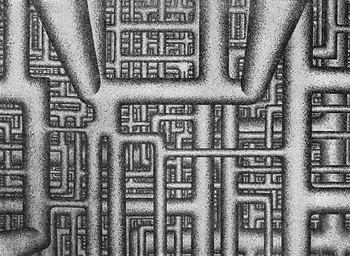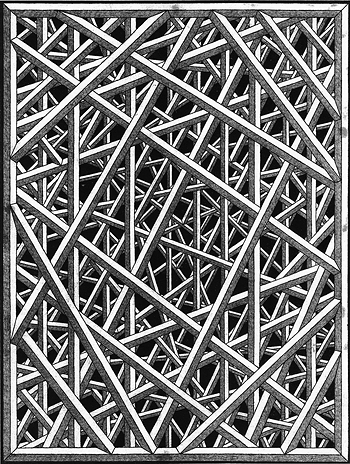第124号 |
|||||||
| 2014年10月11日 | |||||||
「問われている絵画(115)-絵画への接近35-」 薗部 雄作 |
|||||||
閉ざされた空間といえば、わたしは河原温の作品を思い出す。一九五〇年代後半にもっとも目についた画家だ。当時の雑誌「美術批評」(一九五五年一月号)の目次を開くと、そこに彼の「物置小屋の出来事・第一部・不安」という作品が載っている。当時それを見てわたしは衝撃をうけた。自分の内部にもそれにちかい感覚があるのを感じたからだ。描かれているのは、どこか地下室のような場所におびただしい廃物…鉄管のようなものが積み上げられている。その廃物たち…鉄管のようなものは何か生きもののように群れをなしてて動いているようでもある。それらがすべて鉛筆…たぶん鉛筆で克明に描き出されている。きわめて写実的であるのだが、しかし抽象的でもある。同時代の多くの人たちにも衝撃的だったのだと思う。またたくまにスターのような存在になっていった。たとえば滝口修造のような批評界の大御所も「カワラオンの世界は戦後派の絵画にひとつの典型を示した。すべてが焼野原であったとき、そこから何ものかが生まれるのかどうかを問うことができない状態にあって、禿げた不毛のコンクリートの隔壁のなかで、おそろしい繁茂を夢みたのである。そんなところでは、たとえば、「嫌悪」が一種ふしぎな燐光を発する純潔な空間を形づくる」「美術手帖」一九五八年一月号・特集「明日を期待される新人群」)と書いている。
ここでわたしはふと前々回にふれたリシュアン・クトーを思い出した。もしかしたら河原温はクトーの作品を見て、このような作品のイメージを思いついたのではないか、というきわめて唐突かつ独断的な思いが浮かんできた。もちろん、だからといって、「物置小屋の出来事」の独創性が少しでもゆらぐわけではない。にもかかわらず、なぜそんな思いが浮かんできたかというと、クトーには「パン運搬人の戸棚」という作品がある。この作品については前々回にもふれたが、描かれているのは戸棚…いわば密閉空間内での物体たちのドラマである。河原温の「物置小屋の出来事」も、閉ざされた室内での物体…廃物たちのドラマである。クトーの作品は一九五三年の「美術手帖」に掲載されている。そして河原温の「物置小屋の出来事」は一九五五年に日比谷画廊で発表されている……当時の若い画家で「美術手帖」を見ない、というひとはおそらくいない……しかし、両者を比較すれば双方のちがいは歴然としている。クトーの作品には全体としてどこか生物的なぬくもり…滝口修造も触れているようにフロイド的心理学やエロスが内蔵されている。そしてどこかユーモラスな一面もある。しかし河原温の作品にはエロスもユーモアもほとんどない。さらに「浴室」シリーズなどは残酷である。人体が切り刻まれてタイルの上に散乱している。そしてクトー作品の人や物が舞台らしきところに登場しているのに対して、河原温の作品に登場する物たちは、すでにふれたように徹底的に閉ざれ部屋…コンクリートやタイルの壁に囲われた地下室のような空間だ。ここでまたふとビュッフェが浮かんできた。ビュッフェの硬直した人物たちは密室に閉じ込められているわけではないが、やはり現実から極度の圧迫をうけているのが感じられる。両者とも制作の動機に〈現実〉という外側からの力が大きく作用していることはあきらかだ。しかし表現されている様相はまるでちがう。ビュッフェの作品では人体の形や表情が特徴的であるが、河原温の「物置小屋の出来事」に描かれているのは徹底的に物体である。その物体たちの得体のしれないドラマだ。もちろんその物体たちは、物体化された人間のようではある。現実という圧倒的な力によって押しまくられ、心理的牢獄のなかで物体に変身させられたかのようでもあるが……。さらに特徴的なのは画面の〈形〉である。四角形ではなく、内部からの膨張か歪んで多角形になっている。しかし物たちは、その壁を破壊しようとして行動するのではなく、壁のなかに閉じ込められた被害者として描きだされている。一九五七年の「敵」という作品は、それを象徴的に示しているように思われる。また「不在者」では、牢獄の鉄格子のあいだから何本もの腕が外に突き出されている。
当時、脚光を浴びていた若手画家たち…池田龍雄、吉仲大造、芥川沙織、河原温の四人展(一九五七年)が銀座の村松画廊で聞かれた。わたしも見たが、たいへん見ごたえのある展覧会であった。とくに河原温の「敵」は緻密に描き込んだ油絵の大作で、今でも記憶の奥からよみがえってくる。しかし画家自身は、このあたりから油彩の一点制作に疑問を持ちはじめ、印刷絵画ということを主張し始めた。たとえば「表現と機能」と題して「サトウ画廊月報」(一九五八年四月)に書いてる。「最初の動機は、できるだけ多くの人たちに見てもらうためには、一点一点のタブローではとても駄目だという作家としてののっぴきならない実感から始まった」つまり「展覧会は見本市にすぎないと思った。それは実験を発表する場所としてしか今日意味をもたない。今までの展覧会形式を否定して、新しい場所で直接大衆に接したいというのがねらいだった」といい、しかし「実際に製作してみて、これがいわゆる頭の中での理屈、観念の産物でないことが身にしみて分かってきたのである」といって、これは一点制作との「素材の相違や技術的な違い」だけではなく「絵画にとってもっとも本質的な変革ないし絵画の表現の根本的なものにふれるものではないかと感じている」といっている。そして以後、表現の「本質的な変革」を目指して印刷絵画にとりくんで発表していた。わたしもそれを見たことがあるが、意欲のわりに実作は見応えのないものであった。その後どのような事情があったのかは知らないが、まもなく河原温はアメリカにいったということは聞いていた。やがてわたしたちが知った彼の作品は、すでに大画面に日付だけを大きく克明に描いたキャンバスのカレンダーであった。海外では高く評価されていると聞くが、かつては彼自身も自戒していた、きわめて「観念的」な作品であり、わたしの関心はさめてしまった。 彼の想像力が生き生きとくりひろげられたのは、やはり、閉ざされた空間内のドラマであったようにわたしには思える。「浴室」「物置小屋の出来事」「不在者」「敵」など一連の作品は、すべてコンクリートやタイルの厚い壁に囲われた密室内のドラマである。「敵」では、その壁…レンガの壁がますます狭まって、さらに奇怪な圧搾機のようなもので〈わたし〉は潰されている。
ふり返ってみると、当時の画家たちにとって、物質とか現実というものが作品創造のうえで大きな問題であったようである。たとえば「美術批評」(一九五五年一月号)の「新しい人間像を求めて」という(当時の新進画家、浜田知明、河原温、山中春雄、池田龍雄、木内岬、吉仲大造、司会・針生一郎)座談会を読むとそのことを感じる。たとえば「針生・河原さんは新しい人間を考えるのに物質との関係はかなり問題になると思いますが……」「河原・今さかんに人聞が物質化されるとか、人間に対する物質の脅威についていわれているわけですが、瀬木君がいうように、二十世紀の絵画の方法論の根底にはたしかにオブジェの意識が流れていたことは事実だと思うのです。僕自身の問題としては、物質あるいは非合理というものを意識的にやっていくのではなく、とらえていくのではなくて、僕の創作面としては無意識的なものが強いわけです。ただ生活の中では、そういう物質の脅威あるいはいろいろな不安というものは、たしかにあらゆる瞬間に感ずるわけで、それが絵画的な生活だけでなく、われわれが生きている現実を構成している政治とか、経済的不安といったものが個人的な生活を乗越え、浸透している。物質は単なる物としての物じゃなくて、抽象的な物としてとらえていかなければならないんじゃないかという気がするんです」。具体的な物質としてではなく、もっと総合されたものとしてわれわれに作用している抽象的な物質としてとらえなければならないといっている。また池田龍雄は「物質という言葉が出ていますが、僕は物質から見放されているという感じは何かと思うと、やはり物を支配しようという支配欲みたいな物があるんです。それがいつも何かに妨げられる。(中略)そういう物との関係が妨げられていると考えるんですが、その場合、そこで絵を描くということが一つの手掛かりになるし、同時に抵抗感を踏んまえて、もっと接近しようという意欲が働くと思うんです。」という。吉仲太造は「つまり作家の作品をみていると、社会意識が非常にある。意識に対する認識の仕方も明快になってきているが、まず手前にある画面に対する抵抗がそれを切り開いてゆくというふうな操作が全然ないのですね。やはりあるモチーフを見つけると、それを画面にのせるという感じで画面を切って、組み立てていくという操作がない。絵として非常に弱いという面の欠陥も起きつつあるわけですね。そういうことは絵描きとして最初にやるべき操作じゃないかと思うんですよ。」と、社会意識はあるが作品における造形性の欠如を指摘している。まだ現在のように絵画の解体現象はなく、画家たちには絵画の創造ということへの熱気と意欲が感じられる。 そして画家のオリジナリティーの問題へと入っていく。「山中・いろいろ読んできたものから考えると、オリジナリティーというものは様式のうえにあるんで、極端に言ってみますと、表現のうえで、なにか自分の絵にまったくオリジナリティーがないという絶望感があるのですね」。「河原・明治以来の日本の輸入絵画ですか、そういったものを無批判に取り入れたのは、個人的な主体というものの確立していないところからきているのだと思いますね。だからそういう流行も、そういう受け入れ方をわれわれが破っていかなければならない。新しいものができれば、すぐにまねする。ビュッフェができればまたそれをまねする。それでは個性的にはならない」…山中春雄の絵はビュッフェの絵に似ている。山中は弁明する…「僕の絵はビュッフェだといわれるのだけれど、ビュッフェが意識している世界というものは、やはり共感がわれわれのほうにも同じようにありますね。そういったところにビュッフェ自体のオリジナリティーがある。そのことについていろいろ議論したいのですが、この場合の原理は、社会の把握の仕方がフランスの絵画のそれであって、日本でもそういった方法を考えてきているのではないかと思うのですが、ビュッフェがオリジナルなのか、世界的にいわゆる歴史の流れのなかで、おなじような形を把握してきたのが、そういう形ででてきたのか。たとえばこれは日本の新しい具象といわれる人が、むこうのものを真似したのではなく、思想的な流れとしてそういう風になってきたということを考えさせるのですね」。さらに「たとえばビュッフェの持っているああいうテーマ、ああいったものは特定のヨーロッパ人であるとか、東洋人であるとかいうことを飛びこえているのではないでしょうか。ひとつの人間自体の仕事が、現在に追いつめられた人間に対す眼、社会に対する眼になってああいったふうになったということは、たんにヨーロッパ的ではなく、世界的なものではないかと思うのです。」……当時は今では考えられないほどビュッフェの出現は衝撃的であった。そして模倣者も多かった。
山中は、ビュッフェが意識している世界はわれわれにも共感がある。社会の把握の仕方はヨーロッパ的であるが、日本でもそういった考え方になってきているのではないか。そういう感じ方は一種の歴史的な流れで、とくに西洋的でも日本的でもないのではいか。だから日本の新しい具象といわれる人たちがむこうのものを真似をしたのではなく、思想的にそういうふうになってきたので、それは特にヨーロッパ人とか東洋人とかいうことではなく東西共通の現象ではないか、というとをいっている。 一見これはなるほどと思わせるところもあるが、まぎらわしいところだ。ここでは共感することと模倣が一体になり、さらにそれが正当化されているような感がある。この論理でいくと、模倣はとくにこだわりのないものとなる。先にあげた河原温のいう明治以後の「日本の輸入絵画」の範疇に入ってしまう。創造をまえにした画家としては、少し短絡的のように見えるのだが……。
一九五五年六月号「美術批評」目次のページには石井茂雄の「無人地帯」(養清堂個展)という作品が載っている。この作品を見たとき、わたしは河原温を連想した。今では記憶が定かではないが、わたしもこの個展を見ていたような気がする。そして画家の誠実な仕事に心ひかれような記憶がある。そしてそのとき、河原温の影響を感じたのであった。しかし、石井茂雄のばあい、あからさまな影響ではなく……というのは当時河原温の影響は大きかったので……彼独自の世界もはっきり感じられた。たとえば河原温の閉ざされた作品にはある種の非情さや潔癖さがある。そして何よりも画面に…眼には見えないが求心的な力がはたらいている。石井茂雄の作品には求心的な力はあまり感じられない。それよりも、どちらかといえば全体が均等化されているように見える。「無人地帯」も、一見、鉄管群による無機的世界のように見えるのであるが、よく見るとその鉄管群はどこかあたたかく、あえていえば生き物的にさえ見えるのだ。そしてここには、精神を一点に集約させようとする極点のようなものは見あたらない。「無人地帯」とはいうが、そして人らしきものはどこにも見当たらないが、しかし、かたち自体にどこか人の体温のようなものを感じさせ…ようするにもっとあたたかい世界のよに見えるのだ。
わたしは、自分ではまったく意識していなかったのであるが、このたび河原温の「物置小屋の出来事」や石井義雄の「無人地帯」を見たあとで、なんとなくわたし自身の「建築的なもの」を見ていて意外なことに気がついた。というのは、この三者の作品に、形態感覚や空間構造にどこか共通するものがあるように見えてきたからである。それはあたも連続した一連の流れのなかで制作されたかのようにさえ感じられたのだ。河原温の「物置小屋の出来事」と石井義雄の「無人地帯」は一九五五年の作で、わたしの「建築的なもの」シリーズは一九七〇年代に描かれている。わたしが彼らの作品に関心をもって見たのは二十年も前である。時代背景や美術界の状況もすでにまったく変っている。さらに、わたしがこれを描いた当時の心境は、そのような美術界の状況などもすべて排除して、自分の内なる混沌のなかから手探りで何かの形を掴み出し、また空間を切り開こうとして制作したのであった。にもかかわらず、今あらためて「建築的なもの」を見ると、さらに河原温の「物置小屋の出来事」や石井義雄の「無人世界」を並べて眺めて見ると、もちろんそれぞれの絵画世界は異なるが、形態感覚や空間構造において、まるで連続した一つの流れの延長線上にあるように見えるのが不思議である。すでにふれたが「建築的なもの」を描いたのは一九七〇年代である。その間に二十年の歳月がながれている。にもかかわらず、わたしの無意識の層には、彼らの作品が根強く生き残っていたのだろうか。
|
|||||||
「負けること勝つこと(80)」 浅田 和幸 |
|||||||
「近代化の潮流への取り組み方」 深瀬 久敬 |
|||||||
【編集あとがき】 |
|||||||
| - もどる - | |||||||


編集発行:人間地球社会倶楽部