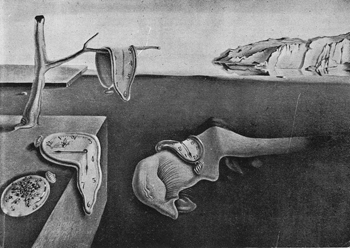第125号 |
|||||
| 2015年1月4日 | |||||
「問われている絵画(116)-絵画への接近36-」 薗部 雄作 |
|||||
「現代詩入門」(一九五五年十月・創刊号)の巻頭論文に安藤一郎の「現代文学における詩の位置」という文章がある。そのなかで「今日、詩はどこの国でも(イギリス、フランス、アメリカ、日本)でも、商業主義のジャーナリズムが栄える一般の社会で、大抵無視にちかい取り扱いを受けている」と書いている。詩の現在(二〇一四年)がどのようになっているのかわたしは詳しく知らないが、しかし今から眺めると、当時はまだ、この雑誌そのものが普通の書店の店頭にちゃんと並んでいたし、その他にも「詩学」や「新詩人」という詩の雑誌が堂々? と並んでいた。わたしの手元にも、さきの「現代詩入門」や「詩学」(一九五五年八月号)そして「新詩人」(一九五五年十二月号)や「ユリイカ」(一九五七年七月号)がある。当時は関心があって買ったのであったが、けれども、なぜかみな一冊づつしかない。あまり熱心に読まなかったのだと思う。というのは、この論文もこのたび初めてしっかり読んだような気がする。この号には「村野四郎訪問記」があり、それが読みたかったのかもしれない。当時わたしの数少ない本のなかに村野四郎の『抽象の城』という詩集があったので……。続いて安藤一郎は「詩は永い将来のうちには滅びるかも知れない」が、それはどうでもいいとし、「少なくとも、詩に過去におけるような栄光が立ち戻ることは、殆ど望まれないということは確かである」という。しかしヨーロッパにおいては「昔からの古い伝統が、文化と教養のなかに深く根を下ろしている」ので。「たとえ世の中で詩が表面的に持てはやされなくても、やはり詩の価値を理解し、それが尊重されるべきだということは、彼らの間ではみとめられていて」それが「自然に他の文芸の部分にもつながる確固とした〈審美眼〉として、どの時代にも生きているとおもわれる」といっている。 けれども、それに比べると「日本の詩は非常に異なった状態にあると知らなければならない。」なぜなら「われわれが現代詩と呼ぶものは、新体詩の発生から考えても、まだ七十年余りを経ているに過ぎない。ところがここ二十年間に、驚くべき飛躍的な変化を遂げてしまった。」そして「新体詩から象徴主義辺りまでは、まだ過去の万葉の長歌、和歌、漢詩、俳諧詩といった過去の日本文学にどこか関係を見出し得るような情緒とそういう情緒をおのずから含むとおもわれる詩語と形式が部分的にももちいられていたのだ。」しかし「シュールレアリスムや新しい詩の運動以後、そういう要素は極力排除されて、日本文学の伝統から全く隔絶するに至ったのである」と。
これは当時の美術…絵画にもそっくり当てはまるように思える。一時的とはいえ、そのような伝統不在…排除の状況のなかから、前回ふれた河原温の仕事なども生まれたのであろう。だから滝口修造もいっていた。「すべてが焼野原であったとき」には現実の都市が消失しただけではなく、自国の伝統的なものも極力排除されたのであった。たとえば敗戦直後に書かれた坂口安吾の「堕落論」などにも、そのような状況感がひしひしと感じられる。「半年のうちに世相は変わった。若者達は花と散ったが、同じ彼らが生き残って闇屋になった」。のしかかっていた重いものがとり払われたかのように、すがすかしく格調高い章で堕落…生が歌い上げられている。もっとも安吾は敗戦以前から、すでにすべてが払り落とされていたようなところがある。戦争たけなわの昭和十七年、国粋のさなかにも「日本文化私観」に書いている。「僕は日本の古代文化についてほとんど知識を持っていない。ブルーノ・タウトが絶賛する桂離宮も見たことがなく、玉泉も大雅堂も竹田も鉄斎も知らないのである」そして「めったに旅行することもないので、祖国のあの町この村も、風俗も、山河も知らないのだ。」いわんや「茶の湯の方式などは全然知らない代わりには、妄り狼(みだ)りに酔い痴れることをのみ知り、孤独の家居にいて、床の間などというものに一顧を与えたこともない」。わたしは思い出す。小学五年のとき(昭和二十年八月十五日)に突然戦争が終わったときのことを。するとすべてがガラリと変わったのだ。頻発した空襲警報のサイレンもピタリと止まった。そしてとりわけ記憶に焼きついてるのは、今まで使っていた教科書のなかの歴史や戦争に関するすべての箇所…行を、太い墨の線で塗りつぶす作業をさせられたことであった。あるいは朝礼のとき御製(天皇のつくった詩歌)を吟じていた先生が、急に英単語の奇妙な発音を大きな声で教えはじめたりしたのが。
戦争の終わった八月十五日、まだ何も知らないわたしたちは、玉音放送があるというので朝から待ちかまえていた。天皇陛下の神聖さは今では想像もできないほどで、その姿はおろか声さえも聞いたことがなかった。うやうやしい写真だけが部屋に飾られていた。その天皇陛下のお話がラジオで放送されるというのだ。いったい何の話があるのだろう、と子供心にも関心があった。その日は真夏の抜けるような快晴で、わたしも近所の人たちと一緒に炎天下の庭でラジオの前に集まって待っていた。たしか正午ごろであったと思う。しかし不思議なことに暑かったいう覚えが全くない。やがておもむろに放送が始まった。しかしわたしには何が語られているのかほとんどわからなかった。わかったのは最初の「朕」(ちん)という言葉だけであった。というのも当時は小学生でも「勅語」を暗記させられていた。その勅語の冒頭が「朕思うに」という言葉で始まっている。そして「朕」とは天皇陛下自身のことであると教わっていた。放送が終わったとき、誰かが「戦争が終わった」といった。それからが世の中の価値の大転換であった。
九月になって新学期が始まり、雨上がりの晴れた朝(なぜか記憶のなかではそうなっている)わたしは学校に行った。校門を入るとすぐ左側に鎖で囲われた芝生があり、その中には奉安殿という小さなお城のような美しい建物があった。それはたいへん神聖な建物で天皇陛下が奉られているという。鎖で囲まれた芝生の中へは誰も入ることは許されず、その前を通るときには最敬礼をさせられていた。ところがそのときには、すでに鎖は取り払われれていて、誰でも芝生の中へ入れるようになっていた。わたしも友人とともに芝生に入り、かつては禁制だった奉安殿に近づき、そして見たこともない裏側へも回って見た。すると扉は打ち壊されていて、内部がむきだしになっていた。しかし中には何もなく、すでに荒らされた後のような乱雑さで、埃にまみれていた。 そんな価値の大転換ではあったが、小学生のわたしはとくに精神的なショックを受けたという記憶はない。まだ十歳そこそこで何もわからなかった、ということもあるかもしれない。しかし、今までの威圧的な重くるしい空気が消えて、とても開放感があったのを覚えてる。
美術においても、すべてが精算されて新たに出発するという雰囲気があった。岡本太郎の『今日の芸術』(一九五四)なども、敗戦直後よりやや落ち着いたとはいえ、そのような状況のなかで出現した。そのなかで岡本太郎は宣言した。「今日の芸術はうまくあってはならない。」わたしたちは「こびりついた…知識や伝統など…の垢におおわれて自分を見失っているだけだ。」それを払い落とせば「誰でも本来は天才なのだ」と。美術評論家の東野芳明も、シュールレアリスム先駆者ロートレアモンの『マルドロールの歌』(栗田勇訳)の書評で「たんに翻訳という作業を超えて、この異端の精神の根が、戦後世代の中に、明確に芽生えてきたことの証拠ではなかろうか」そして「正当な伝統の抵抗もないところに、何の異端がありうるものか、といいたげなペシミストの渋面におかまいなく、否応なく手ぶらで出発させられた戦後世代のぼくらは」(「ユリイカ」一九五七年七月号)と書いている。たしかにそんな状況のなかで、シュールレアリスムや現代美術の思想は、わたしたちの心理にきわめて鮮烈であった。つまり一時的とはいえ伝統不在の美術思潮のなかで、ピカソやダリやエルンストやキリコなどがわたしたちの眼を直撃した。当時、岩波の写真文庫78『近代芸術』という、岡本太郎監修のうすっぺらい本があり、それをわたしは繰り返し眺めたものだ。とりわけ印象が強かったのは、ダリの「記憶の固執」やマン・レイの「天文台の時間…恋人たち」という作品であった。池田満寿夫も何かのインタビューで「西洋の遠近法や明暗法色彩処理も学校教育のなかで果たせられてきて、フォービスムやキュビスム、ダダやシュール・レアリスムに至まで、それらの芸術や芸術観念は同時代という、疑いもない思想によって私たちのものだったのだ」といっている。 新たに出現した一群の批評家たち(針生一郎、東野芳明、中原祐介など)も、旧来の画壇の在り方…団体展などに頼らずに個展を主体にして発表することを、画家の在り方として推奨していた。そんな状況のなかでわたしの二十代は過ぎたので、その思潮をまともに受けてしまった。そしてそのような生き方が、わたしにも、もっとも自分に忠実な道のように思えたのであった。それに後悔はないが、しかし、今から振り返ってみると、その流れも一種の表面的な現象で、やはり事態はたいして変わったわけではなかった。いや、変ったといえば変ったようにも見える。たしかにそれを実行した画家も多く個展も活発化していった……。しかしまた美術界の構造が基本的にとくに変わったようにも見えない。
安藤一郎は、「われわれが今日〈現代詩〉と呼ぶものは、このようにして現代性を獲得した」のであるが、「それゆえに、孤立し、また混乱を招き、詩人各自が、常に未生の領域をさまよう運命を背負わざるを得なくなった」。そして現在「詩はどのような形式、どのような表現方法をとっても、別にかまわない。そこで、批評の基準は明らかでないし、また作品の傾向も種々まちまちである。むしろアナキスティックな混沌を示している。」そして「現代詩は依然として〈進行中〉である。いや、日本の現代文学の一部として、まだ始まったばかりである。」と結んでいる。
その後、またたくまに六十年が経過した。では二〇一四年の現在、詩や美術が社会のなかにおかれている状況はどうなっただろう。美術の場合にかぎっていえば、その方向性はとくに変わったようには見えない。ただ安藤一郎が指摘した当時の状況より、さらに過激でアナキスティックな混沌のなかにあるように見える。いや、アナキスティックという言葉そのものさえ、今ではほとんど聞かなくなった。変わってグローバルという言葉があちこちから聞こえてくる。そして批評の基準はますます明らかではなくなった。それより美術に関しては批評すら、はたして存在しているのだろうか、とさえ見える。六十年前にもすでに「商業主義ジャーナリズムの栄える一般社会で、大抵無視にちかい取り扱いを受けている」といわれたが、今は、むしろ商業主義に取り込まれてしまったようにさえ見える。つまり「批評の基準が明らかでない」だけではなく、むしろ商業主義的な価値の基準が価値観として公然化しているような感さえある。つまり批評不在のなかにおいては、はっきりと目に見える形で存在する商業主義的な価値の優劣が、人々にも強い説得力を持ってきたのだ。しかしまた、その商業的価値の優劣が、必ずしもすべて芸術的な価値の優劣から外れているというわけでもないので、さらに混迷は深くなっている。
|
|||||
「負けること勝つこと(81)」 浅田 和幸 |
|||||
「ポスト近代社会と個の問題」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部