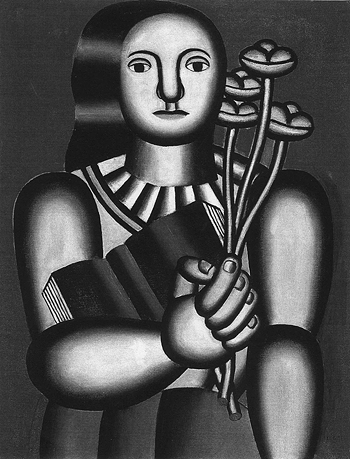第126号 |
|||||
| 2015年3月18日 | |||||
「問われている絵画(117)-絵画への接近37-」 薗部 雄作 |
|||||
たしかに現在、美術においては批評というものをあまり見かけなくなった。たとえば文学では現在でもいくつかの雑誌があり、当然そこには批評作品もあるが、美術には批評の登場する舞台すら見当たらない。新聞にも文芸時評はあるが、美術の時評のようなものは見当たらない。有名作品の紹介や解説のようなものはある。しかしそれはいわゆる批評とは少しちがう。あるいは、そもそも美術というのは感性や好みに属するところが多く、批評ということには適していないということであろうか。しかし一九五〇年代には一時的とはいえ「美術批評」というタイトルの雑誌さえあった。他にも数種の美術雑誌もあり、批評家や学者や画家の文章もよく見かけた。読者もまたそのようなものに関心をもつ人が今より多かったのだと思う。たとえば「美術批評」には「ラウンド・テーブル」という読者の投稿欄があって、そこにはさまざまな意見が寄せられている。それぞれ職業と年齢が記されているので興味深い。一九五五年六月号(前々回の石井義雄「無人地帯」が目次ぺージにある号)を見ると、「太陽を見るにはどうすべきか」(大阪・泉茂・画家・33才)、「何故日本画の批判がないのか?」(鎌倉・三山進・地方公務員・25才)、「日本画に魅力はないか?」 (埼玉・鎌田広一・学生・19才)、「レジェについて若い批評家にご一言」(神戸・船井裕・画家・22才)、「批評・評論の文章について」(東京・馳腱正使・学生・21才)、「難解ということ」(東京・立原晃・会社員・30才)、「新しい美術批評に就いて不在する大衆)(東京・本間吉信・勤人・25才)などがある。
「太陽を見るにはどうすべきか」の筆者は当時中堅の画家でヽわたしも名前や作品を知っていた。彼はここで若い一群の批評家たち……徳大寺公英、針生一郎、瀬木慎一、東野芳明など……のレジェに対する評価が低いのに異議をとなえている。そしてレジェを太陽にたとえ「太陽を直視すれば目が眩むが、彼らはそのような状態になっているのではないか」といっている。当時、レジェをきわめて高く評価する彼を含む一群の画家たちがいたが…画家だけではなく、レジェに対する関心や評価は現在に比べればはるかに高かったように思う。モダンアート…抽象化されてはいるか機械や働く健康的な人間を描く彼の作品が時代風潮にもマッチしていたのかもしれない。というのも、当時は社会主義的なリアリズムという傾向…考え方が美術界のなかでもかなり力を持っていた。レジェを太陽にたとえるのには少し違和感もあるが、あのふっきれたような壮快感が太陽を思わせたのかもしれない。その太陽を若手批評家がそろって軽くあしらうのが意に沿わず、あなたはどう思うか、と読者に問うている。
「何故日本画の批判がないのか」ここでは、当時開かれた日本画家の前田青邨展の作品について、古典と直結しながら見事に近代化していることにふれながら、この展覧会についていわゆる若手批評家…たぶん前記の美術評論家たち…が全くふれていないことに疑問を提示し、彼らは日本画と洋画をわけているようで、油絵の世界でも伝統と現代をもっと考察しないのは怠慢ではないか、新人評論家の出現と活躍はよろこぶべきことにはちがいないが、「まだ足下におおくの問題を残しながら余りにも何かに溺れ込んでいはしないか」と書いている。たしかに当時は、一群の若手批評家たちだけではなく滝口修造のような大御所でも、日本の伝統的な絵画と日本の現代美術との関係、あるいはそこに連続があるのかないのか、などということについては深く考察するということがなかったようにみえる。それより、やはり西洋美術の延長線上で、あるいはそれとの連続観からの批評が主であったように見える。
「日本画に魅力はないのか」では、洋画の展覧会には隅から隅までかかさず見る人でも、日本画の展覧会はほとんど見ないという人が多い、先年のマチス展の会場は混雑していたが、すぐ隣の宗達・光淋展の会場は閑散としていた。マチスやピカソに比べて宗達や光淋はまったくつまらないのでしょうか、いまの若い人がどんな意見を持っているのか知りたいです、と書いている。ここでも、先の投稿者と同様に伝統と現代に関する疑問を提出している。
「レジェについて若い批評家に一言」も若い批評家たちのレジェ評価に異議をとなえている。この号でレジェと若手批評家たちがしばしば登場するのは、前月? にコルビジェ、レジェ、ペリアン・三人展があり、ある座談会で若手批評家たちがその展覧会にふれながら、レジェを小市民的でオプチミズムであるといって簡単にかたずけているのを問題にしている。そして、彼ら…若手批評たちが意識的にレジェの問題を避けているのではないかと思いたくなるといっている。これも画家の意見であるところを見ると、やはり批評家よりも画家の方がレジェに関心が高かったようだ。観念や心理の微妙な調子もなく、単純明快な造形システムが、かえって画家の感覚をとらえたのであろうか。あきらかにレジェの影響を感じさせる画家たちもいた。
「批評・評論の文章について」ここでは新しく登場した一群の若手批評家たちの活躍を歓迎しながらも、彼らの文章が観念過剰で難解であり、一般大衆から遊離しているのではないかということを危惧し、これでは「自ら墓穴を掘る」ことになるのではないか、ということを書いている。
「難解ということ」。読書新聞の「今日の美術ジャーナリズム」という記事に「アブストラクトやオブジェの流行は、誰もが解ったふりをする文化人の虚をついて発展したものが少なくなかった」と書いてあることについて「モダンアートは一時の流行でも、外国礼讃でもなく、今日の建築、彫刻、絵画、デザインなど世界的傾向であり、それに雑誌が力を入れるのは当然である。そして当誌「美術批評」が叱られているようだが、この雑誌が若い批評家に舞台を提供して若い作家を取り上げて美術界を活性化しているのは歓迎す る。難解なレトリックがすべてよいわけではないが「抒情を拒絶した、無機的な思考が近代芸術一般のもつ論理である以上、新しい文体による新しい表現の試みを、私たちは新しい世代に積極的に注文しているわけです」といっている。
「新しい美術批評…不在する大衆」 募集美術評論に入選した中原祐介の「創造のための批評」について、「新しい眼を発見し、豊かな眼へ変革し、作家の現実認識を深めることでる」という、この結論へ達するまでの文章が、完全に大衆から離れたところで論じられている。批評と大衆の間に断層を作ることは、批評の説得力を失う。
こうして見てくると、美術界や批評の在り方などについて、はばひろい多くの読者の関心があったように見える。とくに若い一群の批評家の登場に対する期待と批判が多い。やはり彼らによって活性化されつつある美術界が注目されていたということであろう。 そしてもう一つは、社会…大衆と美術ということが問題にされていたということである。当時は、今では考えられないくらい左翼思想…マルキシズムが美術のなかにもかなり色濃く入り込んでいた。そしてその種のいわゆる社会主義的なリアリズム絵画も多かった。レジェの作品は様式化された明快なモダンアートでありながらも、そこに人間や労働に対する賛歌が歌われているところが、時代の流れにもスムースにマッチし、さらに刺激的であったのかもしれない。
ちなみに、この号(「美術批評」一九五五年六月号)の目次は次のようになっている。 ラウンドーテーブル 奇妙な幕間狂言 針生一郎 オイディプス ─アラゴンのピカソ論をめぐって─ 宇佐美英治 ヨーロッパの話題 内部の問題 ─二十世紀美術の方法─ 瀬木慎一 ■アンケート■ 第三回国際展に出品して 25出品作家 第二回募集美術評論入選作 「美術批評の問題」 金子昭二 展覧会評 記録 |
|||||
「負けること勝つこと(82)」 浅田 和幸 |
|||||
「生命と反生命について」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部