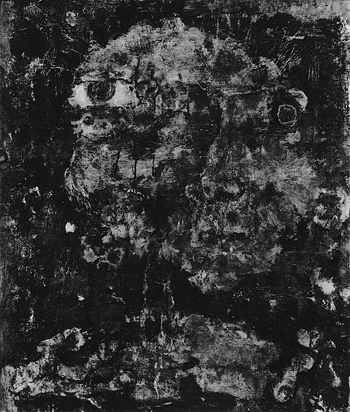第127号 |
|||||
| 2015年6月17日 | |||||
「問われている絵画(118)-絵画への接近38-」 薗部 雄作 |
|||||
数年後の「美術手帖」(一九五八年一月号)には「芸術とヒューマニズム」という座談会(加藤周一、吉田秀和、針生一郎)が掲載されている。サブタイトルに「現代美術への苦言をめぐって」とあるが、苦言とは当時流行していた抽象絵画に対して文学者の側からいくつか批判があり、そのことをめぐって座談会の話が始まっている。批判というのは、文芸評論家・臼井吉見の「抽象絵画への疑問」(読売新聞)と小説家・平林たい子の「抽象絵画」(読売新聞)である。文学者の側からこのような意見が出たのは珍しいことであるような気がする。といっても時々はあるもので、やはり文芸評論家で翻訳家でもある高橋義孝も「美術批評家の宿命的なぶざま」という文章を書いており、そのなかで「美術批評というのは結局、美術というものの解説、あるいは付随的な役割しか持たないのではないか。美術の作品が観光地であれば美術批評は観光案内のようなものであって、独立した精神活動の領域を持っていない」といい「しかしこれは美術だけではなくて、文学批評でも文学作品から独立した力を持ちえないのであって、ただ文学の場合はどちらも素材が言葉であるから、そのギャップがあらわに見えない」のではないか、と。
臼井吉見は「抽象絵画への疑問」のなかで「新制作展を見たら抽象絵画が圧倒的に多く、そして、これが画題からみても〔骸骨とアコーデオン〕というふうな月並俳句的な発想をでていない。外部の現実をそのまま描くことに満足できないほど、内部のあふれでる充溢がなければならないのに、そういう必然性が個々の作品にちっとも感じられない」といい、平林たい子も「抽象絵画」という随想で「アジア青年美術家展を見たら、とくに日本の作品に抽象絵画が多いけれど、文学と並んで現実感を訴える強さを持っている絵画が、音楽の域に堕していいのか」といっているという。「音楽の域に堕している」というのはオヤっと思い、この人の美や感動にたいする意識構造はどうなっているのだろうと思ってしまうが、いずれにしても、二人とも抽象絵画の流行が異様に見え気になって書いたようである。たしかに美術家以外の人がそう思うのもあるいは一理あると思う。というのも、その頃の抽象絵画の流行には異様な勢いがあったからである。たとえば国際展…海外や日本の名だたる現役画家たちをあつめた新聞社主催の展覧会…などでも圧倒的に抽象絵画が多かった。具象的な作品もあるにはあったが、多勢に無勢という感じでどこか肩身が狭そうに見えた。しかしそれは服飾などの流行とおなじで、時の流行のさなかに流行おくれがあると、貧弱とはいわなくても、どこかやぼったい感じに見えるのとおなじだと思う。芸術のばあいも、わたしたちの目が流行に染まってしまうのだ。もっとも、今ではすべてが多様化したせいか際だった流行も見えないが、当時は海外からの新しい波がたいへん新鮮に見えたものだった。
しかしそんな抽象絵画流行のさなかにも具象絵画を貫いていた画家たちもいた。強い信念がなければできないことであろう。というのも流行のさなかには具象から抽象に転向した画家も多かったからである。なかにはすでに具象で名なしていた画家のなかにも抽象に転向した人も目についた。そして抽象に転向したものの、やがて流行のピークが過ぎると、またもとの具象にもどったという画家たちもいた。そんな状況のなかでまったく動じることなく…というふうに見える…岡鹿之助や麻生三郎などの姿勢が印象に残る。わたしは具象・抽象にかかわらず、さらに古今東西にかかわらず、自分の突き当たった問題をひたすら追求している画家に引かれる。それはたぶん自分も…問題の違いやその大小にかかわらず、自分の突き当たっている問題に対して、やはりひたすら突き進んでゆきたいという思いがあるからかもしれない。だからわたしとはまったく異なる傾向の岡鹿之助や麻生三郎のような画家にも注目させられる。そこから自分にも有益ないろいろなことが学べるし、そして何よりも勇気づけられるからである。岡鹿之助については今までにもふれているので、ここでは麻生三郎に目を向けてみたい。
麻生三郎の作品をはじめて見たのはたぶん原画ではなく「美術手帖」に掲載されていた自由美術展評の写真だったと思う。それは何か苦悩しているような人間が描かれいるドラマチックな作品であった。そんなふうに見えたのは、たぶん執拗に描き込まれている暗い画面からきたのかもしれないが、しかしそれに対して評者が高く評価していたのも目を引いた。しかしはじめて見た実際の作品は、たしか「赤い空」という作品であった。いま画集を見ると、それは何点かある「赤い空」シリーズのなかの一点で、あばら屋のような建物の右端に人が立っている作品だが、人物はたよりない端役のようで主役はあばら屋の方にあるようだ。しかしそのあばら屋はなぜか解体しかかっている。というより当時はそんな壊れかかった小屋のような住宅は珍しいものではなく、戦後まもない頃にはよく見かけた風景であった。しかしそういうことだけではなく、麻生三郎のほとんど作品にもこの解体的な様相はうかがえる、といってもよいのではないだろうか。解体的というのは、描いている対象のかたちが、かたちとして完成するということがないのだ。たえず描いている対象…ほとんど人物であるのだが、それを打ち壊す。つまり描いたり壊したりの繰り返しによって、少しづつ作品が完成? してゆくようであるからだ。そしてその行為によって画面は少しづつ厚みと深みを増してゆくように見える。つまり麻生三郎独特のかたちや色やマチエールが現れ出てくるようなのだ。その行為は、画面のなかをあたかも一種の闘技場のようなおもむきにもする。しかし、その行為によって生まれてくる独特のかたちやマチエールが、またその背後からにじみ出てくる熱い情念のようなものが麻生三郎の魅力でもあるように見える。
しかしまた当時のわたしには、その姿勢のなかに何か焦点の絞りきれないところがあるように見えて気になるのでもあった。というのは、さきにもふれたように形成と破壊が画面のなかになまのまま同居しているからである。つまりかたちを決着したいという意思と、そのかたちを打ち壊したいという意思がむりやり合体しているようにも見えるからである。だから画面のなかのかたちは中心に集約しきれず全体にちらばって…あるいは散らばろうとしているように見えるのだ。あるいはこれは当時周囲を吹き荒れた画面を均等化しようとする抽象絵画の影響もあるのだろうか。この傾向は晩年になるにしたがっていっそう強まっているようである。そこにはまた、抽象絵画とは別の何かを確かめたい、そしてしっかり掴みたいという麻生三郎の強い意志が感じられる。しかし力がはいれば入るほど、対象は掴みきれずにはみだして画面に散らばる、というふうにも見える。そういえば彼もある文章で書いている。「わたしが確かめたものをしっかり掴むことだ。そのために何回でも繰り返し繰り返しそれがあるものであるかどうか、そしてつめたい客観的なものであるかをあつい熱で確かめる。そのあつい熱をまたつめたくみる。そうでないと確かなものは掴めない。」と。(「みずゑ」一九七六)
内側のくらやみで格闘しているような、そして赤や暗褐色のどろどろした独特の画面のせいであろうか。このような絵を描く人は、たぶん地方から出て来て都会のきびしい生活をしいられた苦悩の人ではないかと、わたしは早合点していたが、履歴を見ると「京橋に生まれる」とあるので意外な気がした。しかし「屋号を山惣という炭問屋」であったとあるので、炭というものと麻生三郎の絵の雰囲気にどこか共通するものを感じるような気もしてなっとくする。またあの暗いどろどろした画面は、戦後まもない世相の反映もあるのかもしれない。わたしは麻生三郎に会ったことも遠くから見たこともないので、どのような人かは知らないが、比較的世代の近い野見山暁治は、一九五十年代の麻生三郎を次のように書いている。自由美術の会合のあと、酔って荒れ狂った麻生三郎を家まで送ってゆくことがしばしはあったということであるが、「麻生三郎は屋台で、そばのかけを注文すると、お椀の中味をオーバーのポケットに全部あけて、電車に乗ってから、手づかみで取り出して私に食わしてくれた。ポケットのなかでおつゆはしたたれ落ち、そばやカマボコの切れはしや、ともかく色んなものを取り出してくれる友情に私は酔った」と。これを読んで、わたしはなるほどと思った。というのも彼の作品から受ける感じにも、そのような行為をスムースに結びつける何かがあるような気もするからである。
「麻生三郎画集」(南天子画廊)には、画家も写っているアトリエの写真が掲載されている。それを見て、わたしはフランシス・ベイコンのアトリエを思い出した。双方とも強く印象づけられるのは汚れた壁やいたるところに積み上げられた絵の具の山である。そしてそこに座っている画家の悄然? 荒涼? とした姿である。しかし両者を比べて見ると、画家の格闘…制作の臨場感、あるいは画家の呪われ度などの迫力はベイコンの方がまさる。閉ざされたようなアトリエ内の画家その人の印象がそれを増幅させる。画家の存在感にどこか異常の域に入り込んでいるような雰囲気を感じる。それに比べると麻生三郎のアトリエは、汚れた壁や積み上げられた絵の具の山は共通するが、しかし広々としたアトリエは意外に整然としている。あるいは写真撮影のために整理したのかもしれない。しかし画家もふくめて、ペイコンよりはどことなく通常の生活人の面影を感じさせる。通常の生活人がよくないというのではないが、作品の異様性を思うとどこかものたらない感じもする。しかし双方の作品をあらためて見直すと、アトリエだけではなく作品にもどこか共通するところがあるような気がする。たぶん対象に対する画家の姿勢であろう。両者とも攻撃的である。しかし表現された双方の画面は大きく異なる。ペイコンの画面では、攻撃され変形された対象は、そのまま放置…あるいは存在させられているが、麻生三郎の画面では、対象は解体され断片化されて平面にならされている。立体的な対象を平面にならそうとするのは、あるいはそのころ周囲を吹き荒れた平面を指向する抽象絵画の影響であろうか。しかし散乱した断片たちは、また寄り集まってもとのかたちに戻ろうとしているようでもある。そしてなによりも絵のなかで眼だけが異様にリアルである。それは解体のさなかにありながらも、なおも見つづけようとする麻生三郎の霊の眼のようなものであろうか。 |
|||||
「負けること勝つこと(83)」 浅田 和幸 |
|||||
「生命における主観と客観」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部