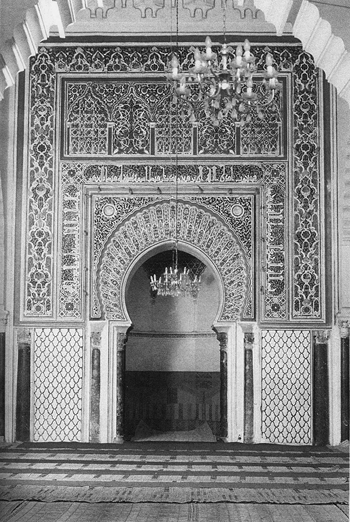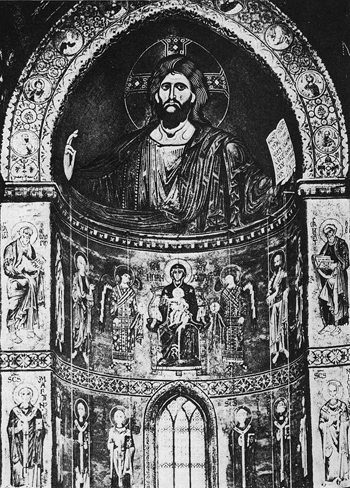第128号 |
|||||
| 2015年9月19日 | |||||
「問われている絵画(119)-絵画への接近39-」 薗部 雄作 |
|||||
しかし、二十代のわたしは具象絵画に向かわなかった。今から当時の自分を思い起こすと、たしかに抽象絵画は流行現象のような観を呈していたが、しかしそれは単なる流行現象だけではなく、そこには何か絵画そのものの可能性があるように思えたのであった。というのも具象的な絵画はすでにえんえんと存在しているし、そこではあらゆる表現が展開されている。一見すべてがやりつくされているようにさえ見える。さらにその上わたしに何かできるだろう……そんな単純なものではないのだが……しかし抽象絵画は目下開拓中で発展の途上である。まだまだ未知数だ。それだけではなく、抽象絵画には西洋とか東洋という区別も具象絵画ほどはっきりしていない、とも思えた。つまり具象絵画では対象に依存して描くので、対象のさまざまな形態が目をとらえ、それに左右されやすい。そしてまた、その対象を選ぶにも、無意識のうちにもすでに学んで頭の中にある西洋絵画の影響を受けやすい。そしてまたその描く基本的な考え方も西洋から移入された絵画思考によってなされている。たとえば何かを描くばあい、そのモチーフをえらぶにも、すでに頭のなかに入っている西洋絵画の影響をうけていることが多い……それほどかたくなになる必要もないのだが……しかしとにかく抽象絵画には東洋とか西洋とかの区別もあいまいだ。とにかく物の外観がないのだから。もちろん抽象絵画そのものも西洋からの影響ではあるし、よく見れば東西の質の違いもあるのだが……。しかしここでは対象物としての事物よりも人間の方に…その内面の方へ目が向けられているので、そして人間の内面には、あるいは人間の本質には東洋も西洋もないので……だからそこに……自分に根差して一から始めれば、たとえささやかなものでも、自分にそった何かができるのではないか、と思えたのであった。 先の座談会にもどると、文学者の抽象画批判に対して、美術批評家の側から徳大寺公英は「臼井氏の発言が画題という末梢の問題にかかずらって、造形上の問題には完全に無知を暴露」しており「新制作の抽象画にはつまらぬ作品が多かったとしても、全部がつまらなかったわけではないし、そういう点では一水会の無気力な作品の方がつまらない」と反論している。つまり臼井氏も平林氏も抽象絵画に対してはきびしく内部の充溢を求めるが、従来の具象絵画にはとくに求めていない、ということである。しかし冷静によく見れば具象絵画にもすべて内部の充溢があるわけではない。これもきびしく問われなければならない。しかるに両者はなにゆえ抽象絵画にだけにきびしいのであろう。 それにはいくつかの理由があると思う。まず具象的な絵画は美術史のなかでも王道のようにあつかわれている。つまり絵画とは何かの外観を描くものであるということが、そこにまざまざと示されているのだ。それにくらべれば抽象絵画は二十世紀に登場した新まいである。そしてなによりもこの絵画には事物の外観描写がない。だからよけいに警戒したり注意したりして見るのであろう。さらに当時はまだ抽象絵画は完全に市民権を得たともいえない。新たに出現したものにたいしては、何時の時代でも、そして何の場合でもそうであるが、期待も大きいし、また欠点も目につきやすい。現に臼井氏も抽象絵画の否定論者ではないのだ。期待がおおきいだけに、いたらなさも目につき気になりやすいということであろう。
加藤周一は、臼井氏も平林氏も抽象絵画の現状に対しては疑問を提出しているが、抽象絵画をつまらないとはいっていず、はっきりこうなるしかないといっているので、むしろ積極的な抽象絵画支持者であり、抽象絵画そのものには反対してはいない。そして「実際に見ておられる作品がつまらないにもかかわらず、抽象絵画を支持しているわけですから、よほど強い抽象絵画支持者でしょう」といっている。針生一郎は「その根底には、明治以来、あたらしい様式をつぎつぎに輸入してきた美術界への不満があるのでしょう」そしてまた「内的要求がないのにもかかわらず、抽象絵画も受け入れている」という。 吉田秀和は、臼井氏のものを読んでいて気になるのは、やはり抽象絵画も具象絵画も内部の充溢を必要としているにもかかわらず、やはり抽象絵画にだけきびしく、写生的絵画には比較的寛大なようにみえるが、これは音楽でも同じようことがいえる。たとえば「近ごろの新しい音楽というのはクラシックやロマンチックの音楽に比べれば、抽象絵画に近い点があるといえないこともないような性格をもっているが」そのような「新しい音楽たとえば十二音の音楽やミュウジック・コンクレートあるいは電子音楽などは、新しい傾向だからといって真似しているケースが少なくない。だけど新しいことをやるのだから、特別、内部の充溢した人がやるのでなければならないというのは、やや現象に囚われた議論だと思う」そして「古い形の音楽は、またみんなが聴きなれたもので、いわば気楽に接しられる。だから比較的抵抗を感じないで聴いて行くというところがあるのじゃないか。僕なんか、そういう形で創作する場合には、なおさら内部の充溢が必要だと考えています」。
そういえば、わたし自身も内部の充溢が先にあって抽象絵画を描きはじめた…あるいは描いていたのではなかった。むしろ抽象的な造形要素…線や面や色…を触手として内面にむかい、むしろ内部の充溢を探し求めながら描いていたように思う。造形的触手…絵の具や筆によって武装?しているとはいえ、内部に目を向けると、そこは充溢どころかむしろ混沌と混乱のきわみであった。しかし、その混沌や混乱がまぎれもない自分の内部であるならば、さしあたりそれに対面するしかなく、そこから直接なんらかの形を掴みだし…あるいは無理やりにでも、何かの形にこぎ着けようとして悪戦苦闘してきたような気がする。
ここで加藤周一は、むしろもっと抽象絵画の反対論者が出てもらいたい、そして「わたしは抽象絵画の反対論者ではないのだけれど……今晩だけ反対することにしましょう」といって、「まず第一に、抽象絵画というか、抽象的な美術は大昔からあり、その代表的なものは「アラビアやビザンチン」で、また「それらの影響を受けた西洋の美術、要するにキリスト教美術は、抽象的な方向ではなく、人間の姿を描くことから始まっていると思う。ところがモレスク(モーリタニア地方に発した一種の唐草模様)の世界では人間像をつくらなかった。彫刻も肖像画も発達していない。その代わりに唐草模様になって、幾何学的な形式の方へいった」といい、それで「美術一般について、美術の本領が、なにか人物なり景色なりを描くのものだという考えは間違いだと思うのです」。「まず第一に抽象的な絵画は大昔からあり、その代表的なものはアラビアでしょう。一方ビザンチン、それからまたその影響を受けた西洋の美術、ようするにキリスト教美術は、抽象的な方向でなく、人間の姿を描くことからはじまっていると思う」。そして「しかし現代の美術が、いちどキリスト教芸術の人間的なもの、さらに個性的なヒューマニズムを通ってきたあとで、もう一遍抽象的な方向を見出だそうするときには、アラビアと同じでは駄目だと思います。現代の抽象芸術はヒューマニズムを何らかの意味で含んでいなければならない」。それなら「ヒューマニズムを通り、それを含んだ上での抽象的な表現ができるかどうか、これが第一の問題である。」そして「モンドリアン」の色と形は、自然と何の関係もないけれど、もちろん何かを表現するための手段でしょう。その抽象的な手段で人間的なものを強く表現できるだろうか。」と疑問を提示し、そして「臼井さんの画家の内部の充溢という言葉は、その意味で単に一般論としてではなく、抽象芸術の場合の特殊な問題として考えられないこともないと思います」という。 (以上)
|
|||||
「負けること勝つこと(84)」 浅田 和幸 |
|||||
「戦後70年談話から思うこと」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部