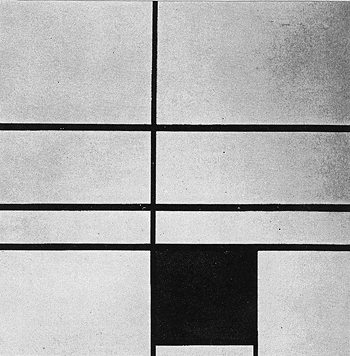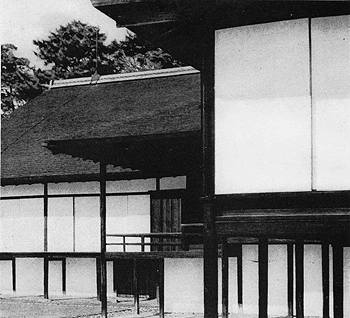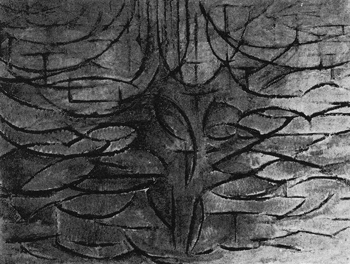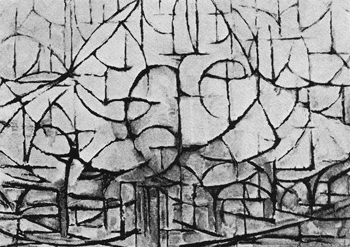第129号 |
||||||||||||
| 2015年12月15日 | ||||||||||||
「問われている絵画(120)-絵画への接近40-」 薗部 雄作 |
||||||||||||
吉田秀和は「音楽は平林さんふうにいえばことごとく抽象的な芸術になってしまうみたいですが」といい、そして「たしかに音は抽象的なものですが、しかし音楽はその抽象的な材料を使って……人間的な感動というものを作り出す。」だから「音楽はそれ自身として、芸術というものが何であるかということを示すのに、非常にぐあいのいい営みだろうと考えています。」「もともと抽象的な感動というものはないわけで、抽象的な芸術である音楽が、人間を感動させる場合に生まれてくるその感動はどんな場合でも具体的で現実的であると思う」。そしてこれは「抽象絵画の場合でも同じではないか」と。
ここで加藤周一は、たとえば「モンドリアンの色と形は自然と何の関係もないけれど、何かを表現する手段でしょう。その抽象的な手段で人間的なものを強く表現することができるだろうか。」といって、いわゆる純粋抽象絵画にヒューマニズムは存在するのか、と問う。たしかにモンドリアンの作品にヒューマニズムは存在するのか、と言われればはっきり存在するとは言いにくい。もともとは具象的な対象を解体しつつ純粋抽象の作品へと向かっていったモンドリアンであるが、その抽象化の果てにたどり着いた〈かたち〉には、すでに具象物の面影はあとかたもなく消えていて、完全に抽象的な形になっている。つまり完全に抽象的な格子の作品には、一見人間的なものはことごとく排除されているように見える。モンドリアン自身がその作品をどのように見、あるいは考えていたかはわからないが、抽象化してゆくことは、彼の場合にはいわゆる生(なま)の具体物の形を排除してゆく過程のように見える。あるいは排除することによって成立しているのがモンドリアンの抽象絵画の世界だ、といえるかもしれない。しかしまた、その一見非人間なものも人間の制作物であるので、つまり形自体には自然や人間の外見的要素は完全に消えてはいるが……その抽象的な形自体の意志というものは、やはりある種の人間的なものであるのだろう。しかし、仮の抽象絵画否定者加藤周一は、そこのところに目をつけて疑問を投げかけているのである。
しかし、たとえば建築物などはほとんど抽象的あるいは幾何学的な断片の集合でできていることが多いが、出来上がった全体の形は、きわめて具体的で具象的である。そしてその形には、はっきりと人間の意志が感じられる。モンドリアンの作品は絵画であるので……そもそも絵画には、とくに現代の絵画には実用的に何のため、というような目的はないが、そしてモンドリアンの作品は人間不在といわれることもある絵画ではあるが、彼の作品の出現以来、一時期その影響は人間社会にもきわめて大きな痕跡を残した。つまり二十世紀後半の一時期、建築やデザインあるいは印刷物の編集・構成などにも大きな影響を与えた。たとえば桂離宮のような建築の構造などもモンドリアン的な観点から見られたりもした。あの作品のコンポジション……基本構造がさまざまなヴァリエーションをともなって人間の生活に浸透していったのであった。ということは、モンドリアンの作品には人間的なものがないにもかかわらず、人間社会に大きな影響をおよぼしたことになるのだろうか。しかしそれは人間的なものがないのではなく、むしろ、あるからであるのかもしれない。というのも、あの作品には自然や人間の外観はまったくないにもかかわらず、そして極端に抽象的ではあっても、それもまた人間の作りだした形であるので、やはりきわめて人間的な形であるからであろう。しかしながらモンドリアン自身は、晩年にいたって、いわゆる無機的構成?から有機的?あるいはリズミカルな画面構成へと移行しつつあった。たとえば「ブロードウェイ・ブギウギ」や「ヴィクトリー・ブギウギ」などを制作した。そういえば「住宅は住むための機械である」と有名な言葉をのこした二十世紀の機能主義建築の巨匠コルヴィジェも、晩年には機能主義的な建築を超えて有機的なかたちの構造に接近して「ロンシャンの教会」を造った。
西洋の旅から帰国してまもない吉田秀和は「日本に帰ってきて、西洋の絵を見たいと思うときに、古い絵がないのに、気がついてひどくがっかりした」「これはずいぶん絵の進展というものに影響しているのではないか」そして「たしかヴァレリーがある画家にふれながら、その画家は、何かを描こうと思うとき、必ずルーヴルに行って、自分で古い絵を見て、それでたしかめながら描くという話があって、そんなものかなと、とても印象に残ったのですが、日本の画家はどうしてきたのでしょうか?」という。それに対して針生一郎は「たとえば日本画の世界でクラシックといえば、光淋なら光淋の技法をマスターしてからということになる」というが、吉田秀和は「ヴァレリーがいっているのはそういうことではないと思うのですが」というと、針生一郎は「そういうことではないと思うのですが、日本の場合はそういうふうな問題になりがちだと思うので、それで僕なんかは逆手みたいだけれども、むしろクラシックにたよらないところから出発すべきではないかと思うわけです」。しかし「クラシックがないのにクラシックのやらなかったことをどうやって見つけだすのでしょうか?」と吉田秀和はいう。そして「抽象的な可能性でいえば、あるいは見てないほうが自由だといえるかもしれないけれども、僕は芸術の場合は非常に難しいような気がしますね。だれも可能性で芸術を信じているのではなく、芸術に感動したからこそ芸術を信ずる。芸術のもとが具体的にそこになければ、話にならないような気がするのですがね。」と。
西洋の絵画を学びながら制作している者にとって、その学んでいる絵画をすぐに見られないということは、たしかに大きなハンデキャップだ。では、わたし自身はそれをどうしたかといえば、無謀なことにも、ほとんど雑誌などの印刷物をとおして実物を想像しながら、いや殆どそれを実物として、そこから学んだり影響を受けたりしていた。しかし後年実物を見るに及んでも、とくに後悔もしないし間違っていたとも思わない。たしかに同じような絵を描くのなら、見ないということはたいへんなマイナスであろう。しかしすでにわたしはそのような方向には向かっていなかったので、とくに実物を見たいとも思わなかった。むしろ見たために、その影響を受け過ぎたりして自分が希薄になり、かえってマイナス面の方が大きいようにさえ思っていた。じじつそのようなケースをしばしば目にしていたので……。
針生一郎は「伝統というものは、無数のエネルギーがあって、大きな麓の上に頂点が出てくるわけですから、そういう見落とされている麓までわれわれは探って行く必要がある。われわれがこれから考えていくクラシックというのは、その全体を探さなければならないわけです」という。そして加藤周一は、いわゆる「名作といわれるものを見ないで、名作を見なければ駄目なんですよ。自分の名作を」という。針生一郎は「それはそうですが批評の問題、高橋義孝さんも書いているように、とくに美術批評がなにか非常に中途半端なものであるし、片輪だというふうな感じは一般にあると思うのです。それがどうして出てくるのか、そういう問題を、ほかのジャンルでの批評とからみ合わせながら出していただきたいと思うのですが」という。そこで加藤周一は「実際に今、行われているのは美術批評の問題から一応はなれて、先の本質論のほうからいえば、作品があってはじめて批評があるというのはうそだと思うのです。批評があってはじめて作品があるといえる。これを切り離すことができると思うのはまちがいで、根本的には、批評のない環境に作品は決してあり得ないと思う。もし批評がなければ創作家が批評家を兼ねるだけのことです。」そして「批評という機能をはなれて絵を定義しようとしたら、一定の枠の平面に絵の具のなすってあるものを絵ということになるでしょう。それでは意味がない。」と。
二〇一五年の現在、この座談会を読んで感じるのは、かつては実に真摯に美術…創造の問題が論じられていたということである。 |
||||||||||||
「負けること勝つこと(85)」 浅田 和幸 |
||||||||||||
「人間の欲望と客観能力」 深瀬 久敬 |
||||||||||||
【編集あとがき】 |
||||||||||||
| - もどる - | ||||||||||||


編集発行:人間地球社会倶楽部