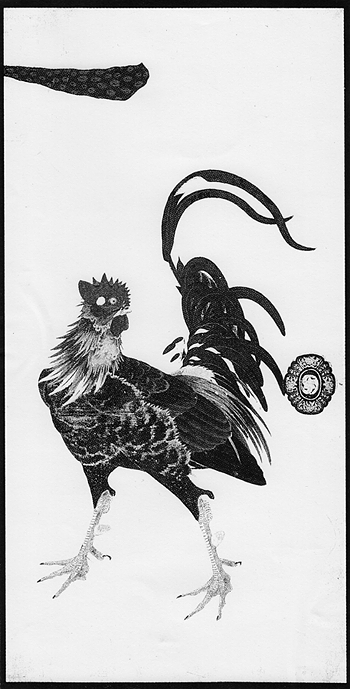第130号 |
|||||
| 2016年3月17日 | |||||
「問われている絵画(121)-絵画への接近41-」 薗部 雄作 |
|||||
ショーペンハウアーは美的なものに対する判断力について。それは「五百年も待たなければ現れないという不死鳥と同じように、判断力というものは珍しい鳥の一種に近く、たいがいは存在しないものである」といっている。それは「美学的にぴったり当たっていることを規則の手引きなしに見つけること」であり、「規則の手引きがないというのは、そこまで規則が及ばないせいであるか、それともあとから反省したときには判断するけれども、実際にそれを使っているときには意識にのぼらないせいである」と。つまり美感、ものを受け取り、見分けるということの本質は「自分でものを生む能力ではなくて、受けとる能力」にある。すなわち「正しいもの・美しいもの・適合しているものをそれと見分けると同時に、…その反対をも見分ける能力」である。つまり「良きものを悪しきものと区別し、良きものを見つけだして評価すると同時に、悪しきものをしりぞける能力なのである」のだと。
そして「文士は流星・遊星・恒星というふうに分類できる」という。「第一の者は瞬間的場当りを提供する」。それは「みんなが空を仰いで[ほら、あれだ!]と叫んだと思うと、それっきり永遠に姿を消してしまうのである」。つぎの「惑星・遊星にあたる者は、はるかに長持ちする」。これは「恒星に近いおかけで、ときには恒星以上に明るく輝き、素人からは恒星にまちがえられる。」しかし「とかくするうちに場所を明け渡さざるをえなくなる」。というのも「その光というのも借り物にすぎず、その影響する範囲は同じ軌道を走っている仲間[同時代人]に限られる」からである。「彼らは動き、変化する。二、三年のいのちで一回りするのが彼らの仕事なのだ。」そして「第三の者だけが不変で、天空にしっかり座を占めており、自分の光をもっている」のであると。
しかし「なんといっても精神的功績にとって不都合なことは、自分はつまらぬものしか生みだせないような連中が、その美点をほめてくれるまで待たねばならないということだ」。いやそればかりではなく「そもそもその王冠を人間の判断力の手から受けねばならないということ自体が不都合な点だ」という。そしてまた「生粋のすぐれた者が登場するとき、まず行く手をはばむのは劣悪な者である。」それはまさに「優れた者が占めるべき場所が、すでに劣悪な者によって占領されているのを見いだす」からである。そして「長い時間とはげしい戦いののちに、ようやくその位置を奪還し、名声を得ることに成功しても、それは永つづきはしない。かれらぼんくらどもが、きどった、才知のない、武骨な模倣者どもをつれてやってきて、まったく平気で、この模倣者を天才とならべて祭壇にまつりあげる」のだ。「こういうわけだから、シェークスピアの戯曲も、彼が死ぬとすぐにベン・ジョンソン、マシンジャー、ボーモント、フレッチャーの芝居に席をゆずり、百年間もその席をこうした連中にあけわたさざるをえなかったのだ。」と。
そして「公衆からの正しい評価を早く受けられる見込みの多いもの」として、それらに順番をつけている。すなわち「綱渡り師・曲馬師・バレエの踊り手・手品師・俳優・歌手・音楽の名手・作曲家・詩人・建築家・画家・彫刻家・哲学者ということになる」と。まったくなるほどと思う。しかし現代では曲馬師の次あたりスポーツ選手などがあげられるかもしれない。つまりこれらのものは誰でも…子供でも…優劣や失敗や成功が一目でわかる。絵画や彫刻なども、ものによっては誰でもある程度わかるが、その価値の微妙なところまでは難しい。しかし哲学となるとその価値や優劣を、子供や多数の人々が簡単に判断するのはきわめて難しくなってくる。
また「にわかに得られた名声のうちに数えいれるべきものに、いんちきの名声というものがある」という。つまり「これはでっち上げられた名声で、大衆が判断力をもたないことを良いことにして、ある作品を不当に持ちあげ、いい友人をさくらにしたり、批評家にわいろを使ったり、上のほうから眼くばせ、下のほうでは協定といったことで、足腰が立たないのを無理に助けおこしたような名声」であると。しかし「こういう名声は重い物体を泳がせる浮き袋みたいなもの」で、そしてそういうものは「よくふくらませて、かたく栓さえしめておけば、その程度によって時間に長短の差はあっても重いものを運んではいくが、しだいに空気がもれてきて、けっきょく重いものは沈むのだ」。そして、それはなぜかというと、それが「その名声を自分のうちにもたない作品の不可避的運命なのである。」と。 ショーペンハウアーがこんなことをいっているのは、あるいは彼が長いあいだ世間から無視されていたからかもしれない。というのも彼の代表作『意志と表象としての世界』は三十歳のときに書かれて出版されたが、ひろく評価されたのは彼が晩年になってからであるので……。
しかしここでわたしは思うのだが、この「自分のうちに名声をもたない作品の不可避的運命である」というのは、作品のなかに確たるものがなくてもひととき名声をえる場合であるが、しかしそれは、ひとときであるとはいえ、注目されるのでまだよいほうである。というのも、まったく名声がない者のなかにも、作品の根拠を自分のうちにもっていないばあいも多々あるからで、気になるところである。しかしそういうばあいでも、もちろん自分では自分なりの価値意識を持っているのは当然で、もしそうでなければ仕事はできない。どういうばあいかといえば、スタイルや方法そのものがすでに何かのあるいは誰かの亜流であるばあいである。そういうばあいはいくら頑張ってもその方法やスタイルを創造した人を超えることは難しい。しかしこういうばあいがひじょうに多いように見えるのはどうしたことか。あるいそれが普通なのかもしれない。しかし、かつて伊藤若冲は「狩野派の手法をいくら自分のものにしても、しょせん狩野派のワクを超えることができない、宗元画を学にしかず……というわけで、宗元画をおびただしく模写したが、また考えてみるに……結局のところ、宗元画の画が[物]に即して描いたものを又描きしていたのではかなうはずがない、自分で直接[物]に当たって描くことに越したことはない」といっている。そして「ところで[物]といってもいったい何を選べばよいのか、騏麟(きりん)のような空想上の動物や、中国の故事人物山水のごときは、画幅の上でしかお目に掛からないしろものだ、とすると、動物はどうだろう、クジャクやオウムなどは、いつも見るわけにはゆかないが、ニワトリなら羽の色も多彩だし、何よりも身近に求められる……」といって「群鶏図」のような傑作を描いたのであった。 今でこそ一般にもよく知られるようになった若冲であるが、しかしこれも比較的最近になってからのことである。もちろん発表当時も彼の周囲では多少の知名度はあったようだが……というのも彼の作品がいくつかのお寺などに残っているので……しかしひろく一般の評価をかちえたのやはりごく最近のことである。そのかんには約三百年の経過がある。
ここでわたしは唐突にも貝原益軒を思い出した。しかしこれは唐突ではないかもしれない。なぜなら両者の生きた時代はわずかな違いはあるがほとんど同時代である。益軒は(一六三〇−一七一四)で若冲は(一七一八−一八〇〇)であるからだ。そして二人とも八五歳で没している。八十五歳というのは当時としてはかなりの長命であったと思う。さらに思想的…思考方法にも共通しているところがあるように思える。たとえば若冲は、さきほどもふれたように中国のものをたくさん模写して勉強したが、それではいつになっても真似からぬけだせない。やはり自分の身近なところのもの…いつでも見られるもののなかから描くものを選ばなければ、真に自分の根ざしたものはできない、といって中国絵画には登場しないが「羽の色も多彩だし、なによりもいつでも見られる」といってニワトリに目をつけたのであった。益軒は学者であるが、そしてやはり中国の文献をひろく研究しているが、やはり中国の古典を勉強するだけではだめである。中国人と日本人では体格もちがうし住む風土もちがう。やはり日本の風土や人に即した思考や思想を持たなければならないといっている。そして、さらにその思想を実践することが重要であるということを強調する。
たとえば「学問は自得することが重要である。それゆえ自得することがなければ、博く多くのことを学び記憶し経義(経書の意義)に詳審(詳しくつまびらか)であっても、それは単なる字句の学習、訓詰の学(字句の解釈を主とする学問)にすぎない。それは学問として価値のないものである。(『慎思録』以下同) 「学問をする者にもっとも大切な点が二つある。一つは未知の事柄を探求し解明すること、いま一つはその解明したことを実行することである」 「ことを実践し行動を定める場合に、それが理に通じているならば、いかに愚俗の人々に誹笑(そしり笑われる)されたとしても決して畏れてはならない」 「学者は書物をよく読んでいるが、根本にある道を探求しないで、ただ章句の解釈にとらわれて、思考し判断力を養う努力をしない」 「真の力がないのに空名を得ることはまことに恥とすべきことであろう。偶然のことで一時的に著名になったとしても根拠なきものであれば、その名はたちまち消えてゆくであろう。著名になったことをよろこぶどころか大いに反省しなければならない。 「思うに世間の毀誉は理にかなっていないものが多い。であればこそ、それによって嘆いたり喜んだりする根拠とすることは大きな間違いである。
ここで、益軒が若冲に共通しているだけではなくショーペンハウアーにも共通しているのに気がつく。益軒というと『養生訓』のみが有名であるが、それよりも彼はきわめてオリジナルな思想家であるのだ。そしてここで特に注目するのは、彼の著作活動がほとんど八十歳を過ぎてからであるということだ。たとえば『大和本草』(80)『岐蘇路記』(80)『和俗童子訓』(81)『楽訓』(81)『五常訓』(82)『自娯集』(83)『養生訓』(84)『慎思録』(85)『大疑緑』(85)などがある。とくに「絶筆となった『大疑緑』は「益軒の学的生活の総決算にふさわしい著書であるとともに、彼の遺言にも相当するものといえるであろう。書名のごとく文字通り大いに疑う書であるが、何を益軒は疑わなければならなかったのか。朱子学者益軒が朱子学への疑問を投げかけたのである。」と伊藤友信は『慎思録』現代語訳の「序文にかえて」に書いている。
|
|||||
「負けること勝つこと(86)」 浅田 和幸 |
|||||
「感性から全人格性の時代へ」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部