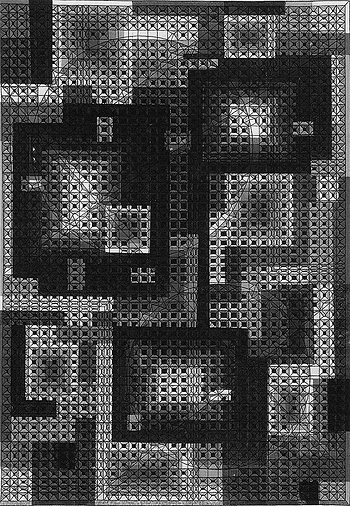第131号 |
|||||
| 2016年6月22日 | |||||
「問われている絵画(122)-絵画への接近42-」 薗部 雄作 |
|||||
二〇一二年に「伊藤若冲の没後二〇〇年特別展覧会」として京都国立博物館で大きな若冲展があった。わたしはその展覧会を見ることはできなかったが、図録だけは取り寄せたので、今その図録をあらためて見ている。分厚い図録を開くと最初に「白象群獣図」という絵が出てくる。それが先ずわたしの眼をとらえた。そこには白い象や獣たちが描かれているのであるが、それらが背景も含めてすべて格子状に描かれているのである。わたしは日本美術史のなかでもこのような作品を見たことがない。いや西洋美術史のなかでも見たことがないような気がする。そもそも絵というものは、一般に人間や物が見えるままに(抽象絵画を除けば)多少変形されているとはいえ、描かれているのが普通である。それが格子状に描かれているということは、それだけでもすでに変った印象を受ける。いったい若冲はなぜ白象や獣たちを格子状に描いたのだろう? それだけではなく、わたしがとくに眼を見はったのは、その格子状の絵がわたしの作品にも酷似しているように見えるのだ! というのは、わたし自身ここ数十年にわたって格子状の作品を描いているからである。
「白象群獣図」の解説では、格子についてとくにふれていないが「空前絶後の絵画世界を構築して」いるといっている。そしておなじく格子状の作品「鳥獣花木図屏風」については「小林論文では、この独創的な画法の発想源になったものとして、「刻系」と呼ばれる中国産の織物があがっており、さらにこの屏風の縁の描表装が、インド更紗のある縁文様と完全に一致することが指摘され」ているという。そして「小林氏は、これらにより、若冲の同時代に突出したこの絵画技法は、若冲が舶載染繊品の縁模様に刺激されて生み出されたのではないかという意見を呈出した」と。 また「近時、染織の立場から、「伊藤若冲の〈枡目画〉作品を再考する−西陣織「正絵」との関係から−」(『金沢美術工芸大学学報』6)を提出した泉美穂氏は、筆者の考えをさらに徹底的に推し進めて魅力的な展開をしている」という。そして詳しくは同論文に就いていただきたいが、西陣織の下絵であり、設計図でもある「正絵」(「紋図」ともいわれるものか)を引き合いに出して論じ、「白象群獣図」「鳥獣花木図屏風」の方眼の大きさが「正絵」の方眼に共通することを指摘した」という。そして「筆者風にいえば、その正絵に面白さを覚え、方眼を残したまま作品にしたのが、それらの作品だったのではないか、ということになる」と。さらに「泉氏は重大な興味深い指摘をしている」といい、「若冲の死後、寛政十二年(一八〇〇)十月二十七日に相国寺で行われて法要についての『参暇寮日記』の記事のなかに記された縁者として、伊藤宮治と金田忠兵衛のふたりの名があがっている。この記事は今までも知られており、伊藤宮治が伊藤家の縁者とは容易に知られるが、金田忠兵衛については何びとか明らかでなかった。泉氏はいくつかの文献によって、金田忠兵衛が代々その名をなのる西陣織物の織成に意欲的に取り組んでいた人物」と同一人の可能性が高いことを明らかにした」といい「若冲のごく近い周辺に西陣の業者がいたのである」と書いている。
さらに解説によると、同じ格子状の作品「樹花鳥獣図屏風」については、これは若冲の作品ではないという説があるという。そして「佐藤康宏氏は一貫してこれらが若冲の作品であることを否定する立場を取って」おり「佐藤氏か唯一、若冲の作品とする認めるのは「白象群獣図」であり」他の二つの屏風は「白象群獣図」に刺激を受けて作られた、若冲とは無関係の屏風である」いう。理由として「白象群獣図」には(「藤女釣印」「若冲居士」「千画絶筆」)の三印を捺した紙が貼られている)という。たしかに両作品をくらべて見ると、同じ格子…方眼とはいえあきらかな違いがある。「樹花鳥獣図屏風」は大作ということもあるかもしれないが、立体的な格子…方形の描き方にむらがあり、たとえばはっきり立体的な格子状のところもあるが、白象やその他の部分などは線状で描かれているところもあり、さらに全体の描き方も少し荒いように見える。というのは、たとえば白い象などは格子が立体的ではなく線状である。推測するに、大きな白象を立体的な格子状にするのには、常識的感覚の絵師には少し抵抗があったのではないかとも思う。さらに、描かれている事物全体の形体感覚に何かヌルイ…弛緩したようなムードがある。樹木の枝や葉などのかたちもへんに丸っこく、このような形態感覚…造形感覚は若冲の作品には見られない。若冲の作品では画面全体の形が均一な神経…精神によって統一され、はりつめた緊張感がある。この細部を省略しないで克明に描くという描法は若冲の特徴であり持ち味…あるいは体質や性格のようなもので、これは他の作品たとえば「動植綵絵」などにも顕著にあらわれている。しかし「樹花鳥獣図屏風」にはこの特徴は見られない。
格子にこだわってきたのは、すでに述べたようにわたし自身が格子の作品を描いているからである。けれどもわたしが格子の作品を描いるのは若冲の格子の作品を見て、それに影響されてではなかった。たしかに、わたしは今までにもたびたび若冲について書いてきた。しかしそれは若冲の作品のもつ独特の力にひかれていたからで、そしてその力のみなもとは何かと探ってゆくと、それは対象を描くときの若冲の目が、かつての名画を描いたどんな画家の目でもない、若冲自身の内なる根源の目によって描かれているという、そのことについてであった。その眼にわたしがとくにひかれるのは、たぶんわたしもわたしなりに、たとえそれが微弱なものであっても、かつて名画を描いたどの画家の眼でもない、わたし自身の眼によって、その眼にかなう形を模索していたからだと思う。その暗中模索のながい過程で格子という形に突き当たったのであった。だからわたしははじめから格子を目指して描いてきたのではなく、また障子などの現実的なイメージから刺激されたのでもなく、それよりもむしろ、格子とは反対のぐにゃぐにゃした形や角柱の交差するような空間をまさぐりながら描いてきた。そして徐々に期せずして格子の形に突き当り…あるいはたどり着いたのであった。その形は心的にも一体感があり、かつ造形的にもきわめて堅固なフォルムのように感じられた。ある意味では最終的な形にも…到達点のようにも思えた。そしてかつてより心の安定感をえた。しかし、やがてそれも決して最終的な形でも到達点でもなく、むしろそれは新たな出発点であるのに気がついたのであった。
|
|||||
「負けること勝つこと(87)」 浅田 和幸 |
|||||
「共同体としての地球社会に向けて思うこと」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部