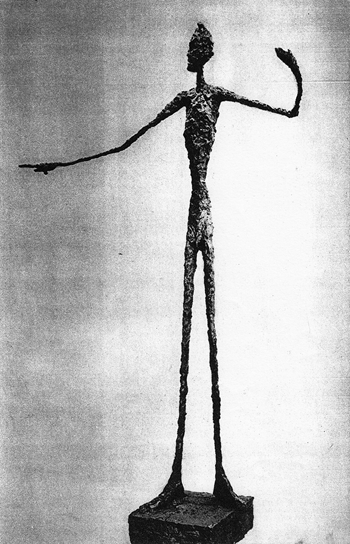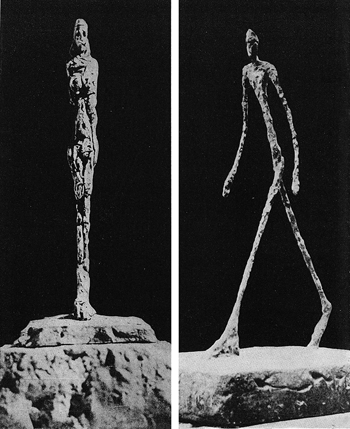第132号 |
|||||
| 2016年9月23日 | |||||
「問われている絵画(123)-絵画への接近43-」 薗部 雄作 |
|||||
たぶん十代の終わり頃であったと思う。ある日ふと思った。今はまだセザンヌやゴッホなど印象派周辺の画家たちの影響のもとに風景や静物を描いているが、これから先…いつの日にか、わたしにもこれがわたしの作品だ、といえるような作品が描けるのだろうかと。そして考えた。今わたしをとらえているセザンヌやゴッホやその他の画家たちにしても、彼らの作品がわたしをとらえて離さないのは、すべて彼らの作品が、まぎれもない彼ら自身の根っこから生まれているからだ、と。だからわたしに感銘を与えている彼らの作品は、それぞれの画家たちが、その作品のなかで自分自身になりきっているからである。つまり彼らはすべて他の画家たちの影響からではなく…もちろん初めはいろいろな影響があったとはいえ、それらが少しずつ消えてゆき、やがてまぎれもないかれら自身の根っこから生まれ出てきた作品であるのだ。そうであるならば、わたしたち各自も、それぞれの人間か彼自身になりきることによって、あるいはなりきることができれば、各自はまぎれもない彼ら自身の根っこから生まれた作品を制作することが出来るのではないか、と。であるならば、わたしも、わたしの作品のなかで完全に…とまではいかなくても自分になりきることができれは、それなりに、これがわたしの作品だ、といえる作品ができるのではないかと。だから、すべての人間は可能性としては彼自身の作品を生み出すことができるのではないだろうか、と。
そんな意識で自己肯定し、とにかく自分の内側を拠点にして制作を始めることだ、と。そして我流の理論を考えた。というよりそれがふと思い浮かんだのであった。そしてそれをバックボーンとして始めた。それは「色環の思想」として今までにも何度か書いたことがある。簡単にいうと、たとえば虹の七色が、輪のなかに分割されて配置されているのを想像し、そしてその輪のなかのそれぞれの色…赤や青や黄が、あくまでも各自の色を堅持していてこそ、その「色の輪」は成立しているのだ。そのなかのどの色かが…たとえば赤なら赤が、隣の色に影響されて濁りあいまいな色になってしまえば、自分の赤としての存在だけではなく、色環としての世界も成立できなくなってしまう。つまり画家も世界の多様…多彩な絵画の輪のなかで、他の色…誰か他の画家の作品に影響されて自分が希薄になり、あいまいになってしまえば、自分だけではなく、絵画という世界にとっても、それだけ単調になり、多様な絵画という輪が崩れてしまうのではないかと。だからわたしたち各自も、世界の多様な絵画という環のなかで、他の目につく色…画家の作品に影響されることなく、あくまでもおのれの色…根っこを自覚し、そこから始めれば、たとえささやかなものであっても、これが自分の作品だ、といえるものができるのではないか、と。 さらにそれだけではなく、それにはまた絵画だけではなく芸術全般も知らなければならないと思った。絵画だけに眼を据えていると、とかく画面上の処理に眼や神経をうばわれ、とかく感覚的にながれやすい。他のジャンル…音楽や文学を知ることによって、それらの芸術の根底にあるものと絵画の根底にあるものとの共通点をキャッチし、たえず比較検証する必要がある、と思った。それによってたとえできたものが周囲とは異なっていようと、その共通の根本精神を踏み外さないならば、たとえ周囲とはことなっていようと恐れることはないのではないかと。
そしてわたしは始めた。はじめはごく単純なかたちや形や色を組み合わせただけのものであったが、それがスムースに進行したというわけではない。そんな習作的ものを描いていたあるとき「美術手帖」(一九五五年・四月号)に掲載されていたジャコメッティの作品が眼に飛び込んできた。それはまるで電光のようにわたしを貫いた。それが何であるかはわからなかったが、とにかく自分の今やっているこのままではだめだ、何かもっと内的な強い意志のようなものが必要だ、という啓示めいたショックであった。それは作品の手法やスタイルという表現様式の問題ではなく、それらを飛び越えた何かであった。というのも、表現様式…方法という問題なら、そのときわたしがやっていたことはジャコメッティとはまるで反対にちかかった。ジャコメッティはあくまでも対象を見てひたすらそれに迫ろうとする写実的な姿勢であるが、わたしのやっていたことは、外的対象のない一種の抽象的なかたちの形成であったからだ。にもかかわらずそんな違いを飛び越えてわたしが衝撃を受けたのは、制作者もふくめて作品群から放射してくる強烈な何かであった。
掲載されていた宇佐見英治の「アルベルト・ジャコメッテイ」には、冒頭いきなり「十五年に一度しか個展を開かなかったというジャコメッティは、ただ一つのものが作れたら、わたしには千の作品がつくれるだろう」といい「彼は粘土をこね上げ、たえまなく叩き潰す。」そして「私はいつも失敗してきた。……けれども私は人間は努力する以上はかならず実現しうると信じている。ああ〈もうこれ以上のものはできはしない。これこそ〉ということができたら」といって制作にのめりこむ、と。そこにはジャコメッティの制作中の写真が載っている。周囲は写っていないのでわからないが「そのアトリエはパリのもっとも貧しい地区にあり、間口四メートル半、奥行き五メートルの小さな暗い部屋」であるという。「天井にちかく上方に中庭に向かって窓か一つとってあるが、中庭といっても幅二メートル、長さ十二メートルの狭いセメントの空き地で、屑物の山が見えたりする。日光は高い窓からしか入ってこないから、このアトリエの印象は何もかもがくすんだ灰色で陰気だ」。そしてとりわけわたしが衝撃をうけたのは、そこから感じられるすさまじい制作者の姿勢であった。かつてセザンヌやゴッホの制作姿勢のひたすらさにも強い感銘をうけていたが、それと同じような何かが熱っぽく語る宇佐見英治の言葉とともに突きささってきたのだ。もちろんセザンヌやゴッホとは作品も制作の環境もまるでちがう。にもかかわらず、そこに何か共通する何かを感じたのだ。たぶんそれは、多くの現代美術家に見られる、かつての芸術を破壊することによって自分を表現するのとはちがう、あくまでも対象を見て描くという、すでに過去…十九世紀的な芸術家の姿勢として否定的に見られることも多い姿勢であった。時の美術潮流はすでに別の方向へ向かっていたからである。にもかかわらず、その時代の流れに逆行するかのような姿勢が異様な鮮度と衝撃でもあったのだと思う。さらに当時の思想界でもっとも注目されていたサルトルの「絶対の探求」というジャコメッティ論が話題にもなっていたことなどあったと思う。
たしかにセザンヌやゴッホも室内で静物も描いたが、またモーフをもとめて屋外にもよく出て行った。しかしジャコメッティは屋外にはほとんど出ない。薄暗く陰気な室内で徹底的に人物だけだ。そしてその人物はぎりぎりまで削ぎ落とされたようなひょろ長い像だ。細く長いという特徴だけなら同時代のビュッフェにも共通する。しかし双方から受ける印象はまるで違う。ビュッフェの作品には社会から疎外されたような人間がしばしば登場するが、ジャコメッティの人間像にはそのような意味での社会的関連性は感じさせない。そしてビュッフェのような大作はほとんどなく、作品はきわめて小さい。ジャコメッティはその小ささな像についていう。「大きな像は私には嘘に見える。小さなものならなおゆるしうる。ところがそれはいよいよ小さくなってしまって、ついにはナイフでちょっとさわれば、埃の中に消えてしまうほどになるのだった。それでも人間の顔と像は小さいときにのみ真実であると思われた。」このような状態は数年間つづいたという。「私はもっと像を大きくしたいという気持ちが起こってきた。すると驚いたことには細く長くしたときにのみこんどは似てくるのであった」と。
|
|||||
「負けること勝つこと(88)」 浅田 和幸 |
|||||
「自分自身を知ることの大切さ」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部