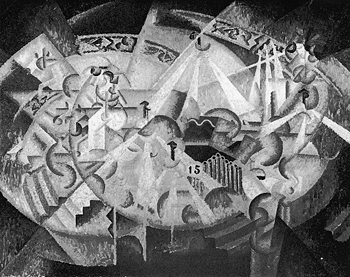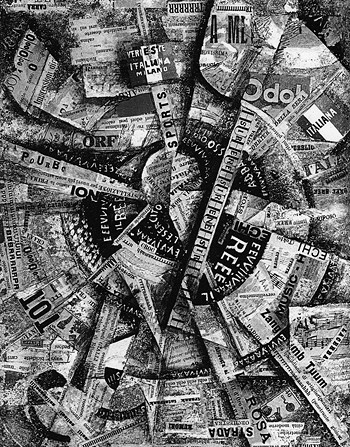第133号 |
|||||
| 2016年12月20日 | |||||
「問われている絵画(124)-絵画への接近44-」 薗部 雄作 |
|||||
稲垣足穂は昭和十六年、第二次大戦直前(「意匠」一九四一年六月号)に「人生は短く芸術は長し」という文章を書いている。戦争の直前であろうが戦中・戦後であろうが、彼のなかで芸術に対する意識はまったく変っていないようだ。坂口安吾なども戦前・戦中・戦後ととくにかわってはいないが、安吾のばあい社会現象に対しては敏感であったようだ。しかし足穂は社会現象にもほとんど関心がないように見える。戦争についても殆ど何も語っていないようだ。先の文章のなかで彼はいう「文学青年のなかからは決して芸術家は生まれない」。もし生まれるとすれば、それは「彼の衷なる文学青年ならざる要素」がそうさせるのである。そしていわゆる文学青年とは既製の対象を追求する類いにほかならい……真の文学とは自発的なものである」と。つまり何かの流派や誰かの影響ではなく、それらを脱ぎ捨てた自分自身の内から生まれ出たものでなければならない。この「既製の対象を追求する」ということは現在でも依然として多々みられる現象である。そして芸術をつくろうとする「努力」に対しても無意味を宣告する。「適宜なる努力の結果はよく成功をかち得るであろう」そしてそれは「一部の人士を羨ましがらせる」かもしれない。しかし「それが何物であろう。彼は最初から生きてはいなかったのだ」と。 そしてまた「芸術家はまず普通人とは異なっていなければならない」。しかしトーマス・マンのいうように「芸術家は常人とは異っている者であるが、常人に成ろうとして絶えざる戦いを続ける所に生まれるもの」ではない。一般にはそのように思われているが、それは「暗夜提灯の前に立って歩くようなものである」。「芸術はもっと自然に生成されなければならない」という。では努力を排したあとに何かあるのか。足穂はいう「われわれに許されるところは念願のみではないか」。そして「約束されたものを受けるために必要なのは忍耐のみではないか」と。「君は絶望する。途中で投げやってしまいたくなる……しかしこんな場合にこそ火花は散り、作成らんとする一歩手前なのである」。そしてそれが「かりに不幸なる反応をもって報いられたとしよう。宜しい、それが君にとってやはり最善の状態であったということは、きっと将来において判明するであろう。そうであるのに、この窺うべく許されざる領域を手軽に、あるいはまた理論的に覆おとしたときに迷妄が発生する」。まったく芸術家は多少の違いはあれ、多くはこんな状態のなかで仕事をする。
「努力」を「放棄」してたあとに残るのは「念願」と「忍耐」のみである。きみは「絶望し途中で放棄したくなるであろう」しかし「そんの時こそ、作成らんとする一歩手前である」。つくる者にとって、まさしくここに大きな蹟きの石がある。とかくこんなとき、わたしたちは生活の方へ眼が向く。一見生活にとっては無益な、そればかりか有害でさえある芸術創作への不信感はつのり、やればそれなりの反応があるかにみえる生活へのウェイトは増す。さらに芸術は生活にはおかまいなしに持てる時間と労力を全面的に要求する。だから「今度こそはやろうとか、部屋に落ち着いたらとか、こんなことをいうのも同様に自分を買いかぶった言い方」で「人間はそんなに自由なかつ力ある物ではない」。したがって「ペンや原稿紙や茶道具や生活費をいくらとり取り揃えたって仕事は出来る訳ではない。そこに在り合せのわせの紙片と鉛筆でよい」。「ノートや参考書などもいらない」。じっさい足穂は、下書きはチラシなどの裏に書き、清書は出版社などで不要になった原稿用紙の裏に書いていたという。身辺無一物となってこそ……この文章と同時期の『弥勒』にはそんな状況の自身の体験が書かれている……人間の存在はむきだしになり、世界はあらたな表情で現れ、見えてくる。
そして「芸術は長く人生は短し」とは何をいっているのかと問う。「芸術は限りないものであるが、それに関わる人生はあまりにも短い。」と一般には解釈されているが、「その最大の誤謬は作品と芸術の混同である。物としての作品などは永劫の中ではもろい。レオナルドあってのモナリザに非ず、モナリザあってのレオナルドでもない。モナリザを制作せざるを得なかったレオナルド、このレオナルドを動かし得たものを称して吾々は芸術という。」そしてこれこそが「不滅のなもの」であり「この確信なくして如何でか吾々はカンバスに向かいまたペンをとろうか!」と。「不滅なるものの火花は、君の及ぼすその無形なる波動は、必ずや四辺に在る君に似た胸奥に伝わるにちがいない」かくてそれは「彼らを動かし、君の夢たりしものはそこにキャッチされ人類の所有と成るに至るであろう。実に芸術は万人のものであり、自分一人の名利や世間の恭敬なんか何になろう。されば世に芸術家あるは人ならず又作ならず、そは彼のまことに於いてなり」。「見ゆるもののうちには、見えざるものものの痕より他に何もあらじ」「これは古いバラモンの言葉であるが、かかる世界を目指すものを、即ち日常身辺の至る所に顕現せる神を観る事が芸術家の使命である」。そして「友よ、稚態を脱せよ、君の机上なるやくざなるあらゆる文学論を投げやって、君の四辺に充ち満ちて呼べば答えんとする無数の霊達と直接会話するべき術を修得せよ。見ゆる的は君の闘する所にあらず、見えざる的を狙う事を、これを生きて甲斐ある芸術家の光栄と言う」。
「人生は短く芸術は長し」などという言葉は今では全く聞かない。人間と芸術の関係がかつてとは違ってしまったのかもしれない。しかし芸術そのもの実情はとくに変っていない。すでに当時でさえそんな言葉をまともにいう人はいなかったかもしれない。しかし文字通りこの精神で生きて書いた『弥勒』は、その後、時代の変転を経た七十五年後の今読んでも、依然として鮮度があり含蓄がある……弥勒とは「釈迦の人滅後五十六億七千万年にこの世に下り、新しい仏として衆生を救うという信じられている仏」である……足穂はここで全面的に芸術に没入しているので、いわゆる普通にいう生活というものが無くなり、身辺は無一物となる。トーマス・マンのように生活と芸術を区別して器用に出入りしなかった。あるいは出来なかった。とういうのも、マンは当初から時の文壇や読者に受入れられ作家として成立していたが、こんな例はむしろ珍しいく、ほとんどの作家は、とくに初期は苦しい生活を強いられていることが多い。そんななかで、しかも生活のための労力を放棄すれば、当然その報いは自身にふりかかってくる。芸術が生活の足しになるということは古来めったにない。生活はそのための時間と労力を全面的に要求するし、芸術は芸術でそのための時間と労力を全面的に要求する。したがっておおかたの場合どちらかにウェイトがかかる事になる。中途半端では双方とも…芸術も生活も満足するような結果は得られない。生活のための労力を放棄した足穂は当然のように断続的な断食状態になる。そして「古畳の上に置いたペン軸がその一方へ転げて行く」ような、おんぼろの「墓畔の館の二階の一室で、朝になると正午を待ち、……十二時の汽笛が鳴ればもうその一日を送るのがよほど楽になる」という日々になる。「夜具も売り払ってしまい、窓際に懸かっていた天竺木綿の古るカーテンを外して、身にひっ被って」寝る。何にもない部屋の枕元には、かろうじて残っている「人からもらった半ば壊れかけて枚数の不足した」辞書があり、そのなかから「主に仏教に関する語彙を拾い読む」という、やむをえずとはいえ町中の修行僧のような日々がつづく。しかしそんに状態で感覚はとぎすまされ、視覚は敏感にり、見慣れていたものが今までとは別の表情で現れてくる。生ゴミを集積してゆく清掃の荷車のなかの残飯が異様な鮮度で目をとらえ「凡そ食べ物は残り物が一等美味であり、人参やキャベツや大根やキュウリにしても人々が捨てて顧みない端くれにこそ真の味が光っている」のに気がつく。「人間のたべものは、その折々にあるもので十分である。ご馳走を食べた時に、われわれはなんと悪いことをしたように思うことか」、では「とるべき態度は何か、それは物質に限らず精神上にあっても常に最小限にとどめる習慣を持つこと」である。 「魂は苦悩と悲哀によって訓練されねばならない」。「君が不安であったり憂誉であったりした折には、ただちに真面目な仕事に取りかかれ」。「人間の魂はいったん覚醒した限り前進ばかりで、退歩も停滞もないのではないか」。かつては「見栄坊的対象でしかなかったショーペンハウエルの訳本三冊中の一冊」を人から貰って読むと、そこには「親切に、丁寧に、あまつさえ情熱的に、苦行者及び聖者の意義について繰り返し説明されてぃる」のにあらためて気がつく。そんな経過をたどりつつ次第に仏教的な世界が心のなかにひろがり、やかて弥勒のイメージが浮上してきて自分と合体する。「波羅門の子、その名を阿逸多、今から五十六億七千万年の後。竜華樹下において成道して、先の釈迦牟尼仏の説法に漏れた衆生を済度すべき使命を託された者は、まさにこの自分でなければならない」。再生の予感のうちに作品は終わる。
しかしここでわたしをとらえるのは文体…文章そのものである。極貧状態がきわめてリアルに書かれているのであるが暗さというものは全くない。軽快でさえある。足穂は当時ヨーロッパの前衛芸術に惹かれていたようなので、事物をそのまま、あるいはコラージュ的に呈示するダダや未来派などの影響があるのかもしれない。しかしそれは完全に消化されいる。とくに筋があるわけではないが、次第に仏教に収斂されてゆくのも興味深い。
|
|||||
「負けること勝つこと(89)」 浅田 和幸 |
|||||
「宗教について改めて思う」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部