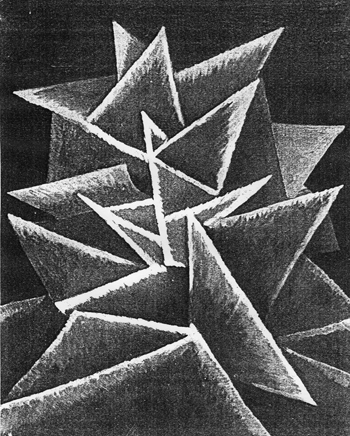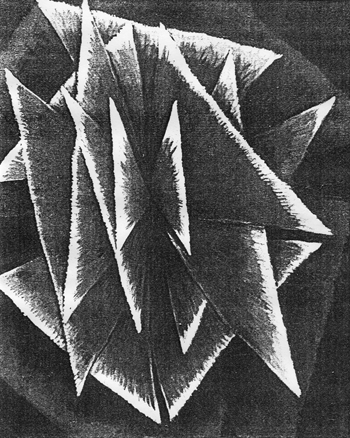第134号 |
|||||
| 2017年3月22日 | |||||
「問われている絵画(125)-絵画への接近45-」 薗部 雄作 |
|||||
ジャコメッティを初めて見たときの衝撃は表面的な造形の問題ではなかった。それは制作者の気迫のようなものだったのだ。だからそれが、わたしの作品にかたちの上で何かの影響を及ぼしたということではなかった。しかしその時のつよい印象はわたしの深層に潜在していたのだ。だからだと思う、だいぶ後になるが一九七三年に池袋の西武美術館でジャコメッティ展があったとき、わたしはすぐにそれを見に行った。そのときの印象がメモにある。「ジャコメッティとは何か。あれだけの作品を見ると、おのずから一つの行為の結果が、あそこにまざまざと浮かび上がってくる。定形を嫌う、固定を、形式を。あくまでも生きて動いているもの、人間の手で作られたものでないもの。自然の表情に肉薄しようとする凄まじいほどの情熱。それは情熱という言葉ではたりない。なにか憑かれた者の仕事だ。だからあそこでは一切の芸術作品から遠のくこと、芸術の概念を取り払ってひたすら対象そのものに肉薄する。もはや芸術は問題ではないのだ。そこでこそ、ジャコメッティの見た対象そのものが、そこに示され始めるのだ。それは戦慄的にこちらに迫り、あらためて見る者に、おまえは本当に物を見ているか、真実に直面しているか、と反省と警告をするどく突きつける。」
一九五六年にわたしは最初の個展を開いた。場所は西銀座のサトウ画廊であった。当時の美術界の状況は、まだ団体展が主流のような時代で、大きな団体展は新聞や雑誌でも必ず取り上げて批評記事を掲載していた。現在のようにいたるところに美術館がある時代ではなく、美術館は上野にしかなかった。そして芸大も上野にあり、美術志望の若い者にとって上野はとくべつなおもむきがあった。若い画家たちも上野の団体展を目指して邁進している者が多かった。しかしまた一方では、それらにたよらず個展やグループ展などで発表する画家たちも少しずつ増え始めていた。時をおなじくして美術批評界でも一群の若い批評家たちが現れて活発化した。「美術批評」という評論の専門誌もあって、そこでは美術に対する論議が…美術と社会や時代との関わりなどについて活発に論じられていた。
時代の気運であったのだろう。それより少し前になるが、目立ち始めていた岡本太郎の言動などの影響もあったのだと思う。彼はすでに一九五四年に『今日の芸術』を世に出している。そのなかで彼は旧態依然とした美術界にたいしても爆弾的な発言をしている。それは若い美術家たちに対して起爆剤のような効果があった。わたしもすぐに買って読んだ。そして大いに啓発された。この本の「まえがき」で岡本太郎はいっている「私はこの本を、古い日本の不明朗な雰囲気をひっくり返し、創造的な今日の文化を打ちたてるポイントにしたいと思います。」さらに「芸術を中心として話をすすめて行きますが、問題は、けっして芸術にとどまるものではなく、我々の生活全体、その根本にあるものです。だから、むしろ芸術などに無関心の人にこそ、ますます読んでいただきたい」といって、従来の価値観をつぎつぎにひっくり返していく。たとえば芸術は「心地よくあってはいけない」「きれいであってはいけない」「うまくあってはいけない」と宣言する。「だれでも、その本性では芸術家であり天才なのです。ただ、こびりついた垢におおわれて、本来のおのれ自身の姿を見失っているだけです」と。そしてまた従来の画壇の在り方や美術家たちの発表形式にも疑問を投げかけたのであった。
当時の美術界の熱気は今にくらべればはるかに高かったが、しかし岡本太郎のように画家自身によるこのこような発言はほとんどなく、きわめて鮮烈で刺激的であった。まだアンフォルメル(偶然性を生かした定形絵画)や読売アンデパンタン展を根城としたネオ・ダタ(六十年代の破壊的な美術運動、ガラクタ芸術ともいわれた)などもなかった頃である。そんな美術界の影響が大きかったのだと思う。次第に若い世代の画家たちも団体展だけにたよらず、個展やグループ展による発表に向かう者たちが増え始めていたのであった。 そういう気運のなかで誰でも自由に個展やグループ展を開ける画廊がぼつぼつ出来始めていた。その種の画廊では銀座中央通りにあった村松画廊や新橋駅ちかくの美松書房の二階にあった美松画廊、そして先にふれたサトウ画廊などか主な画廊であった。あとは日比谷公園入り口の日比谷画廊(河原温の「物置小屋の出来事」はここで発表された)や神田のタケミヤ画廊があった。タケミヤ画廊は滝口修造の人選なので一種特別な感じがあった。当時わたしは、たまたまこの近くにあった画材店にいったとき池田龍雄展の会期中だったので、偶然にも初期のペン画を見たのが記憶に残っている。そして美術雑誌も「美術手帖」「みずゑ」「美術批評」「アトリエ」「三彩」美術だけではないが「芸術新潮」と多彩であった。これらにはそれそれ月評欄があって、目だった個展やグループ展などは取り上げられ批評されていた。そしてそれは画家たちの励みでもあり、一種の登竜門のようなところもあった。
そんな時代の気運のなかで、わたしもその影響をまともに受けたのであった。そして自分なりに納得のいく作品も少しできたので、それを発表したいと思うようになったのであった。そんな気になったのも、それらの作品は…幼稚ではあるが、方法的にも自分を意識し自覚して制作したわたしの最初の作品群であった。方法的な自覚とは、単純な思考ではあるが世界や日本の現代美術を考えた上で、それらにのみ込まれることなく、自己に根差した造形を形成した…とそのときは思った一連の作品であった。そんな気持ちもあってか、おそらく何がしかの反応があるのではないか、と思っていたのでもあったが……しかし思い込みや予想とはうらはらに結果は惨澹たるもので、反応は皆無であった。それに時期も真夏ということもあって、見にくる人もまばらであった。わたしは意気込んでいただけに、そのショックはかなりのものであった……が、しかしそんなことより当時は当面の緊急の課題に、ちょうど卒業前後ということもあって、とにかく生きてゆく方途の方が差し迫った問題で、すべてが暗中模索の状態ではあったが、それでも何とか立ち直って二度目の個展にこぎ着けたのは四年後であった。けれども個展というものは何時でもそんなものであるということは、やがてだんだんわかってきた。むしろ、いきなり評価されたりして…そういうケースもときにはあるが、それはたまたま偶然にとか、時流に合っているとかいろいろあるが、まだこれからというときに一時的に注目されても、それをもちこたえるのは大変で、また美術潮流の変化は激しいので、あとが続かなかったり…そういうこともよくあるので、今から思うと、そんなわたしの状態は、自分のこれからにとっては、たいへんよいことだったのだ、ということを今ではつくづく感じている。
けれども、そのときの芳名録を見ると、若手批評家…針生一郎や瀬木慎一なども来ているし、当時はまだ無名であったが今から見ると、そうそうとした人達が見ているのを知るのだ。ずぶの新人なのにこれだけの人たちがきたということは大変なことだと今は思う。やはり時代の気運だったのだろう。画家や批評家もよく画廊をまわっていた。前田常作や加納光於、真鍋博…当時彼れは新進の油絵画家でイラストレーターではなかった…などのサインがあるのだ! なかでも会期中とくに印象深かったのは、絵の前で立ち止まっては一点一点見つめながら時間をかけて全体を見て帰った人がいた。わたしはその人の後ろ姿しか見えなかったが、いったい誰だろう、と思いながらその背中を眺めていた。帰ってから芳名録のサインを見ると特徴のある細い字で前田常作と書いてあった。当時はほとんど無名であったが、わたしは何かの雑誌…たぶん「美術批評」の月評で作品の写真を見ていたので名前は知っていた。飯田善国も高校の先輩ということもあって…年が離れているのでそれまで会ったことはなかったが…夫妻で見えて大変丁寧にそして熱心に批評してくれた。また、わたしの少し前にここで個展をひらいた芸大出の近藤竜男は、会場を見わたすなり多摩美はすごいな! といった。それがどういう意味かはさだかでなかったが、今でも記憶に残っている。
|
|||||
「負けること勝つこと(90)」 浅田 和幸 |
|||||
「人間存在の自覚の深まり」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部