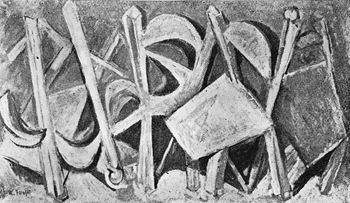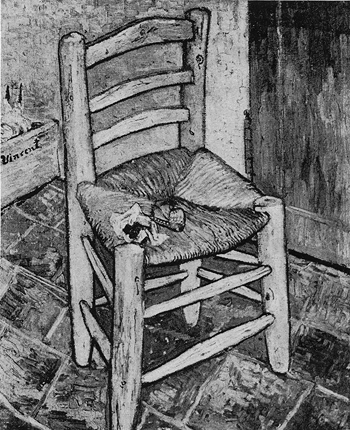第135号 |
|||||
| 2017年7月6日 | |||||
「問われている絵画(126)-絵画への接近46-」 薗部 雄作 |
|||||
たしか一九五五年だったと思う。多摩美の文化祭で今泉篤男と岡本太郎の講演があった。当時、今泉篤男は美術批評界の大御所であったが、どちらかといえば保守的? な批評家という印象があった。岡本太郎は前衛の闘士としてもっとも脚光をあびていた時期であった。対照的な二人でたいへん興味深い組み合わせであった。たぶん、そんな両極的な組み合わせに講演企画の狙いもあったのだろう。会場には大勢の学生たちがつめかけていた。そこで話された二人の話のくわしい内容はほとんど覚えていないが、岡本太郎は例によってすべてをぶち壊して新しいものを創造せよ、というような話だったと思う。壇上の、小柄ではある精悍な岡本太郎は輝いているように見えた。そして彼の語りかけてくる迫力…気迫に呑見込まれたかのように、わたしたちは静まりかえって聞いていた。講演が終わって司会者が何か質問がありましたら手を上げてください、というと誰かが立ちあがって、何かくいさがるような質問をしはじめた。すると途中で、あちこちから「やめろ!」という声が飛び交って、それは立ち消えになってしまった。あとは誰も手を上げなかった。何かが始まりそうなところで立ち消えになってしまったのが、少し残念だったのが記憶に残っている。次に今泉篤男の講演が始まった。こちらは話の内容も語る雰囲気も岡本太郎とはたいへん異なるものであった。ほとんどは忘れてしまったが、一つだけ今でもはっきり覚えているところがある。それは、ある箇所で「諸君はとにかく同じものを十年間続けて描いてみなさい。」そして「たとえば椅子なら椅子を十年間続けて描いてみなさい。」ということを力説していた。今から思うと、たぶん、多くの若者が時の流行に影響されて右往左往しているうちに、貴重な時間が失われてしまうことへの忠告が含まれていたのかもしれない。しかし若いわたしたち…わたしには、何かあまりぴんとこなかった。けれども、その椅子の話を語る身振りが印象的だったので、今でもその光景が目に浮かぶ。たしかに一つのものを長期間追求するということは、大切であり、また何かを生み出すこともあるかもしれない。けれども肝心なのはその一つのものに惹かれるということの方が先で、とくべつ興味もない一つのものを選んで、ただしゃにむに描くというのはどういうものだろう。重要なのは、なぜ、その一つのもの…たとえば椅子に惹かれたのか、そして描こうとしたのか、ということの方ではないのか、と。やはり、それは客観的な目で画家の制作を見た批評家の結果論のように思えたのであった。
たしかに美術史をながめると椅子を描いた画家はいる。すぐ思い浮かぶのはゴッホである。彼も、とりたてて目を引くようなものではない椅子を描いている。ふだん自分の使っている椅子である。同時期に「ゴーギャンの椅子」という作品もある。それらの作品を初めて見たとき、こんなものでも絵になるのだ! とわたしは思った。それだけでなく、そこには何か無限に深い、そして広いものがあるように見えた。たしかにゴッホやゴーギャンが使った椅子ということだけでも、その背後のドラマを感じて、わたしたちは特別の思いを抱くということはある。しかしそれだけではなく、絵画作品としての力と説得力がある。わたしは椅子など描こうと思ったこともなかったので、これを初めて見たとき驚ろいたのであった。
ここで椅子に関して思い出したことがある。わたしは多摩美に入学してしばらくのあいだ寮に入っていた。その寮は大井線の溝ノロ駅(当時は終点)から歩いて数分のところにあった。もと軍の倉庫? であったという三階建の大きな黒っぽい建物であった。二階部分が寮として使われ、三階はデッサンの教室としても使われていた。二階の寮には真ん中に廊下があり、それをはんで両側(南北)にいくつかの部屋があった。主に南側が寮として使わ沁ていたので、北側には空き部屋もあった。そして、そこは自由に使うことができた。かなり広い部屋であったが、窓が少ないせいか薄暗く、そして冬は寒かった。当時は暖房がなかったのだ。そんなことが理由かどうかはわからないが、使う者もほとんどいなかった。わたしは、たまたまその広い部屋を何度か使ったことがあったが、そのときにはいつもO君が一人で黙々と描いていた。しかしそのとき、わたしの目をとらえたのは、彼の描いているモチーフであった。そのモチーフというのは、わたしたちが三階でデッサンを描くときに使っている椅子……椅子とはいっても、板を組み会わせただけの小さな台のようなものである。わたしはその台を描こうなどとは思ったこともなかったので、それを真剣に描いているO君を見て驚いた。さらにわたしが眼を見はったのは、その何の変哲もない台が、あまり大きくはない画面であったが、画面いっぱい描かれ、そして台の木の肌が生々しく、異様な力があった。わたしは、こんなものでも絵になるのだ! と思った。そして、あらためて台を見なおしたが、やはり、それは何の変哲もないデッサン用の台である。しかしその台が、彼の目には、何かとくべつの物に見えていたように思えたのであった。それは彼の制作姿勢と作品が示していた。あるいはまた、彼も、その台を、ただ身近にあるものとして、とりあえずモチーフにしていただけなのだろうか。いずにしてもわたしは、その気迫に押されて…それだけの理由ではないが次第にその部屋へはゆかなくなってしまった。
|
|||||
「負けること勝つこと(91)」 浅田 和幸 |
|||||
「意味を問う自意識のことなど」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部