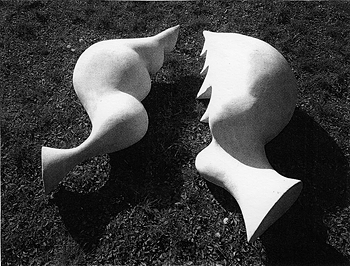第136号 |
|||||
| 2017年10月6日 | |||||
「問われている絵画(127)-絵画への接近47-」 薗部 雄作 |
|||||
同時期の岡本太郎に「テーマと造形」という文章があった。確かめると、それは「美術批評」の一九五六年一月号であった。わたしが個展を開いたのが一九五六年の八月だから、これを読んだのは出品作品制作のまっ最中の頃だったように思う。わたしは共感したり励まされたりしながら読んだ。このなかで岡本太郎は「今日の芸術でこのくらい厄介でまた未解決な問題はない」といい、この問題に「はっきり正しい答えを出した芸術論というものはまだ見当たらないようである。」そしてむしろ「この問題は二つに断ち割られている観がある」と。その二つとは「テーマ主義の写実絵画と純粋美を追求する抽象絵画である」。しかし双方とも理屈はあるにしても「どちらか一方に片付けてしまうのは簡単だし、大いに勇ましい」のだが危険である。「対立するものに食い下がって、相互にそれをのりこえ新しくより高次な段階に問題を進めて行かなければならない」。しかし「新しい芸術の担い手である多くの若い作家が、この二つの傾向の間に、どうしていいか解らないで茫然自失している」のであると。そして彼はいう「テーマ性と造形性は、芸術における永遠のジレンマ」であり「何か一つの作品を描こうと筆を持った、そのとたんにぶつかってくる最初の矛盾的課題でもあるのです。」「モチーフという言葉があるが、これは絵を描きたいという衝動があるとすれば、これがすでにモチーフ」で、そして「それがどういうものを描きたい、と限定された欲求があれば、さらにモチーフが明確化されていることを意味する。」しかし、それはあくまでも「個人の内的な衝動」であり、それが「テーマになるには、外部に伝達できるように客観化されなければならない」。ところで「なんといっても絵画は造形されるスペース」なので、テーマの単なる設計図や説明図ではなく、それを造形化しなければならない」。造形化するとは絵画化することだ。「ここにテーマと造形の問題が目の前にのっぴきならなくたちはだかる。」しかし「私は逆に、テーマ性と造形性を先鋭に引き離し、ぎりぎりのところで対決させ噛み合わせ、この矛盾的要素が猛烈に不協和音を発するようになって行きたい。相互の効果がともに殺されてしまう寸前、そして対決が最も緊張し、一瞬、怪しい幻惑的な光を放った瞬間を捉えるべきと思うのです」と。そして当時描いた「燃える人」という作品が掲載されていた。わたしはこの作品を当時も、また比較的最近も見たが、かなりの大作で力作である。それまでの岡本太郎のテーマと造形が全部ぶちこめられて一体化した集大成のような作品に見えた。一つの仕事が終わった? のかどうかはわからないが、それ以後はむしろ絵画作品よりも立体的な…空間のなかへ自由に形をつくる立体造形の方へ移っていったように見える。彼の爆発的なエネルギーは、やはり平面的な絵画に閉じ込められるには勢いがありすぎたのだろうか。それはわからないが、わたしはやはり、かつての絵画作品の方により愛着を感じる。
共感したり啓発されたりして読んだ「テーマと造形」であったが、わたしは岡本太郎とは人間も資質もまるで違う。まだ漠然としてではあるが、やろうとして向かっている方向も違う。岡本太郎のばあいは、つねに描く対象が、内的であれ外的であれ、明確に対象化されているので、制作にあたって必ずテーマが鮮明であった。それは彼の作品のタイトルを見てもわかる。たとえば「重工業」とか「森の掟」または「哄笑」や「燃える人」など、常に明確で鮮明である。だからそのテーマをどう造形するかということが、まず問題になるのだと思う。しかしわたしのばあいはどうか。そのように客観的で鮮明なテーマというものがない。むしろテーマは自己そのもので、そしてそれは、それ自体が何であるかということも、まだ未知のものであり、その未知のものを造形的に、どう探求してゆくのか、というのがテーマといえばテーマであった。
当時…一九五〇年代の美術の状況を思い起こすと、それは現在のように多様な表現やイズムもなかった。おおまかにいえば抽象絵画的な流れと、シュールレアリスム的な絵画の流れが主なものであった。もちろん当然従来の延長での描写的な絵画もあった。とにかくそのような状況のなかで、自分の方向をまさぐりながら、わたしは抽象絵画の流れの側から出発した。抽象絵画は具体的なモチーフがないので、とくに西洋的とか東洋的とかにこだわることもなく、より世界に共通した様式のように思えたのであった。とはいっても、シュール的な方法も頭のなかには住み続けていた。けれども、とにかくわたしは抽象的な絵画の側からまず出発した。そして単純な考え方ではあったが、具象絵画では、風景でも人物でも東西の違いが一目でわかる。だから西洋絵画を見習って出発したわたしたちの仕事は、その影響も一目瞭然である。しかし抽象絵画には自然の具体的な外形がないので、それにこだわることがなく自由に追求できる。たから自分にも、それなりに何かをつくることがきるのではないかと。そしてとにかく一から、もっとも単純なところから…線や面の簡単な組み合わせで、何かの形らしいものをつくり始めた。たぶんそこには、クレーの「最も単純なところから始める」という言葉の影響もあったと思う。そして、その単純な線や形は、できうるかぎり自分の心情にそったものでありたいと心がけた。
そんな試作を始めた頃であった思う。あるときふと「色環の法則」という考えが浮かんできた。このことはすでに何度か書いたこともあるが、簡単にいえば次のようになると思う。色環とは、ようするに虹の七色が、帯状の環のなかにそれぞれ区切られて配置されている図であるか、それがふと浮んできたのだ。そして思ったのだ。たとえばそのなかの青なら青が、他の色…赤や黄に影響されて混ざり、濁ってあいまいな色になってしまえば、それは赤としての存在が崩れてしまうだけではなく、色環自体の存在も壊れて成立しなくなってしまう。そしてそれは絵画の世界においても同様ではないか。といえるのではないか、と。つまり世界には多様な国々が存在しているが、またそこには、その国々に根ざした多様な美術が存在している。もし、それらの国々のなかのある国が、別の国の影響によって自国の伝統が混乱し曖昧になってしまえば、その国の特質が失われてしまうだけではなく、世界の国々の多様な美術の環も、崩れて貧しいものに…あるいは単調なものになってしまうのではないか。だからわたしたち個々も、自分という個の色を守り、いたずらにまわりの影響に迷わされることなく、あくまでもその個を深めてゆくことが重要なのではないか、と。
しかし心情にそってとはいっても、それだけでは形にならない。どう形を組み立てればよいのか。いろいろ模索はしていているが、なかなか内的一致感のある形までは、もう一歩というところであった。ちょうどその頃であったと思う。この一連の文章の初めにふれたリシュアン・クトーに遭遇したのは。すでに述べたようにクトーの作品は一見外界の風景のように見えて、どこかリアルで具象風にも見えるが、よく見ると、それは自然のままの風景ではなく、抽象的な断片の集合によって、風景や静物のようなものがつくられている。それはキリコなどとは違うが、ある意味では一種の形而上絵画のようなところがあり、その作品形成の方法が、何かヒントのようなものに思え、わたしも、自分なりに抽象的な断片を寄せ集め、そしてそれを、できうるかぎり自分の心情に密着したままで、何かの形をにまでもってゆきたいと思ったのであった。
|
|||||
「負けること勝つこと(92)」 浅田 和幸 |
|||||
「人間とはどのような存在なのか」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部