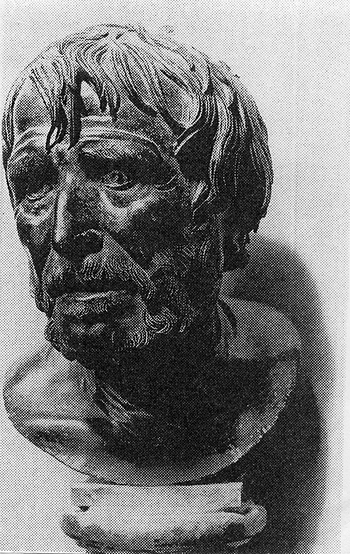第137号 |
|||||
| 2018年1月5日 | |||||
「問われている絵画(128)-絵画への接近48-」 薗部 雄作 |
|||||
学生のとき、石膏デッサンでいろいろな像を描いた。多くはギリシャ・ローマの神々や歴史上の有名人で、たとえばヴィーナスやアポロやヘルメス、アグリッパやブルータスなどで、みな堂々とした格調ある像が多かったが、そんななかにセネカという名前の像があった。それは他の像にくらべると小さく、そして妙にリアルな表情をしていて、わたしには描きにくかったのが記憶に残っている。そのときは、そのセネカという人物が、いったい何者であったのか、ということなどまったく考えずに、ただ目の前に置かれた像を描いていただけであった。
それから三十数年たってからだったと思う。新宿の紀伊国屋書店で何気なく文庫本の棚を見ていると、セネカの『人生の短さについて』という本が目に入ってきた。わたしは、かつての描きにくかった石膏像を思い出し、あの像の人物はいったいどんなことを考えていたのだろう、と思いながら手に取ってみたが、そのまま買ってしまった。 帰りの電車でページを開いてみると、冒頭いきなり「大部分の人間たちは死すべき身でありながら、パウリヌス君よ、自然の意地悪さを嘆いている」とある。そして「その理由は、われわれが短い一生に生まれついているうえ、われわれに与えられているこの短い期間でさえも速やかに急いで走り去ってしまうから」であると、人間共通の大問題に引き込んでゆく。そして「このように万人に共通な災いに嘆息するのは、一般の大衆や無知の群集だけではなく、著名な人々にさえも、このような気持ちが嘆きを呼び起こしている。」だから「医者のなかでも最も偉大な医者の発言がある。生は短く術は長し」と。「それゆえにこそアリストテレスも自然を相手にして、賢者にはふさわしくない告訴を行っているのである」。すなわち「寿命という点では、自然は動物たちに人間の五倍も十倍も長い一生を引き出せるようにしておきながら、数多くの偉大な仕事のために生まれた人間には、遥かに短い期間しか存続しない」からであると。そしてセネカはいうのだ。「われわれは短い時間を持っているのではなく」じつは「その多くを浪費しているのである」と。「人生は長く、その全体が有効に費やされるならば、最も偉大なことをも完成させるほど豊富に与えられている」のである。「けれども放蕩や怠惰のなかに消えてなくなるとか、どんな善いことのためにも使われないならば、結局最後になっていやおうなしに気付かされることは、今まで消え去っているとは思わなかった人生が最早すでに過ぎ去っていることである」と。
セネカを読んでいると、彼が時間についてしばしばそして執拗に語っているのにわたしたちは気がつく。時間といっても、それは物理的な時間…一般的にいう時間のことではなく、人間の持ち時間についてだ。『道徳書簡集』も「時間の節約について」という章で始まっている。そこでも冒頭いきなり「ルキリウス君。君はこうなさったらよいでしょう……自分自身のために自分を自由にし、今までに君から奪い去られ、盗み取られ、あるいは逃げ去った時間を拾い集め、それを守ることです」と。ルキリウス君とは、セネカの友人のようであるが、しかしセネカの文章は現代のように注文によって書かれたものではなく、ほとんどが誰かに当てて書かれた手紙のかたちをとっている。そしていう「次に書くような僕の言葉の真実を、ご自分に説得してください。或る時間はわれわれから裂き取られ、或る時間は運び去られ、ある時間は流れ去る。」そしてまた「よく気をつけて見るならば、人生の最も大きな部分が良からぬことをしている間に、またその大きな部分が何もしていない間に、また人生の大部分が、何かつまらぬことをしている間に、消え失せていることがわかるでしょう」。まったく、自分のことを考えても、時間に対して実にいいかげんに過ごしているのに気がつく。あるときは時間がたりないと言っているかと思うと、こんどは時間を持て余している。そして、そうこうしているうちに数年はまたたくまに過ぎている。「君は誰を僕に教えてくれるでしょうか……いやしくも時間に何らかの価値を認める人を、毎日毎日を重んずる人を、自分が日々死につつあることを知っている人を」と。「死を遠くに見るなどと思ったら大間違いです。死の大部分はすでに通り過ぎてしまっているのです。」そして「どれだけの年月が残されていようとも、死がそれを支配しているのです」。それゆえに「君は現に自分で行っていることを行い」「毎時毎時をしっかり抱き締めることです。」「君が今日のことに手をかけているならば、明日のことには余り頼らなくなるでしょう。愚図々々している間に人生は走り過ぎ去って行くのです」。
「ルキリウス君、あらゆるものは他者のものですが」このまたたくまに「過ぎ去り、滑り去って行く一つのものを所有する」ために「自然はわれわれをこの世に送り込んだのですが、人間どもは愚か者ですから」これを「いったん手に入れると、それらが自分たちに委託されたものと認めるほどです」。しかし「自分がその大切なものに恩を被っていると思っている者はないでしょう。けれども時間だけには、それに恩を感じている人でさえも恩返しの出来ないものです」。そしてたぶん「このようなことを君に言う僕が、では一体どんなことを実行しているのかを尋ねたいでしょう。」それでは「正直に白状しましょう。たとえば贅沢ではあるが勤勉な人間に見られるように、僕の会計の比率は釣り合いを保っています」。セネカは時間についてしばしば浪費とか貧乏とか会計という言い方をする。「僕はなにものにも浪費しない」とはいえないが「少なくとも僕が何を、何ゆえに、どのように浪費しているかを話すことは」できます。そして「僕の貧乏の原因を報告することはできる」が、「しかし僕の場合は、自分の落度で窮乏に陥ったのではない多くの人々の場合と同じ結果」になっています。たとえ自分の落ち度によって時間が窮乏しても、「誰もみな落ち度は許してくれるが、助けに来るものは一人もいません」。 「ではどうでしょう。どんなに少ないものでも本人に残っていて、それだけで十分な限り、僕はその人を貧乏とは思いません」。そしてルキリウス君にいう「君が真に君自身のものを固く守り、良い時期を見て始めることを望みます。」というのも「節約も底をついてからではもう遅いのですから。つまり底には最小のものが残るだけではなく、最悪のものが残るからです。ではお元気で。」
『道徳書簡集』にも「人生の短さについて」という同じタイトルの章があるが、ここでは人生を点に…さらに瞬間としてとらえている。「われわれが生きている時は一つの点に過ぎません。いや、点よりももっと小さいのです。」それなのに「自然は、この最小のものを言わば外見上は、長い時間の間隔のように欺いているのです。」つまり「このなかの一部を幼年期とし、一部を少年期とし、一部を青年期とし、一部を青年期から老年期への言わば変動期とし、さらに一部を老年期とさえしました」「なんと、そのような隘路といったところに、どれほど多くの階段をおいたことでしょうか」そして「つい今しがた君のお供を僕はしたばかり」ですが、しかしこの「つい今しがた」は「われわれの生涯のかなりの部分」ですが、「その短さのゆえに、いつかは尽き果てることになると考えねば」ならない」。かつては僕は時がこんなに短いものとは思いませんでした」が、「今は信じられないほ速いものであることがはっきりわかります」。その「原因は、僕が限界線に近付けられていることを感じているためか、あるいは僕が自分の損害に気付いて、それを数え上げ始めたためです」。
セネカは約七十年の生涯において実に多くの仕事を成し遂げている。政治家であり、悲劇作家であり、哲学者であり、自然研究者であり、さらにネロの家庭教師でもあった。政治家としては「財務官の地位を得、元老院に入り、元老院並びに法廷での弁論によって名声を獲得」したという。劇作家としては十篇の悲劇作品がある。哲学者としては『道徳論集』や『道徳書翰集』がある。『自然論集』では地球上のさまざまな現象や地形について、また宇宙についてまで述べられている。また若きネロの「養育係であり教師」でもあったという。さらに、にもかかわらず決して頑健に体ではなく、どちらかといえば病弱であったようである、ということは自身も語っている。『道徳書簡集』には「呼吸困難について」という章もあり、そこでは自身が喘息に悩まされていたことが書かれている。
|
|||||
「負けること勝つこと(93)」 浅田 和幸 |
|||||
「科学の時代と今後」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部