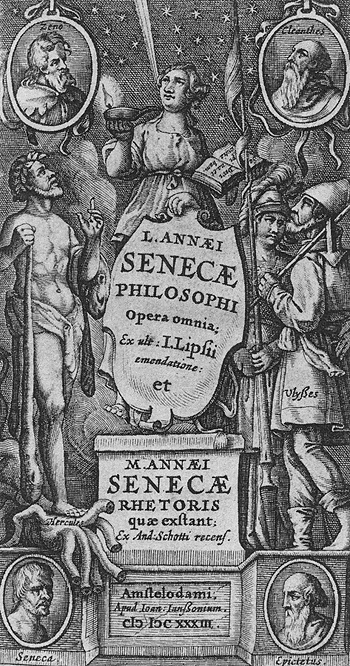第138号 |
|||||
| 2018年4月12日 | |||||
「問われている絵画(129)-絵画への接近49-」 薗部 雄作 |
|||||
セネカは『道徳論』と『道徳書簡集』を残している。双方とも茂手木元蔵訳であるが、はじめにふれた文庫本のなかの「人生の短さについて」は『道徳論』のなかに入っているが、あとからふれた「人生の短さについて」は『道徳書簡集』に入っている。どちらも茂手木元蔵訳であるが、訳者にふれたのは、訳者の違いによって文体や息遣いが微妙にちがうように思うからである。そしてわたしには茂手木元蔵訳がもっともスムースにこちらに入ってくるように思えるからである。
『道徳書簡集』の「時間の節約について」の次には「読書の散漫について」という興味深い読書論があり、これもルキリウス君にあてて書かれている。「僕は君に対して良い期待を抱いています」。なぜなら「君はあちこちへと走り回らないし、よく居所を変えて自分の気持ちを煩わすこともありません。そんなことは病める心の動揺です」。そして次のようにいう。「よく整えられた精神の第一の証拠は、しっかり立ち止まって、おのれ自らとともに静かに落ち着くことの出来ることだと考えます」。しかし「君の注意すべきことは、そのように沢山の著者やあらゆる種類の書物を読むことは、えてして散漫な不安定な何かをもたらすことだけです」という。「それよりも定評のある天才人に深く立ち入り、養育されねばなりません……もし君が、心の中に確実に定着する何ものかを引き寄せんと望ならば」。そして「どこにもいる人間はどこにいない人間です。外国旅行で生活を送る人たちは、結局のところ多くのもてなしは得られるでしょうが、真の友情は得られないことに成でしょう」。そして「これと同じ結果になるのが、いかなる著者の才文にも親しくわが心を傾けることなく、あらゆるものを駆け足で大急ぎで通過してゆく者たちです」。「食物でも、それが摂取されるやいなや直ちに吐き出されるならば何の益にもならないし、体の栄養にもなりせん」。「何か体の回復を妨げるかといって、しょっちゅう薬を変えてばかりいることが一番悪いのです」。樹木でも「しばしば移植されれば大きくなりません」。「通り過ぎながら役立つものは、それほど有益ではありません。」そして「沢山の本を読むだけ心は散漫になります」。
だから「自分の持てるだけの本全部を読むことが出来ない以上、君は読めるだけの本を持つことだけで十分です」。しかし「でもあろうが、と君は言われる」そして「わたしは、今この本を開き、次にはあの本を開く、というように読みたい」と。セネカは言う「選り好みのひどい胃というものは、いろいろの食べ物を試し食いしたいものです」「ですが、食べ物は種類も数も多く食べると、害にはなっても栄養にはなりません」。だから「定評のある書物を君は常に読むべきです」。そして「もし他の本に転じたいと思ったならば、以前に読んだ本に戻りなさい」という。ここで急に転調し「君は日々、貧困に処すべき何らかの助けを、また死に処すべき、さらにその他もろもろの不幸にも処すべき、同様の何らかの助けを用意しておくべきです」と。そして、また戻って「多くの考えにざっと目を通した後では、ただ一つ選んでその日のうちに消化しなさい」。このことを「僕自身も実行しています」。「今日掴んだことは、たまたまエピクロスの本の中で見つけたことです」。「僕は敵方の陣営にさえも入り込むことを習わしとしているのですから……ただし投降者としてではなく、偵察者としてです」と。敵方とは、たぶんエピクロスは快楽主義者として知られるが、セネカはむしろ苦行者のイメージがある。そしてエピクロスの「楽しい貧乏ということは立派なことだ」という言葉をあげ、「貧乏が楽しかったら、それは貧乏ではありません。貧乏なのは過少を有する者ではなく、過大を求める者なのです」。そして「富の限界は何なのか、と尋ねられるのですか。それは第一に必要な物を、そして第二に満足するものを持つことです」と。
読書論は古今に無数あると思うが、わたしはほとんど読んでいないので詳しく知らない。そんなわたしの、わずかかに読んだもののなかで興味深かったのはショーンハウアーの『読書論』であった。ショーペンハウアーはその『読書論』で、「いかに数量が豊かでも、整理がついていなければ蔵書の効用はおぼつかなく、数量が乏しくても整理の完璧な蔵書であればすぐれた効果をおさめる」という。これは書物だけではなくいろいろなものに当てはまると思う。たとえば衣服などにも。そして、これは「知識のばあいにも事情はまったく同様である」と。「いかに多量にかき集めても、自分で考えぬいた知識でなければ価値は疑問」である。そのかわり「量では断然見劣りしていても、いくども考えぬいた知識であればその価値ははるかに高い」と。自分で考えぬいた知識とはどのようなものであろう。彼はいう「なにか一つのことを知り、ひとつの真理をものにするといっても、それを他のさまざまな知識や真理と結合し比較する必要」があるからである。そして「この手続きを経て初めて、自分自身の知識が完全な意味で得られ」るのであり、そしてその「知識を自由に駆使することが出来るからである」と。なぜなら「我々が徹底的に考えることが出来るのは、自分で知っていることだけである」からである。
セネカやショーペンハウアーの読書論を読んだのは五十歳を超えてからであった。学生のころは、せいぜい美術雑誌や美術書などを少し読む程度であった。どちらかといえばあまり本を読まない方であった。中学生のころは、同級生のなかには、休み時間になると教科書とはちがう厚い何かの本…たぶん小説などを読んでいる生徒もいたが、そういう生徒を見ると、自分とは違う何か一種とくべつな知的雰囲気を感じていた。それでも絵本や漫画本は少しは読んでいた。そんななかで今でも記憶に残っている本がある。それは小学生の時だっだろうか。友人と近くの神社の祭りにいった時のことだった。そんなときには神社の周辺にはさまざまま露店が並んでにぎやかだった。そんななかに雑誌やマンガ本などだったと思うが、それらを地面に並べて売っているところがあった。わたしは特に選んだわけでもなかったが、そこで二冊のマンガ本を買った。一冊は忘れてしまったが、もう一冊は今でも覚えている。それは『クロガネ太郎』という題名で後になっても何度か読んでいる。あらすじは、ある日、天から流れ星が落下する。それが地上にすっと立って、わたしはクロガネ太郎だと宣言する。今風にいえば鉄のロボットで、四角っぽい胴体に角ばった頭と腕と足がついている。しかし特徴的なのは両腕の手首…指の部分が強力な磁石になっているのだ。その磁石でいたるところ…工場や家庭のあらゆる鉄製品を吸いつけ、奪ってゆく。そのために工場や家庭の鉄製品はことごとく失われてパニック状態になる。今でも記憶に鮮明なのは、大きな川にすっくと立ったクロガネ太郎が、鉄橋を通過する電車を橋もろともに両手の磁石で吊り上げ、くしゃくしゃに折れ曲げて破壊していゆくシーンだ。そんな緊急事態に国は軍隊を出動してクロガネ太郎を攻撃する。しかしクロガネ太郎は両手の磁石で武器…ほとんどが鉄である大砲や機関銃などをことごとく吸いつけ奪ってしまう。やがて国は空軍を出動させて八方から銃撃や爆弾を投下しする。しかしクロガネ太郎は飛び交う飛行機を両手でわし掴みしてたたき落とす。けれども、やがてさすがのクロガネ太郎も猛攻撃に重傷する。次のシーンも記憶に鮮やかだ。磁石でどこからか溶接工を吸いつける。そして肩に乗せて傷…破損を修復させる。その溶接工のいでたちが印象的だ。何か鉄のマスクのようなものを頭全体にすっぽり被っている。今から思えばそれは溶接の強烈な火炎を防ぐためのものだが、それが異様に見えた。溶接工は不本意ながらも仕事をするが、しかしそこでクロガネ太郎に何かお説教のようなことを言う。やがて元に戻ったクロガネ太郎はまたもや戦い始める。そして飛行機や武器を、さらに爆弾までやみくもに掴み取って食ってゆく。クロガネ太郎の食物は鉄であるのだ。しかし満腹した武器や爆弾が体内で突然爆発する。クロガネ太郎は破片となってあたりに散乱し、終わる。
今から思えば……当時は戦争中だったので、あるいは社会的な何か風刺のようなものがあったのかもしれない。しかし子供のわたしは何も考えない。ただマンガの世界に引き込まれて何度も読んだ。作者もまったく知らない。しかし今あらためて読んでみたい一冊だ。
|
|||||
「負けること勝つこと(94)」 浅田 和幸 |
|||||
「組織の論理と人間存在の小ささ」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部