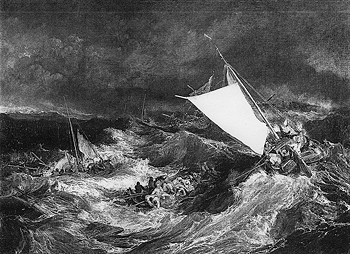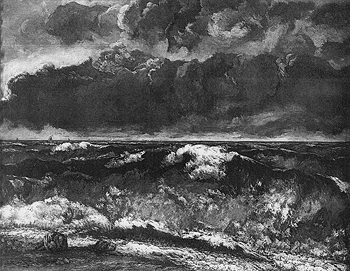第140号 |
|||||
| 2018年10月16日 | |||||
「問われている絵画(131)-絵画への接近51-」 薗部 雄作 |
|||||
たしかに現実の海は想像の海を打ち破る大きな力がある。しかしまた、海は想像のなかでも自由にはぐくまれているように思う。それは描かれた海だ。記憶をたどると、わたしのなかにも二つの海の光景が浮かんでくる。クールベの「波」とターナーの「難破船」だ。どちらも穏やかな海ではない。「波」は荒れ模様の空と海岸に打ち寄せる大波が描かれ、「難破船」は荒れ狂う波に今にも呑み込まれるかに見える難破船が描かれている。なぜこのような絵が浮かんでくるのかはわからない。いずれにしても印象が強かったのだと思う。
萩原朔太郎は『月に吠える』の初版の序文に「詩の表現の目的は単に情調の情調を表現することではない。幻覚のための幻覚を描くことでもない」また「同時にある種の思想を宣伝演繹することのためでもない」といっている。そして「詩の本来の目的は寧ろそれらの者を通じて、人心の内部に顫動するところの感情そのものの本質を凝視し、かつ感情をさかんに流露させる者である。」そして「詩とは感情の神経を掴んだものである。生きて働く心理学である」という。 そして「すべてのよい叙情詩には、理屈や言葉で説明することの出来ない一種の美感が伴う」そしてこれを「詩の匂い」という。この「匂いは詩の主眼とする陶酔的気分の要素」であり「この匂いの希薄な詩は韻文として価値のない」ものである。「言わば香味を缺た酒のようなもの」であり「こういう詩を私は好まない」と。たとえば『月に吠える』には次のような詩がある。
半身は砂のなかにうもれていて それで居てべろべろ舌を出している。 この軟体動物のあたまの上には 砂利や潮みずがざらざらざらざらながれている ながれている ああ夢のようにしずかにながれている。
「くさった蛤」という詩の前半であるが、これを読んだのも二十代前半の頃だったと思う。有機的で生理的な感覚がじかに伝わってきて不思議な快感があった。そして、それは以前リシュアン・クトーにふれたときにも書いたが、描かれたすべての事物にどこか生き物的にものを感じたのであったが、クトーの場合は造形なので事物の形自体に…それがたとえ生物ではなくても、生き物的なものを感じたのであった。しかし朔太郎の場合は詩なので、言葉の集合形態そのものに、やはりどこか生き物的なものを感じ、それが朔太郎独特の詩の世界を醸し出しているように思えたのであった。後半は次のようにつづいている。
ながれてゆく砂と砂とのあいだから 蛤はまた舌べろをちらちらと赤くもえいずる この蛤は非常に憔悴(やつ)れているのである。 みればぐにゃぐにゃした内臓がくさりかかっているらしい それゆえ哀しげな晩かたになると ちら、ちら、ちら、ちらとくさった息をするのですよ。
それに病的な情景もよく出てくる。健全や健康よりも病気の方が詩的なのだろうか。朔太郎には「詩人の風貌」という文章があり、そのなかで「ちかごろの若い詩人はスマートで知識人らしくなってきたが、それだけ世俗の常識人に近く、真の詩人らしいところが、ほとんどなくなってしまった」と嘆いている。そして詩人の風貌を特徴づけるものとして「超族的高貴性、卓抜性、放浪性、不き性。瓢逸性、神経性、憂鬱性、聡明性、偏執狂、感情過敏性、狂熱性」であるという。見わたしたところ大方の特徴が一般社会ではあまり歓迎されそうもないものばかりだ。しかしなぜこのような特徴を持たなければならないのかといえば、詩人は「常に美の幻影を求めて、夜のイメージのなかを往来しているので、夢の世界の地形や風習には慣れ親しんでいる」のだが「白昼の意識や理性の支配するただなかにおかれると、夢の世界と全く違う法則で成り立って現実のごつごつした不慣れな地形が歩行をつまずかせ、ことごとく夢を破壊してゆくので、詩人をたえがたい思いに導いてゆくのである」そして「詩をつくらないときの詩人、白昼の意識を回復しているときの詩人は、穴をはい出した土鼠のようなものである」と。しかし詩人も人間であるので「不可避的に白昼の世界にも出現していざるをえない」。けれども「そんな事情が詩人の表情にそのような特徴をきざみ込むのである」と。次のような作品もある。
ながい疾患のいたみから その顔はくもの巣だらけとなり 腰からしたは影のように消えてしまい 腰からうへには藪が生え 手が腐れ 身体いちめんがじつにめちゃくちゃになり ああ けふも月が出て 有明の月が空に出て そのぼんぼりのゆうなうすらあかりで 畸形の白犬が吠えている しののめちかく さみしい道路の方で吠える犬だよ。(「ありあけ」)
以前わたしは安藤一郎の「現代文学における詩の位置」にふれたことがあるが、そこで彼は詩というものを外側から批評的…客観的にとらえようとしていたようであったが、もちろんそれは「現代文学における詩の位置」という批評文なので当然であるが、朔太郎は詩人なので、詩を内側…つくる者の側からとらえている。「私の詩の読者にのぞむ所は、詩の表面に表れた概念や「ことがら」ではなくして、内部の核心でもある感情そのものに感触してもらいたい」。それは[私の心のかなしみ][よろこび][さびしみ][おそれ]その他言葉や文章では言い現しがたい複雑した特殊の感情を、私の自分のリズムによって表現する」のである。
かといって白昼の詩人は、ただ「穴をはい出した土鼠」としてだけ存在しているわけではない。こんどは「そこで遭遇する現実という避けがたい境遇について懐疑を提出するようになるのである」。それゆえに「詩人の一面は常に必ず哲人としての、あるいは思想詩人としての風貌を持つようになるのである」と。たしかに、哲人朔太郎は、たんに現実のあれこれを懐疑したり考察したりしているが、それけではなく「夜の詩人」に対しても鋭い批評の目を向けている。さらに同時代の詩の現状や、西洋移入一辺倒という当時の日本の特殊な環境における詩の可能性についてまで、じつに多角的に精密に考察している。『詩の原理』がその理論的集大成であった。
|
|||||
「負けること勝つこと(96)」 浅田 和幸 |
|||||
「俳句について」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部