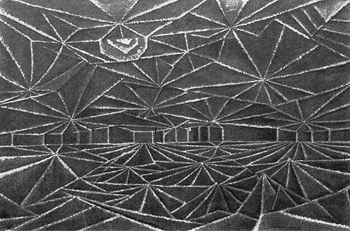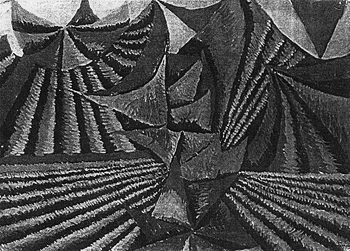第141号 |
|||||
| 2019年1月9日 | |||||
「問われている絵画(132)-絵画への接近52-」 薗部 雄作 |
|||||
最初の個展が終わったあと…一九五六年から五七年にかけてのしばらくのあいだ、わたしはきわめて宙ぶらりんの状態であった。ちょうど卒業前後とも重なる時期でもあった。個展のための制作にのめり込んでいたのはよかったが、卒業後の生活に対する何の準備も努力もしていなかった。当時は今とはちがって大変な就職難の時代であったので、美術大学などを出ても、それを生かせるような仕事などほとんどなかった。同級のなかには、かなり意欲的なよい作品を描いていた者もいたが、卒業後はそれを続けるという生活の基盤もなく、やむなく田舎へ帰っていった者もいた。わたしも、何かしなければと思って、いくつか面接のようなものをしてみたが、当然のようにすべて不採用であった。しかし、とにかく何かアルバイトでもやらなければと思っていたところ、たまたま近所を歩いていると募集の貼り紙広告が目についた。さっそくそこを訪ねてみると、その仕事というのは、細長い小さな<こけし>のような形をした楊子? の頭の部分にきまった色を塗るごく簡単な仕事であった。一本いくらだったか忘れたが、途方もない安さで、時間と労力を思うと、とてもできるものではなかった。近所の主婦があいた時間を利用してたとえわずかでもよいから収入を、と思ってやる仕事のようであった。またあるとき新宿の街を歩いていると琥珀という喫茶店に募集の貼り紙があるのが目についた。とにかく聞いてみようと思って店に入った。すると誰も客のいない薄暗い店内の奥から従業員…若者が出てきて対応してくれた。そのときのこまかい話の内容は忘れてしまったが、彼は、その仕事をわたしにすすめないのであった。できるならあなたは、このようなことはやらないで…わたしは絵を描いているということを言ったかどうかは覚えていないが、今自分のやっていることに専念したほうがよい、というようなことを丁寧に諭すように言うのであった。それは自分の体験をまじえての話でたいへん説得力があったので、わたしもそのアドバイスにしたがって、そのまま外に出たのであった。
それからしばらくは自分の狭い部屋に籠ってくすぶっているような日が続いた。そのころ住んでいた部屋は六畳の間借りで、以前の三畳よりは広かったが、窓を開けても庭はほとんどなく、目の前も両隣も人家の壁でふさがっていて開放感というものがない。部屋にこもっている一日はとても長く、それをどうやり過ごすかが問題の大変な日々であった。そんな閉塞状態のなかで、かろうじて気分転換となったのが、新宿の風月堂へ行くことであった。京王線の代田橋に住んでいたので新宿は近かった。午前十一時までに店に入ると三十円で二時までが五十円であったので、午前中に行くことが多かった。ちなみに当時のコーヒー代は一般に七十円というのが普通であった。最初は友人に誘われて行ったのだったが、こんな店があったのだ! と思ったものだ。ドアを開けて入ると、いきなり天井の高い何の仕切りもない空間がひろがっていた。壁面には絵画が…抽象絵画の大作が個展のように展示されている。入り口から入った正面の壁には大きなスピーカーが二つはめ込まれ、たえずクラシック音楽が鳴り響いていた。側面の棚には膨大なレコードコレクション(当時はCDなどなくLPレコードの時代であった)があり、それが客のリクエストによってかけられていた。その音楽も当時多くみられたいわゆる名曲喫茶とは少し違った選曲であった。
入るとすぐレジがあって、そこには「RECORD CONCERT」という店の月報が置いてあった。それは見開きになっていて、裏側にはその月の購入レコードの記載されている。開くと詩人や音楽評論家などの詩や短文があり、あとはその月おこなわれるレコード コンサートの日時が記されている。今わたしの手元には、たまたま当時の月報…1958年9月と11月がある。先ほどの話からは2年ほど後になるが、11月の号には店主・横山氏の文が、9月の方には椎名麟三の文が載っている。11月号の横山氏は「あなたはどんな音楽が好きか」とよく質問されるが「私はこと音楽に関する限り観賞できる」のだが、「といって秋の夜長の今日とは申せ、ブラームスやチャイコフスキーのシンフォニーで折角の秋の夜を楽しもうとは思わないし、難解な十二音階やミュージック・コンクレートで折角の夜を楽しもうとは思わない」といって、好きな音楽をいくつが並べている。先ず「グレゴリアン・チャント」ラテン語でまるで朗読の様に自由に歌うこの曲に「身が沈めらる思いがする。次にヴィタリ「シャコンヌ」コレルリ「ラーフォリア」クープラン「ハープシコード協奏曲」 テレマン「ターフェル・ムジーク」そしてヴィヴァルディ「四季」 バッハ「オルゲルビユッフライン」そして風月堂はいつもバッハ、バッハと冷やかされるといい「だがともあれ気品と敬虔にみちたこのオルガン曲は素晴らしいと。たしかにいついってもバッハはよく流れていた。そしてハイドン「弦楽四重奏・雲雀・日の出」 モーツァルト「嬉遊曲」などを上げ「私の好きな音楽はバロック以前と言うことになりそうだ。それにしても聴かない曲のいかに多いことか」そして「せめて多くの人にでもとセッセとライブラリーを拡げているが、肝心のリクエストはあまり私の希望に達してくれていないようだ」と書いている。 次に(展示作品)の案内があり、この月は前半が赤穴桂子展で後半が牛玖健治展と記されている。 つづいてコンサートの案内で、2日(民族音楽…カタロニアのサルダーナ)、9日(ジル…鎮魂ミサ曲)、16日(ショスタコヴッチ…交響曲NO11)、23日(ジャヌカン…シャンソン集)、30日(ドホナーニ 童謡の主題二夜変奏曲)となっている。なおPETITE CONCERTが毎週土曜日の午後二時にあり、この月はロマン派音楽特集として、ブラームス、メンデルスゾーン、シューマン、リスト、ブルックナーが記されている。さらに特別コンサート24日午後八時に”最近の前衛音楽” メシアン「異国の鳥たち」 シュトックハウゼン「五木管の為のツァイトマッセ」 チュウ・ウェン・チュン「ランドスケープ」となっている。
ちなみにこの月のLP新盤購入として64枚が記されている。内容はクープラン ルソン・ド・テネブル」、ゲスアルド「マドリガル宗教音楽」、テッサリーニ「フルート奏鳴曲」、ボンチーニ「フルート嬉遊曲」、バッハ「マグニフィカート」、ほぼ年代順に記されているが(多いので中間ははぶく)そして最後の五枚がグランジャニー「舞曲」、「スカンジナヴィアの歌」、「現代作曲家ピアノ曲集」、チフラ「リスト・リサイクル」 デュプレ「オルガン・リサイタル」となっている。すくなくとも当時の数年間はほぼこの購入パターンが続いていたように思う。
店に来ている大人たちにも特徴? があった。とくに午前中は常連のような人も…そして一人で来ているような人たちも多く、それぞれ音楽が目当てのようで、うるさいほどの話し声もなく、静かで自由な雰囲気が居心地よかった。そのような雰囲気が気に入ったのか…仕事がしやすかったのか、ひところ作家の吉行淳之介が隅のテーブルで執筆しているのをよく見かけた。 そんななかで、いつも来ている人の何人かの知り合いもできた。そのなかの一人は、どこかの大学の事務の仕事をしているようであったが、毎月の給料のなかから……当時は普通一般の収入に対してLPレコードの二千円という価額は高価であったが、毎月何枚か購入していたようである。しかし彼の購入予定のメモを見ると、すでに何年分も記されているのであった。わたしは一度彼に呼ばれて、そのレコードを聞きに府中まで行ったことがある。たしかマーラーの第4シンフォニーの新譜であった。
|
|||||
「負けること勝つこと(97)」 浅田 和幸 |
|||||
「これからの地球社会の運営理念」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部