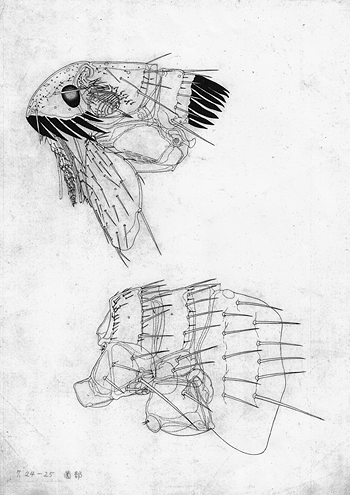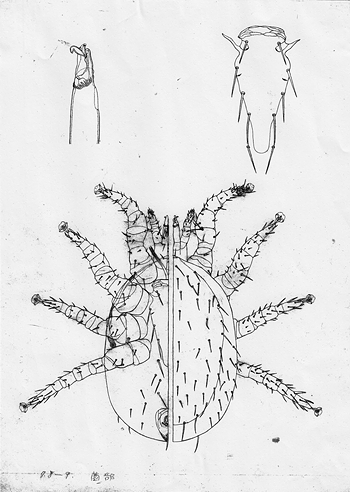第142号 |
|||||
| 2019年4月3日 | |||||
「問われている絵画(133)-絵画への接近53-」 薗部 雄作 |
|||||
とにかく風月堂にきていると少し落ち着いた気分になれるのであった。 そんなある日、店を出て近くの道を歩いていると、以前に友人の家で何度か会ったことのある女性とすれ違った。思わず手をあげて声をかけると、驚いて飛び退いたのには、こちらの方が驚いた。たしかに街の中で見知らぬ人にいきなり手を上げて声をかけられれば驚くのは当然であるが、しかしすぐにわたしだとわかって安心し、少し立ち話をした。そのとき彼女は、結婚するので今までやっていた仕事をつい先日やめたばかりだという。そして、もし今何もやっていないのだったら行ってみたならどうか、といって場所と名称を教えてくれた。それは小田急線の相模大野駅の近くにある米軍病院の敷地内にある406医学研究所というところであった。さっそく連絡してみると、来てくださいということで、わたしは明くる日…たぶん明くる日の朝だったと思うが、行ってみた。初めて降りた当時の相模大野の駅前広場は商店も少なくガランとして、あちこちに英語の看板が目につく、どこか殺風景? な印象であった。その広場を通過して道路をしばらく行くと、まもなく垣根に囲まれた広い敷地の米軍病院の前に着いた。ゲートで簡単な手続きをして事務室の方へゆくと…といってもゲートから事務室まで行くのにはかなりの距離があった。まず突き当たりの病院に入り長い廊下を通過して、いったん外に出る。するとそこは大きな松の木が何本もある広い芝生になっていた。その芝生を通り抜けてようやく406医学研究所のビルの前に到着した。 406医学研究所というところは、米軍の医学班が極東地域の病害虫を研究しているところであるという。そこには病理学とかその他いろいろなセクションがあって、それぞれ学者や助手が仕事をしていた。そしてそのなかに昆虫分類学というセクションもあった。そこには昆虫…病害虫を研究する学者たちと、それとは別にその昆虫の絵…図を描く人たちがいて、七・八名の画家たちが仕事をしていた
事務室で簡単な手続きをしたあと、すぐに仕事部屋の方へ案内された。しかし、そこは406研究所のビル内ではなく、その手前の、先ほど通過してきた長い廊下のあった病院内の一室であった。この建物は、たぶん戦前から日本の病院として使われていたのではないかと思われたが、何故かその一室が画家たちの仕事部屋となっていた。その部屋の近くには院内の教会とその向かいに売店があった。普段は誰もいない薄暗い教会と、明るい店内に色鮮やかに並べられた豊富な商品…だぶん食料品や雑貨類だったのだと思うが、それが対照的でもあり、また当時のわが国の街のなかではついぞ見掛けない光景でもあったので、それが印象的で記憶に残っている。今から思うと、それは現代日本のいたるところにあるコンビニの店内に似ていたような気がする。
ここでも簡単な受け答えがあったが、それではとにかく、今日はテストとしてこれを描いてください、といってテキスト…すでにここで描かれた印刷物を渡され、これを模写してくださいといわれた。それは細い毛筆の線によって描かれたダニの細密な絵であったが、わたしはそれを見て一瞬たじろいた。というのも、わたしは毛筆というものがもともと苦手であった。なよなよした細い筆先を紙に当てて、いざ書こうとすると、とかく手がふるえやすい。筆がスムースにはこばないのだ。小学生のときの習字の時間にも、大きな文字はなんとか出来ても、細い筆で書く名前の部分で失敗することが多かった。緊張すればするほど筆先がふるえやすい。しかし今はそんなことはいっていられない。とにかくそれに取りくんで夕方までになんとか描き上げた。それは後になってからも見ていないので、どんな出来だったかはわからなかったが、しばらくしてから採用の通知が来た。
最初の三か月は練習期間となっていた。それはテストのときに描いたような、すでに描かれている図を模写することであった。模写をすることによって、なによりも筆の線による細密描写に慣れることであった。ここで、なぜペンではなく筆なのか? と疑問に思うかもしれない。ペンの方が筆のなよなよより安定していて描きやすのではないか、と。たしかに文字や簡単な形ならそうかもしれない。しかし昆虫の入り組んだ構造の細密描写には、筆のほうがはるかに自由で描きやすいのであった…掲載図はその練習期間に描いたものであるが、これはすでに描かれた図の上にトレシングペーパーを当てて、それを鉛筆で正確に写し、その鉛筆の線の上を毛筆でなぞって描いたものである。これもやっているうちに次第に慣れてきた。そしてそのときわたしは思った。自分にとって苦手であると思っていたものでも、それを無理にでもやっていると次第に慣れてきて出来るようになる、ということであった。さらにそれを長期間やっていると、むしろそれが得意な技になってくる、ということでもあった。しかしこの模写のだんかいでは比較的容易であったが、じっさいに顕微鏡を覗きながら描くのは、それほど容易ではなかった。そもそも顕微鏡というものに慣れていない。小学生の理科の時間にちらりと見たくらいだ。実際に顕微鏡のなかを覗くと、まず明るい光に眼を射られる。拡大された虫の部分などは、はじめ、それが虫のどこの部分で何の器官なのかもよくわからない。しかしこれも次第に慣れてくる。問題は、スライドにおさめられている虫の体が必ずしも整然としていないということであった。つまり採集した虫をスライド化するだんかいで、虫の体が歪んだり崩れたりしているばあいも多い。さらに微小な虫とはいえ、その体には背と腹があり、たとえばダニのばあいには、足が八本でそれぞれに関節が六個ある。これにも裏と表があり、そのそれぞれの裏表にもトゲのような毛が数本ずつあり、先端には爪…吸盤のようなものがある。そして、これらの数や位置や大きさが重要であり、それを正確に描かなければならなかった。
そのときわたしは思った。同じく対象を見て描く、いわゆる絵画とこの図では見方がまるで違う。絵画のばあいは静物でも風景でも、さらに人物でも、描く人と対象とのあいだには必ず距離というものがある。そしてそれを見る眼と対象物との角度の違いにより、同じものでも少しずつ変化して見える。だからプラトンもそのことにふれながら、描かれた像は、イデアからもっとも離れたものとして低い価値を与えている。その順位は、イデア…その似像(実物)…そしてそれを描いたものは似像の似像であると。しかし、顕微鏡を見ながら描く絵…図には、眼と対象物との距離がほとんどない。また見る向きによる変化ということもない。だから虫の実像にたいしてはもっとも近い像…図になる。それは双方の描く目的が違うからである。一方は主観を通した美の表現であり…だから対象物の部分をカットしたり、デフォルメしたりするということもある。しかしもう一方はあくまでも対象を正確に描くということが第一である。そこでは美というものは介在しない。しかしながら、虫を正確に描いてゆくと、そこにはある種の美が現れてくるということであった。
ここで次のような疑問を持つかもしれない。正確さが第一の目的なら、わざわざ人の手で描くより、写真で撮ったほうが早く、かつ正確ではないか、と。しかしながら、先程もふれたように、スライド化された虫の体は必ずしも整然とした状態ではない。スライドにおさめるとき、虫の体がゆがんだり、崩れたりしている場合もしばしばあるからである。また小さいとはいえ虫の体には背と腹がある。それがほとんど透明にちかい。写真では細部の微妙なところが混同して写ってしまうので、細部の微妙なところの判別がわかりにくい。それを、人間の眼によって確かめながら、本来あるべき虫の姿に修正して描かなければならないので、それがもっとも大変な作業なのであった。
|
|||||
「負けること勝つこと(98)」 浅田 和幸 |
|||||
「人間らしさの探究と科学の意識」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部