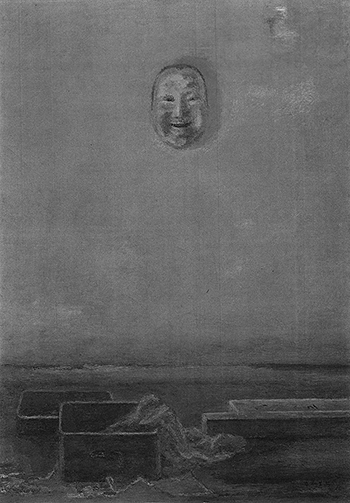第143号 |
|||||
| 2019年7月9日 | |||||
「問われている絵画(134)-絵画への接近54-」 薗部 雄作 |
|||||
京王線の代田橋駅近くに住んでいたので、相模大野まで行くには、まず新宿へ出て小田急線に乗り換えて行くのであった。朝は早かったので駅周辺の店もまだ閉まっていたが、帰りには賑やかな商店街となっていた。京王線に沿って甲州街道があったので、駅から街道までのわずかな距離であったが、その一角に小さな書店があった。いつも横目で見ながら通り過ぎることが多かったが、あるとき店頭の平積みに三島由紀夫の『文章読本』という本がたくさん並んでいた。赤っぽい色の表紙全面に自身の顔写真が載っている。つい手に取ってみたのだが、そのまま買って帰ったのであった。たぶん価額も安かったのだと思う。今でもその本が手元にあるが、奥付を見ると『婦人公論』(昭和三十四年一月号)の付録で、価額は本誌と併せて百五十円となっている。しかしそのときは、なぜか付録の『文章読本』だけが単独で並べられていたのであった。
三島由紀夫という名前は新聞や雑誌でもよく目に触れるので知っていた。しかし本の方はまともに読んたことがない。たぶん何かと話題になる流行作家というイメージが、わたしのなかではつよかったので、あるいは敬遠していたのかもしれない。というよりそもそも本そのものを、あまり読むほうではなかった。ただ、かなり以前になるが『仮面の告白』だけは読んだことがある。しかし今では何がかいてあったかほとんど何も覚えていない。たぶんよくわからなかったのだと思う。手元にある文庫本の『仮面の告白』を開いて見ると、解説を福田恒存が書いている。そこには「豊饒なる不毛──無邪気な悪党、子供のようでいながら大人、芸術家の才能をもった常識人、模造品をつくる詐欺師。だが、芸術家とは才能以外のなにものでもない、芸術家とはつまり詐欺師のことではないか、といわれれば、まさにそのとおり──現代にとっては苦しまぎれの逆説を、逆説でなくした人間、あるいはみずから逆説的人間になることによってそれを逆説ではなくそうとした人間、それが三島由紀夫だ」と。つづいて「三島由紀夫はその逆説を身をもって生きているばかりか、そういう自分の位置をよく承知し、作品においてはいっさいが計算ずみなのである」。そして「『仮面の告白』において、作者はそのからくりをもっとも明確に意識している」。彼はこの作品の創作ノートに「私は無益で精巧な一個の逆説だ。この小説はその生理学的な証明である。私は詩人だと自分を考えるが、もしかすると私は詩そのものかもしれない」と書いていると。
花田清輝にも、発表当時に『仮面の告白』について書いた文章がある。そこには「もしもこの作品の意図するところが、私小説風の告白にあるのなら、なにもわざわざ『仮面の告白』とことわる必要はない。しかし、このばあい。仮面は懺悔聴聞僧を眼中におき、おのれの顔をかくすためにとりあげられているのではなく、逆におのれの顔をあきらかにするために──ほとんど他人の視線など問題にせず、いわば、仮説としてとりあげられている」のであり「ここでは、仮面があればこそ、告白もまたあるのだ。」そして「最初に告白をしたいというやみがたい欲求があり、その結果、仮面がとりあげられているわけではない」「そこに、この告白の独自性があり、仮面の特に強調されるゆえんがあるのだ」と。 そして太宰治の仮面に対する考えかたと比較する。太宰治は『道化の華』のなかで「作家はみなこういうものであろうか。告白するにも言葉を飾る、と仮面にたいするはげしい嫌悪の情を」もらし「所詮、人間は、仮面をかなぐりすてることはできぬと観念した彼が、徹頭徹尾、反語的に、毒をもって毒を制し、虚構をもって虚構を殺し、仮面をつけたまま、仮面を逆用することによって、いかに執拗におのれのほんとうの顔を示そうと努めたかは、いまなお、われわれの記憶に新しい」といい、しかし「こういう悲劇は、三島由紀夫には縁がない」と。そして「太宰の世代にくらべると、三島の世代は、いっそい悲劇的であり、かれらはおのれのほんとうの顔のいかなるものかを知らず、しばしば、顔そのものの存在にさえ、疑惑をいだきながら、ひたすら仮面だけをたよりに、一歩、一歩、みずからの顔にむかって肉迫していくほかに手がないのだ」と。
花田清輝自身にも「仮面の表情」という文章がある。「世にはさまざまな仮面がある。あなたの顔にしっくり合うようにつくられ、ほとんどあなたに、みずからの存在を意識させないような、たいへんかぶり心地のいい仮面もあれば」また「それをつけているあいだ中、たえずあなたの顔をこわばらせるような仮面もある」「極度に誇張しり、歪曲した面もある。神や悪魔の仮面もあれば、鳥やけものの仮面もある。」そして「あなたは常に仮面をかぶる」。「どうしてあなたは、ひと前で、仮面をつけるのであろう。ひと前ばかりではない。ともすれば、あなたは、単にひとりぼっちでいるときでも、しばしば仮面をはずすのを忘れている」。それは「あなたが、きびしく表情の限定された、はっきり輪郭をもった仮面をかぶることによって、あなたのたえず動揺する敏感な顔」を「人眼にふれさせたくないためであろうか。」それとも「あなたの顔の特徴を際立たせることによって、人眼をひこうと試みているためであろうか」。「いずれにせよわたしは、あなたのほんとうの顔をみたことがない」。 能面についての言葉も印象深い。「仮面がほんとうの顔への手がかりを与えるのは、それが、いささかもほんとうの顔に似ていないばあいでも」それは「きわめて単純化された、はっきりした表情をもっている。」しかるに「能面には表情がない。そういう明瞭な表情はきれいに拭い去られている。」「このような仮面から、わたしやあなたの顔を──わたしたち日本人のほんとうの顔を探ぐり出すことは、まったく不可能にちがいない」むろん、わたしたちの祖先にも、おのれのほんとうの顔をみきわめたいという意志が、少しもなかったとはいえないが──しかし、それならばどうしてかれらは、よりによって、能面などという、不埓な仮面を、苦労して発明したのであろう。」「そこには、まるでおのれのほんとうの顔を、いつまでもみきわめたくはないという反対の意志が、同時に、はげしく働いているかのようである。」しかし「こういうと、いまだにわたしたちの周囲にたくさんいる能面の愛好者」たちは「能面の無表情は、ただの無表情ではなく、それは、すべての表情を殺すことによって、すべての表情を生かす、象徴の極致にほかならず」あらゆる表情が、内にむかっておしつつまれ」「おのれのほんとうの顔を、内側からとらえようとする、たくましい意志によって支えられているのだ」と「能面とは似ても似つかない不機嫌な表情をしながら、抗議するかもしれない。」しかし「能面は、正直なところ、わたしに、外界との接触を失い、自分だけのせかいに閉じこもって、とりとめのない空想にふけっている精神分裂者の無表情な顔を思わせる」「能面をつけた人物が、しばしば、舞台の上で、面白うくるいたまえ! と要求されるところをみると、これは、まんざら、わたしの独断とばかりとはいえないらしい」。「能面の背後にするどい探求精神の隠れていようばずもなく、無表情なドアの背後にみいだされるものは、塵埃と蜘蛛の巣、荒れ果てた部屋のなかのつめたい沈黙だけかもしれない。」おそらく「意思のアンヴィバレンツのため──おのれのほんとうの顔をみきわめようとする意志と、みきわめたくないという意志が、どうじに存在したため、仮面の背後に、このような荒廃がもたらされたのであろうか──しかし、事のおこりは、むろん、人びとが、あやしげな仮面に、ふと、心をひかれたために他ならなかった」。
文学にはしばしば登場する仮面であるが、では絵画においてはどうであろう。意外にも、それほど多くはないようだ。絵画は視覚的なので、登場させるには直接具体的に描かなければならない。描かれた仮面は、すでに表情が鮮明なので背後の顔を探し出すのはむつかしい。文学とはちがって、探すために仮面を使うのではなく、隠すために仮面を使うからであろうか。すぐに思い浮かぶのはベルギーの画家ジェームスーアンソール(一八六〇─ー九四九)である。彼はしばしば仮面を描いている。なかでも、よく知られているのは『仮面たちに囲まれた自画像』であろう。おびただしい仮面たちのなかに、ひとり彼自身だけが生身の顔で登場している。わたしは、この絵をはじめて見たとき、無数の奇怪な仮面よりも、なぜかただ一つの生身の顔のほうが、さらに不気味に見えた。わが国の画家で思い浮かぶのは坂本繁二郎(一八八二─一九六九)である。アンソールとはかなりおもむきは違うが、彼もよく仮面…能面をモチーフにして描いた。
さて、はじめにふれた三島由紀夫の『文章読本』であるが、わたしはこれを読んで、それまで抱いていた、彼に対するイメージが一変したのであった。きわめて真面目な、そして内面的な心を感じたのだ。
|
|||||
「負けること勝つこと(99)」 浅田 和幸 |
|||||
「俳句と人間存在への問いかけ」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部