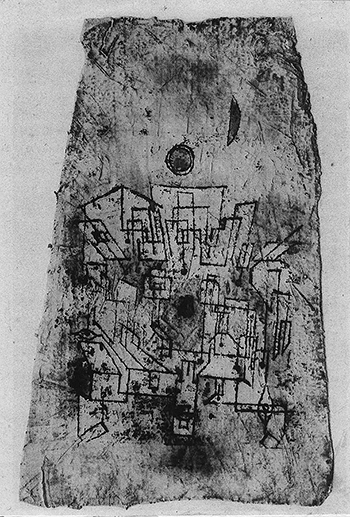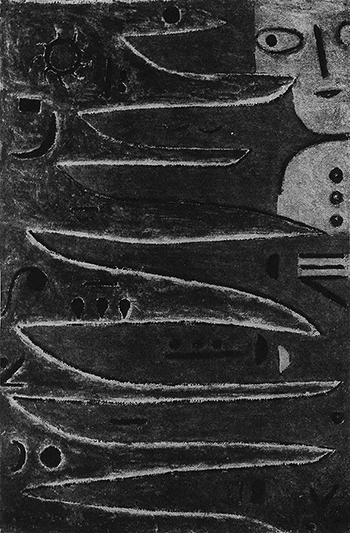第144号 |
|||||
| 2019年10月16日 | |||||
「問われている絵画(135)-絵画への接近55-」 薗部 雄作 |
|||||
わたしはとくに読書が好きというタイプではなかった。そんなわたしが、わずかではあるが本を読むようになったのは、毎日乗る通勤電車の影響が大きい。朝夕乗る行き帰りの数十分という時間は何もやることがない。はじめは漠然と窓外の風景を見ていたが、それも毎日同じなので、しだいにあきてしまう。やがて何か本でも読めばよい、ということに気がついた。というより自然にそんなかたちになったのかもしれない。当時よく読んだ本はヴァレリイの『テスト氏』と『文学論』、そして『アンリ・ミショー詩集』であった。それはとくべつ選んだというより手元にあったものだ。ヴァレリイは、今から比べると当時はよく読まれていたようだ。美術評論などでもしばしば引用されていた。記憶に浮かぶのは、たとえば東野芳明の『美術批評』に連載していた「グロッタの画家」でボッシュを論じた文章で「操り人形など殺してしまい、にっこりともしなかった」はずのテスト氏が「生涯の幕切れに。自意識という神の目をかすめて腹いっぱいわらっている風景を想像して見るのも無駄ではあるまい」と書いている。こういう文章を読むと、当時のわたしにはとてもかっこよく思え、そして、引用されているヴァレリイとはどういう作家なのか、ということが気になり、できれば、彼の引用している原典を読んでみたいものだ、と思うようになった。そんなことも忘れていたが、それから何年か過ぎてからであったが、たしか新宿の古書店でヴァレリイの『文学論』を見つけた。『テスト氏』の方はどこで買ったか覚えていない。なぜ『文学論』のことを覚えているのかというと、これも風月堂の帰りだったと思うが、新宿駅東口近くの古書店に寄ると、偶然にも高校時代の美術部の先輩がその店で働いていたのであった。そしてそのとき、その店で買ったのであった。と思っていたが、今あらためてその本を開いて見ると、岩森書店・荻窪南口前という古書店のシールがはってある。記憶はじつに曖昧なものだ。荻窪のことは何も覚えていない。勝手にいろいろな事をむすびつけてしまっている。
『テスト氏』は小林秀雄が訳している。 訳者序序
となっていて、わたしは主に「テスト氏との一夜」をよく読んだ。「操り人形など殺してしまい、にっこりともしない」という、抽象的人間テスト氏に魅せられたのかもしれない。そして、それを自分の生活に重ね合わせるようにして読んだりしたかもしれない。というのも、その頃の毎日通勤するパターン化した生活を、そうすることによって慰めていたのかもしれない。「デカルトの生涯はもっとも簡単な物である」というエピグラムのあるこの章でテスト氏は言う。「僕は、元来、馬鹿な真似をするのは得意な方ではないのだ」そして「たくさんの人々を見て来た。諸国を訪れた。好きでもないいろいろな仕事もやって来た」。「今思い浮かべれば、二か三百の人間の面相、素晴らしい光景の二つや三つ、ことによったら二十冊ぐらいの本の内容ぐらいは思い浮かぶところだが」とくに「上等なもの下等なものを覚えていたわけではない。つまり残ることが出来たものが残ったのに過ぎぬ」。 「この算術のおかげで、われながら年をとったなと驚かなくてもすむ」「僕はいつも自分の身の上は立派に審判してきた。自分を見失ったなぞは希有のことだ。自分を嫌悪し、自分を熱愛し、……かくて両人諸共に年老いたのであった。」「僕は、自分にとって何も彼も終わった、と思い込んでみた」「何か苦しい局面を、どうかして解き究めようと思い患っては、力を使い果たし、もう万事休す、と思い込んでみた。」そのおかげで「僕たちには、自分の考えを他人の考えの表現にしたがって理解することが、むやみに多過ぎるということだ」。 「歳は四十位であろう」「恐ろしく早口」だが「すべてのものが定かでない」しかし「肩は軍隊的にがっちりとしていて、驚くほど規則的な歩調である。話す時、腕を上げたり、指を動かしたりは決してしない。つまり冒頭に引用した[操り人形など殺してしまっていて]にっこりともしない。今日は、も、今晩は、も言わない」。おそらく「いかがですかご機嫌は」などということは「彼には何のことやらわからない」。 こんな人間と一夜を過ごした語り手は、テスト氏の住まいまで同行する。そして彼が眠りにつく様子を見ながら帰途につく。 「建物の頂上にある、いかにもささやかな『家具付』の部屋に通った。本一冊もない。やりつけの仕事のある様子はまったくなかった」「僕は、今まで、これほど或る任意のという印象を受けたことはない」。その部屋のベッドに横たわってテスト氏は言う。「人間に何が出来る。僕は、あらゆるものと戦います……自分の身体の苦痛を乗り切っても、ある定量を踏み越えても」。「僕は考える。考えることは誰の邪魔にもならない」「俺はこうしている。事案を眺めながら、自分を眺めるのを眺めながら、以下これに順ず……」「おやおや、人間はどんな題目の上にも眠るし……、眠りはどんな考えでも続けるし……」「彼は静かに鼾をかいた。僕はもう少し静かに蝋燭を取り、足音を忍ばせて外に出た」。
では当時、美術の方では何をよく見ていたのだろう。もともとセザンヌやゴッホやモネなど印象派周辺の画家たちにひかれて、その影響のもとに風景や静物などをおもに描いていたのであったが、次第にそれらを離れて、現代の画家たちに関心が移っていった。現代を生きているという時代の影響ということもあるが、また個人的な生活の影響ということもある。というのは、かつて学生のときには自由な時間があった。しかし職業をもつと、ほとんどの時間がそれについやされる。また空間…描く場所も、かつてよりずっと狭い空間になった。そのような条件のなかでできることは何か、とうことが切実な問題として迫ってくる。そんなときに思い出したのが、高校時代に『美術手帖』で読んだ滝口修造の「パウル・クレー」であった。そこには「パウル・クレーという画家は、ピカソやマティスのように、眼や心を大きくゆすぶる大画家ではありません。彼は大作を描きませんでした。油絵でも大きなものはなく、多くは水彩、素描、版画などの小さな作品のなかで、心を惹きつけるふしぎな魅力の世界を創造したのです。ちょうど音楽なら、それは大管弦楽ではなく、小さな室内楽の親しさに似ています。」「ある意味では、膝の上で。しずかに読むのにふさわしい絵だといえるかもしれません」「しかしクレエは近代絵画の流れのなかで、大画家たちにも劣らなぬ高い位置をしめています。」そして「クレエは一九四〇年、六十一歳で故国スイスのベルヌで他界しましたが、死後、彼の芸術への関心が急にたかまり、その影響は世界的に広がりはじめています。」と。わたしはこれを読んで、画家はとくに大作を描かなくてもよいのだ。そして、その小さな作品を描いた画家が、大作を描く大画家にも劣らず世界的にも評価や影響が広まりつつあるのだ、ととても安心感をえたのであった。その雑誌に載っていた図版では「灰色の男と海岸」「帆走する町」「アラビヤの町」などが目を引いた。とくに「灰色の男と海岸」には、よくわからないにもかかわらず、不思議な感銘を受け、何度もくり返し眺めた記憶がある。
|
|||||
「負けること勝つこと(100)」 浅田 和幸 |
|||||
「人間とはどのような存在なのか、と問うこと」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部