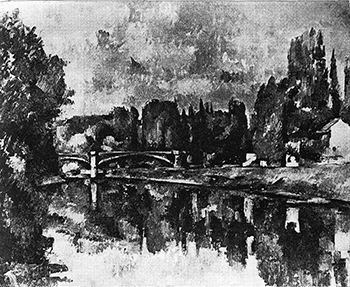第145号 |
|||||
| 2020年1月1日 | |||||
「問われている絵画(136)-絵画への接近56-」 薗部 雄作 |
|||||
絵画にのめり込んでいたわたしが、少しずつ文学にも関心を持つようになったのには理由もあった。絵画は、制作にさいして感覚はフル活動しているが、そこには言葉の介在が少ない。色や形による造形的な思考が主なので、むしろ言葉を排除する。言葉の介入は、むしろ作品を弱くする。説明的になりやすいのだ。だから批評などでも、この作品は文学的である、というのは批判的なばあいが多い。ということは後から考えたり気づいたりしたことであるが、それとはまた別に、作品を描いても、たえず心の片隅には、かすかな不安がつきまとっていた。描いてはいても、確信というものがなく、果たしてこれでよいのか、という懐疑的な思いがくすぶっていた。そんなときに思い浮かんだのが、別のジャンルの芸術…文学や音楽と比べることであった。比べるとはいっても、文学や音楽は、表現の素材や方法がまるで違うので、たんに表面的な比較はできない。だから、表現の形式ではなく、作品の根底、そこに流れている心情のようなもの…表現形式は異なっていても、それは同じく人間のつくったものであり、その奥底に流れているのは同じものではないか。であるなら、文学や音楽の根底を探り、それを知ることによって、それを絵画の根底に流れているものと比べることによって、はたして、自分も、その流れに合流することができるかどうかを知ることができれば、なにがしかの安心感がえられるのではないか、と。
ヴァレリイの『文学論』は堀口大学が訳している。奥付には、昭和二十年十二月十五日発行とある。ぶ厚く文字が大きいのが有り難い。 先ず冒頭に「書物は人間と同じ敵を持つ。いわく、火、湿気。虫、時間、そうしてそれ自らの内容」。なるほど、と思う。後に、これに対して、ヴァレリイの弟子であったブルトンがエリュアールとの共著で、すべての句を反転して書いた本の文庫本が出版されたことがあった。たとえばその一句を「書物は人間と同じ味方を持つ。いわく、火。湿気。虫、時間、そうしてそれ自身の内容」と。しかし、本が手元にないので、はっきりしたことが言えない。わたしは、当時その本を、書店で手に取って開いて見たのだがなぜか買わなかった。今では後悔している。次に「素裸の思想も感動も、素裸の人間と同じに弱い。だからそれらに着物を着せる」。これに対しては「素裸の思想も感動も、素裸の人間と同じに強い。だから、それらに着物を着せない」と。しかし記憶なので少し違っているかもしれないし、あとはまったく記憶にない。
「思念には両性が備わる。それは自ら受胎し、成育する。」
「詩の存在は本質的に否定し得る。さればこそ、次のごとき高邁な欲望も抱きえる次第。……この点、詩は神に似ている。」
「人は詩に対してつんぼであり、詩に対して盲であることもできる……しかも、その結果は目立たない。しかし、万人がその存在を否定し得るものであり、しかも、吾人がその存在を欲するもの……が、吾人の存在の理由の中心をなし、強力なシンボルをなす。」
まったく絵画にも同じことが言える、とわたしは思った。人は絵画がなくても、また描かなくても、とくに困らない。生活することはできるし、その結果はとくに目立たない。しかし、多くの人がそれを特に必要としなくとも、しかし、それをやることが、わたしの存在の中心になっている、と。
一篇の詩の主題が、その詩に取って、無関係でありまた重要であることは、ちょうど一人の人間とその名と同じである。」 以前、自分の作品のタイトルについて書いたとき、わたしは描いているときにはタイトルを念頭にしていないが、発表するときにタイトルがないのも変なので、一応つけてはいる。 しかし、まったく無関係でもない。それは人の名前と同じようなものかもしれない。人も生まれたときに名前をつけるので、その人の将来をあらわしているわけではない。しかし、後のその人が自分の名前と無関係でもない、というようなことを言ったが、そこにはヴァレリイのこの言葉が頭のなかにあったのだと思う。こんな影響があったのか、わたしも制作に当たって、インスピレーションとかイメージというものを極力排除しようと意識した。そこには何か偶発的なものとか映像的なものの優先を感じたからである。 しかし、ヴァレリイも意識していたとは思うが、彼を含めた象徴派の詩人たちに影響を与えたアメリカの詩人エドガー・アラン・ポーは、自らの詩『大烏』の制作過程を論じた「構成の哲学」でいっている。この詩は霊感によって泉のごとくこんこんと溢れ出てきたものではなく「その構成の一点たりとも偶然や直感には帰せられないこと、すなわちこの作品が一歩一歩進行し、数学の問題のような正確さと厳密な結果をもって完成されたものである」と。しかし、にもかかわらず、その詩には暗闇のなかから明るい部屋に紛れこんできた、黒い鳥の神秘が発散されているのはポーの詩才のなせる技であろうか。 それに比べると、知性の人ヴァレリイは、批評や評論には冴えを感じるが、詩作品には…わたしの感受能力や、また翻訳ということもあると思うが、なぜか読み通すことにさえ困難を感じる。
インスピレーションについても次のように言う。「その観念は、無償のものが一番価値のあるものだ。また一番価値のあるものは無償のものでなければならない。なおまた、自分に一番責任のないものをもって自分の光栄とすること」である。 しかし、この言葉の影響もあるのだろうか。わたしも、制作に当たって、インスピレーションとかイメージというものを極力排除しようと意識した。そこには何か映像的なものとか偶発的なものを感じたからである。それより、もっと構造や永続的なものが必要のように思った。
「新しさということは、その本質からいって、ものの消滅すべき部分なのである。新しさの危険な点は、それが自動的に新しくなくなり、しかもただ単純に失われてしまうことにある」。これを読んでいた頃は、わが国でも前衛芸術がたいへん盛んであった。とくに若い世代においては、前衛でないものは芸術ではないかのごとくであった。そしてたしかに、前衛は次々メンバーをかえて登場し、交替していった。前衛として登場した作家は、交替しても、なおももちこたえるということは難しかった。その交替劇をどれほど眺めてきたことだろう。だからといって、波にのらなければ浮上しやすいということはない。
「多くの詩人は、世界中を歩きまわって熱心にしかも難儀しながら、人間に似た形の岩が偶然見つからないかと尋ねている男に似ている。」
この言葉にも感じるものがあった。ここで言っているのは、創造は外を探すことではなく、内を探し開拓してこそ始まる、と言うことであろう。わたしたちは、とかく自分の作品のモデルを自分の外に求めがちである。というのは、当時は今よりも絵画の本場は西洋…特にフランスにあるという考えが支配的であった。美術学校でも絵画を学ぶことは西洋絵画を学ぶことであった。わたし自身も当初フランス印象派の画家たちの影響のもとに写生をしていた。しかしやがて、次第に思うようになった。印象派の画家たち、モネやセザンヌやゴッホなど、それぞれ独自の世界を切り開いているが、彼らが彼らたりえているのは、すべて自分の資質に根差したところで表現を展開しているからだ。だからわたしたちも、ただそこから学ぶだけではなく、それぞれ各自が、自身に向き合い、自分の資質に根差したところから出発するべきである、と。
|
|||||
「負けること勝つこと(101)」 浅田 和幸 |
|||||
「現在の問題意識-雑感」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部