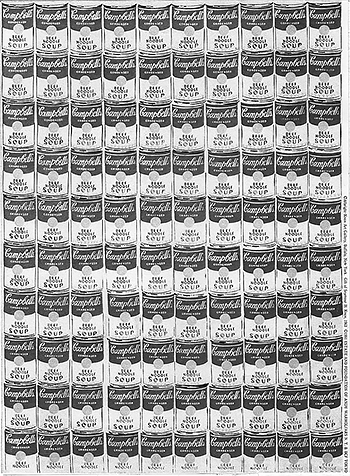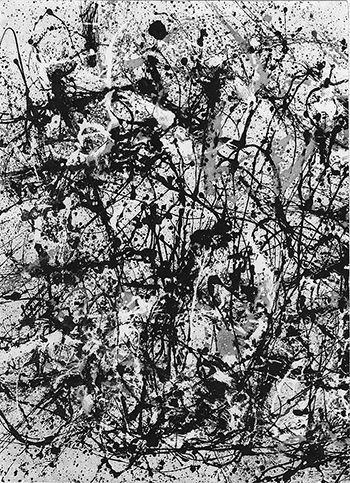第146号 |
|||||
| 2020年4月4日 | |||||
「問われている絵画(137)-絵画への接近57-」 薗部 雄作 |
|||||
ヴァレリイの『文学論』は角川文庫にもなっている。単行本ではぶ厚かったが、文庫本になるととても薄い本になってるので驚く。奥付けには昭和三十年発行で、平成元年に改版八版とあるから、かなり読まれているようだ。たしかにこれは、文学制作にあたっての懇切丁寧で実用的な本として、またリアルな人間観察の書としても読める。もっとも、今では文学というものが、一般にどのように考えられているのかよくわからないが。しかしわたしにはそのように思える。
「人間は閉じ込められた動物だ……自分の籠の中に」
たしかにわたしたちは自分の体のなかに閉じ込められている。閉じ込められている、という言い方は少し強引かもしれないが、しかし、だからといってその体の中か外に出ることはできない。想像的には抜け出すことができるかもしれないが、生きているかぎり完全に抜けだすことはできない。そんなことをつくづく感じたからだと思う。後年わたしは『牢獄と宇宙』という本を書いた。それに対してある友人は、牢獄に入ったことのない人間が、牢獄について書いても説得力がない、といったが、わたしは犯罪人を閉じ込める牢獄について書いたわけではない。自分の肉体を…この肉体から外に出られない自分という意識の存在を、牢獄の住人として例えただけであった。
「一つの作品のあらゆる部分はそれぞれ「作用」しなければならない」 「ある一つの作品のそれぞれの部分は一本以上の糸でお互いに結びつけられていなければいけない」
絵画は、文学や音楽のように一定の時間の中で表現するわけではないが、やはり区切られた一定の平面のなかで、表現しなければならない。そこでは、やはり各部分はそれぞれ互いに、一つの主題をもりあげていなければ、作品は成り立たない。ということは自分の制作体験によっても実感していた。それは作品だけではなく、自然界を見わたしても納得させられる。たとえば樹木を見ても、そこには根と幹と枝葉がつながりあって一本の木として存在しているように。 もっとも現代美術のなかには、一つの画面のなかに、物やパターンをただ並べただけで、とくに有機的なつながりのない作品もある。たとえばアンディ・ウォーホルの「ワンハンドレット・カンズ」のように、ただ缶詰を並べただけの作品もある。しかしこれさえも、どこか抜けていたり、いくつかの空白があったりすれば作品としての緊張感がなくなってしまう。またジャクスン・ポロックの「秋の韻律」のようにアクションによるオートマチックな作品もある。 いずれも当時はきわめて斬新であったが、しかしこれらの作品も今現在眺めると、なぜか落ち着いたものに見え、すでに現代美術の古典的作品として見えるから不思議である。
「急いでいて何を食べているのかも分からずにいる人が食べたり飲み込んだりするような調子で、文句を無意識に書くのでない人が文人」
たしかに私もそう思う。しかしまた、意識し過ぎた…あるいは自覚しすぎた作品も、何か自由さや自然さを欠いた窮屈なものになりやすい。わたし自身の作品も、かなり意識的に制作されているためか、これに対して、ときおり見る人から、どこか崩れたところや抜けたところがあったなら…という感想を聞くことがある。たしかに一見整然とした意識的作品は、そんな印象を与えるところがあるのだと思う。しかし、わたし自身としては、整然と組み立てられた構成のなかにも、意識を超えた無意識がにじみ出て…発散しているのが望ましい。そういえば平面ではないが建築物や家具なども一見きわめて堅固で整然とはしているが、とくに窮屈とか不自然な感じは受けない。それよりこれらの物のどこかが崩れていたなら、きわめて不安定だし使いものにならない。
「ある作品について成される模倣は、その作品から模倣され得る物を剥ぎとる」 模倣され得るものをはぎ取られた作品は、そのあと何が残るのか。何も残らないとしたら、それは何なのか? 何か残るとしたら、それはまた何なのか。
「ある一人の芸術家の理論は、常にその本人をそそのかして、彼が愛しないものを愛し、愛する物を愛さないようにする」 画家においても、理論的でありすぎると、作品がかわいたものになり、感動が薄れる。 これは技術と心との関係にも置き換えられる。技術だけが表面を支配し、心がかき消されてしまう。また心だけはあっても、それを表現する技術がなければ作品は成りたたない。双方が堅く結び合ってはじめて成立する。 とはいっても、現代芸術のなかには、いわゆる技術を放棄して、心…あるいは衝動だけを頼りにして制作された作品もある。先にあげたジャクソン・ボロックの作品がよく知られている。
「一つの作品は、人の魂を、他の作品に対して、感じ易くする」
「あらゆる人間のうちで、詩人は最も実用的な人間である。懶惰、失望、言葉の不完全、変な目つき等…いわば、一番多くの実用的な欠点なり、弱点となり、邪魔となり、損失となるものを集めて、詩人はその芸術によって、それに何らかの価値を付与するものだから」
「剽窃家というのは、他人の養分を消化しきれなかった者の謂である。だから彼は、元の姿の認められるような作品を吐きだすのだ」 少し違うかもしれないが、このような状態におかれると…自分もその剽窃している作品の世界の住人のようになってしまうので、ごく自然にその影響下になってしまう。
「実用的でないものの明快さは、常にイリュージョンの結果だ」
「世界で一番むづかしいこと。自分の知能の総和、発見の総和を、役立たせること」
「僕にとって困難なものは、僕にとって常に新しい」
自分に根差した作品を、というどこか雲を掴むような…というのも、自分というものが、よく分からない状態にありながら自分を目指すということは、たいへん漠とした方法なので、何をどうすれば、それを探せるのか判然としないので……さしあたり形の上で誰かの影響ということを極力排除した。しかし排除すればするほど、そこに残るのものは、あいまい模糊とした無味乾燥なものとなってくる。しかしとにかく、そんな何もないようなところに、無理やりでも何かの形を作り上げたい、という不可解で困難とも思えることにエネルギーをついやしたのであった。
|
|||||
「負けること勝つこと(102)」 浅田 和幸 |
|||||
「個の自由と責任について」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部