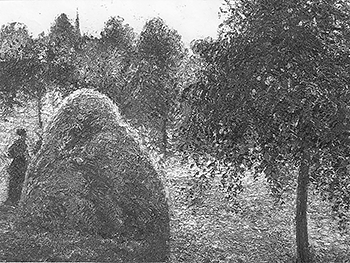第147号 |
|||||
| 2020年7月28日 | |||||
「問われている絵画(138)-絵画への接近58-」 薗部 雄作 |
|||||
新型コロナウイルスによってわたしたちの生活が一変してしまった。こんな変わり方…非常事態宣言とか、外出自粛という言葉は、ここ何十年もきいたことがなかった。かつて第二次大戦…太平洋戦争のさなか、とくに敗戦間際の頃には、状況は異なるが、どこか似たような雰囲気があったように思う。もう七十数年も前になるので、今ではその頃のことを知っている人も少なくなったのではないかと思う。
わたしは当時小学生であったが、その頃のことは、今でも記憶の底にはっきり残っている。だからであろう。このたびの緊急事態宣言とか、自宅待機とかいう言葉に触れて、かつてのことが思い出されたのは。しかし似たような雰囲気を感じたとはいっても、細かく見れば、やはり、かなり異なっている。かつてのときも、たしかに緊急な事態の発生ではあったが、しかし、それは敵機という、はっきり目に見える存在による危機であった。けれども、この度の新型ウイルスは、わたしたちの目には見えない。にもかかわらず、かつてのことが思い出されたのは、やはり双方にどこか似たところもあるからだと思う。
たしかに、双方とも、われわれを襲ってくるときには、まずメディアなどによって警報がある。かつて空襲・B29の来襲のときには、まずラジオ…当時はテレビはなかった…によって警戒警報が知らされる。放送中の番組が突然中断されて警報に変わる。そして東部軍官区情報という言葉が繰り返され、内容が知らされる。現在の緊急地震予報や速報にも少し似ていたように思う。だからであろう、今でも放送が突然中断されて緊急放送が流れると、ハツとして、ふと当時のことが思い出されるのは。そして敵機の来襲が知らされる。その警報は、警戒警報と空襲警報に分れていた。警戒警報はサイレンの音も長く、ゆったりとして、まだ少し余裕を感じさせた。警戒警報のときには、ほとんどのばあい、B29がただ一機で、高度一万メートルの上空を大きく旋回しながら偵察して帰ってゆくのことが多かった。真っ青な空のなかを小さく銀色に光るB29の機体は今でも眼底に焼きついている。 しかし、空襲警報のばあいは一変する。サイレンの音も短く断続的に鳴り渡り、より切迫感や緊迫感を感じさせた。そんなとき、わたしたちが学校の教室や校庭のいるときであれば、ただちに下校して自宅退避となる。あのサイレンの音は耳にこびりついている。今でもときどき救急車のサイレンが突然鳴りだすとハツとする。
当時、それぞれの家には、庭の片隅に土を掘ってつくった穴蔵のよう小さな防空壕があった。空襲警報が鳴りだすと…状況によってはそこへ避難するのである。しかし今から考えると、あのような簡単な壕では、いざというときには、あまり役にたたないのではないかと思えるが、しかし当時はそんなことを考える余裕もなかった。あの穴の中へはいったときの感覚…暗く湿っぽい、そして不安感には独特のものがあった。東京からは少し離れていたので、実際に爆弾や焼夷弾が落ちてくるということはなかったが、一度だけ近くの町の軍事工場がB29の編隊によって爆撃されたことがあった。
それは、よく晴れた日の午後であった。真っ青な空…高度一万メートルの上空を、銀色に光る爆撃機B29の編隊が通過してゆくのであった。それを、わたしたちは数人で、利根川の土手の上に立ってずっと眺めていた。編隊は真上ではなく少し離れた上空だったので、わたしたちが爆撃されるという危険は感じなかった。地上からは高射砲がしきりに発射されるのであったが、高度一万メートルまでは達しなかったようだ。B29の編隊よりは少し下の方で爆発し、煙の塊だけがいくつも見えた。やがて編隊の周囲に、わが国の戦闘機が何機か現れて攻撃…空中戦がくり広げられた。その光景は、大きなB29の機体の周辺を舞う小さな銀色の点のように見えた。一瞬、B29の機体から煙のようなもの噴き出した。と思うまもなく一機が傾いて墜落しはじめた。戦闘機が体当りしたのだと思う。するとそれが隣のもう一機に衝突して二機が真っ逆さまに墜落しはじめたのだ。上空では小さな銀色の塊にしか見えなかったが、墜落してくる機体を横から眺めると…かなり離れてはいたが、それでも、それが意外に大きく感じられたのを、何か奇異な思いととも見ていたのを覚えている。
当時は、自分が将来絵を描くようになるなどとは、まったく思ってもいなかったので、その頃に関する絵の思い出は何もない。美術に関心をもちだしたのはもっと大きくなってからであった。中学の終わり頃か、あるいは高校の初めの頃だったと思う。その頃、家に『光』という雑誌があったが、その表紙にいつも西洋の名画が載っていた。そのなかにピサロの『昼寝』という作品があった。積み藁と横になっている人物が描かれている作品で、今から見るとわかりやすく親しみやすい作品であるが、当時のわたしには何か不思議な作品に見えた。しかし積み藁自体は、わたし自身の身近な存在でもあり、見慣れてもいたので、それでこの絵に親しみを感じたのだと思う。ピサロには同じモチーフを描いたと思える作品がもう一点あるが、それは『積み藁と夕暮れのエラニー』というタイトルなっている。
|
|||||
「負けること勝つこと(103)」 浅田 和幸 |
|||||
「人間存在をより深く理解した政治へ」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部