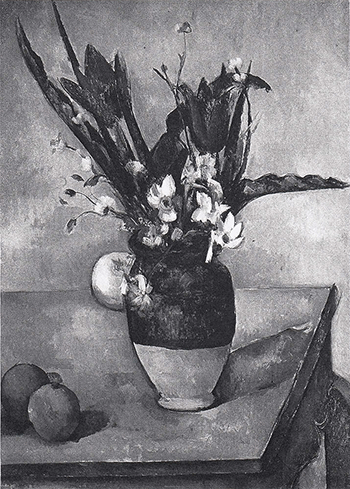第148号 |
|||||
| 2020年10月21日 | |||||
「問われている絵画(139)-絵画への接近59-」 薗部 雄作 |
|||||
小学校に入学して間もなくだったと思う。藁半紙にクレヨンで日の丸を描かされたのを覚えている。出征する兵士を見送るときに自分たちが振る旗であった。太平洋戦争が始まった年だったと思う。しばらくのあいだは戦勝ムードが続いたが、やがて戦況は次第にきびしい状態となっていった。若い受け持ちの先生は次々に徴兵されていなくなり、わたしたち学校生活も変化していった。学校には行っても、教室で勉強するということが少なくなった。それより、近辺の農家へ勤労奉仕にかり出されることが多くなった。若者はみな徴兵されていなくなり人手に困っている農家への手伝いである。それだけではなく、いろいろな作業もさせられた。樫の実…ドングリを拾い集めて学校に提出させられた。加工して食料にするためのようであった。養蚕の地帯であったので桑の木も多くあった。その葉を蚕にあたへたあと、桑の枝の皮を剥く作業もやらされた。剥いた皮を干して束にし、そして学校に提出するのであった。衣服などの繊維に加工するためのようであった。なにしろ極端に物資不足の時代である。わたしたちは新しい服やズックなどもほとんどなかった。ごくたまに服や運動靴が…年に一回ぐらい配給として、くることがあったが、それもクラスに一着とか一足である。だから抽選になるのであったが、当然のようにめったに当たらない。
当時、田舎の道路はほとんど砂利道であった。その道の両端には幅一メートルほどの草地の部分がある。その草地へ、一メートル置きくらいに小さな穴を掘って、そこに大豆の種を蒔くのであった。大豆は強い植物で、自分の根に自分の肥料…のような物質を作りだす性質があり、そのような場所でも十分収穫できるのであった。人家のあるところ、道はどこにもあるので、その収穫は大変な量であったが、すべて学校へ提出するのであった。 また鉄製品の供出もあった。住宅のある部分に使われている鉄製品を、取り外して供出させられた。強く記憶に残っているのは、家の、ある窓に何本かの鉄の桟が取り付けられていたが、それらを全部外して供出させられたのであった。鉄砲の弾など兵器の材料にするということであった。それは子供心にも何か強い印象として残っている。またそれぞれの家には、竹竿の先に藁の縄の束をくくりつけた火はたきが用意させられた。そして敵が上陸して攻めてきたら竹槍で迎えよ、ともいわれてもいた。
今でも生々しく思い出されるのは、雪の中を裸足で歩かされたことである。小学三年か四年のときであった。前もって予告されてたわけではない。雪の日に学校へ行ったら、いきなり今日は雪のなかを歩くということになったのだ。クラス全員、素足のまま、一列になって校門を出た。さいわい雪は止んでいたが、道路という道路は一面真っ白で、土の見えるところはどこにもない。それだけではなく、大勢が一列になって歩いてゆくので、雪は踏み固められて、氷のような凸凹になっている。裸足の足は冷たさに加えて痛かった。それを避けようとしても、周囲はすべて同様である。どうしようもない。前へ進むしかないのだ。校門を出てから数キロは歩いた。しかし途中で倒れた者は一人もいなかった。学校に戻ったわたしたちは、すぐ井戸に直行した。足を水で暖めるためである。水で暖める? というのは、あるいは不思議に思えるかも知れないが、長時間、雪の上を歩いた足の裏は、すでに無感覚にちかい。しかしそれでも、地下深くから噴出する掘り抜き井戸の水は雪に比べれば遥かに暖かい。湯気さえ出ている。その水のなかへ足を浸すのだ、それは、何とも心地よかった。
東京の大空襲のときの光景も記憶に焼きついている。かなり離れてはいたが……わたしの住んでいたところから東京まで十八里といわれていた。キロになおすと七十数キロである。 それは夜だった。わたしたちは利根川の土手の上に立って東京方面の空を見ていた。大人も何人か交じっていた。周囲は真っ暗であったが、はるか東京の上空は一面真っ赤であった。その赤い空が横に長くひろがっている。誰かが右端の方を指して、あれは八王子のあたりだ、といったのが耳に残っている。真っ赤に染まった東京の上空には、あちこちに、ひときわ明るい照明弾が、揺らめきながらあちこちに、ゆっくりと落下していくのが見えた。
終戦の年・昭和二十年八月十五日からの後半は、学校で何をやったのかはほとんど何も覚えていない。ただ終戦直後に、教科書の指定されたなりの行を、墨をすって塗りつぶす作業をしたこと、また突然、先生から英単語を不思議な発音で教えられたことは覚えている。学校には連続して毎日通っていたのだが…そして勉強もしていたのだと思うが、何も覚えていない。あくる年…小学六年になった。そして教科書が渡された。しかしそれは、二・三十ページの薄っぺらい藁半紙に、新聞の文字のような小さな文字が二段組みに印刷されていた。かつてそんなことは一度もなかったので、つよく印象とともに記憶に残っている。たしか国語の教科書だったと思うが、その他の科目は教科書があったのかどうかも、そして何をやっていたのかも、まったく覚えていない。
中学になってからのことは、はっきりと記憶に残っている。それまでは小学が六年と高等科が二年であったが、学制が変わって、小学は六年で同じであるが、新制は高等科がなくなって中学が三年となった。 中学一年になってからしばらくの頃だった。ある朝、校門をはいって教室に向かって校庭を歩いているとき、足もとに小さな何かの破片のようなものが落ちていた。拾いあげて見ると、それは何か絵の部分のようなものであった。厚紙のようなものの上に絵の具が盛り上がったように塗ってあった。その頃はまだ絵に関心はなかったが、なぜかそれをとても生々しく感じたのを、今でも覚えている。
絵に少しずつ関心がでてきたのは、たしか中学も終わりにちかい頃になってからであった。はじめは、図画の教科書やそれに類した本のなかから、易しそうなものを選んで真似て描いていた。しかし、それが大変面白く、だんだんのめり込んで、やがて写生などもするようになっていった。また外国のいろいろな名画…ほとんど印象派周辺の画家たちであるが、ゴッホやセザンヌやルノアールなどの複製も見るようになっていった。たまたま友人の家にセザンヌの画集があったので、それを借りて繰り返し眺めたり、また模写などもしてみた。油絵の具で描いた作品を水彩で真似て描くのであるが、それでもとても面白く、見るだけとは違って、作品に直接触れたような感覚があり、それがたいへん刺激的でもあった。
|
|||||
「負けること勝つこと(104)」 浅田 和幸 |
|||||
「地球社会のこれから」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部