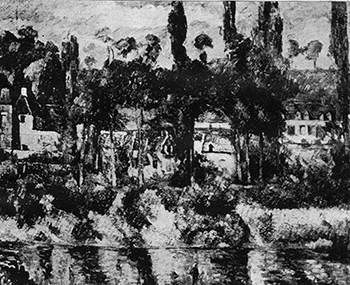第149号 |
|||||
| 2021年1月21日 | |||||
「問われている絵画(140)-絵画への接近60-」 薗部 雄作 |
|||||
前回の終わりにセザンヌについてふれたのであったが、セザンヌへの関心は、若い頃だけではなく、それ以後、現在にいたるまで断続的であったとはいえ消えたことがなかった。だから、わが国におけるセザンヌ展や、また、ときどきある印象派に関する展覧会などで、セザンヌの作品が何点か含まれている展覧会なども見てきた。そしてそんなときに買った絵ハガキやポスターなどもある。手元にある雑誌や図録や画集などもときどき見ている。古いものでは、アトリエ・別冊の里見勝蔵著『セザンヌ研究』という本がある。今では表紙も奥付もなくなっているので、出版年も値段もわからない。出版はたぶん昭和三十年代の初め頃だと思う。 これは、学生のころ渋谷でアルバイトをしているとき、通りがかりに覗いた書店に並んでいるのを見て、その場で買ったのであった。初期から晩年にいたるまで順序をふんで掲載されているので、セザンヌの作風の変化や流れが見やすい。しかし、ほとんどがモノクロの写真で、それも小さな図版なのが少し物足りない。けれども、当時はカラー印刷が現在のように当たり前の時代ではなく、一冊の本にわずかな作品しか掲載されていないというのが普通であった。しかし、制作年代や作品の大きさなども、すべて記載されてるのでわかりやすい。 今では画集や文献も多いが、わたしは、とくにセザンヌの研究者ではないので、それを全部見ることはできないし、またそのような必要も感じていない。手元にあり、興味のあるものを見るだけだ。今、目の前にあるのは先の『アトリエ別冊』とエミール・ペルナールの『回想のセザンヌ』、そして『セザンヌの手紙』と『セザンヌ画集』である。 ベルナールの『回想のセザンヌ』は、昭和二十八年に有島生馬の訳で、岩波書店から文庫として出版されている。定価は四十円となっている。訳者は有名な洋画家で、わたしも名前はよく知っているが、どんな作品を描いていたか今では覚えていない。わが国でも、セザンヌの影響を受けた画家は多いと思うが、それをしっかり生かした画家というのは少ない。岸田劉生の初期の静物などにもセザンヌの影響を感じさせる作品もあるが、しかし、構図にはそれがうかがえるとはいえ、あきらかに劉生の作品になっているのはさすがである。 セザンヌの画集というのは、1996年にロンドンのデイトギャラリーで開かれたセザンヌ展のときの図録であるが、ハードカバーで分厚く、初期から晩年に至までかなり綿密に集められている。このなかには、わが国にあるブリヂストン美術館の「サント・ヴィクトワール」もある。それにアンリ・ペリュショの『セザンヌ』である。この『セザンヌ』は伝記であるが、著者も「序」で言っているように「これは小説化した伝記ではない。わたしは、今日われわれがセザンヌについて知り得るすべてのものを集めた。彼についてわれわれが所有している諸記録を集めて検討し、彼が暮らした場所を訪ね、風景と事物に質問した。」そして「要するに、わたしが確かめ得たもの以上には一歩も出なかったのである」と。著者のアンリ・ヘリュショは「フランスの中部モンソー・ミーヌに生まれる。主著は本書をその一冊とする『芸術と運命』のシリーズ、ほかにゴッホ、ロートレック、ゴーガン、ルノアールなどの生涯が扱われている」という。
たしかに、この『セザンヌ』を読むと、セザンヌという人間とその周囲の人たちが、またそれらの人たちとセザンヌの関係がよくわかる。作品だけを見ると、きわめて一貫したゆるぎない作品を制作した、このセザンヌという画家は、よほど堅固でゆるぎない人間であったのではないかと思ってしまうのであるが、じつは作品とはうらはらに、制作者自身は、きわめて不安定で落ち着きのない人間てあったようなのである。あるいはそれは、長いあいだ周囲の人たちの無理解や、さらにまた、時の美術界からもきわめて不当なあつかいを受けることによって、すっかり世間や人間たいして懐疑的になってしまったのかもしれない。晩年になっても、彼はしばしば「人生は恐ろしい」と言っていたという。にもかかわらず生涯の作品を眺めると、きわめて一貫した進展の経過を示している。そればかりではなく、作品にはそのような人間的なもろい側面は微塵もなく、堅固な構造と奥行きを感じさせるのだ。もっとも画面に向かっていざ制作に入ると、一見、人間的弱点とも見えかねない、迷いや変わりやすい人間的側面とは別な、きわめて堅固な造形への意欲のかたまりとなって、その世界に入り込んでゆくのかもしれない。あるいは制作しつつある作品そのものが、彼を、その強固な世界に…画面の造形秩序のなかへ引き込んでゆくのかもしれない。そしてまた、その世界に入り込むことによって、また真に生きている感覚が持てるのかもしれない。
その画面…絵画の世界とは、いったいどんなものなのか。セザンヌはタンペラマント(日本語では気質と訳されている)という言葉を、生涯にわたってしばしば言っている。しかし、この気質というのは、一般に、わたしたちが言っている「気質」という意味とは少し違うようだ。たとえは辞書などには、気質は「気立て、気性、一般的な感情傾向から見た、個人の性質」とあるが、セザンヌの言っている気質というのは、もっと個人の根底にある何か普遍的なものを指しているようなのだ。たとえば、ある手紙のなかで「人を、その到達すべき目標にまで連れて行くことの出来るは、ただ根本の力、すなわち、気質だけである」とか、また、マネに対しては尊敬しているにもかかわらす「マネは注意深く現実を見つめ、それを客観的に描く」そして「彼は生き生きとした調子を出すのに成功している」しかし「彼は気質が少し欠けているのではないだあろうか」と。 このような観点を見ても、その気質というものが、セザンヌ独特の意味を何か持っているように感じられるのだ。そして、さらにこの言葉を念頭におきながら彼の一連の作品を見てゆくと、それが何であるかを考えさせるし、またなっとくさせられるようにも思える。それが簡単に何であるかとは、うまく言えないが、推測するに、それは自然を見て、ただ眼に映る、きらめく光や色彩面に主点をおいて描くということだけではなく、もっと自己のなかに存在する根底的なものと合致した、ある感覚をも表現しなければならない、ということなのかもしれない。たとえばセザンヌは、印象派のなかには色彩の優位を強調して表面的なものに向かう傾向があるといっている。彼自身が、当時新しく登場した印象派の方法に開眼して自分の仕事を始めたとはいえ、それだけでは彼の内なる眼は満足できなかったようである。セザンヌはその眼に映る色彩の奥にある、自然の構造にまで目を向けなければならない、と。彼の眼に見える自然の奥にある構造的なものとは何であろう。それに対しては、たとえばエミール・ベルナールヘの手紙で「自然を円筒形と球形と円錐形によって扱い、すべてを遠近法のなかに入れなさい」と言っている。 これはセザンヌを語るときによく言われる言葉であるが、また、誤解されやすい言葉でもあるようだ。この言葉はキュビズム…立体派の発生や二十世紀の芸術の発生や発展にヒントや影響を与えたといわれるが、自然の事物をストレートに幾何学に結びつけて考えるのは、そこに少し飛躍やズレを感じるのだ。そうはいっても、セザンヌは決して単純に幾何学を思わせるような作品は描かなかった。またキュビズムのように事物を分解するということもやらなかった。それは、自然の複雑な事物を見るときの、心のありよう…眼の背後にある思想のようなものであったのではないかと思える。
|
|||||
「負けること勝つこと(105)」 浅田 和幸 |
|||||
「DXを超えた地球世界へ」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部