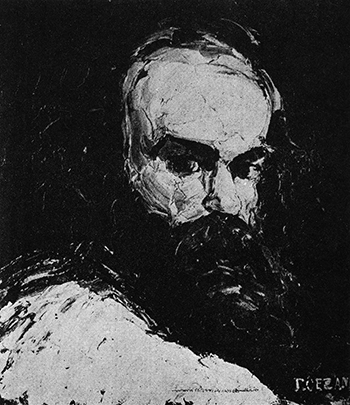第150号 |
|||||
| 2021年4月14日 | |||||
「問われている絵画(141)-絵画への接近61-」 薗部 雄作 |
|||||
一貫した思考で構造的な奥行きある絵画の世界を切り開いたセザンヌではあるが、しかし初めは、むしろそれとは逆な世界から始まっているように見える。ドラクロアを尊敬していたといっているように、初期はきわめて情念的でドラマチックな作品を描いていた。たとえば二十八才のときに描いた「誘惑」(1867)という作品などが、それを示している。そしてまた、特徴的なのはきわめて厚塗りで大胆な一連の作品を描いていることだ。「弁護士」(1866)や「ドミニク伯父」「自画像」(1865~66)などがそれである。パレットナイフを使って絵の具を厚く盛り上げた荒々しい作品だ。何かに触発されたのか、あるいは内からの衝動によって一気に描かれたのか、それはわからない。これらの作品は、後年の…普通セザンヌとして知られている作品とは、まったくおもむきも異にしている。とはいえ、気質においてはやはり共通の何かを感じるような気もする。しかしこのような世界から、あの秩序だった世界へ……ペリュシも「彼の描いた絵ほどに、静かでよく秩序づけられ、至上の均衡を保っている絵は他にはない」と言っているような、あの構築的な世界はいったい何によって、どんな心的変化によって制作されていったのであろう。
後年の手紙であるが、彼はそのなかで「趣味は最良の判定者でこれを持つ人はめったにありません。芸術は実に数少ない人々にのみ呼びかけるものなのです」といっているが、ここでいわれている「趣味」という言葉は、わたしたちが一般に使っている趣味という言葉の意味とは少し違うように思える。たとえば辞書などには、趣味とは「楽しみとして興味を持つ事柄」というように出ているが、しかしここでいわれている趣味は、何かに対するもっと深い審美眼のようなもののように思える。たとえばショーペンハウアーなども美的なものに対する判断力について、それは「五百年も待たなければ現れないという不死鳥と同じように、判断力というものは、珍しいし鳥の一種に近く、たいがいは存在しないものなのである」といっている。セザンヌのいっている「趣味」は、これとは少し異なるかもしれないが、やはりきわめて稀な内面的な一つの現象であるのかもしれない。セザンヌは、その「趣味」に導かれて、徐々にあの独自の創造世界のなかに入っていったのであろう。そしてまたここで思うのは、制作者各自が、セザンヌのいう自分の内なる趣味…美に導かれて制作することができるならば、そこにはきわめて多様で豊かな創造の世界が展開されるのではないか、と思えるからである。なぜなら、内なる趣味…美に従い導かれるな らば、そこには、それぞれ各自の個性が発現され、模倣的要素は消えてなくなるのではないかと思えるからである。
また「芸術家は、性格の知的観察にもとづかぬ意見を軽視せねばなりません。文学的精神をも疑う必要があります。これは実にしばしば画家をしてその真の道から……つまり自然の具体的研究から遠ざけ、触知できない思弁のなかに長い間迷い込ませるのです」といっている。若き日は詩に親しんだ文学青年でもあったセザンヌではあるが、ここでは、絵画にとって、言葉というもののもつ…つまり意味や論理を介入させて、私たちの自然に対る感覚の直接性を阻害することがあるということだろう。たしかに、自然や物を見るということは、言葉よ力先に、まず何かをわたしたちに感じさせる。そしてその受けた感覚を、絵画は言葉の介入なしに、じかに色や形で表現する、ということである。そこに言葉が介入すると、ある種の説明性があらわれてしまいがちなのだ。もちろん文学的であるという、ことがいけないということではない。文学的ですぐれた作品もまた多いからである。
とはいっても、わたしは、かつてこの言葉を読んで、絵画に文学性を持ち込むもとを警戒した。徹底的に造形要素のみによって何かを表現したいと思ったのであった。しかし、今から思うと、そこで排除された文学的な要素が、長いあいだに蓄積されてきたのだと思う。わたしは文学的なものにも関心があったからである。だから、絵画から排除された文学的なものが、しだいに蓄積され、それが後年になって出口をもとめて表現を要求してきたのだと思う。
セザンヌはまた「ルーブルは参照すべき良書です。しかし、これも単なる仲介物であるにとどまらねばならない」とベルナールへの手紙に書いている。そして「とりあげるべき本物のすばらしい研究対象、それは自然という絵画の多様性なのです」と。また「文学者が抽象的な思想によって自己表現を行うのに対し、画家はデッサンと色彩によってその感覚を、知覚を具体化します。自然に対してどんなに綿密、誠実かつ従順になっても、そうなり過ぎると言うことはないのです」といっている。そして「自分のモデルに対して、特に自分の表現手段に対しては、多少ともつねに主人なのですから。眼前のものに深く入ること、そしてできうるかぎり論理的な自己表現を忍耐強く行うことです」と。
これらの言葉は、いったんは忘れていたが、わたしの深層には潜んでいたのだと思う。後年になって若冲の多くの作品に直に触れたとき、それらの作品に、セザンヌのいう…文学の介在なしに物そのものを直視しする眼…精神を見たのは。若冲とセザンヌ…こんな結びつきはあまり見かけないが…しかし、ここでわたしのいっているのは、表現された物の形のうえでのことではなく、自然や物に対する、画家の眼の根拠についてであるのだ。制作者各自が、セザンヌのいう「趣味」…に徹して描くことができるならば、そこにはまた、きわめて異なる表現が…むしろ多様で豊かな表現世界がくり広げられるのではないかと思うからである。
|
|||||
「負けること勝つこと(106)」 浅田 和幸 |
|||||
「権威主義と民主主義のこれから」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部