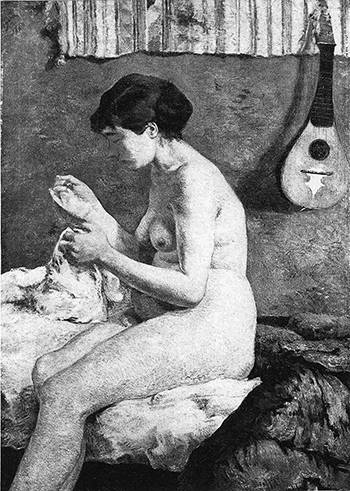第152号 |
|||||
| 2021年10月7日 | |||||
「問われている絵画(143)-絵画への接近63-」 薗部 雄作 |
|||||
たしかに、ゴーギャンの画家としての出発は遅かった。なにしろ、それまでは株式仲買人としての仕事をしていたのだ。それだけではなく、さらに有能な仲買人として大きな利益を得ていたという。そんなかれが、その仕事とは、まるで異なる<画家>になるなどということを、いったい何が、かれに決心させたのだろう。
もっとも、株式仲買人として莫大な利益を得ていたというさなかにありながらも、すでに絵画には関心があったようである。もともとあまり「外に出ることを好まなかった」というかれは「もっぱら好んで自宅にとじこもって、読むこと、絵を描くこと、スケッチをすることなど、ただこうしたことが彼の気晴らしであった」という。それに、もともとどこか変わったところのある人間であったようでもある。ペリュショは書いている「ゴーギャンは、自分がそれ相応の場所にいるという気持ちを、どこにいても感じることができず、どこに行っても環境になじめない人間であった」と。株式仲買人として「あんなに華々しい成功を収めたのに、あの商売人連中の世界になじめない人間」であり、それだけではなく「パリという社会の、習慣や礼儀作法」にも、さらに「かれの時代にさえも、つまり、精神的なもの、主観的なもの、夢と感性の力などは、すべて否定されてしまうほど、科学への待った信仰に煽られた十九世紀末の、ブルジョワ的で物質的なヨーロッパ世界にもなじめない人間」であったと。それだけではなく、みずから好んで入った絵画の世界においてさえ、どこか「場違いな気持ちを抱くのであった」という。
たとえば、当時さかんになっていた印象派の画家たちのグループに対しても「また別の場違いな気持ちを抱くのであった」。それは「かれらが、ものではなく、その外観を描くのは、客観的な観察をするという意図のためなのだ」といい、そして「かれらは、束の間の光の幻影を分析し、表現する折に、眼と手の間に精神が入ってくることを拒絶するのである」といって批判する。そしてペリュショはいう「そう、この魂を探求し、どこに行ってもなじめず、至るところ順応することができない男とは、まさにこの株式取式所員なのである」と。
「絵画がゴーギャンにとってこのような執念となったのは、それがかれにとっての解放であったからでしかない」。かれは自分の「職業的奴隷状態」に不満をいだく。そして「株式取式所に費やす時間とは、死に与えられた時間」であり、これは「浪費の時間であり、失われた時間である」と。しかし、その仕事で莫大な利益を得たかれは「カルセル街八番地にある、大きな庭に面した広いアトリエを備えた豪華な別棟を借りた」のであった。その頃に描いた『カルセル街の雪の庭』という、どこか哀愁をおびた抒情的な作品がある。また同じ頃に描かれた「裸婦習作」は第六回印象派展に出品され、批評家ユイスマンスに注目された。「昨年もゴーガン氏は出品した……それは一連の風景画で、ピサロのまだあやふやな作品を水増ししたものである。が、今年、ゴーガン氏は、一枚の全くかれのものである油絵、近代画家としての動かし難い資質を示している油絵をもって参加している。その絵には『裸体習作』という画題がついている…… わたしは恐れずに断言するが、裸体を描いた多くの現代圉家たちのなかにあって、いかなる画家も、現実のなかにこれほど烈しい色調を与えたものは、まだ一人もいなかった…… 肉体は叫んでいる。それはもはやプラタナスの葉のような、滑らかな、粟つぶのようなものも、細いつぶも、毛穴もないあの皮膚ではないし、また、ばらの桶一律に浸され、すべての画家たちによって生ぬるいアイロンをかけられたあの皮膚でもない。それは血が赤く染めている肌であって、その下には、神経がぴくぴくしている」。ようするに「ゴーガン氏は、ここ数年来、始めて、今日の女を描こうとしたのだ…… かれは完全に成功し、大胆にして、真実な絵を創りだしたのだ」と書いている。
ペリュショは「芸術と宿命」シリーズを書き始めた理由を「一つの意図が、すでに何冊出ているこのシリーズを書かせたのだ」が「その意図とは、真実を探るというただ一つの関心しかない」といっている。そして「その人間とは一体何か? 私か書いた伝記の一冊一冊が答えようとしているのは、じつに、こうした質問に対してなのである」と。しかし、ポール・ゴーギャンの場合には、とくに複雑である」という。「かれについて私が明確に知るようになればなるほど、かれが真の姿を認められない人間…見知らぬ人間である、というわたしの確信は、ますます強く確認されていった……かれは数々の伝説の、その敵や友人や、また自分自身によってつくりだされた伝説の犠牲者だった」そして「かれは自ら進んで、謎であるふりをした」しかし「かれはまず、かれ自身の眼に謎と映らなかっただろうか? 目覚めた夢想家で、世のなかにその不安と不満を闊歩させたかれは、どんなときにもその宿命という文字に気がつかなかった」。
<美>がゴーギャンの生活を、今までとは別の方へ向かわせていった。あるいはそれは、かれ自身にとっても予想以上であったかもしれない。それまでは趣味として描いたり、またコレクターとして美術作品を買ったりはしていたが……しかし、すでにかなり深入りしつつはあったようである。「仲買所の仕事は、かれを夢中にさせ」てはいたが「このように仕事がどんなに忙しくても、ゴーギャンはシュフネッケルと一緒にコラロッシのところに熱心に通い始める」。そして「描いてゆくうちに、自分の仕事がますます複雑になってゆくことを認識する」のであった。
|
|||||
「負けること勝つこと(108)」 浅田 和幸 |
|||||
「近代民主主義の抱える課題」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部