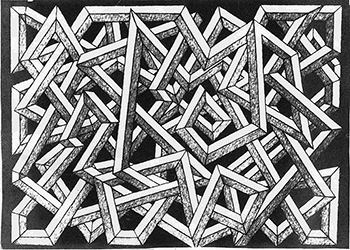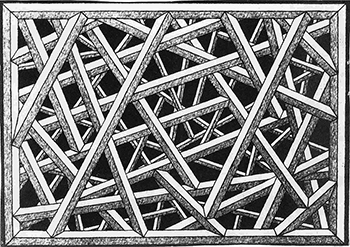第156号 |
|||||
| 2022年10月12日 | |||||
「問われている絵画(147)-絵画への接近67-」 薗部 雄作 |
|||||
ながいあいだ絵を描いてきたので、その間に数多くの作品を発表してきた。何かの会に所属しているわけでもないので、発表といえばほとんど個展ということになる。したがって、たくさんの人々に作品を見てもらい、いろいろな感想も聞いてきた。そんななかで、わたしが意外に思った言葉のなかに、あなたは数学をやっていたのですか? というものがある。あるいはまた、これはパソコンによって製作したのですか? というのもあった。
しかし、ふりかえってみて、わたしは小・中・高をとおして、数学はもっとも苦手な学科であった。低学年の頃の「さんすう」はまだよかったのですが、中学・高校になるにしたがって、数式や記号がはいってくると、もうだめで、ほとんど受けつけなくなってしまったのであった。それはわたしが、絵画に興味を覚えだしたのと軌を一にしていたように思う。
とくに勉強が好きということもなく、ほとんど無味乾燥のように思えた毎日であったが、なにかのきっかけで絵を描くことになり、そして描きはじめると、手応えもあり、また、それがまたたいへんおもしろく、ぐんぐんのめり込んでいったのであった。そしてその世界に頭も気持ちもとらえられて、今までの無味乾燥のように思えた毎日の生活が、急に生き生きとしてきて、なにかとても充実感を感じるようになったのであった。 その頃わたしが描いていたのは、ほとんど写生や何かの手本などの模写であったので、それらの絵のなかには抽象的な形…あるいは記号や数字というものはまったくなかった。描く対象は、すべて具体的な物…静物や風景なので、それらを、眼で、じかに見て、そのまま描いてゆくのだが、しかし、それが何ともいえない生き生きとした快感のようなもので、わたしを全身的にとらえたのであったが、しかし、そこには抽象的な思考というものは入り込む余地もなく、また必要もなかった。 だから、わたしのなかでは、数学と絵画というのはまったくかけ離れていて、関係のない世界であったのだ、と思っていた。むしろ、絵画が思考的になることを警戒していたのだ。抽象的な思考の世界が入りこむと、作品が観念的になる、そして観念的になるということは、周囲からもまた批判的にみられることの方が多かった。たしかに、それは自分でも、何か感覚や感性が薄められたり、疎外されたりするもののように思っていた。
しかし、それがだんだん変わってきたのだ。それは、たぶん写生的な絵画をやめてからのようである。写生的な絵をやめたのには、いくつかの理由がある。職業をもち、通勤生活をする生活になると、いつでも自由に写生にゆけるということはできない。描けるのは夜か休日だけということになる。夜は写生にはゆけない。静物でも電灯の光…当時はまだ蛍光灯は普及していなかった。電灯の光では影の部分が極端になって描きにくい。それにまた、時代的な影響もある。1950年代(第二次世界大戦後)は、戦中には閉ざされていた世界…西洋の現代美術が一気に押し寄せてきた。それには大きな流れとして、抽象的な絵画とシュールレアレリム絵画の傾向であった。
そんな状況のなかで、わたしは、抽象的な造形を手段として、手さぐりで何かを造りだそうとしたのであった。しかし、自分の内なる世界といっても、そこには、ほとんど何もない、としか感じられなかった。にもかかわらず、わたしは、あえて、そこから何かの<かたち>をつくりだそうとした。そして極力模倣をさけ、むりやりにでも、何かの<かたち>を強引につくりだそうと取り組んでいったのであった。 はじめは、ぐにゃぐにゃした紐状の形が交差したり並列したりした、混沌とした画面であったが、やがてそれらが固まって何かの形のようなものとなり、羅列したり入り組んだりしたのであった。
そして今、あらためて考えてみると、そこには数字や記号こそないが、線や形によって、さまざまに思考されているのは事実のようである。それは、あるいは数学的なのかもしれない。
|
|||||
「負けること勝つこと(112)」 浅田 和幸 |
|||||
「近代民主主義社会における人間存在の意味や価値にどう向き合うか」 深瀬 久敬 |
|||||
【編集あとがき】 |
|||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部