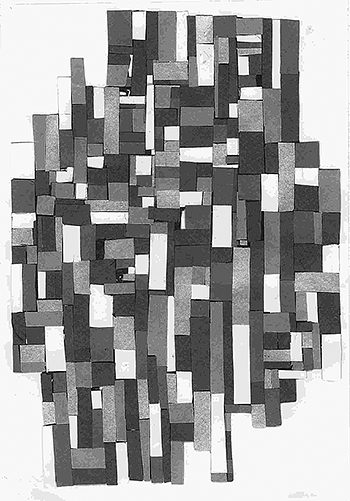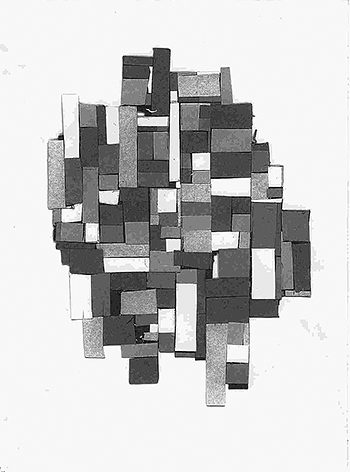第157号 |
|||||
| 2023年1月4日 | |||||
「問われている絵画(148)-絵画への接近68-」 薗部 雄作 |
|||||
もう一つの質問というのは、初めて作品を見た人のなかには、ときとして「これはパソコンによって作られたのですか?」というものであった。画面がシスティマティックにできているので、それが一見デザインのように見えて、あるいはそんな質問がでるのかもしれない。そして、たしかにシスティマティックではある。しかし、制作の実際は、きわめて手づくり的につくられたものなのだ。
そして、それがわかると、次は、では、どのようにして作られ…あるいは描かれたのですか? と、技法の面からの質問もよくある。たしかに、画面をよく見ると、様々な小さい色面がつなぎ合わせてあるのが、その継めの部分のわずかな凹凸でわかるからだ、と思う。そして事実、それは大小のさまざまな四角い色面がつなぎ合わされて、ある大きさの画面になっている。 つまり、まず、そのような画面を作ってから、描く仕事が始まることになる。そして、その繋ぎ合わせの画面づくりも、一気にできあがるわけではない。まず、核になる中心の部分を、いくつかの小さな色面を繋ぎ合わせてつくる。そして、その核…色とかたちの不定形をながめながら、それを少しずつ増やして大きくしてゆく。そのとき、それをむりやり…あるいは強制的に増やすというのではなく、できるだけ…あたかも有機物が増殖するかのように配慮しながら大きくしてゆく。また、不思議なことに…あるいは当然かもしれないが、その核になる不定形が、となりにくる色面を、なかば呼び寄せるようなところもある。なぜなら、その部分に合う色面と合わない色面があるからである。合わないものを、わたしの意思で無理やり接合しても、そこには有機的な増幅もなく、緊密な画面にもならない。
自分としては、自然にこんな制作方法になったのであるが、おそらくこれは、かつてコラージュの作品を制作していたことに起因しているようだ。そのコラージュについては書いたこともある。 「コラージュを始めたのは、一九六三年頃だったと思う。当時、職場の仕事で、たまたまハサミやノリを使っていたからかもしれない。あるとき、なにげなく雑誌の写真を見ていて、ふと、この写真をいくつかに分割して、別な組み合わせ方をしてみたらどうなるだろう、と思いついたのであった。そこで、さっそくその写真をいくつかに切断してつなぎ合わせたのであった。すると、そこには元の写真とは違う、一見、何の写真か見分けがたい不思議なかたちが現れたのであった。今からみれば、その試作は実にささやかなものであるが、わたしはそのとき、ある種のヒラメキを感じた。これをおし進めれば何かできるのではないか」と。
さっそくわたしはやってみた。そしてそのコラージュの制作には異様な吸引力があり、のめり込むようにして次々に作っていった。そして発表もした。そのコラージュ展のときの批評文がある。「一見きわめてメカニックで、抽象風景的な表情をたたえて透明にみえる。しかし近づいてみると、その猥雑な狂騒さと、内側から沸きたってくるような膨張欲にほとんど辟易させられる。ここでは、写真がコラージュされることによって、まさに絵の具に転化されている。個々の写真は、つぎつぎと薗部の感性の方程式の中に、既知数として導入されながら、同時にたんなる材質として未知数を堆積していく、従来のコラージュの手法にみられる等号の機能は揚棄され、出会いによる既成の意味の扼殺というより、意味構造そのものを骨抜きにしてしまう追跡がなされている」(石子順造)
そのときには、四角に切られた写真の集合体は、一つ一つの断片だけを見ると、ほとんど何の写真かわからなくなっているばあいも多いが、その不可解な断片の集合は、一種スリリングな画面を作りだしたのであった。その画面は、完成されたものとして、その上に何かを描くということはなかった。しかし、こんどは写真ではなく、大小さまざまの四角い色面の集合である。しかしそのときの、四角く切って繋ぎ合わせるという方法が、この色面構成の画面をつくるということに生かされている……余談になるが、ここでふと思う。この制作方法は、素材的にみると、きわめて省エネ的であるということである。なぜなら、まず素材としての紙に、ほとんど無駄というものがでないということだ。つまり、四角い大小の色面に刻むと、それには必ず残りの部分かできる。そして、それもまた、別のところに利用することができる。さらに、出来上がった色面構成の画面も、眺めていると、どこかに何か不足や不満を感じるようになることがよくある。そんなときには、その部分を切り抜いて、別の色面を当てはめて繋ぐことができる。さらにまた、そこで切り抜かれたいくつかの色面も、それらを寄せ集めて、あらたな別の画面構成として使うことになる。さらに、この余った色面同士の集合には、意識を超えた意外性もあって、別の展開を可能にすることが多い。
|
|||||
| 「負けること勝つこと(113)」 浅田 和幸 | |||||
| 「一人ひとりが自らの存在の意味や価値を問うこと」 深瀬 久敬 | |||||
| 【編集あとがき】 | |||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部