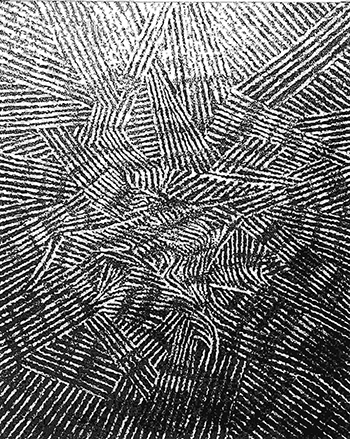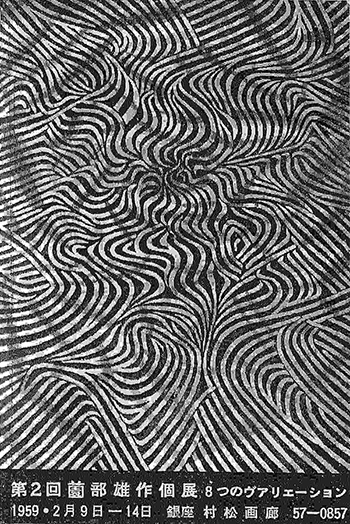第161号 |
|||||
| 2024年2月14日 | |||||
「問われている絵画(152)-絵画への接近72-」 薗部 雄作 |
|||||
かくしてかなり意気込んで開いた最初の個展(1956)の結果が、ほとんど無反応に近かったのは、わたしにとって、かなりショックであった。今から思えば、若い無名の画家たちが、開いている、多くの個展やグループ展を、いちいち批評の対象として取り上げるということがないのは当然のことであった。それでも、今、その芳名録を見ると、当時は無名であったかもしれないが、後になって名を成した人たちも多くいるのにはおどろいている。しかし、当時の美術界は、現在では想像できないような熱気があった。たとえば美術雑誌だけでも数種類あった。たとえば『美術手帖』『美術批評』『みづゑ』『三彩』そして美術専門ではなく芸術全般であるが……そして、それらには、それぞれに個展やグループ展について、批評家による月評というものがあった。だから美術評論家も、よく画廊をまわって見てた。今日では考えられないことである。
それはとにかくとして、最初の個展のショックもさめやらぬ気持ちのまま、まもなく美大の卒業ということにも重なったりして…だから今度は、生活のことも考えなければならないことになった。なによりもまず、何か仕事を探さなければならない。しかし、当時は、現在とは違い、就職難の時代であった。職種も今日のように多様ではなかった。そもそもテレビというものがなかった。テレビが出現しそれが一般家庭に普及するにつれ、世の中全体にあたえた影響には、きわめて大きなものがある。なにしろそれまでは、メディアとしては、新聞、雑誌、そしてラジオというところであったのであるから。 けれども、たまたま偶然にもある仕事に巡り合い……そのことについてはすでにふれたこともあるが、その仕事というのは米軍の「406医学研究所」というところだった。そこは、小田急線の相模大野駅の近くのおおきな病院の敷地のなかにあった。松林や広い芝生のなかに、その研究所はあった。その研究所は、極東地域に生息する昆虫…おもに害虫を、ささまざまな角度から昆虫…おもに害虫をさまざまに研究するところで、いくつかのセクションがあり、多くの人たちが研究やまた仕事をしていた。そのなかにエンタモロジイ…昆虫分類学というセクションがあり、そこには研究者と、またそれとは別に、その虫の絵を描く画家たちが、ほぼ十名ちかく虫の絵を描いていたのであった。その仕事についても、すでにふれたこともあるが、簡単にいうと、スライドになっている昆虫を、顕微鏡を覗きながら…拡大された虫の絵を忠実に描くという仕事であった。
わたしは、この昆虫を描くという仕事に直面して、ずいぶん描くということに関して考えさせられたのであった。それまで、わたしは長いあいだ絵は描いてきたが、それは、いわゆる写生であった。写生というのは、ご存じのように、対象である風景や静物を、ある距離をもって、それを眺めながら描くわけであるが、この絵は眺めて描くというものではなかった。いわゆる接写である。そこには、おおきな違いがあった。つまり、眺めるばあいは、対象としての静物あるいは風景が、また遠近法にしたがえば、眺める距離やまた位置によって、同じ対象でありながらも、さまざまに、異なる形となって、眼には見えるということになる。しかし、この顕微鏡による接写では、まず対象物と眼との距離がない。一方、レンズの上下の移動によって…スライドの虫の細部の拡大や縮小によって、虫の背中の面と腹側の部分の違いや、肉眼では見えないほど小さな虫でありながらも、背中と腹側がある。あるだけではなく、それはまたきわめて鮮明正確な器官や足などがある。しかし、そこには遠近感や、また向きによって形が変化するということもない。同じ描写ではあっても、まるでことなるものであった。
|
|||||
| 「負けること勝つこと(117)」 浅田 和幸 | |||||
| 「地球人アイデンティティーの構築に向けて」 深瀬 久敬 | |||||
| 【編集あとがき】 | |||||
| - もどる - | |||||


編集発行:人間地球社会倶楽部